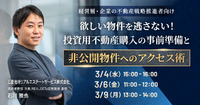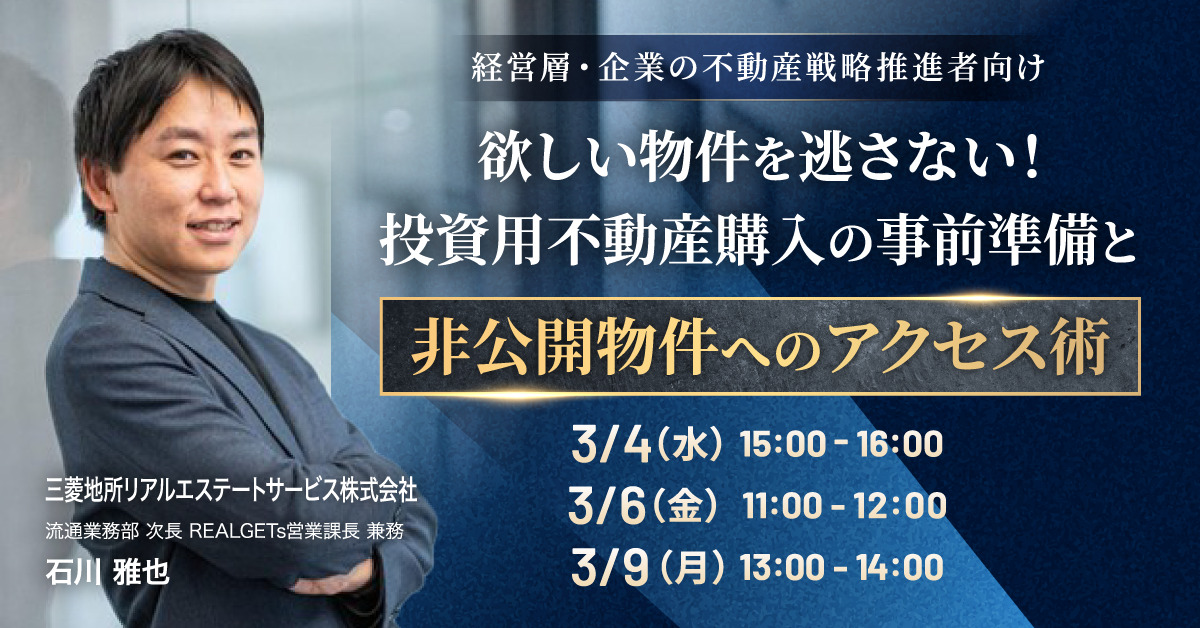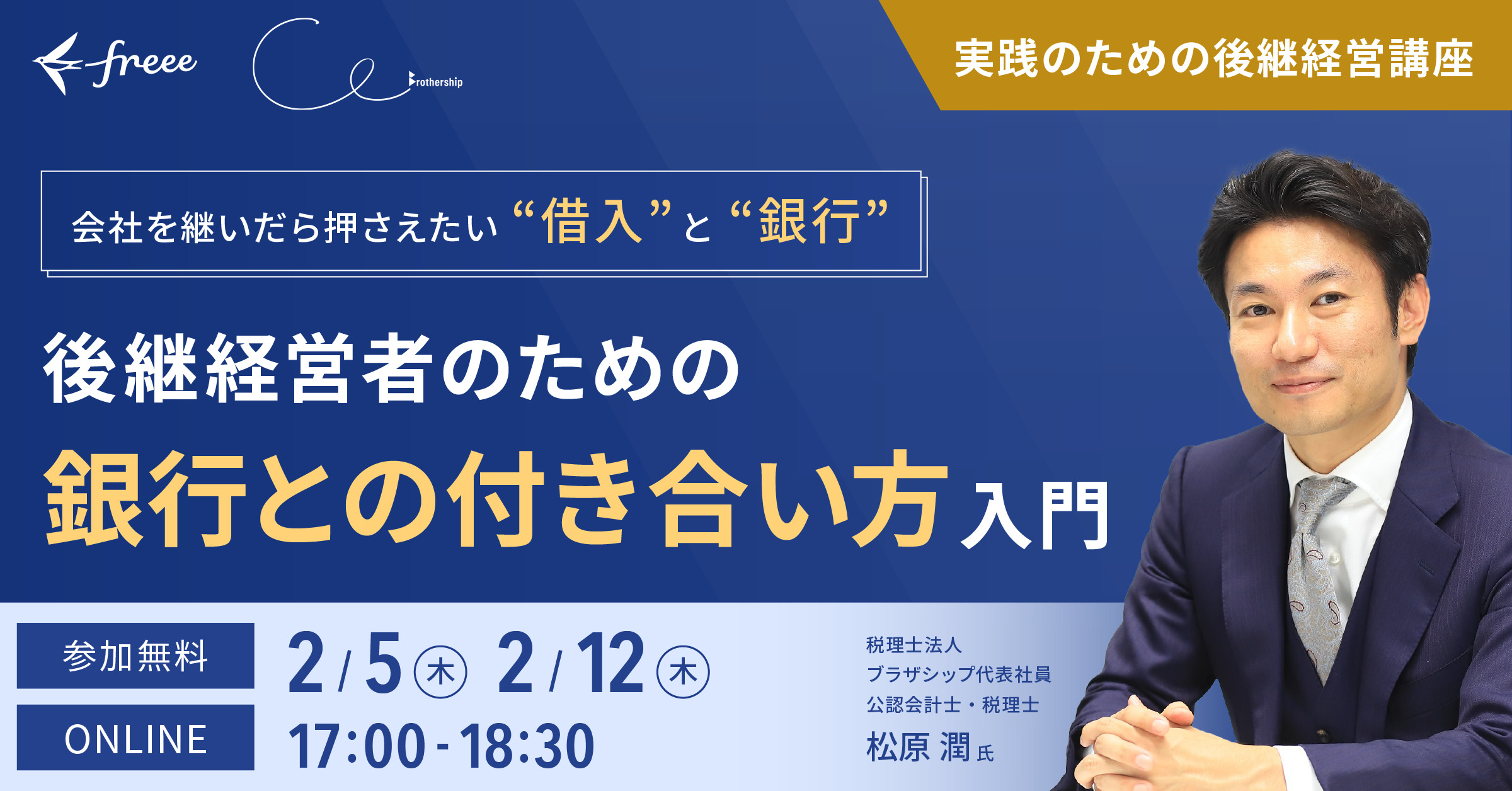公開日 /-create_datetime-/
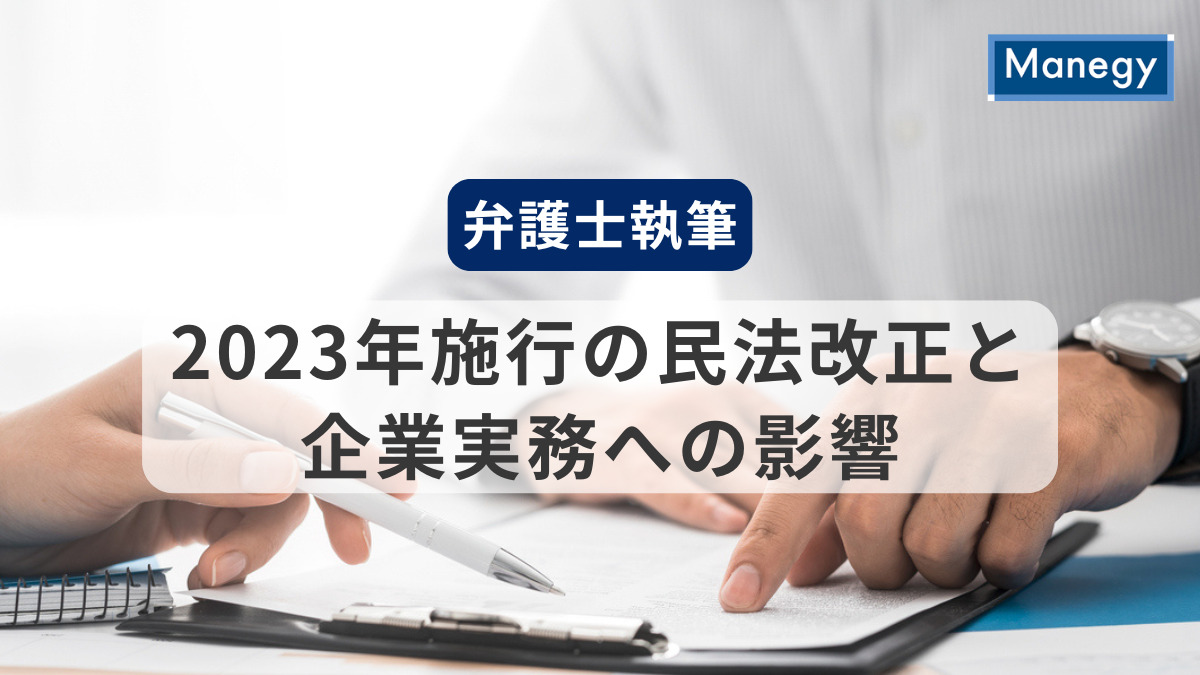
目次本記事の内容
この記事の筆者

牛島総合法律事務所パートナー弁護士。CSR推進協会環境部所属。 環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。 「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」「ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応」のほか、数多くの著書・執筆、講演・ 研修講師を行う。

牛島総合法律事務所アソシエイト弁護士。2022年弁護士登録。 不動産分野では、不動産ファンドに係る不動産取引やファイナンス案件を数多く取り扱う。その他、M&A等、企業法務一般を取り扱う。
1. 2023年4月1日施行の民法改正の制定背景/民法改正とは
近年、我が国では登記簿などの情報を参照しても所有者がすぐに判明しない、又は所有者が判明しても連絡が取れない土地、いわゆる「所有者不明土地」や「所有者所在不明土地」が増加しています。また、適切な利用や管理が行われない土地については、草木の繁茂や害虫の発生などが原因となり、周辺地域に悪影響を及ぼす事態が広がっています。令和5年に国土交通省が実施した調査によると、所有者不明土地の割合は26%に達しています*1。
これらの土地は、再開発や民間取引の場面で土地の利活用を妨げるだけでなく、管理が不十分な土地が隣接する土地に悪影響を及ぼす可能性もあります。その結果、インフラ整備や防災に重大な支障が生じ、生活環境の悪化を引き起こすことになります。この問題は、高齢化の進展や死亡者数の増加に伴い、今後ますます深刻化するおそれがあります。所有者不明土地の解決は、喫緊の課題とされていました。
そこで、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的な法改正が行われました。まず「発生の予防」については、不動産登記制度の見直しや相続登記・住所変更登記の申請義務化が進められ、さらに相続土地国庫帰属制度の創設などによって対応が図られています。
本記事では、特に「利用の円滑化」の側面から、土地・建物等の利用に関する民法の規律を見直すために行われた令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正について、企業実務に与える影響という観点から解説します。2023年4月1日施行の民法改正を網羅的に解説するものではない点につきご留意ください。
*1 法務局「令和3年民法・不動産登記法改正、 相続土地国庫帰属法のポイント」(令和7年1月版)1頁
lockこの記事は会員限定記事です(残り5336文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -
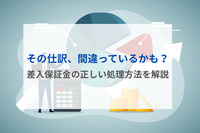
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説
ニュース -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
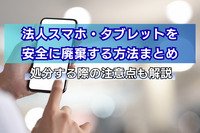
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説
ニュース -
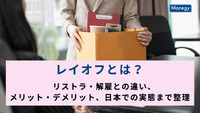
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
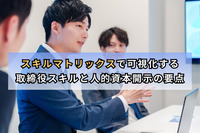
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース