公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

現代社会では、デジタル技術の進化とともにサイバー攻撃の脅威が増しています。個人情報の漏えいや企業機密の流出、不正アクセスなどの問題を放置していると、企業活動に深刻な影響を与える可能性があるため注意が必要です。
こうしたリスクはIT部門だけではなく、一般社員の行動によっても引き起こされるため、それぞれが自覚をもって日々の業務に向き合わなければなりません。本記事では、一般社員が知っておくべきサイバーセキュリティと、法務の基本について解説します。
サイバーセキュリティとは、自社のコンピュータシステムやネットワーク、データを外部の脅威から守るための対策です。サイバー攻撃は日々多様化しており、不正アクセスやハッキング、マルウェア感染、フィッシング詐欺などさまざまなものに対応しなければなりません。
たとえば個人情報が漏えいしたり、企業機密が流出したりすると、企業の信用失墜につながる可能性があります。また、単なる情報漏えいにとどまらず、業務停止やシステム障害を引き起こすリスクも考えられるでしょう。こうしたリスクを防ぐためには、技術的な対策だけでなく、社員それぞれが正しい知識・意識をもって行動することが不可欠です。
サイバーセキュリティは技術的なものだけでなく、法務的な観点からも重要な意味をもちます。法務部門は、企業が法令を遵守(コンプライアンス)し、情報セキュリティに関するリスクを最小限に抑えるための役割を担っています。
たとえば個人情報保護法やデータ保護法などの法律は、企業が個人データをどのように収集・管理・保護するかについて厳しい基準を設けたものです。違反した場合は、多額の罰金や行政指導の対象となります。
企業がサイバー攻撃を受けた場合、単なるシステム障害にとどまらず、顧客データの漏えいによる損害賠償請求や取引先からの訴訟に発展するケースもあります。大規模な情報漏えい事件では、被害者への賠償責任だけでなく、株価下落やブランドイメージの毀損といった二次的な損失も発生するでしょう。
こうしたリスクに備えるため、法務部門はセキュリティポリシーの策定や、契約書へのセキュリティ条項の盛り込みなどを行い、企業全体の体制を強化しています。そのため、一般社員も法的リスクを理解し、日常業務で適切な情報管理を実践しなければなりません。
サイバーセキュリティに関連する法的リスクを回避するためには、法務を含む一般社員も基本的な法律知識を身につけておく必要があります。具体的に必要になる知識は、以下の通りです。
個人情報保護法は、氏名、住所、連絡先などの個人を特定できる情報の適切な管理に関する法律です。企業で個人情報を扱う際、取得・利用に関しては必要最低限にして、利用目的を通知または公表する必要があります。漏えいや不正使用が発覚した場合、企業だけでなく個人にも法的責任が問われる可能性があるため注意してください。
不正アクセス禁止法は、他人のIDやパスワードを無断で使用する行為や、システムに不正に侵入する行為を禁止しています。たとえ悪意がなくても、上司や同僚のIDでログインするだけでも違法と見なされる可能性があります。もちろん職場上の立場を利用して、顧客のパスワードなどを盗み出す行為も禁止です。不正アクセス行為をした場合は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
業務で使用する資料や画像、ソフトウェアにも著作権が存在します。インターネット上で見つけた画像や文章を無断で使用・共有すると、著作権侵害に該当することがあります。また、他社の機密情報やアイデアを不正に利用する行為も知的財産権の侵害と見なされ、損害賠償請求を受ける可能性があるため注意が必要です。
法律だけでなく、企業ごとに定められた情報セキュリティポリシーや、ITガイドラインの遵守も不可欠です。たとえばUSBメモリの使用制限や、社外へのデータ持ち出しルール、パスワード管理ルールなどが挙げられます。こうした規定に違反すると、社内での懲戒処分や法的責任を問われる場合もあります。
サイバーセキュリティの法的リスクを最小限に抑えるためには、日常業務での具体的な対策が不可欠です。たとえばパスワードは、複雑で推測されにくいパスワードを設定し、定期的に変更します。同じパスワードを複数のサービスで使い回すのは避け、二要素認証(2FA)を活用すると、セキュリティを強化できます。
不審なメールやリンクへの対応方法を心得ておくのも重要です。フィッシング詐欺やマルウェア感染の多くは、不審なメールやリンクから始まります。差出人不明のメールや不自然なリンクは絶対にクリックせず、添付ファイルも安易に開かないようにします。定期的なセキュリティ研修や法務研修で、知識をアップデートするのもよいでしょう。
サイバーセキュリティと法務の知識は、IT担当者だけでなく全社員にとって重要です。個人情報の漏えいや不正アクセスといった「インシデント」は、社員それぞれの意識・行動によって防げます。
法律を理解しておくと、トラブルの未然防止に役立ち、万が一の際にも適切な対応を取りやすくなります。サイバー攻撃は日々進化しているため、継続的な学びと実践を忘れないようにしましょう。
参考:
kaspersky|サイバー攻撃とサイバーセキュリティについてわかりやすく解説します
政府広報オンライン|「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?
株式会社日立ソリューションズクリエイト|不正アクセス禁止法とは? 押さえておきたいポイントを解説
文化庁|知的財産権について
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

経理BPRの現状分析手法:業務可視化とボトルネック特定の実践ツール

社員研修を成功させる計画立案とKPI設定と効果測定

経営者と従業員の退職金はどう備える?小規模企業共済・iDeCo・特退共・中退共の違いと節税メリットを徹底比較
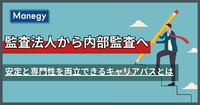
監査法人から内部監査へ|安定と専門性を両立できるキャリアパスとは(前編)

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
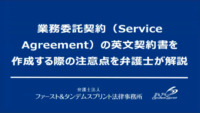
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

サーベイツールを徹底比較!
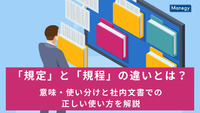
「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説
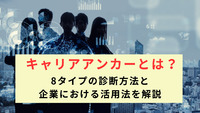
キャリアアンカーとは? 8タイプの診断方法と企業における活用法を解説
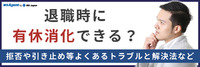
退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など
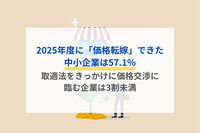
2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満
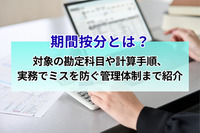
期間按分とは?対象の勘定科目や計算手順、実務でミスを防ぐ管理体制まで紹介
公開日 /-create_datetime-/