公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が労働市場から離れていくことで、「2025年問題」がしばしば論じられるようになりました。団塊世代の高齢化によって日本の社会保障制度や経済、企業の人事戦略などに大きな影響を与えると考えられます。
本記事では、2025年問題の背景や企業が直面する課題、具体的な対策についてわかりやすく解説します。
「2025年問題」とは、2025年に団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が全員75歳以上の後期高齢者となることで、日本社会に影響を及ぼすさまざまな問題のことです。
日本はすでに超高齢社会に突入していますが、2025年以降は高齢者の割合がさらに増加し、医療・介護・労働力不足などの課題が深刻化すると予測されています。企業にとっては、人材確保や生産性向上のための対策が必要になるでしょう。
2025年問題の本質は、日本社会の急速な高齢化とそれに伴う労働力不足、医療・介護負担の増大にあります。
団塊世代(1947〜1949年生まれ)の出生数は約800万人にのぼり、日本の労働市場や経済を長年支えてきました。しかし、2025年にはこの世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、医療・介護サービスの需要が急増すると考えられています。後期高齢者医療制度への影響は大きく、厚生労働省も制度の持続可能性を維持するための見直しを進めなければなりません。
団塊世代の大量退職によって、企業の人手不足が深刻化するのも、2025年問題の重要な背景です。団塊世代はかつて生産年齢人口(15-64歳)の多くを占めており、主要な労働力としての役割を果たしていました。労働市場に多くの労働者が供給されなくなり、企業が思うように人材を採用できない状態が続くと考えられます。
2025年問題は、単に社会全体の課題ではなく、企業経営にも大きな影響を与えます。とくに「人材不足」「ITの課題」「物流の変化」の3つが主要な問題となり、企業はそれぞれに対策を講じなければなりません。
まずは人事・労務管理の課題です。2025年には、団塊世代の大量退職が進み、企業にとって貴重なノウハウの喪失が避けられない状況となります。たとえば、製造業・物流業などの現場作業を支えてきたベテラン層の離職によって、現場の技術継承が難しくなるといった問題も指摘されています。
日本全体の若年層の人口は減少しているため、退職した労働力を新たな若者で補うのも困難を極めるでしょう。すでに現在もその傾向が見られますが、採用競争もさらに激化すると考えられます。
次に、ITの課題です。2025年問題と並行して、日本企業は「2025年の崖」とも向き合う必要があります。「2025年の崖」とは、経済産業省が指摘する、企業の生産性低下・競争力低下の危機のことです。
DXの推進(デジタルによる変革)をしなければ、業務効率・競争力の低下が起こり、多くの経済的損失が発生するとされています。DXの推進が遅れている企業では、業務の自動化や効率化が進まず、労働力不足がさらに加速するでしょう。
最後に、物流の変化です。2025年問題は、物流業界にも大きな影響を与えます。ドライバー不足が深刻化すれば、輸送コストの上昇が避けられない状況となるでしょう。働き方改革関連法によって、ドライバーの拘束時間や休憩時間などが見直されたため、こうした観点でも労働力が不足すると考えられます。
企業はDXや自動運転技術を活用し、物流の効率化を進める必要があります。また、EC市場の拡大により、スムーズな配送を求める消費者のニーズにどう対応するかも課題となるでしょう。
団塊世代の大量退職による労働力不足とノウハウの喪失を防ぐためには、シニア人材の有効活用が不可欠です。定年延長や再雇用制度の強化を図り、単なる労働力確保だけでなく、組織内の知見・経験を維持することも考えましょう。
DXの推進も重要です。労働力不足の解消だけでなく、業務の生産性向上や競争力強化にも直結します。システムの導入による業務効率化から始まり、AI(人工知能)やRPAの活用などを考えましょう。ITスキルをもつ人材の確保と同時に、既存社員へのリスキリング(再教育)を積極的に進めるなどの取り組みも欠かせません。
医療・介護支援の充実も、企業がアプローチできる部分です。とくに介護離職の防止と、健康経営®*の推進は重要な課題です。産業医や保健師を活用した健康診断・メンタルヘルス対策や、介護離職を防ぐ支援制度の整備などを考えましょう。
*「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
2025年問題の本質は、「労働力不足」と「高齢化」にあります。団塊世代の大量退職と人口減少により、企業は今後ますます人材確保が困難になり、生産性向上が求められる時代へと突入するでしょう。
今後、医療・介護の負担も増大するとされており、社員の健康管理やワークライフバランスの確保も重要な経営課題となります。人材活用やDXなど、さまざまな角度からのアプローチを考えましょう。
参考サイト)
内閣府|第1章 高齢化の状況(第1節6(1))
HITACHI|経済産業省の「2025年の崖」について分かりやすく解説
altcircle|物流における2025年問題の解決策は?課題や対策を徹底解説
国土交通省|「2024年問題」について
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
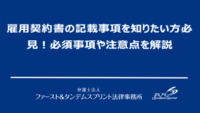
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
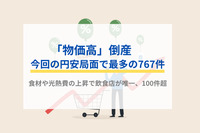
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
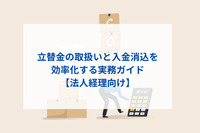
立替金の取扱いと入金消込を効率化する実務ガイド【法人経理向け】
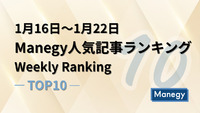
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
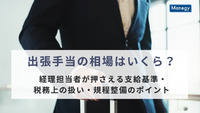
出張手当の相場はいくら?経理担当者が押さえる支給基準・税務上の扱い・規程整備のポイント
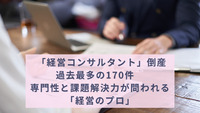
「経営コンサルタント」倒産 過去最多の170件 専門性と課題解決力が問われる「経営のプロ」

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
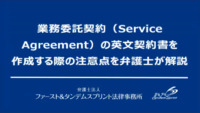
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
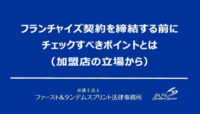
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
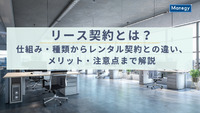
リース契約とは?仕組み・種類からレンタル契約との違い、メリット・注意点まで解説
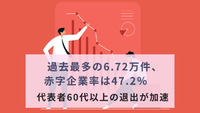
過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速
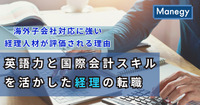
海外子会社対応に強い経理人材が評価される理由|英語力と国際会計スキルを活かした経理の転職(前編)
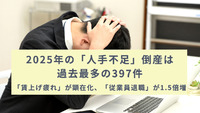
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増

キャッシュフロー計算書を武器にする|資金繰りに強い経理が転職市場で評価される理由(前編)
公開日 /-create_datetime-/