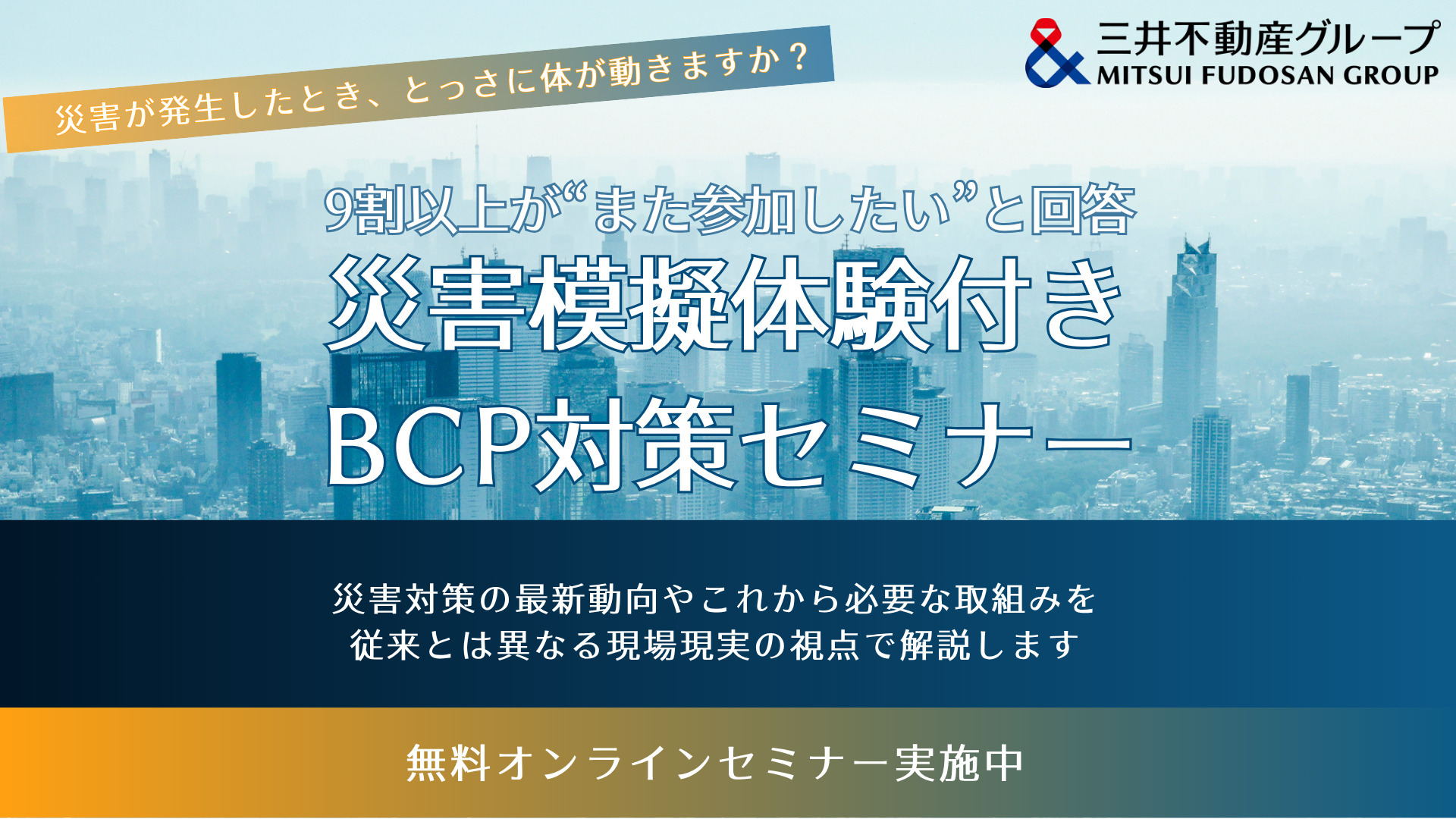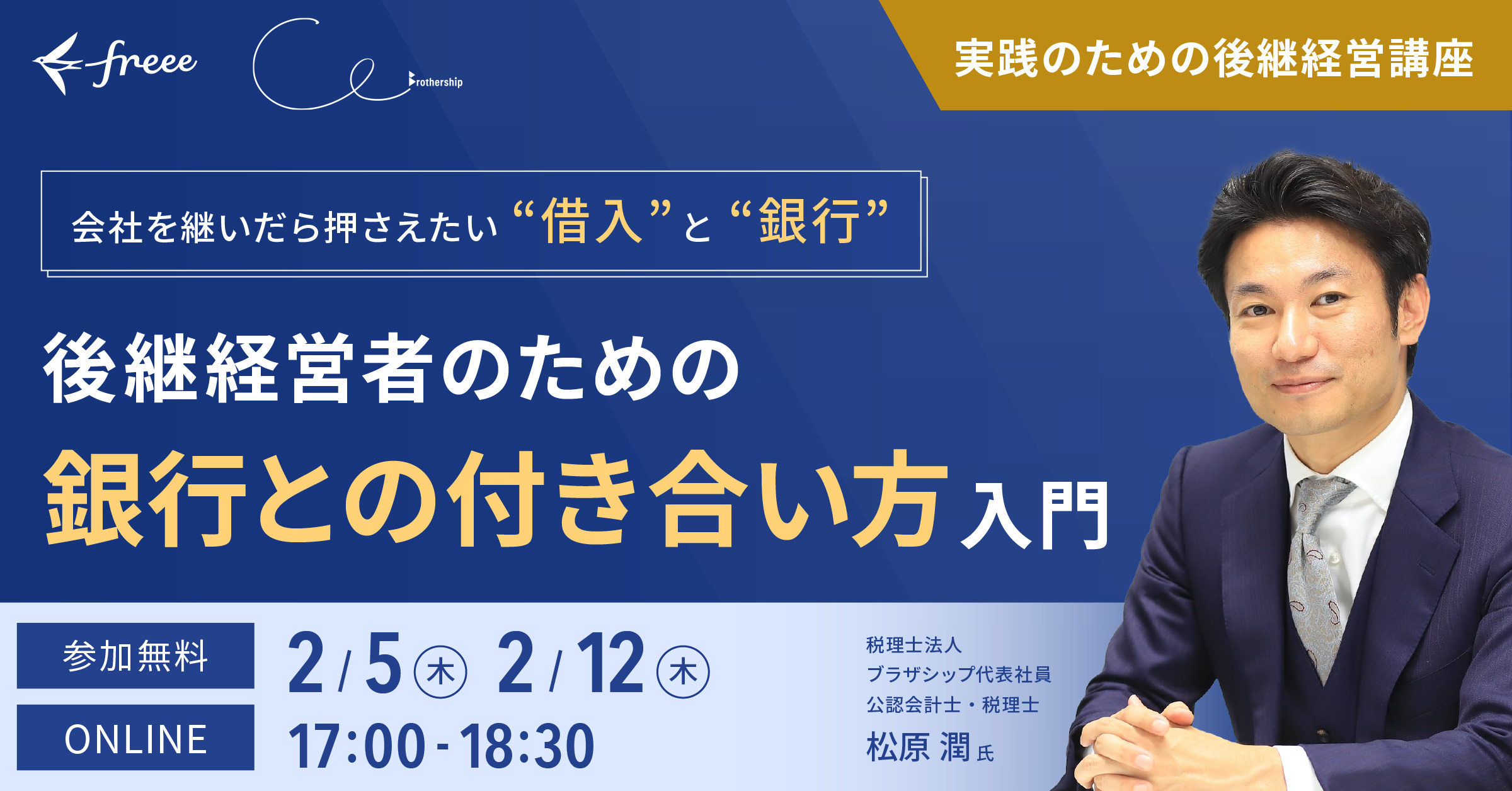公開日 /-create_datetime-/

はじめまして。起業支援税理士の水野です。
これから会社設立をして起業をお考えの方は、「長年の夢や希望が叶った」という気持ちと、「これから大丈夫だろうか」という気持ちが入り混じっているのではないでしょうか。
特に後者の「これから大丈夫だろうか」は、「起業して無事生きていけるか?」とも置き換えることできます。
起業して生きていくためには、黒字化してお金を生み出せば良いわけですが、黒字化に時間がかかり、半年から1年程で廃業というケースが多いのも事実です。
廃業になってしまう理由は、“赤字だから”ではなく、“仕入のため事業資金がなくなり、給与が払えず生活が出来なくなるから”です。
逆を言えば、赤字でもお金さえ底が尽きなければ、廃業する必要はなく、 お金がある間に、改善を繰り返し黒字化できれば生き残ることができます。
“お金がある=黒字化のための立て直しの時間的猶予がある”ということになるので、追い込まれる前に余裕資金を調達しておく必要が出てきます。
ですので、会社設立と同時に創業融資による資金調達をすることをおすすめします。
会社設立と創業融資の基本
・会社設立の手順と必要な資料
【手順1】会社名・本店所在地・資本金・決算月などの基本設計を行います。
商号=会社名を決める
商号を決め、法務局で商号調査し会社の商号が決まると、同じ名前の法人が、同一の住所に存在しないか確認します。法人の名前が商標登録されたものであるか、どうかも調べたほうがよいでしょう。商標権の侵害となると商標使用差し止めや、損害賠償の請求対象になるかもしれません。
商号=会社名が決まったら、次は資本金を決める必要があります。
資本金は多すぎると1期目から消費税が出たり、少なすぎると取引相手の会社から心配されるなどメリット・デメリットがあります。
資本投入しても会社で自由にお金は使えますから、会社に投入できる最大限の資本金を推奨します。ただし、1,000万以上にしてしまうと1期目から消費税の申告納税の義務が出てきますので、注意しましょう!!
商号=会社名、資本金が決まったら、次は決算月を決めることになります。
こちらは繁忙期ではなく、閑散期がおすすめです。繁忙期にすると稼いだ利益に節税対策する前に決算・締めがきて、税金がかかってしまうからです。
逆に閑散期だと繁忙期に稼いだ利益にじっくりと節税対策を行えます。
【手順2】個人の印鑑登録・会社実印の作成・登録
法人の重要事項を定めた契約書などに捺印するための代表印(実印)を作成し登録します。一般的に、代表印と別にリスクを分散するために、金融機関用の銀行印を作成することが多いです。法人であれば登記と同時に法務局に「印鑑届出書」を提出して登録します。
【手順3】定款を作成する
定款とは法人運営に関するルールです。
こちらは上記で決めた会社名・資本金・本店所在地・決算月など基本設計を文書に落とし込んだものです。
【手順4】定款の認証
定款の認証は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱います
紙の定款の認証に必要なもの
・定款3通
・実質的支配者となるべき者の申告書
・委任状(定款の認証手続きを代理人依頼の場合)
・発起人全員分の印鑑証明書
・定款を受け取りに行く方の印鑑
・定款を受け取りに行く方の身分証明書
・収入印紙代(4万円) 電子定款の場合は無し
・認証手数料(約3万~5万円)
・その他、公証人から指示されたもの
なお、電子定款の時は電子データなので課税文書には該当せず、印紙税は発生しません。
【手順5】資本金の払い込み
定款認証が終わり次第、資本金を払い込みます。振込みがされた口座の通帳コピーを添付して登記申請することになります。
ちなみに金銭以外の出資を現物出資といいますが、それが500万円を超えると、検査役による現物出資財産の調査が必要となります。
現物出資は、調査に時間を要することになるので、多額の現物出資はおすすめできません。
【手順6】登記申請をする
本店の所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に、申請書および添付書類一式を提出します。郵送による申請も可能ですが、慣れていない人は、窓口で申請するほうが確実です。
以上が株式会社や合同会社設立までの流れです。
【 登記完了で 】めでたく会社が出来上がります!
創業融資の種類と利用条件
これから会社設立をしたい方で、重要なことは、上述した通り【起業時のお金】の準備です。全額自己資金で起業される方は一部で、多くの方は、創業融資を利用されます。
そして創業融資のうち主要な資金調達方法としては、
【1 日本政策金融公庫の創業融資】
【2 各自治体の制度融資】 の大きく2つがございます。
【2 各自治体の制度融資】 は、各自治体により要件が異なるため、今回は省略致しますが、基本的な考え方は日本政策金融公庫の創業融資制度と概ね同様となります。
日本政策金融公庫の創業融資である新規開業・スタートアップ支援資金の条件では、
【新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方で、
新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。】
となっております。
言い換えれば無事に利益を出してお金を返せる方ともいう事ができます。
それでは実際の現場では、どのようにして判断されるかといいますと、まず自己資金の金額が確認されます。これは起業までにどれだけ準備をしてきたかを計数化した重要な要素のひとつです。
要件には自己資金が全体資金の何割と規定されていませんが、日本政策金融公庫総合研究所の「新規開業実態調査」のデータによると、創業資金調達総額に占める自己資金の割合は24%となっています。したがって、最低限これだけは確保しておいた方がよろしいと読むこともできます。
また、ここで気を付けたいのがいずれも 「自己資金というお金さえあれば良い」というわけではなく、その自己資金(貯金)を、どのような過程を踏まえて貯められたのかも重要です。
コツコツと夢に向かって努力(貯金)された方は、しっかりと期限までに返済できると、日本政策金融公庫など各金融機関の創業融資でも評価されます。
反対に、一例として、お金があっても競馬で得たお金など自分で貯蓄したお金でないと金融機関からの評価は悪くなります。過去に返済が滞っている場合は難しくなります。この確認のプロセスとして通帳の半年分の動きが確認されます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り2636文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -
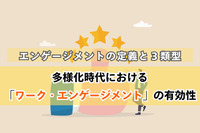
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
ニュース -
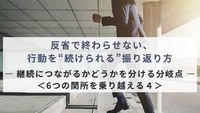
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>
ニュース -

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
ニュース -

事業用不動産のコスト削減ガイド
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
ニュース -
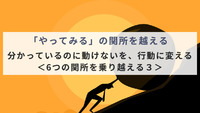
「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>
ニュース