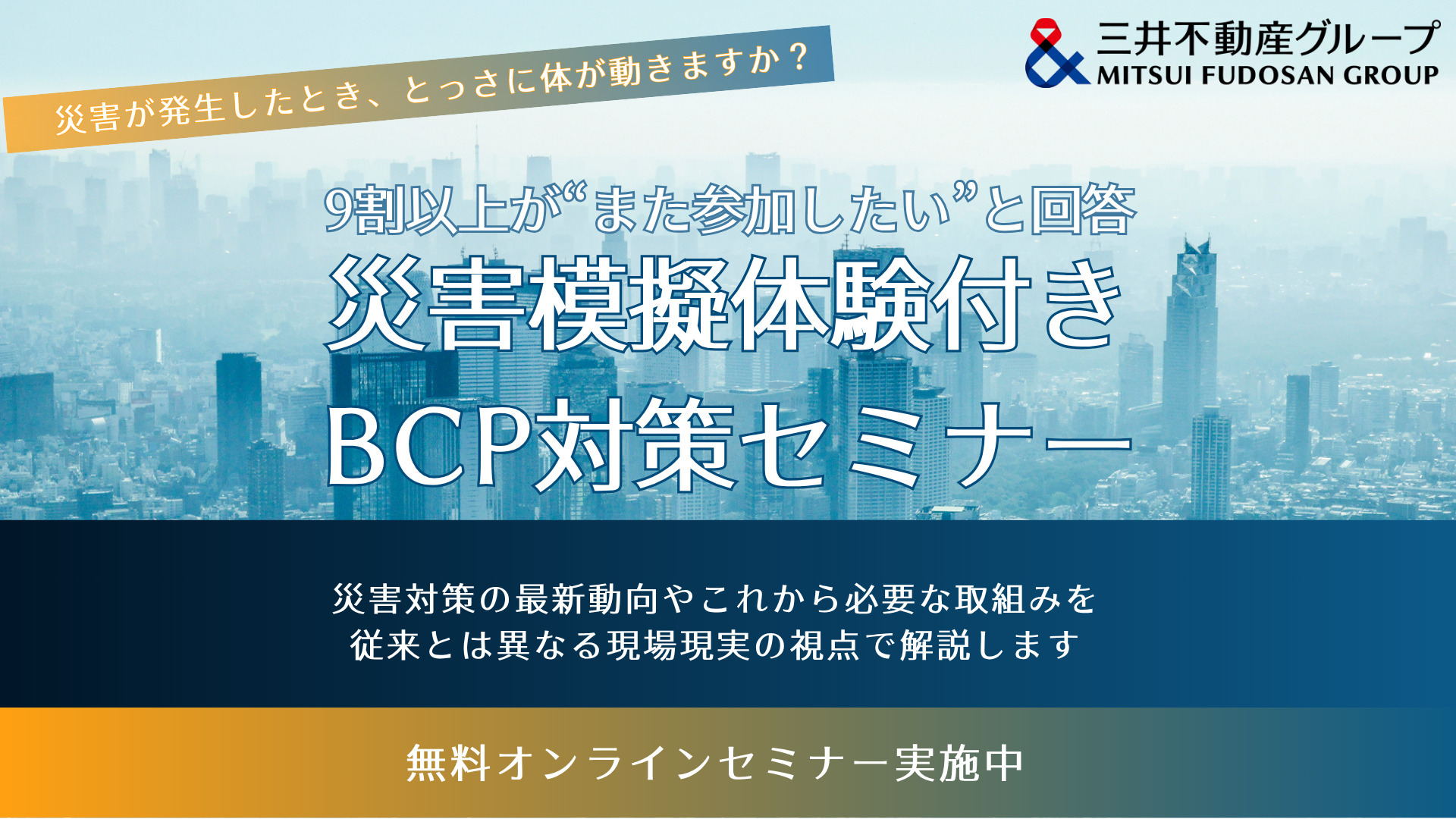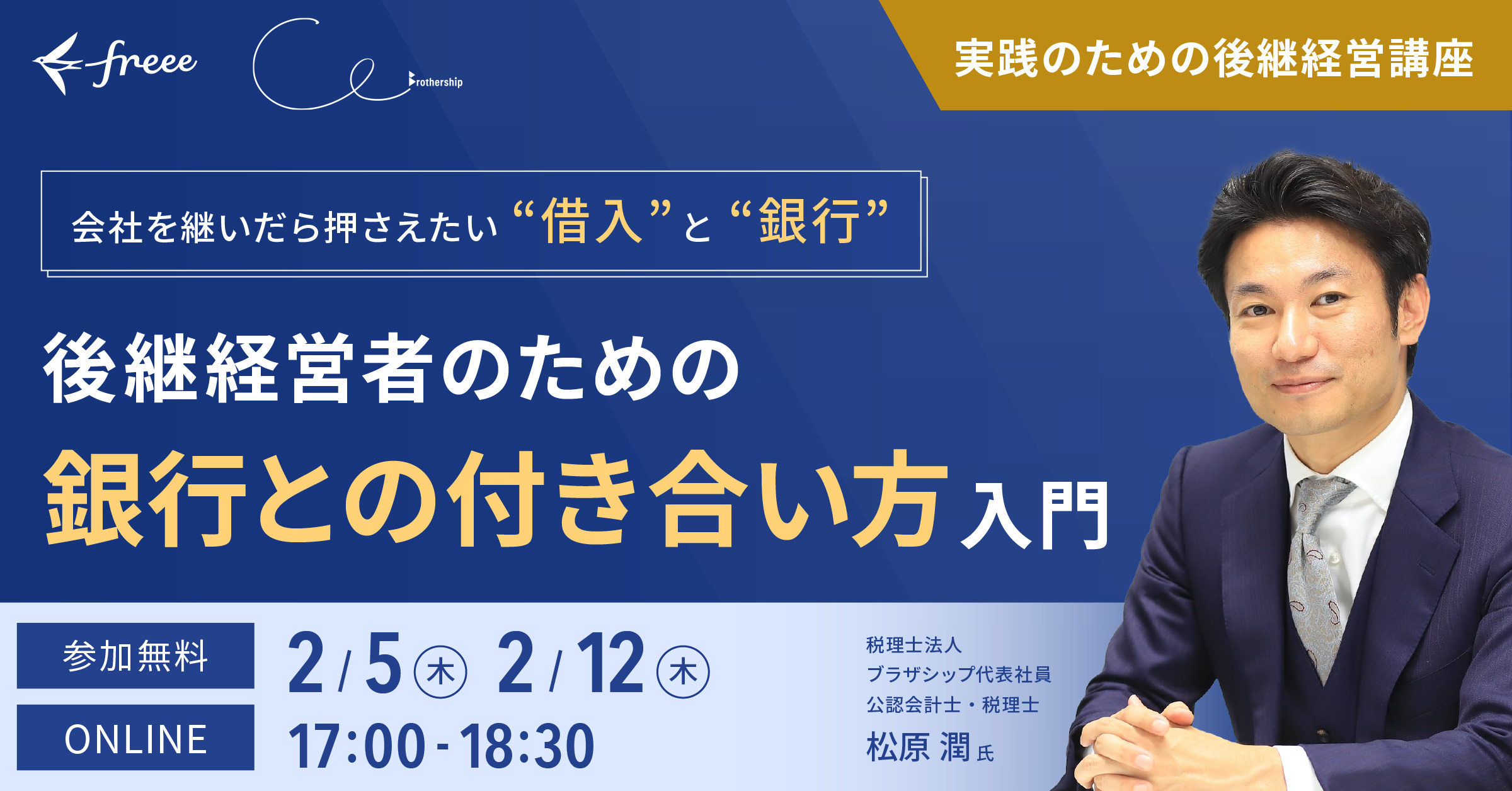公開日 /-create_datetime-/
2026年卒の新卒採用スタート!早期内定獲得に向けたスケジュール管理とは?
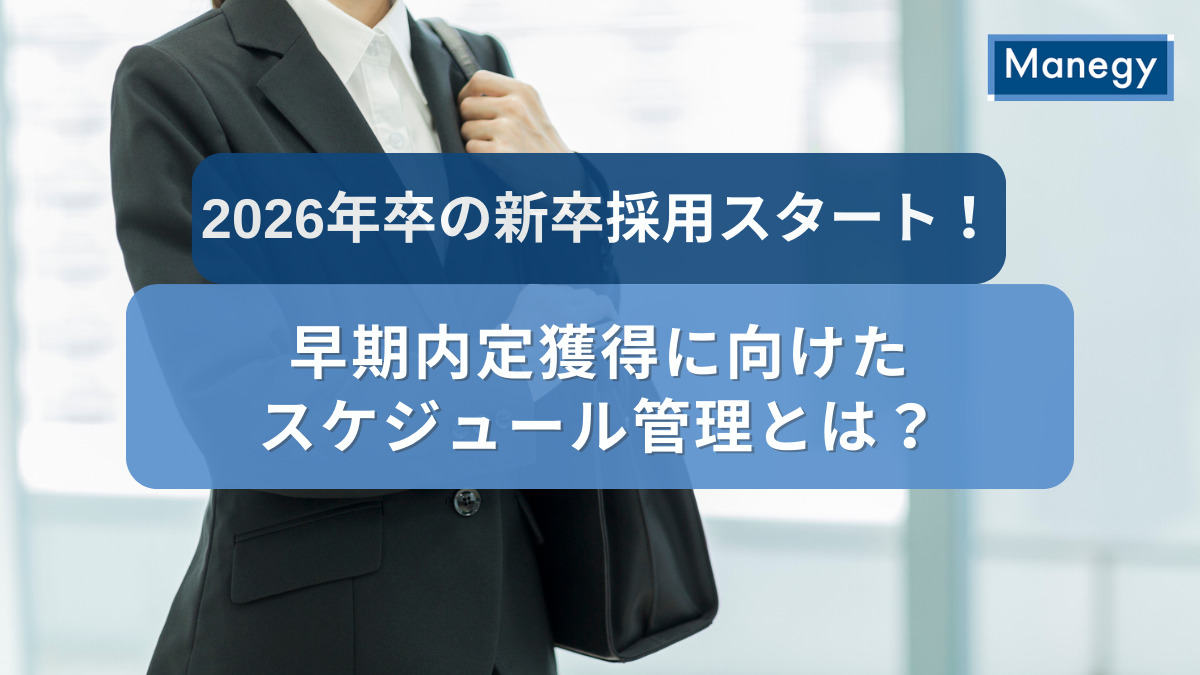
3月からは2026年卒採用の広報活動が解禁され、企業説明会も本格化します。必要な人材を確保するためには、早期内定獲得に向けて早めにスタートを切らなければなりません。それにはどのような採用計画を立てればよいのか、ここから2026年卒採用の最新トレンドについて解説します。
学生側から見た就職活動
学生の就職活動(就活)は、以前よりも開始時期が早まる傾向にあります。就職支援サービスのデータによれば、2026年卒の学生は2024年の6~9月に就活を始めているようです。企業のインターンシップが、この時期に設定されていることも大きく影響しています。
学生たちは主に卒業前々年夏のインターンシップに参加し、業界・企業・業務内容などについての情報収集と分析を始めます。その後就職説明会などを経て、卒業前年の6月には内々定を得ているなど、就活のプロセス自体が早期化しています。
2026年卒の採用スケジュール
2026年卒の採用活動日程は、政府の関係省庁によって以下のように決定されました。
・広報活動開始:2025年3月1日以降
・選考活動開始:2025年6月1日以降
・正式内定日:2025年10月1日以降
出典:「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」厚生労働省
しかしこれらの日程はあくまでも原則です。現在は多くの企業が、独自のスケジュールで採用活動を進めるようになっています。3月以降の流れをまとめてみましょう。
①3月~企業説明会の開催
単独・合同を問わず、企業説明会は例年3月に最も多く開催されます。最近では業種や採用対象者など、ターゲットを絞った合同説明会も増えているようです。また、6月スタートが原則の面接についても、この時期に始める企業が増加しています。
②6月~選考スタート
近年は採用活動の前倒しにより、この時期には複数の内々定を得ている学生が増えています。そのため、最終的に学生がどこを選ぶのかはまだわかりません。企業側にはインターンシップ体験者へのアプローチや、面接を拡充して採用につなげる努力が求められます。同時に内定辞退を防ぐ対策も必要になるでしょう。
③10月~内定者のフォロー
内定者研修や社員との交流会などを通じて、内定者が抱く不安を解消する時期です。最近の若い世代は、具体的な業務内容や基本的なビジネスマナーなど、仕事に直結する研修内容を望んでいます。こうした期待に応えながら、定期的に連絡をとるなどのフォローも必要です。
企業は長期計画と早めの行動が必要
新卒採用活動は、卒業の前々年に始まる傾向が強まっています。夏のインターンシップがその第1ステップですが、対象学年を設定しないオープン・カンパニーという説明会兼イベントなどにより、さらに活動を早める企業も現れています。
早いほど有利とはいえませんが、採用計画は長期的視点から策定し、それぞれの時期の要になる活動を効果的に設定する必要があるでしょう。人事部の経験による採用活動と同時に、採用ツールを検討することもおすすめします。
まとめ
人材確保が厳しさを増す中で、企業は独自の戦略により新卒者にアプローチしなければなりません。ただし、効果的な採用活動は多くの企業が試しており、活動時期を早める策にも限界があります。企業に求められるのは就活する者の立場を理解しながら、試行錯誤を重ねることではないでしょうか。
参考サイト)
「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」厚生労働省
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
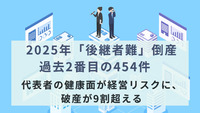
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える
ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
ニュース -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
ニュース -

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース