公開日 /-create_datetime-/
管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!
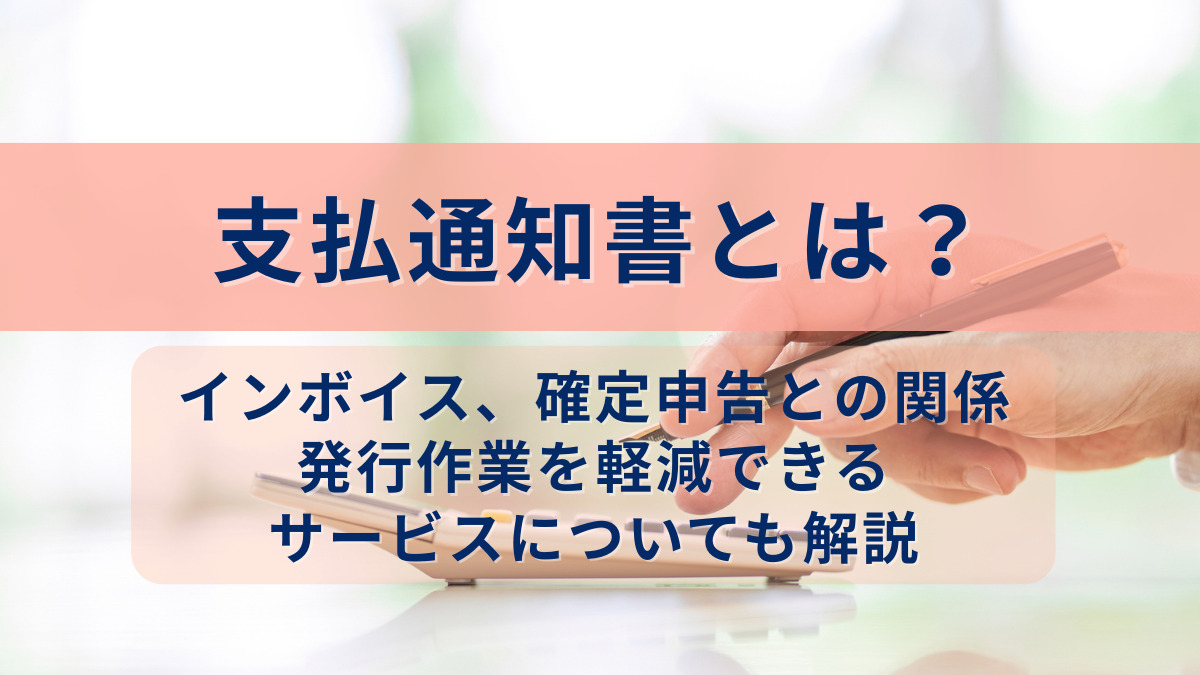
支払通知書は、企業間もしくは企業と個人事業主との間で行われる商取引の「支払業務」において作成される書類です。
ビジネスシーンではよく見る書類の1つですが、発行義務はあるのか、発行したら保存義務はあるのか、作成する場合にどのような形式にする必要があるのかなど、細かい点についてはご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、支払通知書とは何かについて、インボイスや確定申告との関連性も含めて詳しく解説します。
支払通知書とは、買い手側(発注者)が売り手側(受注者)に対して発行する、「支払内容を通知するための文書」です。
この書類には法的な発行義務や書式の規定はありませんが、商取引における商慣行として広く利用されています。
支払通知書は「証憑書類」として扱われるため、裁判など公的な場でも、取引内容を証明する書類として有効性を持つ可能性があります。
証憑としての効力を持たせるためには、以下の情報を支払通知書に明記する必要があります。
・書類のタイトルとして「支払通知書」と明記されていること
・発行年月日
・発行者(法人名や氏名)と連絡先
・宛先(取引先法人名または個人名)
・支払予定金額
・取引日
・取引の簡潔な内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨も記載)
・商品・サービスの単価と数量
・消費税率ごとの小計、本体価格・税額の内訳
・合計(税込金額)
・備考欄(必要に応じて)
企業が発行義務のない支払通知書を送付する背景には、取引の証拠となる文書としての役割を果たすという目的があります。
上記の項目に不備があると、証憑としての要件を満たさなくなるため、記載漏れがあれば再発行されるのが通常です。
支払通知書に関する実務上のポイントとして、最低限おさえておきたい事項は次のとおりです。
支払通知書は古くからの商慣行として用いられている書類であり、法律上で発行が義務付けられているわけではありません。
発行の有無は、取引契約書や各社の社内規定に準じて判断されます。
一度発行された支払通知書は、「証憑書類」として法的な保存義務が発生します。
保存期間は発行主体によって異なります。
・法人の場合:法人税法により、保存期間は7年間。
・個人事業主の場合:所得税法により5年間。ただし、消費税法上では7年間の保存が求められるため、両方を意識する必要があります。
また、支払通知書を電子データとして受領した場合は、電子帳簿保存法が適用されます。
この場合も保存期間そのものは変わりませんが、改ざん防止措置や検索機能の確保など、所定の保存要件を満たす必要があります。
保存期間のカウントは、支払通知書の発行日または受領日を起点とし、以下のとおりとなります。
・法人:7年後の法人税申告期限まで
・個人事業主:5年後の確定申告期限まで
インボイスとは適格請求書とも呼ばれ、仕入税額控除が認められる請求書のことです。
支払通知書は条件を満たせば適格請求書にもなりますが、そのために以下の内容を記載する必要があります。
・支払通知書の宛先(売り手側)である「課税仕入れの相手方」の登録番号を記載
・税率ごとに分けて合計した税抜きの支払額
・適用税率・税率ごとに分けた消費税額
・税率ごとに税抜き支払額、消費税額の総計を提示して、税込みの総計を記載
適格請求書になるように支払通知書を発行すれば、買い手側(発注者側)において仕入れ税額控除が認可されます。
支払通知書は法的に発行が義務付けられている書類ではなく、確定申告で提出する必要のない書類です。
個人事業主の場合、事業収入から事業上で発生した必要経費を差し引いた事業所得の申請が必要です。
その際、収入総額の確認のため、支払通知書が必要になる場合は考えられますが、確定申告においてはそれ以上の役割はもたない書類となります。
なお確認事項として、株式関連の収益については、2019年度までは所得税申告の際、「オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書」「配当等とみなされる金額の支払通知書」「上場株式配当等の支払通知書」「特定割引債の償還金の支払通知書」などの添付が必要でした。
しかし、国税関係手続の簡素化を目的とした税制改正によって、2019年度以降に提出する書類については、これらの添付は不要になりました。
2025年現在、支払通知書は株による収益に関する確定申告においても、提出不要の書類となっています。
支払通知書の発行作業をサポートしてくれるBtoBサービスもあります。
支払通知書も含めた「見積・請求書発行システム」のサービスを利用することで、経理関連の書類発行の負担を大きく軽減できます。
発行所類の追跡、管理が容易になり、出金・入金の確認作業の負担軽減、電子帳簿保存法の要件を満たす証憑保存も可能です。
支払通知書は法的な発行義務はないものの、商取引の事実を証明できる証憑書類であり、取引相手に必ず送付するのが通例です。
請求書としても利用でき、インボイス対応の形での作成・発行もできます。
もし発行した場合は、証憑書類となる重大性により、法律上の保存期間を厳守する必要があります。
自社での効率的な作成・発行・保存が大変なときは、外部事業者による見積・請求書発行システムを導入するのも有効な方法です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

英文契約書のリーガルチェックについて

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
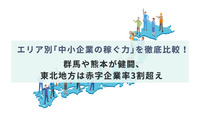
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
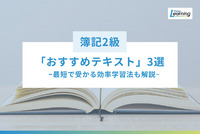
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説

レンタル料の勘定科目の考え方|賃借料・地代家賃・雑費の使い分けと仕訳例

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

経理業務におけるスキャン代行活用事例

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
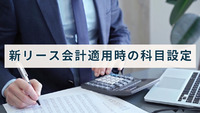
新リース会計適用時の科目設定

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
公開日 /-create_datetime-/