公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
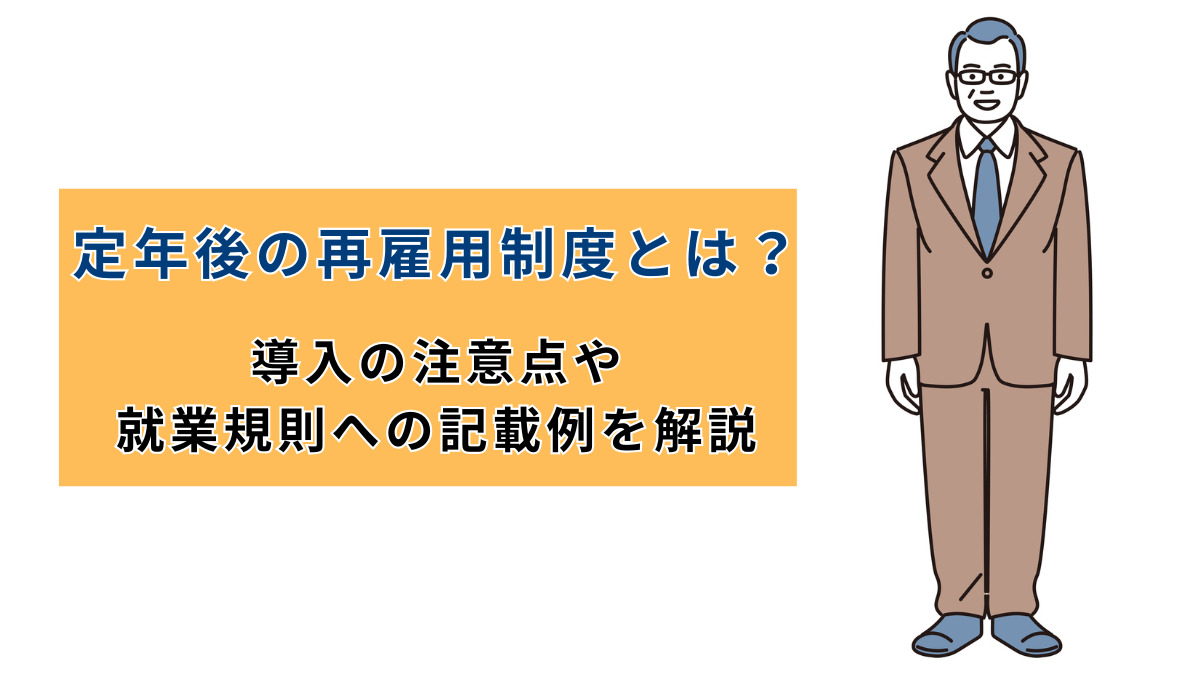
社会保険労務士の玉上 信明(たまがみ のぶあき)です。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するためには、働く意欲がある人が、誰でも年齢にかかわりなく、能力を十分発揮できる環境を整える必要があります。「高年齢者雇用安定法」はそのための法律です。
「再雇用制度」が一つの選択肢として定められていますが、実際には高齢者雇用として一番広く用いられている制度です。
今回は、この「再雇用制度」について、制度の内容、制度設計・契約時のポイント、導入のメリットや注意点について解説します。
はじめに、高齢者雇用の基本法である「高年齢者雇用安定法」(以下「法」)の全体像に簡単に触れます。「65歳までの雇用確保義務」「70歳までの就業機会確保の努力義務」という2段構えになっています。
本稿では65歳までの「継続雇用制度」のなかの「再雇用制度」について解説しますが、将来的にさらに適用対象年齢が引き上げられる等の可能性も考えておく必要があります。
この法律は頻繁に改正が行われており、今後も改正がありうるでしょう。事業者としても、制度全体の現在の姿のみならず、進んでいる方向を見定めておくことが望まれます。
事業主は、希望する従業員全員に対し、65歳までは就労の機会を与えることが義務付けられています。この「就労の機会」というのは、自社で継続的に働く他に、グループ会社などで働くことも認められます。具体的内容は以下の通りです。
60歳未満の定年は禁止(法第8条)
事業主が定年を定める場合には、定年年齢は60歳以上としなければなりません。
65歳までの雇用確保措置義務(法第9条)
定年を65歳未満としている事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません(高年齢者雇用確保措置)。
1.65歳までの定年引き上げ あるいは定年制の廃止
2.65歳までの「継続雇用制度」(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
「継続雇用制度」の適用者は原則として「希望者全員」です。過去の労使協定により、制度の対象者を一定の範囲で限定することも認められていましたが、これは2025年3月31日までの経過措置です。
記事提供元
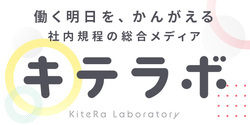
企業のバックオフィスを支える人事・労務の皆さんに向けて、社内規程に関する最新情報や役立つ知識をお届けします。
法改正やトレンド、実務に役立つヒントを分かりやすく解説し、専門家の知恵とアドバイスを通じて、未来の働き方を共に考えるメディアです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

経理業務におけるスキャン代行活用事例

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

サーベイツールを徹底比較!

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

ラフールサーベイ導入事例集

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
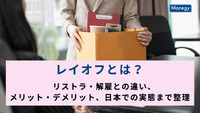
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
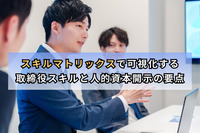
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
公開日 /-create_datetime-/