公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

経理の現場で必ず向き合うことになる「総勘定元帳」の管理と運用は、多くの実務担当者にとって重要な業務です。
この記事では、総勘定元帳の基本的概念から実務的な書き方・読み方、法令に基づく保存義務、そして財務諸表作成への活用方法まで、実務に直結する知識を包括的に解説します。
「仕訳帳」と「総勘定元帳」、この二つの言葉は、会計の世界では切っても切れない関係にあります。
同じ「帳簿」でありながら、その性格は大きく異なります。
まずはこの二つの違いを見ていきましょう。
会計初心者が最初につまずくのが、「仕訳帳」と「総勘定元帳」の違いです。
両者は同じ取引データを扱いながらも、全く異なる視点で情報を整理します。
仕訳帳が「時系列の日記」だとすれば、総勘定元帳は「項目別の書類棚」と考えるとわかりやすいでしょう。
| 比較項目 | 仕訳帳 | 総勘定元帳 |
|---|---|---|
| 記録方法 | 時系列(日付順) | 勘定科目別 |
| 目的 | 取引の一次記録 | 勘定科目ごとの集計 |
| 形式 | 日付・借方・貸方・摘要 | 借方・貸方の二欄式または残高式 |
| 役割 | 取引の網羅性確保 | 勘定科目ごとの残高管理 |
| イメージ | 日記帳 | ファイリングキャビネット |
この流れの中で、仕訳帳は「情報の入口」、総勘定元帳は「情報の整理庫」としての役割を担っています。
どちらが欠けても、正確な財務情報は得られません。
仕訳帳から総勘定元帳への転記は会計処理の基本的なフローであり、この作業を「転記(posting)」と呼びます。
転記の基本的な流れは以下の通りです。
1. 仕訳帳に取引を記録(日付、借方科目、貸方科目、金額、摘要)
2. 借方科目の総勘定元帳ページを開く
3. 借方金額を借方欄に転記し、相手科目(貸方科目)を記録
4. 貸方科目の総勘定元帳ページを開く
5. 貸方金額を貸方欄に転記し、相手科目(借方科目)を記録
6. 各元帳ページの残高を更新

転記作業は、料理で例えるなら「食材の仕分け」のようなものです。
まず仕訳帳では、全ての食材(取引)を買ってきた順番(時系列)でテーブルに並べます。
次に総勘定元帳では、それらの食材を種類別(肉、野菜、調味料など=勘定科目別)に分けて整理するのです。
仕訳帳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 |
【現金】勘定元帳
| 日付 | 相手勘定科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〇〇/〇/〇 | 売上 | 〇〇 | 10,000円 | 10,000円 |
【売上】勘定元帳
| 日付 | 相手勘定科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20〇〇/〇/〇 | 現金 | 〇 | 〇 | 10,000円 | 10,000円 |
会計システムには、総勘定元帳以外にもさまざまな種類の元帳が存在します。
特に重要なのが「補助元帳」です。
会計帳簿の世界は、実は階層構造を持つ家族のようなものです。
総勘定元帳が「親」なら、補助元帳は「子」の関係にあります。
総勘定元帳は、すべての勘定科目の残高と変動を記録する「主要な帳簿」です。
一方、取引量が多い勘定科目や、より詳細な管理が必要な勘定科目については、総勘定元帳とは別に「補助元帳」を設けることがあります。
補助元帳の例としては以下のようなものがあります。


総勘定元帳と補助元帳の関係は、スマートフォンのアプリとフォルダの関係に似ています。
スマホの画面(総勘定元帳)には「写真」というアイコン一つが表示されていますが、そのフォルダを開くと(補助元帳)、何百、何千もの個別の写真(詳細データ)が保存されているのです。
総勘定元帳は、会計の言語で書かれた「物語」です。
その物語を正しく書き、正確に読むためのスキルを身につけましょう。
総勘定元帳のフォーマットには主に「標準式」と「残高式」の2種類があります。
これは同じ情報を記録するための異なる「方言」と考えることができます。
標準式は最もシンプルなフォーマットで、以下の欄で構成されています。
【現金】勘定(標準式)
| 日付 | 摘要 | 相手科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 前月繰越 | 100,000 | ||
| 4/2 | 文房具費 | 文房具費 | 5,000 | |
| 4/3 | 売上 | 売上 | 30,000 |
残高式は日本で広く使われているフォーマットで、標準式に「残高欄」が追加されたものです。
【現金】勘定(残高式)
| 日付 | 摘要 | 相手科目 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 前月繰越 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4/2 | 文房具費 | 文房具費 | 5,000 | 95,000 | |
| 4/3 | 売上 | 売上 | 30,000 | 125,000 |
借方と貸方の概念は、会計初心者にとって最大の難関かもしれません。
簡単に言えば、「借方(左側)」はお金や価値が「入ってくる側」、「貸方(右側)」はお金や価値が「出ていく側」と考えるとわかりやすいでしょう。
たとえば、あなたの財布(現金勘定)の場合、
「借りる」「貸す」という言葉とは異なる意味を持つため、初めは「左側記入」「右側記入」と覚えるのも一つの方法です。
英語では "Debit on the Left, Credit on the Right" という覚え方もあります。
勘定科目一覧(Chart of Accounts)は、企業が会計処理に使用する勘定科目を体系的にまとめたリストです。
この一覧は企業ごとにカスタマイズ可能で、業種や規模によって適切な科目設計が異なります。
勘定科目は、料理のレシピにおける材料リストのようなものです。
基本的な材料(基本勘定科目)は共通していますが、その企業の「味」(業種や取引内容)に合わせて、オリジナルの材料(独自勘定科目)を追加することができます。
▶勘定科目を一覧表で解説!経費の科目や経理に役立つ仕訳のコツも紹介
1. 資産の部:現金、預金、売掛金、棚卸資産、固定資産など
2. 負債の部:買掛金、短期借入金、長期借入金、未払金など
3. 純資産の部:資本金、資本準備金、利益剰余金など
4. 収益の部:売上高、受取利息、雑収入など
5. 費用の部:仕入高、販売費、一般管理費、支払利息など
freeeの基本勘定科目例
クラウド会計ソフトを使うメリットの一つは、業種に合わせたテンプレートが用意されていることです。
初期設定の科目をそのまま使いながら、必要に応じて追加・変更していくとよいでしょう。
▶経費精算システム |比較前に知っておきたい基礎情報とおすすめサービス13選
総勘定元帳における残高の見方は、勘定科目の種類によって異なります。
基本的なルールを理解しましょう。
【現金勘定】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 4/1 入金 | 100,000 | 4/2 出金 | 30,000 |
| 4/3 入金 | 50,000 | 4/4 出金 | 10,000 |
| 合計 | 150,000 | 合計 | 40,000 |
⇒ 差引残高:110,000(借方残高=現金が残っている)
この例では、現金の借方合計が150,000円、貸方合計が40,000円で、差引すると110,000円の借方残高となります。
これは現金が110,000円あることを意味します。
勘定科目がその性質と逆の残高になる(例:資産科目が貸方残高になる)ことを「マイナス残高」や「逆残」と呼びます。
マイナス残高が発生した場合は、以下の原因が考えられます。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| 記帳ミス (金額や借貸の記入誤り) |
元帳・仕訳帳を照合し、訂正仕訳を入れる |
| 転記漏れ | 仕訳帳と照合し、漏れた転記を行う |
| 取引記録の漏れ | 証憑書類を確認し、漏れた取引を記録 |
| 相手勘定科目の誤り | 取引内容を再確認し、修正仕訳を入れる |

マイナス残高は、会計の「警告灯」と考えると良いでしょう。
車のダッシュボードに赤いランプがついたら点検が必要なように、マイナス残高が出たら記帳内容の点検が必要です。
放置すると決算時に大きな問題になる可能性があります。
総勘定元帳は「情報の倉庫」ですが、その情報を活用して初めて経営に役立ちます。
試算表は、その第一歩となる重要なツールです。
試算表は、総勘定元帳の各勘定科目の残高を一覧表にまとめたものです。
これは、家計簿でいえば「月末の収支まとめ」に相当します。

総勘定元帳が「詳細なレシート」なら、試算表は「ひと目でわかる家計の状況」です。
経営者にとっては、毎月の財務状況を素早く把握するための「ダッシュボード」の役割を果たします。
試算表は「合計試算表」と「残高試算表」の2種類があります。
| 合計試算表 | 残高試算表 |
|---|---|
| 各勘定科目の借方合計額と貸方合計額を表示 | 各勘定科目の期末残高のみを表示 |
試算表の最大の特徴は、借方合計と貸方合計が一致するという点です。
これは「複式簿記の自己検証機能」とも呼ばれ、記帳が正確に行われているかをチェックする重要な指標となります。
借方合計 ≠ 貸方合計 の場合は、どこかに記帳ミスがあることを意味します。
これは、方程式の左右が等しくならない状態と同じで、解が合っていないことを示しています。
試算表をエクセルで作成する基本的な手順は以下の通りです。
1. 総勘定元帳の各勘定科目の残高を集計する
2. エクセルシートに勘定科目を列挙する
3. 借方残高または貸方残高を適切な列に入力する
4. 借方合計と貸方合計を計算し、一致するか確認する
5. 差異がある場合は原因を調査し、修正する
試算表作成時には、次のようなチェックポイントを設けると、記帳ミスの早期発見につながります。
こうしたチェックを月次で実施することで、年度末の決算作業が格段に楽になります。
これは毎日の掃除と大掃除の関係に似ています。
毎日少しずつ整理しておけば、年末の大掃除はスムーズに進みます。
財務諸表作成の基本的なフローは、「総勘定元帳→試算表→財務諸表(貸借対照表・損益計算書)」という3ステップです。
財務諸表作成の流れは、料理に例えると分かりやすいでしょう。
この3つのステップは、それぞれが次のステップの基礎となります。
基礎がしっかりしていなければ、その上に立つ構造物も不安定になってしまいます。
ステップ1: 総勘定元帳の集計
ステップ2: 試算表の作成
ステップ3: 財務諸表の作成
この一連の流れを毎月のルーティンとして定着させることで、以下のメリットが得られます。
これを「経理の時間」として確保し、毎月のルーティンワークにすることで、年度末の決算に追われるストレスから解放されます。
さらに、月次での経営判断が可能になり、問題の早期発見・対応につながります。
総勘定元帳は単なる記録ではなく、法的な証拠書類でもあります。
適切な保存と管理は、法令遵守の観点からも非常に重要です。
会計帳簿類には法律で定められた保存期間があり、その期間内は適切に保管する義務があります。
主な帳簿の保存期間は以下の通りです。
| 帳簿・書類の種類 | 法人税法上の 保存期間 |
消費税法上の 保存期間 |
|---|---|---|
| 仕訳帳 | 7年 | 7年 |
| 総勘定元帳 | 7年 | 7年 |
| 補助簿 | 7年 | 7年 |
| 決算書類 | 7年 | ー |
| 棚卸表 | 7年 | ー |
| 請求書・領収書等 | 7年 | 7年 |
| 契約書 | 重要なものは 10年 |
ー |
帳簿書類を保存期間内に破棄したり、改ざんしたりした場合、以下のような罰則が適用される可能性があります。
帳簿の保存方法には、「紙保存」と「電子保存」があります。
それぞれの特徴を理解し、自社に適した方法を選択しましょう。
紙保存のメリット・デメリット
電子保存のメリット・デメリット
電子帳簿保存法は近年大きく改正され、企業の電子化対応を促進する方向に進んでいます。
特に2022年以降の改正では、これまでの厳格な要件が緩和されました。
1. 電子取引データの電子保存義務化
2. 電子帳簿等保存の要件緩和
3. スキャナ保存制度の要件緩和
電子帳簿保存法に対応するには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
特に注意すべきは「タイムスタンプ」です。
これは電子データの存在時刻と非改ざん性を証明する電子的な印のようなもので、第三者機関によって発行されます。
クラウド会計ソフトを利用すれば、こうした機能が自動的に組み込まれていることが多いため、導入を検討する価値があります。
▶【2025年最新】電子帳簿保存法とは?2024年1月~「電子取引のデータ保存」は完全義務化に!
税務調査に備えて、総勘定元帳をはじめとする帳簿類は適切に管理しておく必要があります。
以下は税務調査での指摘事例と対策です。
事例1:
電子データと紙の不一致 あるコンビニオーナーAさんは、日中はPOSシステムで売上データを管理し、夜に手書きの総勘定元帳に転記していました。
しかし、一部の現金売上がPOSシステムに入力されず、元帳にだけ記載されていたことが税務調査で発覚。
記録の不一致として指摘を受け、追徴課税となりました。
事例2:
保存期間不足による否認 製造業のB社が5年前の固定資産の減価償却費について税務署から質問を受けましたが、「5年以上経過した帳簿は破棄した」として提出できませんでした。
結果、その減価償却費が否認され、追加納税となりました。
事例3:
バックアップなしでのデータ消失 IT企業のC社がハードディスクの故障により前年度の電子帳簿データをすべて喪失。
バックアップも取っていなかったため、税務調査において取引の実在性を証明できず、多額の追徴課税を受けました。
1. データバックアップの二重化
2. 検索性の高いファイル管理
3. 証憑書類との紐づけ
4. 電子データの真実性確保
▶税務調査のチェックポイント8選|事前対策と調査官が狙うポイントを完全解説!
どんなに経験豊富な経理担当者でも、ミスはつきものです。
しかし、適切なチェック体制を整えることで、多くのミスは未然に防ぐことができます。
会計処理における主なエラーとその防止策は以下の通りです。
| エラー内容 | 説明 | 防止策 |
|---|---|---|
| 二重計上 | 同一取引を複数回記帳してしまうミス 例:請求書と領収書の両方で計上 |
・証憑書類に「記帳済」のスタンプを押す ・取引番号を採番して管理する ・月末に取引リストで重複チェック |
| 転記漏れ | 仕訳帳から元帳への転記を忘れるミス | ・仕訳帳の各行に「転記済」の印をつける ・月末に転記済チェック欄で確認 ・自動転記機能のあるソフトを使用 |
| 期ズレ | 取引発生時期と記帳時期がずれるミス 月末や年度末の取引で発生しやすい |
・取引発生日と入力日を区別する ・月末・期末の取引は特に注意 ・定期的な取引は自動転記設定 |
| 勘定科目誤り | 類似科目の混同、理解不足によるミス | ・勘定科目一覧表の常備 ・定期的な科目運用ルールの確認 ・よくある取引のテンプレート化 |
| 金額誤り | 入力ミス、計算ミスによる誤り | ・ダブルチェック体制の構築 ・大きな金額は特に注意して確認 ・電卓の印字結果保管 |
相手勘定科目とは、取引の相手方となる勘定科目のことで、適切に選択することが正確な会計処理の鍵となります。
会計取引は「お金の流れ」を記録するものです。
そしてお金は必ず「どこかから来て、どこかへ行く」という性質を持っています。
相手勘定科目とは、そのお金の出どころや行き先を示すものです。
例えば、現金で文房具を購入した場合、
この「現金」と「文房具費」が互いの相手勘定になります。
| 取引内容 | 借方科目 | 貸方科目 (相手勘定) |
|---|---|---|
| 現金での 商品販売 |
現金 | 売上 |
| 掛けでの 商品販売 |
売掛金 | 売上 |
| 現金での 商品購入 |
仕入 | 現金 |
| 掛けでの 商品購入 |
仕入 | 買掛金 |
| 売掛金の 回収 |
現金/預金 | 売掛金 |
| 買掛金の 支払 |
買掛金 | 現金/預金 |
| 給料の 支払 |
給料賃金 | 現金/預金 |
| 借入金の 受取 |
現金/預金 | 借入金 |
| 借入金の 返済 |
借入金 | 現金/預金 |
| 家賃の支払 | 地代家賃 | 現金/預金 |
相手勘定科目を選ぶ際のポイントは、「取引の経済的実態」を正確に反映することです。
例えば、同じ「パソコン購入」という取引でも、事務用なら「備品費」、販売用なら「商品」、長期使用目的なら「工具器具備品」と、目的によって適切な科目が異なります。
「残高突合」とは、会計記録と実際の残高を照合することで、記帳の正確性を確認する作業です。
特に重要なのが、預金残高との突合です。
1. データ収集
2. 照合作業
3. 差異分析
4. 調整処理
| 原因 | 例 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 入出金タイミングのズレ | 月末に振り込んだ金額が翌月に口座に反映 | 「未入金」「未引落」として認識し、調整表に記載 |
| 未記帳取引の存在 | 口座引落しが行われたが会計帳簿に記録されていない | 漏れた取引を追加記帳する |
| 記帳ミス(金額・日付・科目) | 実際の入金額と記帳額が異なる | 訂正仕訳を入れる |
| 銀行手数料の未計上 | 振込手数料や口座維持費が未記帳 | 手数料科目で追加記帳する |
残高突合は「会計健康診断」のようなものです。
定期的に行うことで、小さな問題が大きな問題になる前に発見し、修正することができます。
A: 総勘定元帳の英語表記は「General Ledger」です。
読み方は「ジェネラル・レジャー」となります。
国際的なビジネスシーンでもこの表現が一般的に使われています。
A: 仕訳の英語表記は「Journal Entry」です。
また、仕訳帳は「Journal」と呼ばれます。
借方は「Debit」、貸方は「Credit」と表記します。
A: 通常、確定申告時に総勘定元帳を提出する必要はありません。
ただし、税務調査が入った場合には提示を求められることがあるため、適切に保存しておく必要があります。
A: 一概にどちらが優れているとは言えません。
電子帳簿は検索性や保管の効率性に優れ、紙の帳簿は停電などのリスクに強いという特徴があります。
会社の規模や業務フローに合わせて選択するのがベストです。
A: 法律上は、総勘定元帳と仕訳帳の両方を作成・保存する必要があります。
実務上も、仕訳帳は取引の時系列記録として重要な役割を果たすため、省略すべきではありません。
A: 基本的に勘定科目は会社の実態に合わせてカスタマイズ可能です。
ただし、財務諸表の表示区分や税法上の区分に合致するように設計する必要があります。
A: 法律上の義務はありませんが、売掛金や買掛金など、取引先ごとの管理が必要な科目については、補助元帳を作成することが実務上強く推奨されます。
A: 手書きの場合は、間違った箇所に一本線を引き、正しい内容を書いて訂正印を押します。
電子帳簿の場合は、訂正の履歴が残るシステムで修正するか、訂正仕訳を別途起こします。
A: インボイス制度自体は総勘定元帳の記載方法を直接変更するものではありませんが、インボイス番号の管理が必要になるため、取引の摘要欄にインボイス番号を記載するなどの対応が推奨されます。
A: 青色申告で65万円の特別控除を受けたい場合は、複式簿記による記帳が必要です。
白色申告や簡易な青色申告の場合は、単式簿記でも認められています。
ただし、事業の成長や資金調達を考えると、最初から複式簿記で始めることをお勧めします。
総勘定元帳は、企業の財務状況を的確に把握し、税務対応や経営判断を下すために欠かせない帳簿です。
本記事では、仕訳帳との違いや記帳方法から、試算表・財務諸表への連携、電子帳簿保存法への対応まで、実務で必要な知識を体系的に解説しました。
改めて押さえておきたいポイントは、「仕訳帳との違いを理解し、転記フローを正しく構築すること」「残高管理・試算表連携で、毎月の経営数値を可視化すること」「電子帳簿保存法や税務調査に備えた管理体制の整備」の3つです。
会計帳簿は、単なる法的義務ではなく、経営の羅針盤です。
正しく活用することで、ビジネスの航海をより安全に、より効率的に進めることができるでしょう。
今日からでも、この記事で紹介したポイントを一つずつ実践してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
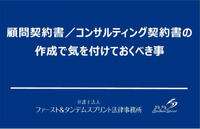
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
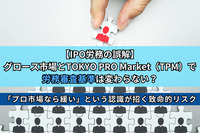
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
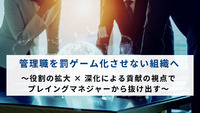
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理

サーベイツールを徹底比較!

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
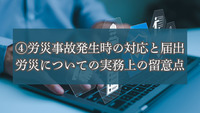
④労災事故発生時の対応と届出│労災についての実務上の留意点
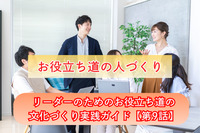
お役立ち道の人づくり/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第9話】

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表
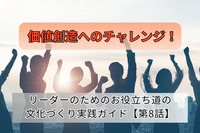
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
公開日 /-create_datetime-/
企業における記帳の流れは、川の流れに例えることができます。
まず、取引という源流から始まり、証憑書類(領収書や請求書)という小川になり、仕訳帳という支流に合流し、最終的に総勘定元帳という大河に流れ込みます。
そして最終的には、試算表や財務諸表という海に注ぐのです。