公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
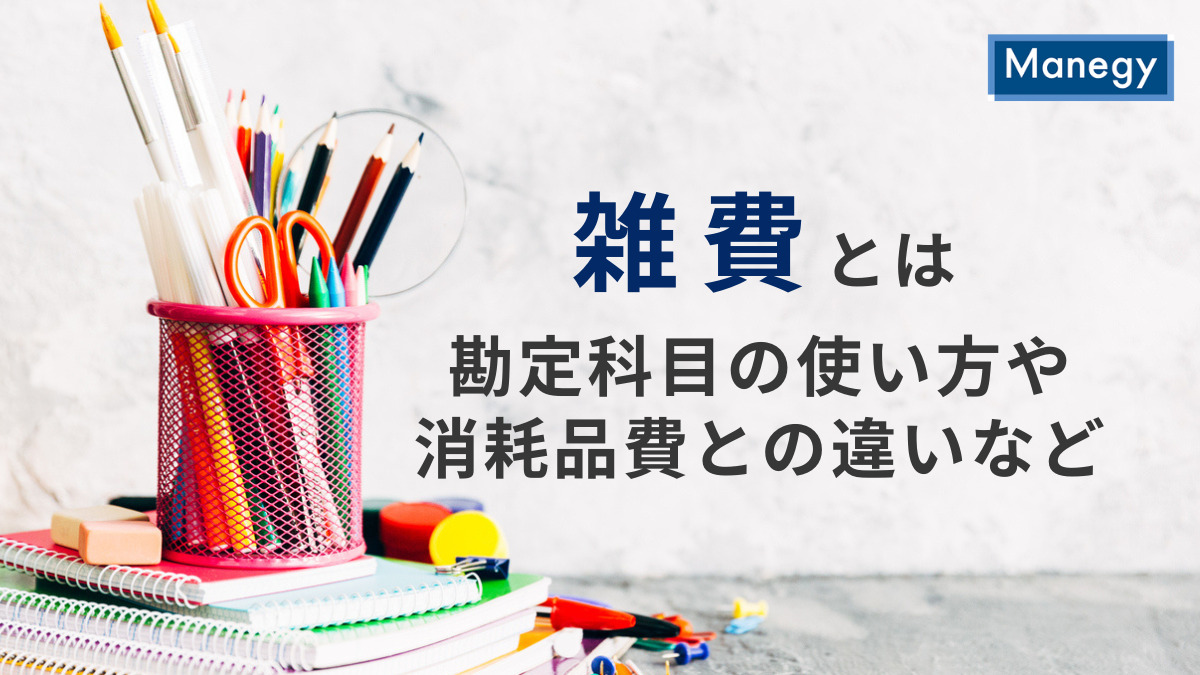
雑費とは、会計上の経費の一種で、他の勘定科目に当てはめにくい少額の支出に使われる項目です。
便利な反面、使い方を誤ると税務リスクや会計の不正確さにつながることもあるため、適切な理解とルール設定が必要です。
この記事では、雑費の定義や具体例、消耗品費や備品との違い、実務での処理の注意点まで幅広く解説します。
雑費は「販売費及び一般管理費(販管費)」に該当する勘定科目で、会計上は費用として扱われます。
他の勘定科目に当てはまらない、継続性のない一時的な支出で、かつ金額が少額であることが目安です。
ただし、本来は他の勘定科目で処理すべき支出まで雑費で処理すると、税務上の問題として指摘されるリスクがあります。
また、財務状況の正確な把握が困難になるため、社内で雑費の定義や処理基準を明確にしておくことが重要です。
以下のような支出は雑費として処理されがちですが、別の勘定科目での仕訳が適切な場合があります。
適切な勘定科目がある場合はそちらを優先し、判断に迷う場合でも金額が小さいことを前提としたルールを設定しておくとよいでしょう。
雑費と重複、もしくは同じように扱われる勘定科目に、消耗品費や備品があります。
こうした科目と雑費との線引きについて考えてみましょう。
消耗品費は、文房具や日用品など使っていくうちに消耗し、補充が必要となるものが該当します。
目安としては、購入金額が10万円未満で、使用期間が1年未満のものです。
雑費も消耗品費も費用として処理されますが、金額が比較的大きいものは消耗品費として仕訳されることが一般的です。
社内で金額や用途に応じた使い分け基準を設けることが有効です。
備品は高額かつ長期間使用する資産で、原則として固定資産に分類されます。
取得価額が10万円以上、または使用期間が1年以上であるものは、耐用年数に基づき減価償却を行う必要があります。
勘定科目の判断がつきにくく、かつ金額が小さい一時的な支出は雑費として処理します。
ただし、消耗品費や備品に該当する場合はそちらを優先すべきです。
勘定科目の判断が難しい場合には、使用目的で仕訳するという方法もあります。
たとえば、パソコン本体は資産になる可能性が高いですが、その周辺機器であるUSBメモリ、マウス、キーボードなどは使用期間が短いと考えられるため、消耗品費が適切でしょう。
また、ノートや文房具などは消耗品費でも扱えますが、本来の使用目的からすれば、事務用品費で仕訳するほうが適切といえます。
ここでは、雑費で仕訳するうえでの注意点を確認しておきましょう。
雑費として計上する金額に上限はありませんが、税務面での適正な範囲と、支出費用を正確に把握することを考慮すると、経費全体の5~10%以内に抑えるのが一般的な目安とされています。
それを超えてしまう場合には、別の勘定科目で仕訳し直すことをおすすめします。
少額の支出をすべて雑費として処理し続けると、経費全体の中で雑費の割合が不自然に高くなってしまうことがあります。
本来なら他の勘定科目にするべきところ、付け替えミスが生じていると判断されて、税務署などから会計処理の信頼性を疑われるリスクもあるので注意したほうがよいでしょう。
雑費の仕訳は借方を「雑費」で計上し、貸方は支払方法に合わせて以下のように行います。
何の費用なのかが明確になるように、摘要欄に詳細を記載することがポイントです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 雑費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | 書籍代 |
最後に、雑費に関する疑問の中から3つ事例を選んで紹介します。
A.業務に係る費用が雑費であり、本来の業務とは異なる場合の出費が雑損失です。
A.雑費は基本的に費用扱いで消費税の対象ですが、なかには課税対象にならないケースもあります。
A.取得価額や耐用年数などからも、雑費と固定資産は完全に別です。
固定資産は雑費で計上できません。
ただし、10万円未満であれば少額減価償却資産や一括償却資産として費用処理も可能な場合があります。
仕訳の手間を考えると、少額の支出は何でも雑費で計上すれば簡単で済みます。
しかし、適切な費用管理や財務状況の把握の面で考えると、該当する勘定科目がある場合は、雑費での仕訳は避けたほうがよいでしょう。
金額と支出内容を基準に、経理部門で雑費扱いにするルールを決めておくことをおすすめします。
Manegyのオススメ記事
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

オフィスステーション導入事例集

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

サーベイツールを徹底比較!

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
公開日 /-create_datetime-/