公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
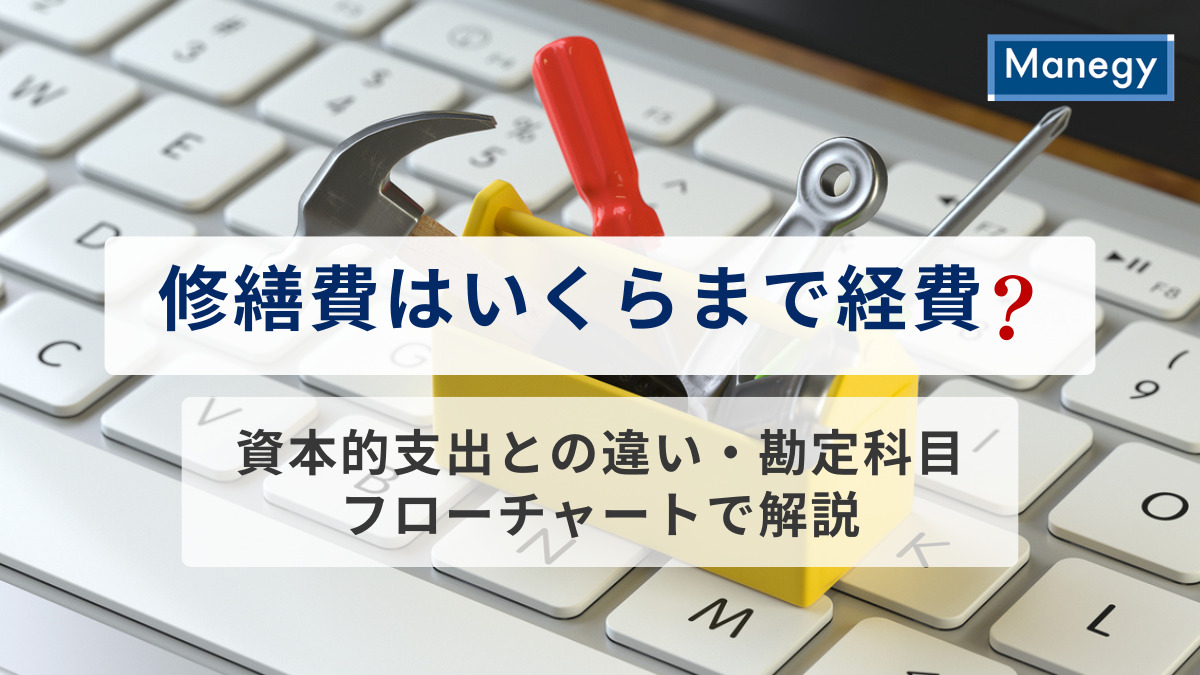
修繕費とは、企業が所有するさまざまな資産について、改修や整備のためにかかった費用を計上する勘定科目です。
ただし消耗品費や資本的支出など、同様の目的で仕訳される項目もあるため、それぞれの違いを明確にする必要があります。
この記事では、経理担当者にとっての修繕費の扱い方を分かりやすく解説します。
企業が経営を続けるためには、社屋・工場・設備・備品などのように、経年劣化するものを維持管理しなければなりません。
修繕費とは、こうした企業の資産を修理や交換などの方法により、原状回復したときに計上される経費のことです。
資産は経年劣化以外にも、自然災害や外部からの損傷などでダメージを被ることがあります。
また現代のビジネスにおいては、ソフトウェアの改修が必要になる場合もあります。
その場合にかかった費用は、基本的に修繕費として仕訳しますが、金額や条件によっては別な方法で計上しなければなりません。
そのために必要な基本的知識と、特に修繕費と資本的支出との判別方法について以下で解説します。
企業が保有する建物や設備に対して修理や改良を行った場合、その支出は工事完了後の資産の状態に基づき、会計上「修繕費」または「資本的支出」のいずれか適切な勘定科目で処理する必要があります。
この二つのどちらで会計処理を行うかは、税法などで定められた詳細な基準に沿って決定されますが、基本的な考え方としては、支出が資産を元の機能に戻す(すなわち原状回復させる)ためのものであれば修繕費、資産の価値を増加させたり、機能を向上させたりするものであれば資本的支出として扱われます。
両者の区別をより詳しく見ていくと、建物の機能性を高めるための増設、設備の用途を変更するための改造、あるいは従来品よりも品質や性能が格段に優れた部品への交換といった支出は、修繕費ではなく資本的支出に分類されます。
具体例としては、オフィスビルに新たに避難階段を設置する費用や、既存の会計ソフトウェアをより高機能なバージョンにアップグレードするためのコストなどが挙げられます。
会計上で、修繕費と資本的支出との判断が難しいケースもあります。
一例を挙げると、会社の設備が古くなったため改修工事を行った場合、通常は修繕費と見なすべきですが、改修によって設備の使用可能期間が本来よりも長くなったり、機能的に向上したりすると資本的支出で計上しなければなりません。
この判断には金額や耐久性などが関わるため、修繕費と資本的支出とで迷うケースがありますが、国税庁が判断基準になる修繕費のフローチャートを公開しているので、それに従って仕訳や計上を行うとよいでしょう。
修繕費として計上する場合には、大まかな金額による基準も規定されています。
まず費用が10万円未満の少額で、短期間で消耗する備品などのケースでは、修繕費ではなく消耗品費で計上できます。
また、修理費用が20万円未満であり、3年程度の周期で修理する場合と、費用が60万円未満であり、対象になる資産の取得価額の10%以下の場合は、原則的に修繕費として計上します。
修繕費について『100万円以上の修理は認められない』といった金額の上限は特に定められていません。
たとえ修繕費が100万円を超えた場合でも、その費用が原状回復に該当するものであれば、修繕費として計上することができます。
高額の修理費が必要になる場合を考えてみましょう。
社内の設備が老朽化して使えなくなったとき、部品交換もしくは設備そのものを交換したとします。
これで以前と同等に使用できるようになり、原状回復と見なすことができれば修繕費で計上できます。
一方で以前よりも高性能な設備への交換や、新しい機能を追加するなどしたことで、原状回復の範囲を超えた場合には、修繕費ではなく資本的支出で計上しなければなりません。
修理の状況によっては、修繕費か資本的支出か明確に区分できない場合もあります。
こうした場合には、修理した資産の使用可能期間を長くする部分、または資産の価値を向上させる部分を資本的支出にして、それ以外を修繕費として計上することも可能です。
修繕費と資本的支出では会計処理も異なります。
修繕費は全額が損金として一括計上されるのに対して、資本的支出は固定資産として計上し、その後、減価償却の対象として費用計上されます。
ここでは、修繕費の具体的な会計処理を確認しましょう。
修繕費は法人では「販売費・一般管理費」として、個人事業主では「経費」として扱い、どちらも勘定科目は「修繕費」で仕訳します。
以下に挙げる項目については、修繕費と資本的支出との判断が難しいものですが、条件を満たせば修繕費として計上します。
これら以外の項目については、前述したように原状回復であるかどうかを基準にして、国税庁のフローチャートで勘定科目を判断してください。
社内の設備などを修理して振り込みで代金を支払ったとき、勘定科目が修繕費に該当する場合、以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
会計業務で修繕費を計上するときには、修繕費と判断できる条件を確認し、その他の仕訳と区別したうえで経費として扱う必要があります。
まず国税庁のホームページやフローチャートなどを参考にして、資本的支出に該当すると判断されるときには、資産になるため経費では計上できません。
また、設備や備品を新たに購入する場合に、それが修理に該当しないときには、金額によって資産もしくは消耗品費で計上する必要があります。
これらに該当しない場合のみ、修繕費として経費計上ができます。
経費で認められるのは、当然事業の維持に関わるものだけです。
単年度で考えると、修理にかかった金額が大きい場合でも、修繕費で一括計上すれば経費が大きくなるため、節税効果が高くなるといえます。
しかし、本来資本的支出であるべきものまで修繕費で計上してしまうと、利益操作を指摘されるかもしれません。
同様に、修繕費と資本的支出を明確に区別せず、その場の都合で仕訳を変えてしまうと、会計処理に一貫性がなくなります。
この場合も確定申告などでミスを指摘される恐れがあるため、仕訳の基準を遵守することと、判断が難しいときには税理士や会計士に相談することをおすすめします。
修繕費の規定には、20万円未満や60万円未満という条件がありますが、金額がさらに大きくなった場合でも、修繕費として認められないことはありません。
その場合は取得価額の10%が1つの目安になるでしょう。
取得価額が1,500万円の設備を改修し、100万円を支払ったとしましょう。
この改修が原状回復かどうか明確ではないケースでも、支払いが取得価額の10%に満たないため、全額を修繕費で計上できます。
さらに、修繕費と資本的支出の線引きが難しい場合、支払額の7割を資本的支出にして、残り3割を修繕費で計上することも可能です。
ただしこのケースでも、修繕費で計上する経費は取得価額の10%未満という条件があります。
会計実務や税務上のトラブルを防ぐためには、国税庁が公開している「資本的支出と修繕費」の内容を理解しておく必要があるでしょう。
必要に応じて、専門家のアドバイスも受けるとよいでしょう。
修繕費として計上する費用は、原状回復が原則だといえます。
その範囲を超えて、機能性の向上や用途の変更などが認められる場合は、資本的支出として計上しなければなりません。
判断が難しいときには、国税庁の資料などを参考にすることになりますが、仕訳に関しては正確さと一貫性を厳守することを心がけるとよいでしょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
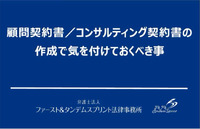
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
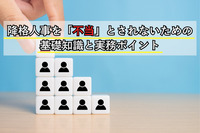
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
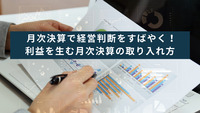
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
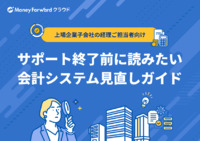
サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
公開日 /-create_datetime-/