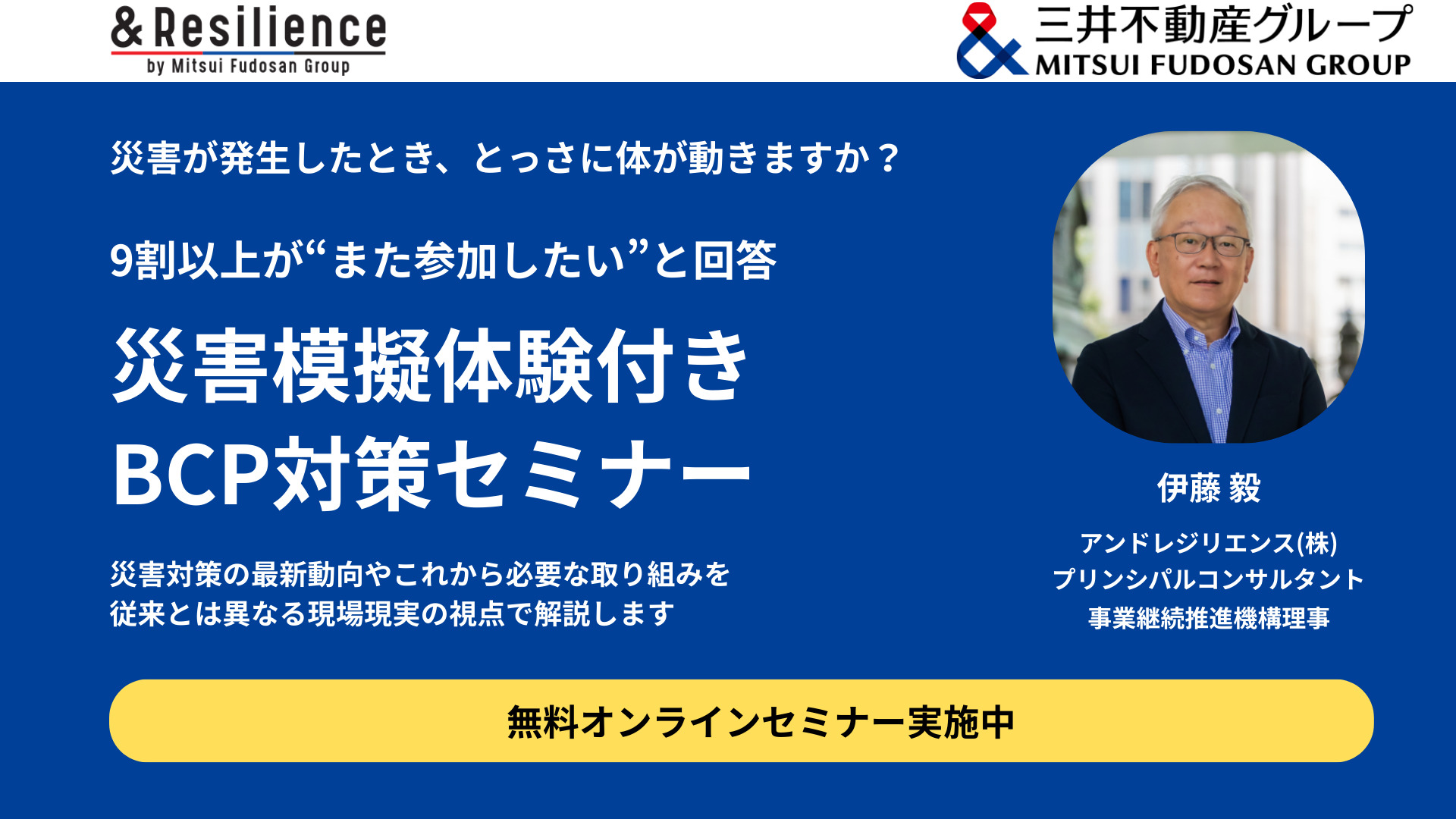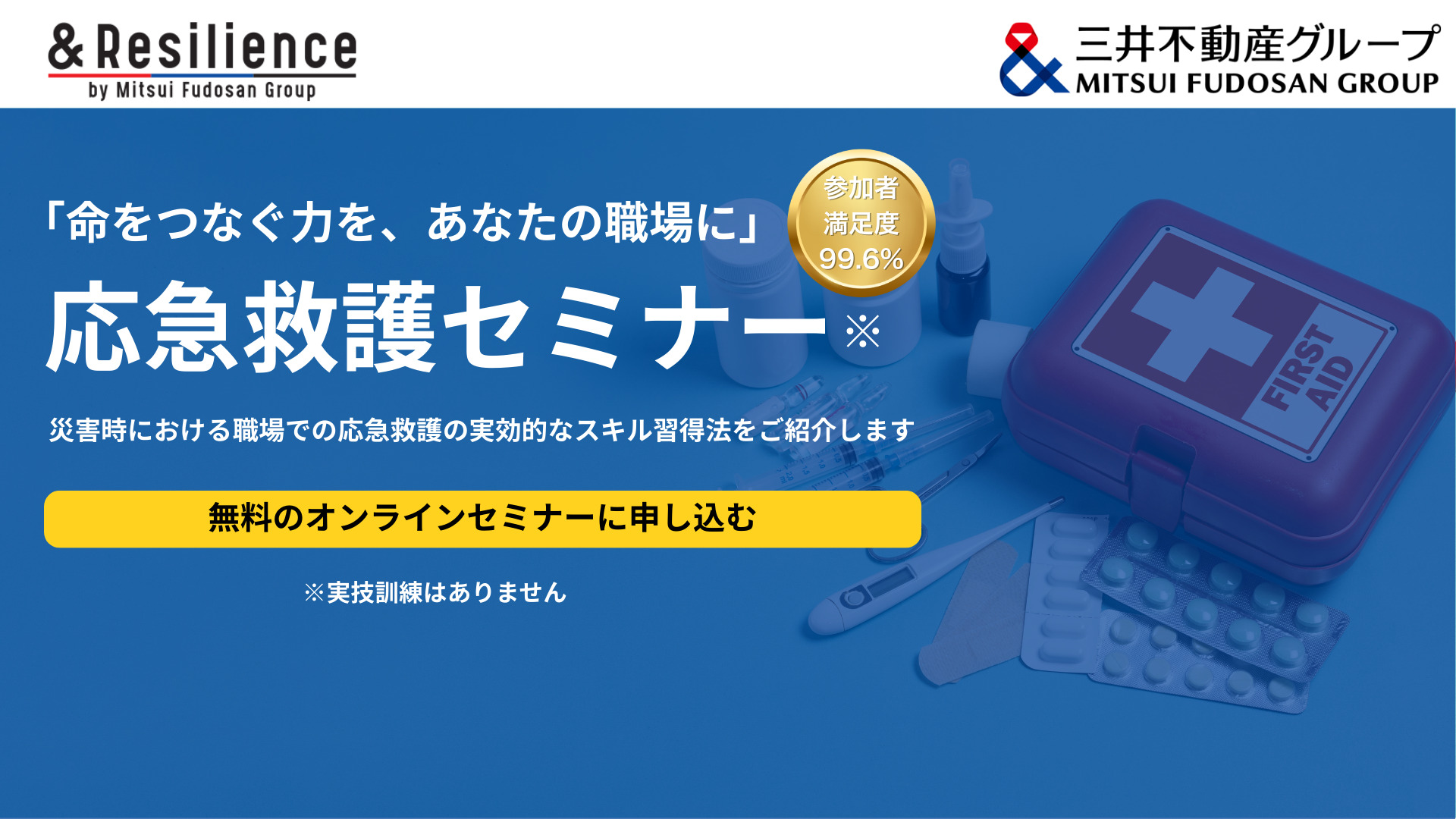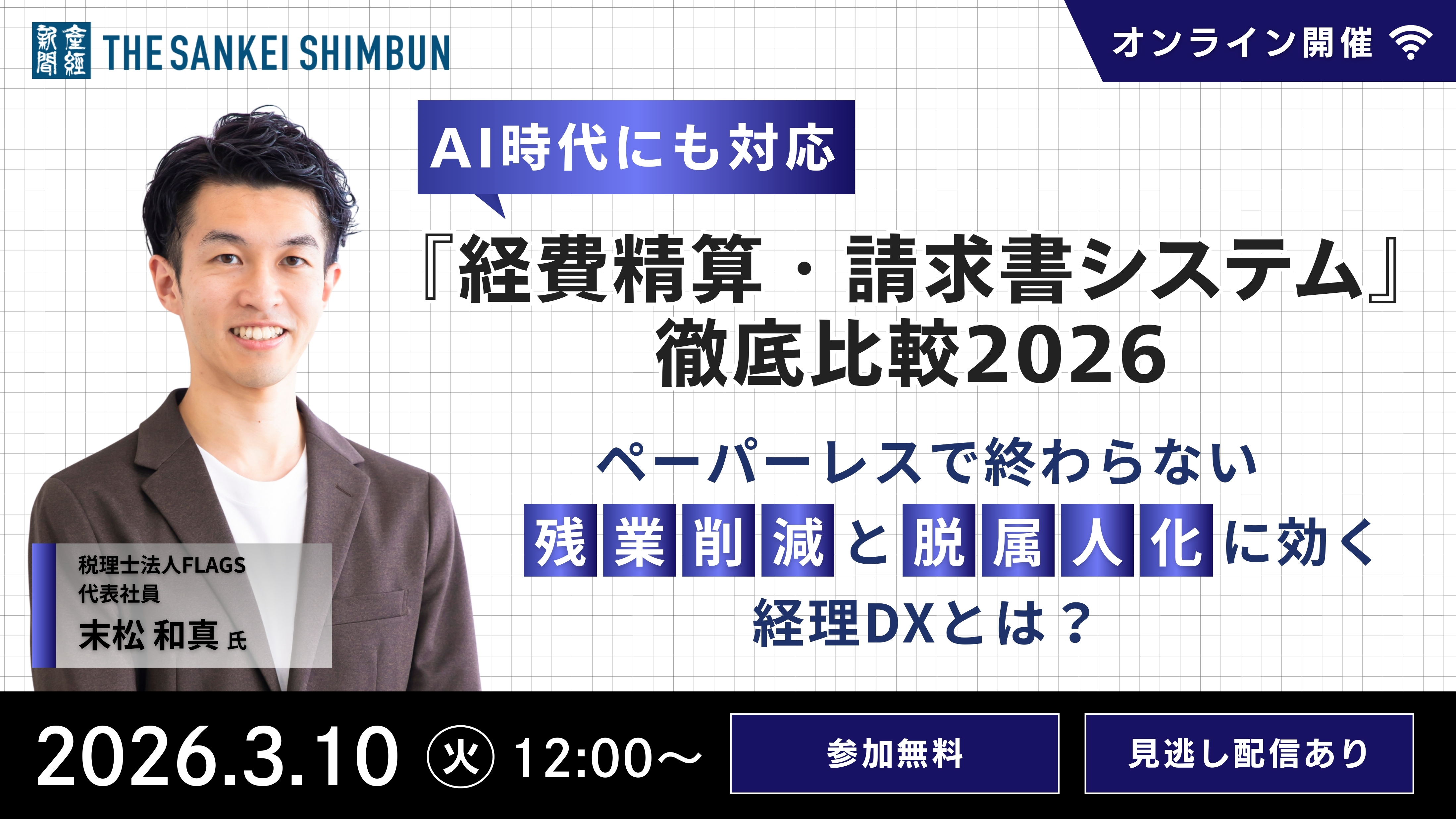公開日 /-create_datetime-/
「上場期限はずらさない」4回のIPOを達成した、覚悟と逆境のキャリア【CFOインタビュー : GVA TECH株式会社 取締役/管理部長 秦野 元秀氏】

今回は、GVA TECH株式会社で取締役/管理部長を務める秦野 元秀氏に、キャリアのターニングポイント、仕事に対する価値観、現職の事業及び組織の魅力を伺いました。
現職で取締役/管理部長として活躍する秦野 元秀氏の考えに触れることで、キャリア形成のヒントを得て頂ければ幸いです。
秦野 元秀(はたの もとひで)
GVA TECH株式会社 取締役/管理部長
新卒で証券会社に入社して10年勤務
2001年、イーコンテクスト(現デジタルガレージ)、管理部門で上場準備、2005年にIPO
2008年、駅探に入社、管理部門で上場準備、2011年にIPO
2016年、Gunosyに入社、管理部門で東証一部市場変更担当、2017年に東証一部上場
2018年、KIYOラーニング入社、管理部門で上場準備、2020年にIPO
2024年、GVA TECH入社、管理部門で上場準備、同年IPOを経て、現在に至る
秦野さんのご経歴や経験
ーー最初に、秦野さんが現職に至るまでのご経歴をお伺いしてもよろしいでしょうか。
新卒で証券会社に入社して、10年間勤務しました。
最初の3年は本社の引受部門で、いわゆる内勤の業務をやっていて、その後は支店で営業として外回りの仕事も経験しました。
証券会社で長く働くと勘違いが始まり「自分はある程度、経済・経営の知識や金融リテラシーも持っているじゃないか」とおかしな自信があったんです。
でも、友人を介して当時の社長に誘われ、事業会社であるイーコンテクスト(現デジタルガレージ)に転職してしばらくすると、その自信は簡単に打ち砕かれました。
B/SとかP/Lといった言葉は証券時代から当たり前のように使っていましたが、いざ実務に向き合うとB/SとかP/Lがどう出来上がっていくのか、売上計上のプロセスや費用計上といった話になると、まったく歯が立たなかったんです。
正直、自分の知識は“四季報の内容がある程度理解できるレベルだったんだな”と痛感しましたね。
この経験は大きくて、振り返ると実務の現場でこそ学べることがあると強く感じましたし、周囲からのアドバイスやサポートのありがたみも身に沁みて理解するようになりました。
イーコンテクストでは、管理部門で上場準備を担当して、2005年にIPOを実現し取締役も拝命したんですが、2008年には親会社との合併により上場廃止となりました。
その際にイーコンテクストを離れて3ヶ月くらい無職の期間があり、ハローワークにもはじめて通いました。
自身も30代半ばで子どももまだ小さかったですし、精神的にはかなりきつい時期でしたね。
その後は、駅探、KIYOラーニング、GVA TECHと、計4社のIPOと、Gunosyでの東証一部(現プライム市場)への市場変更に携わって、運よくすべて上場できました。
結果だけみると順風満帆と思われてしまうかもしれませんが、どれも決して順調にいったわけではなく、山あり谷ありでした。
イーコンテクストの次に入社したのが、乗り換え案内サービスを手がける「駅探」です。
ここは東芝の一部門がMBOで独立してできた会社で、IPO準備のために声をかけていただきました。
2011年3月に上場したんですが、上場後1週間後に東日本大震災が起きてしまいました。
当日準備していた上場記念パーティーは当然中止になりましたし、株価も大きく下がりました。
事業自体には直ちに大きな影響はなかったものの、人の移動が極端に減ったことで、サービスの利用にも少なからず影響はありましたね。
当時はガラケーからスマートフォンへの移行期でもあり、アプリが無料化していく過程でいろんなことがありました。
その後はニュース・エンタメのアプリを提供するGunosyに管理部長として入りました。
ここでは東証一部への市場変更を担当したんですが、ちょうどそのタイミングでトランプ政権が誕生して、一時的には市場が荒れていて。
本当にこのまま進めて大丈夫なのか、不安になりながらもなんとか対応して市場変更ができました。
2018年に参画したのがオンラインでの資格取得を提供するKIYOラーニングです。
ここでは、VCからの資金調達を経て、2020年7月にIPOを実現しました。
この年は春からのコロナ禍で上場延期や株価低迷が相次ぐ中での東証審査もバタバタでオンラインでもなく電話での審査対応で、何時間も審査官と電話でやり取りしました。
どうなるのか全く暗闇の中でしたが、競合の資格予備校の一時的な閉鎖などもあり、逆にオンライン学習の需要が高まって株価が上昇しました。
今思えば、あの上場は本当にタイミングに恵まれていたと思います。
その後、現職のGVA TECHのIPOに続きますが、各社の上場は、社会情勢や経済の波に大きく左右されました。
外部環境との向き合い方が、IPOの成否を分けることを痛感しています。
また、当たり前ですが一人でIPOができるわけでもなく、それぞれの会社で社長やメンバーにめぐまれ、私ができないことをサポートしてもらった結果だったな、と、これは本当にきれいごとではなく、心から感謝しています。
ーー現職のGVA TECHについても後ほど詳しく伺いたいのですが、その前にこれまでのご経験からIPOを成功させる上で最も大切なことは何だとお考えですか?

IPOを成功させる上で最も大切なことは、「上場期限を決めたら、ずらさないこと」だと思います。
上場準備はマラソンと同じで、山あり谷ありの長い道のりを走り、最後は超短距離走でもがいてゴールを目指して走っていく感覚です。
決まっていたゴールが直前で急に先に延びるとなったら、普通は気力も体力も持たなくなってしまいます。
仮に「〇年後の12月に上場する」と決めたら、それを起点に全てを逆算して、絶対にそのタイミングで上場するという覚悟と行動が必要です。
これは、精神論だけではなく、期日を伸ばすことが実際に企業経営にとって、非常にリスクが高いと考えているからです。
何度も時期を変更して、長らく“上場準備中”の状況から抜け出せなくなっている企業は、働く人も疲弊するし、ホントに上場するの?と社員からの疑いも出てきます。
上場準備には、管理部門の人の採用、監査法人、証券会社の費用など、年間何千万円というお金がかかります。
期限をずらすということは、このコストをかけ続けるということです。
場合によっては事業投資ができたかもしれない企業の成長機会を逃してしまいます。
事業部門ががんばって稼いでくれたお金を上場準備に投資していくわけですし、特に上場前の1年は、全社的に一体感を高めつつ、社員の皆さんにも上場ルールに沿って管理部門からいろいろな依頼事項が増えていきます。
そのなかで事業を伸ばし勢いを失わずに上場準備を進め、上場が達成できることが理想です。
そのようなぎりぎりの状況が続く中で、上場延期となると、管理部門や社員の脱力感、緊張感が一気にさがることになると思います。
なので、一度決めた期限は絶対にずらさない、これがIPOを成功させるために一番大事な点ではないか、と思いますね。
――IPOを決めた期限で達成するために必要な要素についても伺いたいです。
何よりも大事なのは、事業を予算どおりに伸ばすための事業部門の強化に加え、管理部門では、上場会社での管理部門経験者、経理経験者を採用することが必要になります。
概ね上場1年前から、上場会社と同じ決算開示資料を作れ、となりますし、上場した瞬間から上場企業のルールが適用されるので「IPO準備をしながらスキルを身に着け、成長してください」では間に合いません。
上場1年前から決算短信や有価証券報告書など金商法書類の作成や審査が始まるため、経験者を採用してこれらに耐えうる資料を作れないと、そもそも審査が進まず、途中でとん挫する要因になります。
管理部門においては、専門性の高いメンバーの採用に加えて、人柄や関係性も重要です。
IPO準備は、厳格な上場ルールが適用される上場企業に組織のフェーズが変わる取り組みとも言えます。
その中で、今まで作ったことのない書類の作成や、審査対応に加え、気づいたらやるべきことなのにやってなかったことなどがバラバラと出てきます。
誰かがやらねばならないことを自ら拾いにいく行動が求められ、やってなかったことが判明するとどうしてもギクシャクする場面が出てきます。
そういったことが起こると予め想定し、上場準備の初期段階で主体的で柔軟でチームワークのよいメンバーで組むことが欠かせません。
そして、そのチームの中心となる主担当者は、自分で手を動かして資料を作るべきですね。
例えばIPOコンサルなどに任せきりにすると、いざ審査で「この資料の意味は?裏付けデータは?」と突っ込まれた時に自分で説明できなくなってしまいます。
証券会社や東証からは一度に何百という質問が来るので、IPO準備の主担当者は、会社の隅々まで把握していないと対応できません。
もちろん全部自分で回答する必要はないですが「これは誰々が回答できる」といったかたちで認識しておくのが大事ですね。
また、外部パートナーである証券会社や監査法人と上手く付き合うことも大切です。
要求されることの中には、明確な線引きがあるもの(絶対守らねばならないもの)と、要求はされるが実はある程度バッファがあるものがあります。
彼らが合格点を出せるラインを理解して、落としどころを探る賢いコミュニケーションも必要になってきますね。
ーーありがとうございます。柔軟なメンバーを集めているとのことですが、組織づくりで大切にしていることとはありますか?
基本的には「自分より優秀なメンバーをどう集めるか」だと思っています。
僕の能力がその組織の限界にならないように常に考えてます。
全部じゃなくてもいいんですが、「この分野は絶対に僕より優れている」というメンバーを集めることを常に考えていますね。
あとは、「自分を信じない、過信しない」こと。
僕はよく勘違いもするし間違えるので、自分をあまり信じていないんです。
だから、弁護士や会計士といった専門家や、社内の優秀なメンバーの意見を聞きながらチームで進める。
それが僕の価値観に近いかもしれません。
それから、「自分の失敗を隠さない」ことですね。過去にマネジメントでなんども失敗をした経験があります。
個人に纏わる話しなので、詳細は控えますが、IPOのために無理にある方にある役割を任せたことがあります。
IPOというミッションには重要なことだったのですが、やはり組織的にうまくいかず、僕にとっては今でもトラウマとして残る苦い思い出です。
こういう自分が“大怪我”した経験を話すのは、メンバーにできれば同じような嫌な経験をしてほしくないし、「それやって失敗したよ」と、自分の経験をオープンに伝えて、気づかせてあげたいと思っています。
ケガしないと覚えないこともあるかもですが、こと、短期間で達成するIPO準備では僕がやった失敗を、次の誰かが繰り返さないように支えてあげられたらいいな、という感じですかね。
GVA TECHの魅力とIPO
ーー示唆の多い話をありがとうございます。IPOの酸いも甘いも味わってきている中で、現職のGVA TECHに参画した決め手は何だったのでしょうか?魅力を感じた点をお聞かせください。
GVA TECHに興味を持ったきっかけは、信頼する方からご紹介をいただいたことでしたが、決定的な決め手は山本社長の事業に対する強い情熱と圧倒的な推進力への共感です。
また私自身が当社事業を山本社長からお聞きしたとき、このサービスは上場企業で最も欲しいサービスで、管理部門の生産性向上に間違いなく効果があると、管理部門の当事者として価値を感じたことでした。
山本社長は元々弁護士として既に十分な地位を確立していて、安定したキャリアを築かれていたのですが、この事業の価値を心底信じて、情熱を傾けて事業拡大とIPOに取り組んでいることに心を打たれました。
「事業に対しすごくピュアな方だな」というのが第一印象で、一緒に仕事をさせていただくようになった今でもその魅力は変わりません。
組織の面でも、社長の情熱が伝播していて、全社員が真面目に事業と向き合っていて、手を抜く人がいません。
特に上場後、全社はもとより、管理部門にも春先から優秀な人材が急速に集まり始めています。
既存メンバーの意識も一気に上向き、実践経験の厚いメンバーがそろってきたことも大きな追い風であると思っています。
ーー現職であるGVA TECHでは、何を期待され、どのような経緯でご入社されたんでしょうか?
一つには、当時のGVA TECHには上場準備の経験がある人が少なく補強が必要だったのだと思います。
それと、上場後の管理部門を見据えると、そこでもリソース不足が懸念されていたので、そのあたりを期待していただいたのではないでしょうか。
管理部門には経営企画部長を兼務する若い取締役がいて、彼が対外的なIRや株主対応、数値管理、予算、経営戦略といった仕事を担当していて、僕が経理や人事労務といった分野を担う役割分担です。
入社の経緯はある信頼できる方からのご紹介だったのですが、実は入社を決めてから社長と会食した際「実は今年N期です(今期が上場する年度)」とお聞きしたんです。
「え、今年ですか!?」みたいな感じで(笑)。
会社のことを肌感覚で理解するにはやっぱり2年くらいはかかるので、正直、あまり役に立てないかもしれないなとは思いました。
ただ、目の前に上場が迫り、人手不足も顕著な状況だったなかで、これまで以上に危機感と強い当事者意識を持って取り組めました。
結果的にはチームみんなで一緒にIPO準備に取組めて良かったと思っています。
振り返ると、上場まで1年もなく、1年分の準備を半年で終わらせなければいけない状況は、短期間でキャッチアップしながら、実務も進めていく必要があったのでさすがに堪えました。
ーーこれまで数多くのIPOを経験されてきた秦野さんだからこそ感じる部分も多いと思うのですが、IPO準備企業の善し悪しの見極めポイントを教えていただけますでしょうか?
何より、社長が上場に対してどれだけ本気か。その熱量が組織全体に伝播しているかをお聞きするようにしています。社長の本気度は、上場してその会社をどうしたいか、を聞けると良いですね。もちろん、事業・会社を成長させるためということなのですが、その先の目的や目標、もっと言うと個人的な願望でも、それが強い意欲になっているなら本気と考えて良いと思います。
また、IPO準備の状況を見極める際には、実態としてどこまで実務として取り組んでいるかが確認できると良いと思います。例えば、最もシンプルな方法は、主幹事証券や監査法人の名前を聞いたときに、明快な回答があるかは重要な指標です。“今、選定中です”という段階だと、IPO準備がそれほど進んでいない可能性があります。
もちろん、その段階からジョインするのも大事なことで、前述したとおり会社を本当に理解するには2年くらいはかかるため、N-3期で入社するのもよいかと思います。さらに詳しく見極めるためには、管理部門の体制(人員数や、それぞれの経験が高いメンバーがいるか)や、会社の課題、株主の管理状況がしっかりしているか、などもチェックポイントかと思います。

これまでのキャリアを振り返って思うこと
ーーさまざまな組織や局面を経験されてきた中で、仕事のスタイルや大切にされている価値観について、改めてお聞かせいただけますか?
やはり「良いチームを作り上げること」が自分の役割であり、一番好きなことなのかもしれません。
僕は長く1年任期のなかで取締役をやってきたので、まずは優秀で他人をリスペクトできる柔軟なメンバーを集めて良いチームを作り、そのメンバーがさらに成長していく土壌を作れればそれでいいと思っています。
けっこうたくさんの面接を経験してきたので、「この人は違うかもな」という感覚は、だんだんズレてこなくなりました。
チームを作っていく上では、自分より絶対に優れている人、もしくはどこか一部分でも強みを持っている人を採用するようにしています。
そうしないと、良いチームはできないんじゃないかと思っています。
あとは、結局、会社って言っても人の集まりですよね。
「会社のルールだから」という曖昧な主語を使うのは少し違うなと思っていて。
ルールは誰か特定の人が作ったものだから、「それは〇〇さんが作ったルールです」「それは〇〇の会議で決めたことです」といった感じで責任の所在をはっきりさせることが大事だと考えています。
そうやって、優秀な人たちがそれぞれの役割をしっかり果たせる環境を作っていく。
そのためのセットアップをすることが、僕の好きなことであり、パーソナリティなのかもしれないですね。
ーー仕事上で尊敬している方や影響を受けた方はいらっしゃいますか?
振り返ってみると、やっぱり影響を受けたのは、各業界や企業で出会った社長や経営陣の方々ですね。
現職の山本社長もその一人です。
今でも付き合いが続いている先輩たちも多くいますが、結局、僕にとって「本当に尊敬できる人たち、好きな人たち」だからこそ、関係がずっと続いているんですよね。
毎年、先輩方とは忘年会を開いていて、会うたびに「やっぱりこの人たちは尊敬できるな」と感じます。
尊敬できるから残っています。
これはもう、理屈じゃなく結果論ですね。
僕自身、そういう人たちとの縁はできるだけ自分から切らないようにしています。
たとえば、今はもう75歳になったある会社の元社外取締役の方もいるんですが、たまに「生存確認です!」ってメールを送って、返信がくるかどうかで、元気にしてるかなって確認したりしています(笑)。
こういう関係は、これからも大切にしていきたいですね。
――ご経歴の中でやっていてよかったなって思うこと、もっとこうすればよかったことなどはありますか。
証券会社に10年間勤めた経験は、結果的に非常に役立ちました。
事業会社に始めて転職した時には、経験を活かせない苦い思いをしましたが、IPO準備や上場後の資本政策において、証券市場の肌感覚を持っていたことは大きな強みとなったと思います。
どのような経験でも、その価値をどう発揮するかが大事だと思います。
IPOでは証券会社や監査法人とのやりとりが必須になりますが、例えば“CB” (転換社債)「ワラント” (新株予約権)」「公募増資」といった用語や実務の流れを、感覚として理解できていたのは大きかったです。
証券会社側からも「この人は話が通るな」と思ってもらえるので、コミュニケーションもスムーズでした。
当時の同期とは今もつながっており、趣味のロードバイクでの交流や上場当日の立ち会いといった思い出も多いので、証券会社での10年間は、一通りの証券業務を経験できたことが今でも自分の強みとして活きています。
一方で、もっとやっておけばよかったと感じているのは、“失敗事例に触れる””経験の厚い方と知り合う“です。
若い頃は、成功事例や成功者の本ばかりに目を向けていましたが、実際に役立つのは失敗からの学びの方が多いな、と感じます。
知識の深い方や経験の厚い方と積極的に知り合うようにしていたら、マネジメントのミスを減らせていたかもしれません。
だからこそ、自身が過去に経験した“失敗”を隠さず伝え、次世代の役に立てばよいと思っています。
ーー最後に、秦野さんご自身が現在取り組んでいる自己研鑽や日々の活動について教えてください。
本を読んだり、色々なアプリを触ってみたり、YouTubeで情報収集したり、既存の知識だけで凝り固まらないように、積極的に新しい価値観にも触れるようにしています。
あとは、できるだけ多くの人と会話する環境をつくるよう意識しています。
前職の同僚や昔の知人に声をかけて、久しぶりにお酒や食事を楽しむ場を設けたりもしますね。
そういった何気ない交流から得られる学びは大きいです。
健康面では、年に4~5回ロードバイクのレースに出場していて、日々のトレーニングが良いリフレッシュになっています。
また、日本経済新聞の連載『私の履歴書』もよく読んでいます。
やはり、失敗談が語られている経験談の方が惹かれますね。
成功した事例だけのお話だと、やっぱり物足りないです。
成功と失敗の両面がある、そういったリアルな経験を、自分のキャリアに活かしていきたいと考えています。
ーーありがとうございました。

インタビュアー
清水 悠太(しみず ゆうた)/ 株式会社MS-Japan マーケティングDivision / 執行役員
ベンチャー・IPO準備企業を中心とした法人営業を経験した後、キャリアアドバイザーとしてCFO、管理部長、会計士、税理士、弁護士を中心に延べ5000名のキャリア支援を経験。
現在はマーケティングDivision長および執行役員として、マーケティングと新規事業・新規サービスの開発を担当。
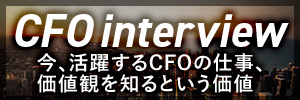
CFOインタビュー掲載ご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -
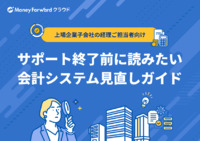
サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

アウティングとは?知らないと危険な“同意なき暴露”の意味と企業リスク
ニュース -

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入
ニュース -

1on1を「雑談」から「成長設計」へ変える――役割を軸にした仕組みで実現する、形骸化しない対話とは?
ニュース -
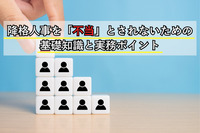
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント
ニュース -

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
ニュース -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -
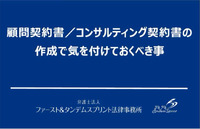
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査
ニュース -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
ニュース