公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
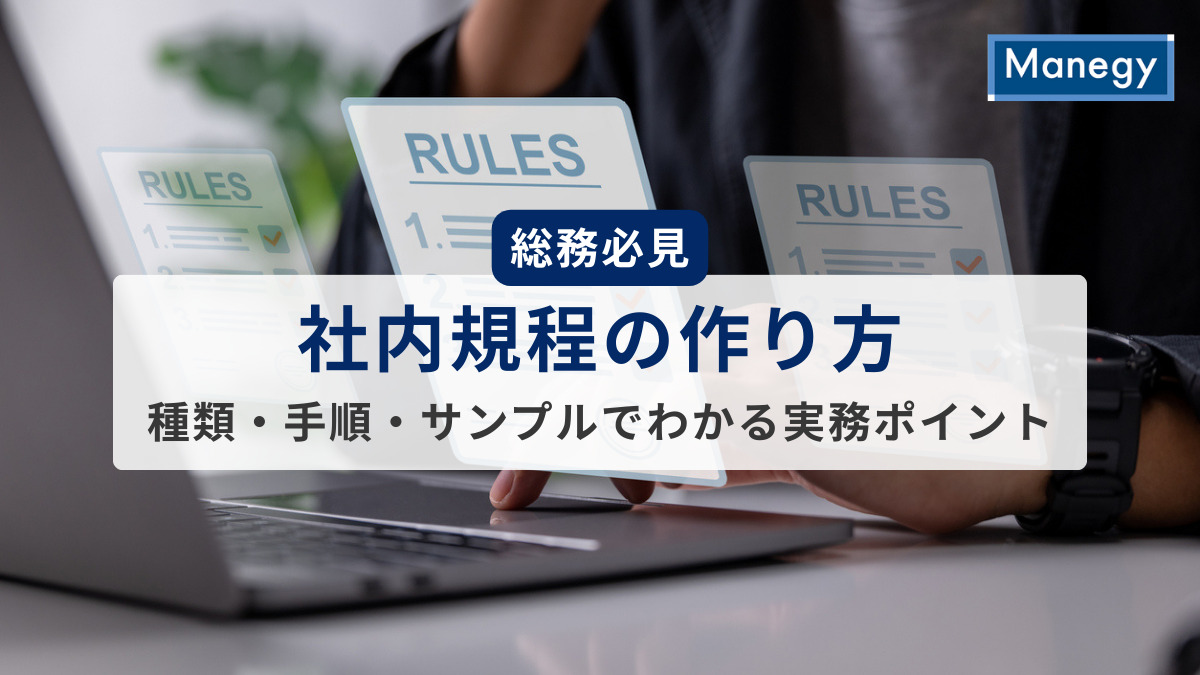
社内規程は、単なるルール作りではなく、会社の秩序と信頼を守るための“土台”です。
明確な基準があれば、トラブル防止や業務効率化、法令遵守の徹底につながります。
本記事では、実務で役立つ「社内規程の作り方」を5ステップで解説し、すぐ使えるサンプルも紹介します。
まずは自社のルール整備の第一歩を踏み出しましょう。
社内規程とは、企業内での行動や業務の進め方を定めた公式なルール集です。
就業規則のような必須規程だけでなく、経費精算やテレワーク、ハラスメント防止など、多様な分野に及びます。
もし社内規程がなければ、判断が人によってバラついたり、トラブル発生時の対応が後手に回ったりと、業務や人間関係に深刻な影響を及ぼしかねません。
規程は「面倒な書類」ではなく、組織の秩序と信頼を守るためのインフラといえます。
このような事態は、規程を整備していれば未然に防げたケースが多いので、社内規程はしっかり定めておきましょう。
| 対象者 | 規程の例 |
|---|---|
| 全従業員対象 | 就業規則、経費精算規程、情報セキュリティ規程、ハラスメント防止規程 |
| 特定の職種対象 | 営業手当支給規程、現場作業安全規程、リモートワーク規程 |
| 役員対象 | 役員報酬規程、役員退職慰労金規程、取締役会運営規程 |
自社の業務形態や規模に合わせ、必要な規程を取捨選択して整備していきましょう。
社内規程は、作成して終わりではなく、組織全体に浸透し、実際に運用されることが重要です。
ここでは、実務担当者が迷わず進められるよう、5つのステップに分けて具体的な作成プロセスを解説します。
まずは、すでに存在する規程や「暗黙の了解」となっているルールをすべて洗い出します。
現場担当者や管理職へのヒアリングでは、以下の質問が有効です。
【活用例:業務棚卸しシート項目】
| 項目 | 現状 | 問題点 | 改善の方向性 |
|---|---|---|---|
| 経費精算ルール | 口頭ベースで上限額共有 | 部署ごとに判断が異なる | 金額・対象の明文化 |
このように、業務棚卸しシートを使って、規程化が必要なテーマを網羅的に洗い出していきましょう。
規程は、必ず関連法令や行政ガイドラインに適合させる必要があります。
例えば、労働基準法、個人情報保護法、男女雇用機会均等法などが代表例です。
行政機関が公開しているモデル規程やひな形は、法令対応の参考になります。
規程は、基本構成を押さえて作成すると抜け漏れを防げます。
一般的な構成
サンプル:テレワーク規程(抜粋)
第〇条(目的)
本規程は、従業員が自宅等で勤務する際の条件及び手続き等を定め、業務の効率性と従業員のワークライフバランスを確保することを目的とする。
第〇条(勤務場所)
テレワーク勤務は、自宅又は会社が認めた場所で行うものとする。
このように実際の条文を提示すると、作成のハードルが下がります。
規程案ができたら、人事、総務、法務などの関係部署や、現場の管理職へ回覧し、実務上の課題や改善点を洗い出します。
特に、運用負荷や現場の実情を反映させることが重要です。
ポイント:修正依頼や意見は書面で残し、改定履歴を明確にしましょう。
最終案は、必要に応じ取締役会や経営会議で承認を得ます。
承認後は以下の方法で周知を徹底します。
作ったけれど誰も読んでいない状態を避けるため、理解促進の仕組みづくりが欠かせません。
どんなに完成度の高い社内規程でも、現場に浸透せず、運用されなければ意味がありません。
規程を生かすためには、制定後の周知・相談体制・改定管理の3つを確実に実行することが重要です。
規程を文書で配るだけでは、理解や遵守につながりにくいものです。
説明会や研修を通じて、「なぜ必要か」「どう適用されるか」を具体的に伝えましょう。
実施タイミング
内容構成例
工夫の例
説明後は資料をイントラネット等に掲載し、いつでも参照できる状態にしておきましょう。
新しい規程や改定内容は、現場で疑問や解釈のズレが発生しやすいものです。
早期に解消するため、相談窓口を明確にしておきましょう。
設置方法の例
対応のポイント
こうした仕組みづくりによって、誤解によるトラブルや自己流運用を防ぐことができます。
規程は、一度作って終わりではなく、常に最新の法令や業務実態に沿うよう更新が必要です。
見直しサイクル
改定フロー例
管理の工夫
継続的な改定管理は、規程の信頼性と実効性を保つための必須プロセスです。
社内規程の整備は一度きりではなく、作成前・作成中・作成後の各段階で確認すべきポイントがあります。
以下のチェックリストを活用すれば、抜け漏れを防ぎ、実務の品質とスピードを向上させられます。
| チェック項目 | 確認欄 |
|---|---|
| 規程を作成・改定する目的を明確化したか(例:法令改正対応、業務効率化、トラブル防止) | ☐ |
| 関係部署から意見を集め、必要性を合意形成できているか | ☐ |
| 担当者・プロジェクトチームを決定したか | ☐ |
| 関連法令・ガイドラインを事前に調査したか | ☐ |
| 他社事例やモデル規程を参考資料として収集したか | ☐ |
| チェック項目 | 確認欄 |
|---|---|
| 総則・目的・適用範囲を明記しているか | ☐ |
| 用語の定義を明確にしているか | ☐ |
| 必須記載事項(ルール、手続き、違反時の措置)が網羅されているか | ☐ |
| 表現があいまいでなく、誰が読んでも同じ解釈ができるか | ☐ |
| 図表や箇条書きを活用し、視認性を高めているか | ☐ |
| 関係部署からのフィードバックを反映したか | ☐ |
| チェック項目 | 確認欄 |
|---|---|
| 承認プロセス(取締役会、経営会議など)を経ているか | ☐ |
| 社員への周知方法(説明会、メール、ポータル掲載など)を決定・実施したか | ☐ |
| 最新版と旧版を区別して保管しているか | ☐ |
| 改定履歴を明記しているか | ☐ |
| 年1回以上の定期見直しスケジュールを設定したか | ☐ |
このチェックリストは、規程の新規作成だけでなく改定時にもそのまま使えます。
ブックマークして、必要なタイミングで活用してみてください。
社内規程を整備・改定する際、多くの担当者が抱く疑問をまとめました。
ここで解決できれば、スムーズに作成プロセスを進められるでしょう。
A. 多くの企業では総務部や人事部が中心となって作成します。
ただし、規程の内容によっては担当部署が異なることもあります。
例えば、情報セキュリティ規程は情報システム部、経費精算規程は経理部が主導する場合があります。
ポイントは、最終的には関係部署が連携して内容を確認し、承認プロセスを経ることです。
A. 法律に関わる規程(就業規則、ハラスメント防止規程、労働時間管理に関する規程など)は、専門家へのリーガルチェックを推奨します。
A. 就業規則は、労働条件や服務規律など、全従業員に共通する基本的なルールを定めた「上位規程」です。
その他の社内規程(経費精算規程、テレワーク規程など)は、就業規則の内容を補足・具体化する下位規程にあたります。
下位規程の内容が就業規則と矛盾すると無効になる可能性があるため、作成時は必ず就業規則との整合性を確認しましょう。
社内規程は、一度作って終わりの書類ではなく、会社の成長や社会環境の変化に合わせて進化させていく「生きたルールブック」です。
作成・承認・周知といった整備プロセスだけでなく、運用や定期的な見直しまでを含めて一連のサイクルとして回すことで、組織の秩序と信頼性を長期的に保つことができます。
明確なルールがあれば、トラブル防止や業務効率化、法令遵守の実現が容易になり、社員が安心して働ける環境づくりにもつながります。
本記事で紹介した手順やチェックリストを参考に、まずは自社の規程を棚卸しし、必要なルールを整備してみましょう。
「作るだけ」で終わらせず、常に現場で活きる規程を目指すことが、組織の強固な基盤を築く第一歩です!
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

オフィスステーション導入事例集
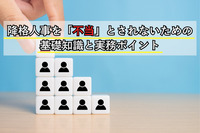
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
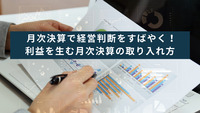
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
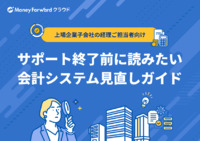
サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
公開日 /-create_datetime-/