公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

経理におけるAI活用は、もはや避けて通れないテーマとなっていて、効率化はもちろん、不正検知や将来予測といった高度な領域への応用も進んでいます。
その一方で、導入コストや運用面に不安を抱く担当者も少なくありません。
本記事では、経理におけるAI活用の成功事例と導入ステップを整理し、実務に役立つポイントを解説します。まずは、自社に適した一歩を確認してみましょう。
経理のAI活用には関心が高まっていますが、なぜ今これほど注目されているのでしょうか。その背景には、人手不足や制度改正といった外部環境の変化、そして経理部門に求められる役割の大きな転換があります。
経理部門を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。少子高齢化による人手不足や採用難は年々深刻化しており、特に経理のように専門知識が必要な職種は慢性的に人材確保が難しい状況です。
さらに近年は、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正への対応、スピーディーな決算や経営データの開示要求など、経理に求められる役割も高度化しています。
これまでのように「過去の数字をまとめる作業者」にとどまるのではなく、経営層と同じ視点でデータを読み解き、会社の未来を支える「ビジネスパートナー」としての役割が期待されているのです。AIの導入は、こうした役割変化を後押しし、限られたリソースを付加価値の高い業務へ振り向けるための有効な手段といえます。
AIは「大量データの高速処理」「パターンの認識」「反復作業」といった分野を得意とします。例えば、数百枚に及ぶ請求書の読み取りや、過去数年分の経費データから不正パターンを抽出するといった作業は、人間が手作業で行うと膨大な時間がかかりますが、AIであれば瞬時に処理できます。
一方で、AIは「例外的な取引への判断」や「社内外の関係者との交渉」「経営戦略に基づいた意思決定」といった、背景を読み取る力やコミュニケーションを必要とする領域は不得意です。つまり、経理部門がAIを取り入れる際は「AIは正確で迅速に事務処理してくれるアシスタントで、人間は戦略的判断をすべき人」という役割分担を意識することが重要です。この考え方を明確にすることで、AI導入による業務効率化と人間ならではの付加価値提供を両立させることができるでしょう。
経理におけるAI活用といっても、その対象業務は多岐にわたります。入力やチェックといった定型作業から、社内対応、さらには将来予測まで幅広く応用可能です。ここでは代表的な業務ごとに、実際の活用事例と得られる効果を紹介します。
経理部門で最も工数がかかる業務の一つが、請求書や領収書の入力作業です。AI-OCRを活用すれば、紙の請求書をスキャンするだけで日付・金額・取引先名を読み取り、勘定科目まで自動で推測して会計システムに登録できます。従来は1件あたり数分かかっていた入力が短縮され、結果として月間で数十〜数百時間の工数削減につながった事例も報告されています。特に請求書の枚数が多い中堅・大企業ほど効果が大きく、繁忙期の残業削減にもつながります。
経費精算は「カラ出張」「金額の水増し」「規定外の飲食費計上」など、不正の温床になりやすい領域です。AIは過去のデータから不正パターンを学習し、異常値をリアルタイムに検知できます。例えば「同日に複数の交通費が計上されている」「過去平均を大きく上回る金額が申請されている」といったケースを自動でアラート化し、承認者に通知します。これによりチェック漏れを防ぎ、内部統制の強化や監査対応の効率化に貢献します。人間が全件を目視確認する負担も軽減され、ミスや不正の早期発見につながります。
「この経費はどの科目に振り分ける?」「来月の締め日はいつ?」といった社内からの定型的な問い合わせは、経理担当者にとって意外に大きな負担です。生成AIを搭載したチャットボットを導入すれば、こうした質問に24時間365日自動で回答できます。
経理部門は問い合わせ対応から解放され、数字の分析や改善提案といった本来の業務に集中できます。さらに、回答ログを蓄積することで「よくある質問集」をアップデートでき、社内全体のナレッジ共有にもつながるでしょう。
近年では、AIを使った売上や資金繰りの予測も注目を集めています。過去の財務データに加え、季節変動や取引先ごとの発注傾向などを取り込み、将来のキャッシュフローを精度高くシミュレーションすることが可能です。
たとえば「半年後に資金が足りなくなる可能性を事前に察知し、銀行への融資相談を早めに進められた」という事例もあります。AIのこうした活用は、単なる作業効率化を超え、経営の意思決定を支える経理の“戦略的な役割”を実現する武器となります。
AIは経理部門の強力な味方となりますが、導入の進め方を誤ると期待した効果が得られないどころか、コストやリスクばかりが膨らんでしまうケースもあります。ここでは、実際に多くの企業で見られる失敗例と、その回避策をあわせて紹介します。事前にリスクを知り、備えることで成功の確率を高めましょう。
AIは学習データの質に大きく左右されます。フォーマットがバラバラだったり、入力ミスが多かったりすると、正しい仕訳や予測ができず「思ったほど精度が上がらない」という事態に陥りがちです。
回避策:導入前にデータクレンジングを実施し、勘定科目や取引先名の表記ゆれを統一することが重要です。また、入力ルールやテンプレートを定め、データを標準化しておくとAIの効果を最大限引き出せます。
トップダウンでAIツールを導入しても、現場担当者が「操作が複雑」「業務フローに合わない」と感じれば定着しません。結果として宝の持ち腐れになってしまいます。
回避策:いきなり全社導入せず、まずは一部の業務で試験導入(PoC)を行い、現場担当者を巻き込んでフィードバックを得ることが大切です。小さく始めて成功体験を積み重ねることで、スムーズに全社展開できるでしょう。
AIは万能ではなく、誤判定をすることもあります。すべてを機械任せにすると、不正や異常値を見逃し、重大な損失につながる恐れがあります。
回避策:AIの結果をそのまま採用するのではなく、最終確認は必ず人間が行う仕組みにしましょう。AIは「第一段階のチェック担当」と捉え、人間は「最終判断者」として役割を分担するのがポイントです。
高機能なAIシステムを導入したものの、活用範囲が限定的で投資に見合う成果が出ないケースもあります。
回避策:導入目的とKPIを明確に設定してからツールを選定することが重要です。例えば「請求書処理時間を50%削減」「月次決算を3日短縮」など具体的な目標を定め、それを実現できる機能に絞って投資することで、費用対効果を確保できます。
経理データには機密性の高い情報が含まれており、セキュリティ対策が不十分だと情報漏えいのリスクがあります。クラウド型AIサービスを利用する場合は特に注意が必要です。
回避策:導入前にセキュリティ要件(暗号化、アクセス権限管理、データ保管場所など)を明確に定義し、ベンダーを選定することが不可欠です。また、定期的な監査や社内研修を通じてリスク意識を高めることも有効です。
AI導入は「とりあえずツールを入れてみる」だけでは成果につながりません。明確な目的設定から始まり、プロセスの整備、ツールの試験運用を経て、最終的に経理担当者の役割を進化させる──この流れを踏むことが成功の鍵です。ここでは、実際のプロジェクトを進めるうえで押さえておきたい4つのステップを紹介します。
最初に取り組むべきは「何のためにAIを導入するのか」を明確にすることです。例えば「請求書処理時間を50%削減する」「月次決算を3日早める」といった具体的なKPIを設定します。目的が不明確なまま導入すると、費用対効果が見えず失敗しやすくなります。まずは自社の業務を棚卸しし、特に工数が多く標準化しやすい領域(請求書入力、経費精算チェックなど)から優先的に検討するのが効果的です。
AIはデータをもとに学習・判断するため、業務フローやデータがバラバラだと十分に機能しません。導入前に「業務手順の標準化」「入力フォーマットの統一」「過去データのクレンジング」を行いましょう。例えば取引先名の表記ゆれを統一するだけでもAIの精度は大きく向上します。また、マニュアルを整備して誰が見ても同じ手順で処理できる体制をつくることが、AI導入の基盤となります。
次に、目的達成に合ったツールを選定します。比較ポイントは「機能」「コスト」「セキュリティ」「サポート体制」です。最先端の機能があっても、自社の課題解決に直結しなければ意味がありません。また、いきなり全社導入するのではなく、特定部署や業務に絞った試験導入(PoC)から始めるのが賢明です。小規模で効果を検証し、現場の声を取り入れながら改善を重ねることで、現場定着と全社展開がスムーズになります。
PoCの成果を確認したら、本格導入に移行します。このとき重要なのは「AIに任せる領域」と「人が担う領域」を明確に切り分けることです。単純作業をAIに任せる一方で、経理担当者は分析・経営支援といった付加価値業務へシフトする必要があります。そのためには、データ分析力やITリテラシーを高める研修、社内での勉強会などリスキリングの機会を設けることが欠かせません。AI導入はツールの導入にとどまらず、経理部門全体のスキルアップと役割進化につながるプロジェクトと捉えることが大切です。
経理にAIを取り入れる際、多くの担当者が抱くのは「自分の仕事はどうなる?」「コストは高くない?」といった現実的な疑問です。ここでは特によく寄せられる質問に答えていきます。
いいえ。AIは経理担当者の仕事を奪うのではなく、サポートする役割を担います。請求書入力や経費精算チェックといった定型業務はAIに任せ、人間は分析や経営支援など高度な業務に集中できます。AI導入は「仕事の置き換え」ではなく、「仕事の質の転換」を促すものだと考えると良いでしょう。
あります。最近はクラウド型で月額数千円から利用できるAI-OCRや経費精算システムが普及しています。導入時の初期費用を抑えられるサービスも多いため、中小企業でも手軽に試せます。まずは「請求書入力の自動化」など効果が見えやすい業務から小規模に導入し、費用対効果を確認してから範囲を広げるのがおすすめです。
基本的に不要です。市販されている経理向けAIツールは、プログラミングスキルがなくても操作できる仕様になっています。ただし、Excelや会計ソフトの基本操作、データの整理スキルは必要不可欠です。将来的には、データ分析やBIツールの基礎知識を身につけておくと、AIと組み合わせて活用の幅を広げやすくなります。
はい。AI-OCRや仕訳自動化ツールを利用すれば、領収書・請求書のデータ化や保存要件を満たした管理を効率化できます。インボイス制度対応では、適格請求書の判別や番号チェックをAIが自動で行う機能も登場しています。こうした仕組みを活用すれば、法令遵守の負担を減らしつつ、監査や税務調査への備えも強化できます。
経理におけるAI導入は、単なる効率化のツールではなく、部門の役割を根本から進化させるきっかけとなります。定型業務をAIに任せることで、担当者は数字の変動の背景を分析し、経営課題を可視化して提案できる「戦略的パートナー」へとシフトできます。
重要なのは、AIを脅威ではなく“味方”として位置づけ、人間ならではの判断力やコミュニケーション力を発揮することです。これからの経理には、AIによる効率化と人の付加価値の両立が求められます。まずは身近な業務から小さく導入を試し、自社の未来につながる第一歩を踏み出してみましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
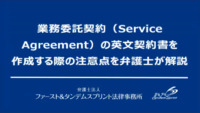
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
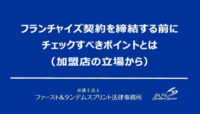
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
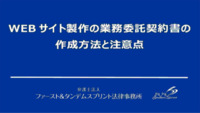
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
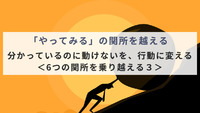
「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)
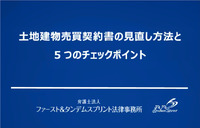
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
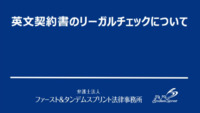
英文契約書のリーガルチェックについて

事業用不動産のコスト削減ガイド

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
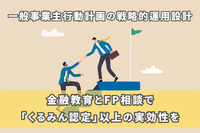
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは
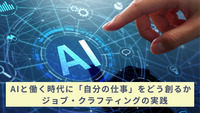
AIと働く時代に「自分の仕事」をどう創るか —ジョブ・クラフティングの実践
公開日 /-create_datetime-/