公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
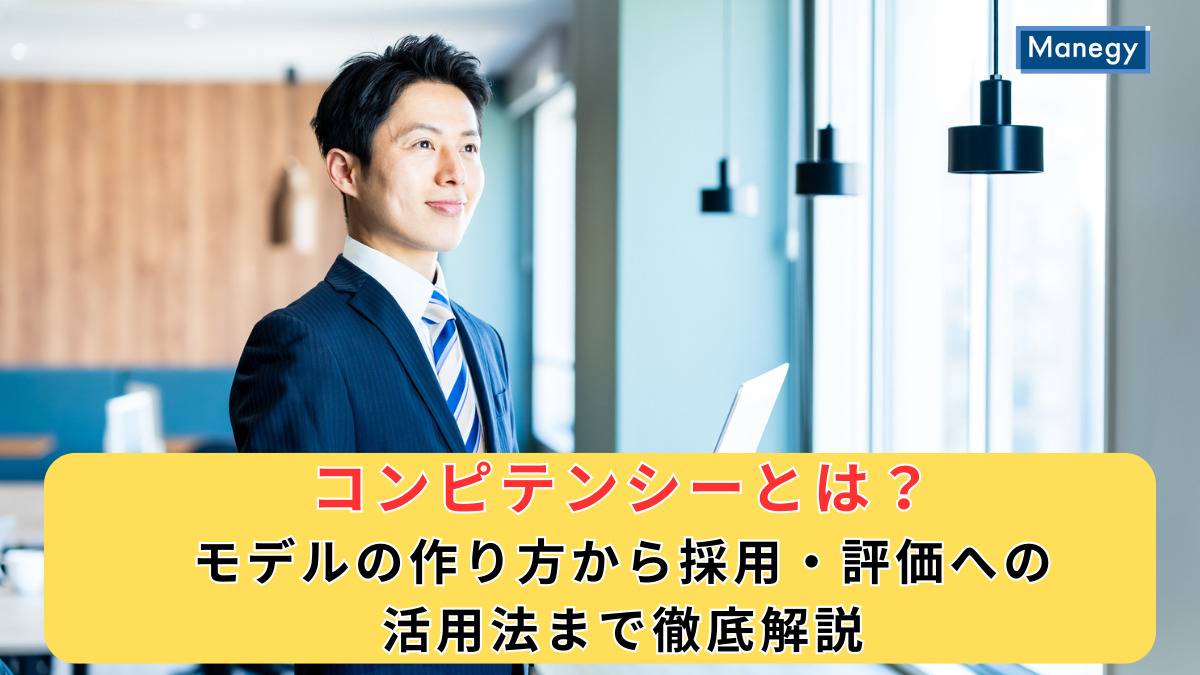
「なぜ、同じような経歴なのに、成果を出す人と出せない人がいるのだろう?」そんな人事担当者の根源的な問いから始めましょう。
その答えの鍵を握るのが、学歴やスキルといった目に見える能力だけでなく、成果に繋がる"行動特性"を可視化する「コンピテンシー」です。
人材の流動化が加速する現代において、優秀な人材を見極め、育成し、適切に評価することは、企業の競争力を左右する重要な課題となっています。この記事では、コンピテンシーを基礎から理解し、自社に合ったモデルを設計し、採用・育成・評価という人事の全領域で活用するための、具体的な手順書をお届けします。
コンピテンシー(Competency)とは、高い成果を上げる人材に共通して見られる「行動特性」のことです。
1970年代にハーバード大学のデイビッド・マクレランド教授によって提唱された概念で、直訳すると「能力」や「適性」を意味しますが、人事領域では単なる知識や技術ではなく、「優秀な成果を生み出す行動のパターン」として定義されています。
例えば、トップ営業マンに共通する行動特性として「顧客の真のニーズを聞き出すために、表面的な会話から一歩踏み込んだ質問を投げかける」「提案前に必ず競合他社の動向を調査する」といった具体的な行動が挙げられます。
これらは単なる営業技術ではなく、成果に直結する思考と行動のパターンなのです。
多くの企業で混同されがちなのが、「スキル」と「コンピテンシー」の違いです。
スキルは「できること(知識・技術)」を指すのに対し、コンピテンシーは「成果を出すために、その知識や技術をどう使いこなしているか(行動)」という点で大きく異なります。
具体例で説明すると、「Excel操作ができる」はスキルですが、「データ分析結果を相手の理解度に合わせて資料作成し、説得力のあるプレゼンテーションを行う」はコンピテンシーです。
同じExcelスキルを持っていても、それをどう活用して成果につなげるかは人によって大きく異なります。
この違いを理解することで、採用時に「資格やスキルは十分なのに、なぜか成果が上がらない」という人材のミスマッチを防ぎ、真に活躍できる人材を見極めることが可能になります。
現代の労働市場では、人材の流動化が進み、従来の終身雇用制度を前提とした人事制度では対応しきれない課題が山積しています。
また、デジタル化の進展により、求められるスキルセットも急速に変化しています。
このような環境下で、自社で活躍できる人材を的確に見極め(採用)、育て(育成)、正当に評価する(評価)ための一貫した「ものさし」として、コンピテンシーが不可欠となっています。
コンピテンシーは、表面的な経歴や資格に惑わされることなく、本質的な成果創出能力を測る指標として機能するのです。
効果的なコンピテンシーモデルは、以下の3つの階層を組み合わせて設計します:
この3階層構造により、全社的な統一感を保ちながら、各々の役割に応じた具体的な評価・育成が可能になります。
ステップ1:調査・分析
まず、社内のハイパフォーマーを特定し、彼らの行動を詳細に分析します。
インタビュー調査では「具体的にどのような場面で、どのような思考プロセスで、どのような行動を取ったか」を聞き出します。
また、実際の業務場面での行動観察も重要な情報源となります。
ステップ2:共通項目の抽出
複数のハイパフォーマーから得られたデータを分析し、成果に繋がる共通の行動特性を洗い出します。
この際、表面的な行動だけでなく、その背景にある思考パターンや価値観も含めて整理することが重要です
ステップ3:言語化・体系化
抽出した行動特性を、組織の全メンバーが理解できる言葉で定義します。
さらに、各コンピテンシーについて5段階評価など、レベル分けを行います。
例えば「リーダーシップ」であれば、レベル1「チーム内で自らの意見を明確に伝える」からレベル5「組織全体のビジョンを示し、変革を推進する」といった具合です。
ステップ4:経営層とのすり合わせ
完成したモデルが、会社のビジョンや経営戦略、企業文化と整合性があるかを経営層と確認します。
この段階で調整を行うことで、実際の人事運用時に現場と経営層の認識齟齬を防ぐことができます。
コンピテンシー面接では、候補者の過去の行動を掘り下げることで、将来の成果創出可能性を評価します。
ここで活用するのが「STARメソッド」です。
Situation(状況): 「どのような状況・環境だったか」
Task(課題): 「あなたが果たすべき役割や課題は何だったか」
Action(行動): 「具体的にどのような行動を取ったか」
Result(結果): 「その結果、どうなったか」
例えば、「チームワーク」を評価する質問として「チームで困難な課題に直面した経験について教えてください」と投げかけ、STARの順番で詳細を聞いていきます。
「どのような困難で(S)、あなたの立場は(T)、具体的にどう行動し(A)、結果はどうなったか(R)」を順次確認することで、候補者の真の行動特性を見極めることができます。
コンピテンシー評価は、単なる査定ツールではなく、人材育成の指針としても機能します。
評価後のフィードバック面談では、本人の現在のコンピテンシーレベルと、目指すべきレベルとのギャップを具体的に共有します。
例えば、「顧客対応力」がレベル2の営業担当者に対し、レベル3到達のために「顧客の業界動向を事前調査してから提案に臨む」という具体的な行動目標を設定します。
そして、その実現のための研修参加やOJT計画を策定することで、効果的な成長支援が可能になります。
この仕組みにより、抽象的な「営業力を向上させてください」ではなく、「具体的にどの行動を、どのレベルまで高めるか」という明確な育成計画を立てることができます。
従来の成果主義評価は「結果は良いが、プロセスに問題がある」「結果は出ていないが、努力は評価したい」といった場面で判断に迷うことがありました。
コンピテンシー評価では、「成果(MBOなど)」と「行動(コンピテンシー)」の両輪で評価することで、このような課題を解決します。
具体的には、評価シートに「目標達成度」と「コンピテンシー発揮度」の両方を設け、総合的に評価します。
これにより、短期的な成果だけでなく、持続的な成果創出に向けた行動も適切に評価でき、被評価者の納得感も高まります。
また、コンピテンシーは具体的な行動で定義されているため、評価者による主観的なブレを軽減し、評価の公平性担保にも寄与します。
コンピテンシー導入の主なメリットは、採用精度の向上、人材育成の効率化、評価制度の公平性確保です。
一方で、導入時には社員の理解不足による抵抗や、評価者の負荷増大といった課題も生じる可能性があります。
成功のためには、導入前の十分な説明と研修、段階的な運用開始が重要です。
いきなり全社展開するのではなく、特定の部署や職種から試行的に開始し、運用の改善を図りながら拡大していくことをお勧めします。
コンピテンシー導入により、多くの企業で採用ミスマッチの減少、離職率の改善、昇進・昇格の透明性向上などの成果が報告されています。
特に、新入社員の3年以内離職率が30%から15%に改善した事例や、管理職候補の育成期間が従来の半分に短縮された事例などがあります。
コンピテンシーモデルは「作って終わり」ではありません。
事業環境の変化、組織の成長、求められるスキルセットの変化に応じて、定期的な見直しが必要です。
年1回程度、モデルの有効性を検証し、必要に応じて項目の追加・削除・修正を行うことで、常に実効性の高いツールとして活用し続けることができます。
A. スキルは習得可能な知識や技術(例:Excel操作、英語力)を指し、短期間で身につけることができます。
一方、コンピテンシーは成果を生み出す行動パターン(例:相手の立場に立って考える、率先して行動する)で、価値観や性格に根ざしているため変化には時間がかかります。
採用時にはコンピテンシーを重視し、入社後にスキルを身につけてもらうのが効果的です。
A. 可能です。まずは社内のトップパフォーマー2〜3名に対して「なぜ成果が出せるのか、具体的にどんな行動をしているか」をヒアリングすることから始めてください。
外部の汎用的なモデルよりも、自社の実情に合ったオリジナルモデルの方が効果的な場合も多くあります。
A. コンピテンシーは「減点評価」ではなく「成長支援のためのツール」であることを強調してください。
現状の行動レベルを客観視し、次にどのような行動を身につければ成果が向上するかを明確にするためのものです。
導入初期は処遇への反映を控えめにし、育成・指導の材料として活用することをお勧めします。
A. MBOで「何を達成したか(結果)」を評価し、コンピテンシーで「どのように取り組んだか(プロセス)」を評価するという使い分けが効果的です。
例えば、総合評価の70%を目標達成度、30%をコンピテンシー発揮度とするなど、両方をバランスよく組み合わせることで、短期的成果と持続的成長の両方を促進できます。
コンピテンシーは、採用・育成・評価というバラバラになりがちな人事施策を、一気通貫で繋ぎ合わせる「背骨」のような存在です。
自社で活躍する人材の「成功法則」を可視化し、全社で共有することこそが、個人の成長と組織の成長を両立させる鍵となります。
人材獲得競争が激化し、働き方が多様化する現代において、コンピテンシーモデルは企業の競争優位性を支える重要な基盤インフラと言えるでしょう。
制度設計から運用まで一定の時間と労力を要しますが、その投資効果は必ず組織全体の生産性向上という形で返ってきます。
まずは、自社で最も輝いているハイパフォーマーの「行動」を観察することから始めてみてはいかがでしょうか。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

OEM契約とは?メリット・デメリットからOEM契約書の重要条項まで整理
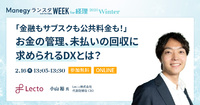
お金の回収を頑張らない時代へ!DXで変わる管理と回収の新常識【セッション紹介】

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応

「一律50万円支給」の転勤支援金制度を新設。住友重機械工業、転勤を“前向きな挑戦”に変える人事施策を導入
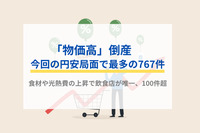
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
公開日 /-create_datetime-/