公開日 /-create_datetime-/
管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!
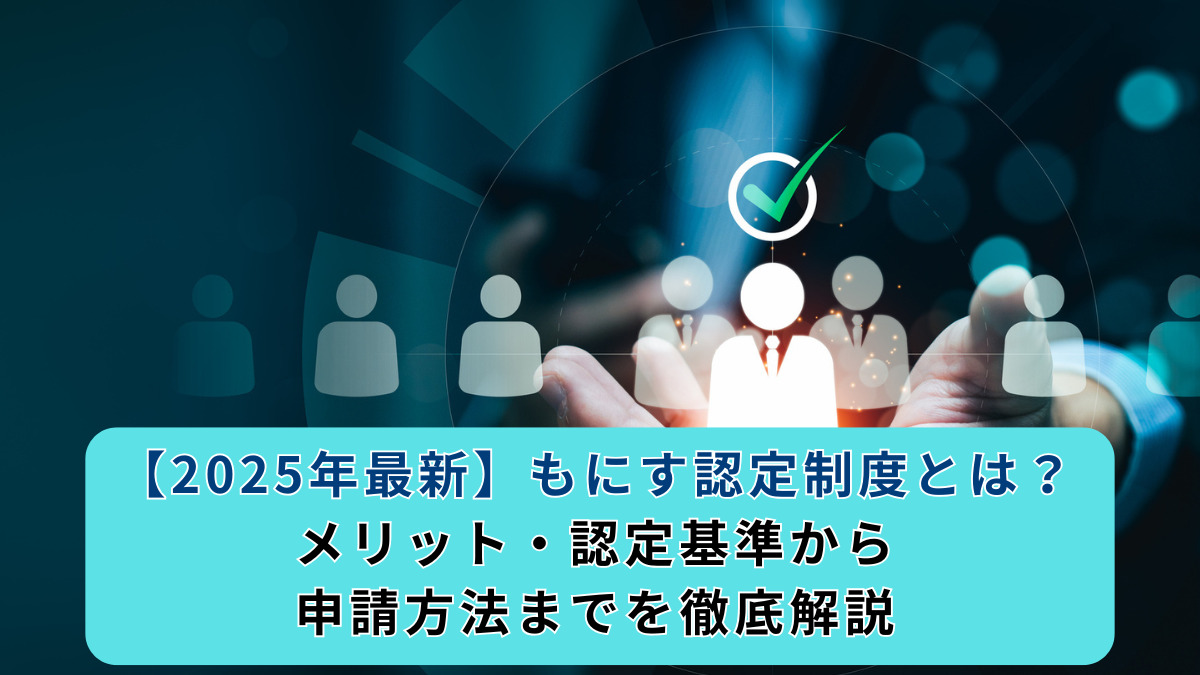
深刻化する人手不足の中、多様な人材が活躍できる職場づくりは、もはや企業の存続に不可欠な経営課題となっています。その試金石の一つが「障害者雇用」です。
この記事では、厚生労働省が優良な取り組みを行う企業を認定する「もにす認定制度」に焦点を当て、そのメリットから、具体的な認定基準、そして申請・活用の手順までを、人事担当者向けに分かりやすく解説します。
もにす認定制度は、障害者雇用に関して特に優良な取り組みを行う企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
正式名称は「障害者雇用優良事業主認定制度」で、2020年4月からスタートしました。
「もにす(MONIS)」という愛称は、「More Inclusive Society」の頭文字に由来しています。
認定企業には専用のシンボルマーク「もにすマーク」が付与され、これを自社ウェブサイトや名刺、商品パッケージ、求人票に掲載することができます。
このマークは、障害者雇用に積極的で、社会貢献度の高い企業であることを視覚的に示す強力なツールとなります。
特にESG経営やSDGsへの関心が高まる現在において、ステークホルダーに対する企業の社会的責任への取り組みを明確に示すことができ、投資家や取引先からの評価向上にも繋がります。
若年層を中心とした求職者の価値観は大きく変化しており、単に給与や待遇だけでなく、「働きやすさ」や「企業の社会貢献度」を重視する傾向が強まっています。
もにす認定は、多様性を尊重し、誰もが活躍できる職場環境を整備している証拠として機能します。
実際に、認定企業の多くが「求職者からの問い合わせ増加」や「応募者の質の向上」を実感しており、優秀な人材確保における差別化要因として活用しています。
もにす認定企業は、各種の優遇措置を受けることができます。
日本政策金融公庫では、認定企業向けの特別利率での融資制度があり、通常より0.9%の金利優遇を受けられます。
また、多くの自治体では公共調達における総合評価落札方式において、もにす認定企業に対して加点評価を行っています。
これにより、同程度の技術力であれば、認定企業が優先的に契約を獲得できる可能性が高まります。
認定を目指すプロセス自体が、組織全体のダイバーシティ推進を加速させる効果があります。
障害のある従業員が働きやすい環境は、結果として全ての従業員にとって働きやすい環境となることが多く、従業員エンゲージメントの向上や離職率の改善に繋がります。
また、多様な視点や経験を持つ人材が集まることで、イノベーションの創出や課題解決力の向上といった組織力強化の効果も期待できます。
もにす認定を取得するためには、厚生労働省が定める評価項目において一定の基準を満たす必要があります。
申請前に自社の現状を確認し、不足している部分を改善することが重要です。
最も重要な前提条件は、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率(2024年現在2.3%)を達成し、かつ雇用率を申告していることです。
さらに、過去3年間において障害者雇用促進法に基づく勧告を受けていないことも必要です。
この項目では、実際の雇用実績と定着状況が評価されます。
具体的には:
評価においては、単に雇用率を満たすだけでなく、継続的で安定した雇用実績が重視されます。
積極的な採用活動と雇用機会の拡大に向けた取り組みが評価されます:
重要なのは、単発的な取り組みではなく、継続的で計画的な活動を行っていることです。
採用後の定着支援と能力開発に関する取り組みが評価されます:
この項目では、障害のある従業員が長期的に活躍できる環境整備が重視されます。
もにす認定の申請には、以下の書類が必要です:
申請書類は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
取り組み内容を証明する添付資料については、研修記録、相談窓口の設置資料、職場環境改善の記録等、具体的な活動が分かるものを準備しましょう。
申請書類の準備が完了したら、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に申請します。
申請方法は窓口持参または郵送で、手数料は無料です。
申請から認定までは通常2〜3ヶ月程度かかるため、認定マークを活用したい時期から逆算して申請時期を決定することをお勧めします。
労働局による書面審査の後、必要に応じて実地調査が行われます。
審査では、提出書類の内容確認に加え、実際の職場環境や従業員への聞き取り等が実施される場合があります。
認定基準を満たしていると判断されれば、厚生労働大臣による認定が行われ、認定通知書とともにもにすマークの使用が許可されます。
認定取得後は、積極的な活用が重要です:
広報活動:プレスリリースの配信、自社ウェブサイトでの認定取得の告知
採用活動:求人票や採用サイトでのもにすマーク表示
営業活動:提案資料や名刺への認定マーク掲載
相乗効果の創出:えるぼし認定(女性活躍推進)、くるみん認定(子育てサポート)等、他の認定制度と組み合わせたダイバーシティ経営のアピール
認定は企業の信頼性を高める重要な資産として、様々な場面で積極的に活用しましょう。
A. もにす認定の申請に費用は一切かかりません。
申請書の提出から認定まで、全て無料です。
A. 認定の有効期間は3年間です。
継続を希望する場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。
A. 法定雇用率の達成は認定の前提条件のため、未達成の場合は申請できません。
ただし、特例子会社制度を活用している場合は、親会社とのグループ全体での雇用率で評価されます。
A. 認定自体に対する助成金はありませんが、日本政策金融公庫の優遇融資制度や、各種の補助金申請時の加点評価を受けることができます。
もにす認定制度への取り組みは、単なる障害者雇用の問題ではなく、ダイバーシティ&インクルージョンを推進し、多様な人材から「選ばれる企業」になるための重要な経営戦略です。
人手不足が深刻化する中、多様な人材が活躍できる環境を整備することは、企業の持続的成長にとって不可欠な要素となっています。
認定取得により得られるメリットは、企業ブランドの向上、優秀な人材の確保、各種優遇措置の活用など多岐にわたります。
また、認定を目指すプロセス自体が、組織全体の働きやすさ向上と生産性向上に繋がる好循環を生み出します。
この記事を参考に、まずは自社の現状が認定基準とどれくらい近いかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

経理業務におけるスキャン代行活用事例

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
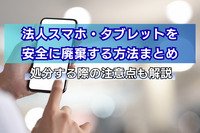
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
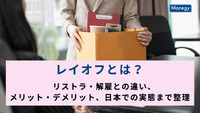
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
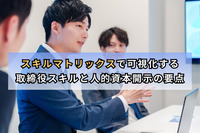
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
公開日 /-create_datetime-/