公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
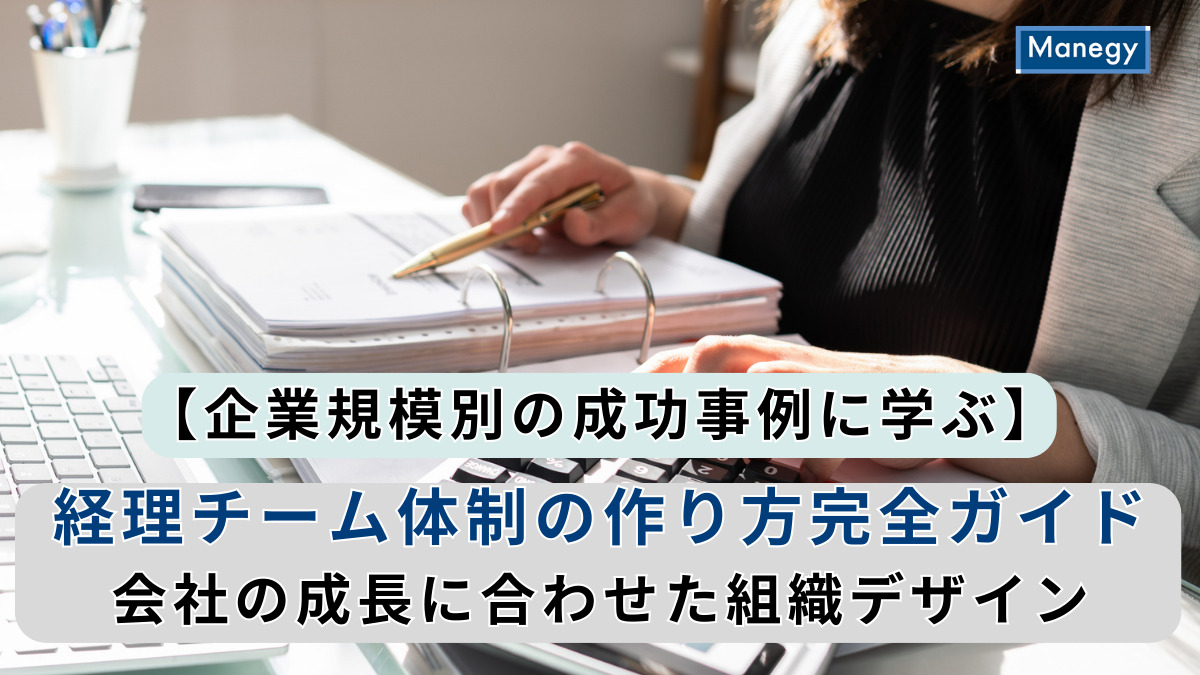
「うちは経理が1人しかいないから、いつも業務が属人化している…」「組織が急拡大し、これまでの経理体制ではもう限界だ…」。企業の成長は、経理部門に必ず"成長痛"をもたらします。
規模の拡大に伴い、取引件数は増加し、業務の複雑性は高まり、求められる内部統制のレベルも向上します。昨日まで機能していた経理体制が、突然ボトルネックとなって会社全体の成長を阻害するケースは決して珍しくありません。
この記事では、会社の規模や成長フェーズに応じて、どのような経理チーム体制が最適なのかを、具体的な成功事例を交えながら徹底解説します。スタートアップから上場企業まで、それぞれのステージで求められる経理組織の設計図を提供し、あなたの会社の「5年後も戦える経理チーム」を作るための実践的なガイドとなることを目指しています。
企業規模や業界を問わず、優秀な経理チームには共通する設計思想があります。個別の体制論に入る前に、これらの普遍的な原則を理解しておくことが重要です。
経理部門の役割を明確に定義することは、効率的なチーム運営の出発点です。
明確にすべき境界線:
注意点:
業務範囲が曖昧だと、責任の所在が不明確になり、業務の漏れや重複が発生します。
また、他部門との連携もスムーズに進まなくなります。
属人化は経理部門にとって最大のリスクの一つです。
特定の担当者しか分からない業務があると、その人の退職や体調不良時に業務が停止してしまいます。
効果的な役割分担の方法
プロセス別分担:起票→承認→支払→記帳のように工程を分ける
取引先別分担:主要顧客や仕入先ごとに担当者を配置
業務種別分担:売掛・買掛・固定資産・税務など機能で分ける
チェック機能の内蔵:作成者と承認者を必ず分離する
権限設定のポイント:各メンバーの経験とスキルに応じて、適切な承認権限を設定します。
過度に権限を集中させず、かつ内部統制を担保できるバランスが重要です。
経理部門は企業の金銭を扱う部署として、厳格な内部統制が求められます。
基本的な統制活動:
職務分離:現金の取扱いと記帳業務の分離
相互牽制:複数人によるチェック体制
証憑管理:全ての取引に適切な証憑書類を整備
定期的な照合:銀行残高や在庫との突合
アクセス制限:システムへの適切なアクセス権限設定
これらの原則を踏まえた上で、企業の成長ステージに応じた具体的な体制設計を見ていきましょう。
企業の成長に伴い、経理チームに求められる機能と体制は大きく変化します。
ここでは、代表的な3つのフェーズごとに、最適な組織モデルと実際の成功事例をご紹介します。
特徴と役割
創業期から従業員数十名程度の企業では、経理担当者1〜3名が日次の記帳業務から月次決算、年次決算、さらには労務管理まで幅広く担当する「何でも屋」的な役割を求められます。
この段階では、専門性よりも幅広い業務に対応できる柔軟性が重視されます。
よくある課題
業務の属人化:特定の担当者にしか分からない業務が多数存在
緊急時対応の脆弱性:担当者の急な退職・休職で業務が完全停止するリスク
成長への対応不足:業務量の急激な増加に体制が追いつかない
専門知識の不足:複雑な会計処理や税務申告への対応力不足
解決策と成功事例
IT商社A社(従業員25名)の成功モデル
A社では、経理担当者1名体制の限界を感じ、以下の施策で大幅な業務効率化を実現しました。
導入施策
クラウド会計ソフトの全面導入:従来の手作業による仕訳入力を自動化し、税理士とリアルタイムでデータ共有
記帳代行サービスの活用:日次の取引データ入力を外部委託し、担当者は月次締めと分析業務に専念
給与計算のアウトソーシング:社会保険労務士事務所に給与計算業務を委託
資金繰り管理の強化:週次での資金繰り表作成により、経営陣への報告頻度を向上
成果
月次決算の早期化(従来20日→10日)
担当者の残業時間50%削減
急な休職時でも業務継続が可能な体制の構築
特徴と役割
従業員数百名程度の中堅企業では、経理業務を機能別に分業化し、各担当者がある程度の専門性を持つ体制に移行します。
日次経理担当、月次決算担当、売掛・買掛担当、固定資産・税務担当など、業務領域を明確に分けることで効率性と専門性を両立させます。
よくある課題
担当者間の情報連携不足:縦割りの弊害により情報共有が滞る
業務プロセスの標準化の遅れ:各担当者が独自のやり方で業務を進める
繁忙期の負荷偏在:決算期に特定の担当者に業務が集中
人材育成の難しさ:専門分化により他の業務を理解する機会が減少
解決策と成功事例
製造業B社(従業員180名)の成功モデル
B社では、急激な事業拡大に伴う経理業務の複雑化に対し、以下の組織改革を実施しました。
組織体制
日次経理チーム(2名):仕訳入力、現金管理、小口現金管理
債権・債務チーム(2名):売掛金管理、買掛金管理、支払業務
決算・税務チーム(2名):月次決算、年次決算、税務申告
管理会計チーム(1名):予算管理、原価計算、経営分析
導入施策
ワークフローシステムの導入:請求書発行から承認、支払までのプロセスを完全電子化
定期的なジョブローテーション:四半期ごとに担当業務の一部を交換し、多能工化を推進
月次業績レビュー会議:各チームの進捗と課題を共有する定例会議の設置
業務マニュアルの標準化:全業務のプロセスとチェックポイントを文書化
成果:
月次決算日数の短縮(15日→7日)
請求書処理時間の70%削減
担当者の相互カバー率向上(50%→90%)
内部監査での指摘事項ゼロを3年連続達成
特徴と役割
従業員数千名以上の大企業では、経理機能を高度に専門化し、グループ全体の効率性を追求する体制となります。
単体決算、連結決算、開示業務、税務、管理会計、財務など、それぞれが独立した専門部署として機能します。
また、グループ会社の経理業務を集約するシェアードサービスの導入も一般的です。
よくある課題
部門間の縦割り意識:専門分化により他部門との連携が希薄化
グループ会社間での経理レベルのバラつき:子会社ごとに業務品質に差が生じる
複雑な承認プロセス:組織階層の深化により意思決定が遅延
高度な専門人材の確保難:IFRS対応や連結決算の専門家不足
解決策と成功事例
総合商社C社(従業員3,500名)の成功モデル
C社では、グループ全体の経理品質向上と効率化を目的として、大規模な組織再編を実施しました。
組織体制
シェアードサービスセンター:グループ全社の日次経理業務を集約(50名体制)
連結決算部:連結財務諸表作成、セグメント管理(8名体制)
開示・IR部:有価証券報告書、決算短信、投資家対応(6名体制)
税務部:法人税、移転価格、国際税務(5名体制)
管理会計部:予算管理、業績分析、事業評価(7名体制)
導入施策
グループ統一ERPの導入:全子会社の会計システムを統一し、リアルタイム連結を実現
会計基準の標準化:グループ全体で統一した会計ポリシーを策定・運用
RPA・AIの積極活用:定型業務の自動化により人的リソースを高付加価値業務にシフト
グローバル人材の育成:海外子会社とのローテーション制度を導入
成果
連結決算早期化(従来45日→15日)
グループ全体の経理コスト30%削減
内部統制の強化とコンプライアンス違反ゼロ
海外展開スピードの大幅向上
企業規模に関わらず、経理チームが持続的に成長し続けるためには、以下の4つの仕組みが不可欠です。
作成すべき文書
業務フロー図:各プロセスの流れと担当者を視覚的に整理
作業手順書:具体的な作業ステップとチェックポイントを明記
例外処理マニュアル:イレギュラー対応のパターンと判断基準
システム操作マニュアル:会計ソフトや各種システムの操作方法
効果的な運用のコツ
主要KPI例
定例会議の構成
週次ミーティング:進捗確認と課題の早期発見
月次レビュー:KPI実績の振り返りと改善策検討
四半期戦略会議:中長期的な体制見直しと人材配置
導入すべき技術
クラウド会計ソフト:リアルタイム連携と自動仕訳
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション):定型業務の自動化
AI-OCR:紙書類のデジタル化と自動データ抽出
BI(ビジネスインテリジェンス)ツール:データ分析と可視化
成功のポイント:
パートナー選定基準
効果的な連携方法
A. 経理は主に「過去の取引の記録と報告」を担当し、財務は「将来のお金の調達と運用」を担当します。
経理の主な業務
財務の主な業務
中小企業では経理担当者が財務業務も兼任することが多いですが、企業規模が拡大するにつれて専門分化が進みます。
A. 経理部長には、専門知識と組織運営能力の両方が求められます。
必要な専門知識
組織運営能力
求められる経験
A. 上場申請の2〜3年前から本格的な体制強化を開始することが一般的です。
タイムライン例
早期から準備することで、上場審査での指摘事項を最小化でき、スムーズな上場が可能になります。
A. 「教える過程で仕組みを作る」アプローチが効果的です。
両立のための具体策:
この方法により、人材育成と業務効率化が相乗効果を生み、組織全体のレベルアップが実現できます。
経理のチーム体制に唯一絶対の正解はありません。
それは会社の成長フェーズ、業界特性、経営方針によって変化し続ける"生き物"のようなものです。
成功している企業の経理チームには、必ず共通点があります。
それは、現状に満足せず、常により良い仕組みを追求し続ける文化です。
完璧な体制を一度に作ろうとするのではなく、小さな改善を積み重ねることで、持続的に強いチームを作り上げているのです。
この記事を参考に、まずは自社がどの成長フェーズにあり、次に目指すべきはどの"型"なのかを経営陣や関係者と議論することから始めてみてはいかがでしょうか。その議論こそが、あなたの会社の経理チームが次のステージに進むための第一歩となるはずです。
強い経理チームは、会社の成長を支える重要なインフラです。今日から始める小さな一歩が、5年後、10年後の企業価値を大きく左右することを忘れずに、継続的な改善に取り組んでいきましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

オフィスステーション年末調整

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
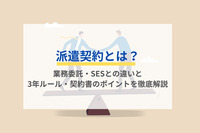
派遣契約とは?業務委託・SESとの違いと3年ルール・契約書のポイントを徹底解説
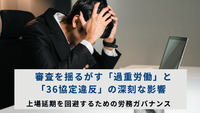
審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス
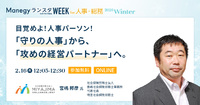
「守りの人事」から、「攻めの経営パートナー」へ【セッション紹介】
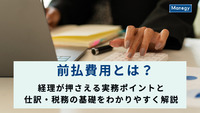
前払費用とは?経理が押さえる実務ポイントと仕訳・税務の基礎をわかりやすく解説

勢いづくりの五原則/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第4話】

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

早期退職制度を正しく運用するには?社員の納得を得るための実践知

税務調査はどこまで調べる?請求書は必要?調査の流れについて
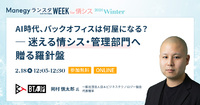
「脱・便利屋」管理部門・情シスの進むべき道を解説【セッション紹介】

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?①〜構造変化時代に求められる自発性とエンゲージメント〜
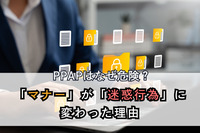
PPAPはなぜ危険?「マナー」が「迷惑行為」に変わった理由
公開日 /-create_datetime-/