公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
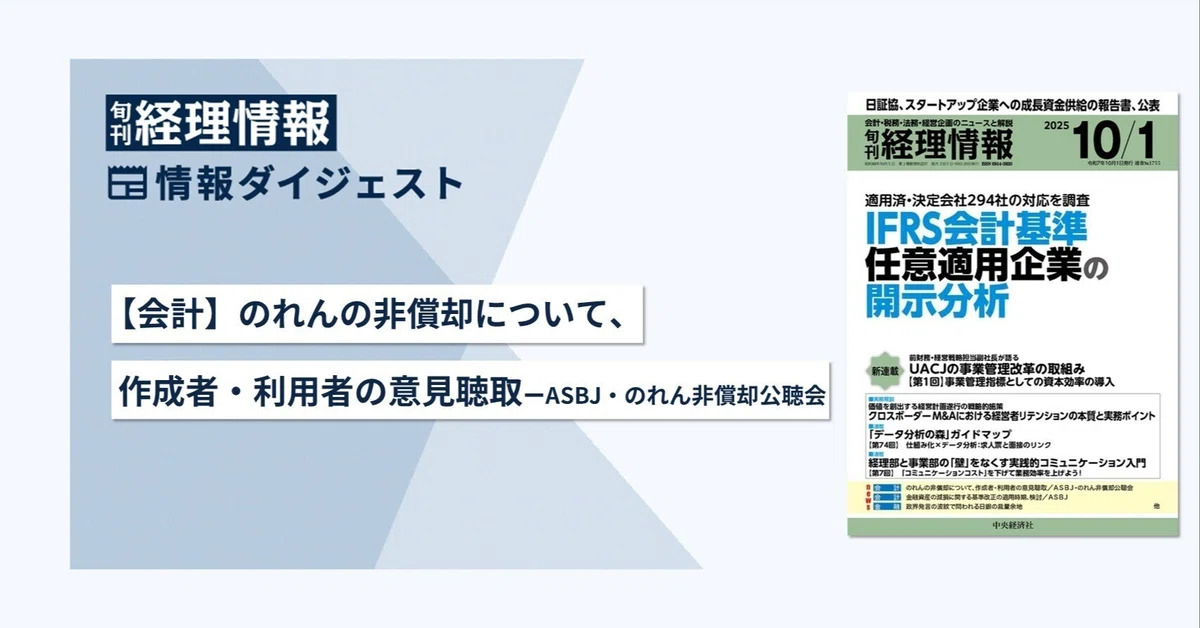
去る9月3日、企業会計基準委員会は、第554回企業会計基準委員会(第2回「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関する公聴会)を開催した。
「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関して、財務諸表の作成者および利用者から意見を聴取した。
次の財務諸表作成者が説明を行った。
|
説明者からは、「のれんの定額償却には、会計上の利益圧迫、成長戦略と会計の不整合、海外企業と比較した競争力低下、投資家とのコミュニケーション負担といった課題がある。IFRSと類似した毎期の減損テストを実施する形式を可能としてほしい。また、短期案として、のれん償却費を販管費ではなく、営業外費用など、営業利益に影響しない科目へ変更することが考えられる(山崎氏)」、「のれんの定期償却が機械的な費用配分にとどまり、統合の成果やM&Aの成否が財務諸表から読み取りにくく、経営責任を曖昧にする傾向がある。非償却・減損テストのほうが、経営者に関するアカウンタビリティを高め、資本コストを意識した規律ある経営につながる(森氏)」、「のれんの償却は、毎年一定ではなく、さまざまな要因によって上下するもの(笠井氏)」、「資本市場において、のれんの償却があるために、作成した財務諸表を正しくみてもらえていないのが問題(間下氏)」などの説明があった。
委員から、選択制の是非について問われ、説明者は「一本化すべきであり選択制は不要(間下氏)」、「段階的に適用するならあり得る(笠井氏)」と回答した。
委員からの計上区分の変更に関する質問に対し、説明者から「のれんの非償却への基準改正などに時間がかかるならば、それまでの対応としてはあり得る(間下氏)」との回答があった。
また、委員からIFRS並みの減損テストを受け入れられるか聞かれ、説明者は「毎期償却している金額に比べれば、減損テストのコストは誤差の範囲(間下氏)」と回答した。
次の財務諸表利用者が説明を行った。
|
説明者からは「のれんの定期償却は日本のM&Aマーケットが成長しない阻害要因の1つ。日本基準ののれんの定期償却を廃止し、IFRSののれんの考え方に移行していくべき。移行に際してはある一定の移行期間を設けることや減損処理の透明性を高めるべくルールの明確化を提言する(飯沼氏)」、「スタートアップがスタートアップを買収する場合でも必ずのれんを償却しなければならない現行の会計制度を見直すことを提言する(郷治氏)」、「のれんの償却により、IFRS適用企業に比してM&A後の収益性が悪くみえる(井浦氏)」などの説明がされた。
委員から、選択制の是非について問われ、説明者から「反対だが、移行期間は選択制もあり(飯沼氏)」、「選択制もありだが、開示の義務づけは必要(郷治氏)」との回答があった。
また、委員からの計上区分の変更に関する質問に対し、説明者は「反対。マーケットはEPSに反応しており、いい解決策でない(飯沼氏)」と回答した。
9月18日開催予定の第3回では、監査人と学識経験者から意見聴取を行う予定。
去る9月3日、企業会計基準委員会は、第555回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。
金融資産の減損に関する会計基準の開発に関して、第244回金融商品専門委員会(2025年9月20日号(№1754)情報ダイジェスト参照)に引き続き、次の論点に関して検討が行われた。
⑴ 適用時期の検討
今回の金融商品会計基準等の改正における適用時期を定めるあたり、考慮すべき事項について検討が行われた。
事務局から、財務諸表作成者における準備期間、国際的な会計基準の適用時期からの乖離、関連諸制度との関係についての分析が示された。
なお、今回の改正は金融機関に対する影響が大きいため、金融当局の金融機関に対する監督の観点から、前回の専門委員会で金融庁監督局の担当者による説明があり、「3年以上の期間が置かれる必要性が極めて高い」との見解が聞かれた旨が報告された。
また、事務局から早期適用を認める方向性が示された。
委員からは、「準備期間を3年以上取ることに賛成」などの意見が聞かれた。次回以降、事務局から具体的な期間を提案され、検討が行われる予定。
⑵ 文案等の検討
予想信用損失適用指針、金融商品会計基準、金融商品実務指針等のほか、時価開示適用指針について「破産更生債権等」に関する記載を削除するなどの他基準修正、コメント募集文書の文案が示され、審議が行われた。
第171回実務対応専門委員会(2025年9月20日号(№1754)情報ダイジェスト参照)に引き続き、バーチャルPPAに関する実務対応報告公開草案70号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応が審議された。
今回は、特定卸供給事業者(アグリゲーター)等が関わる取引についての検討が行われた。
公開草案では、その適用範囲を「発電事業者と需要家の相対の契約」としており、アグリゲーターが関わる取引については特段言及していない。そのため、「発電事業者」に該当しないアグリゲーターとの相対契約等の場合に適用対象となるか、アグリゲーターを介した取引や小売電気事業者を含めた三者契約も範囲に含まれるか、といったコメントが寄せられていた。
これを受けて、事務局から、次の提案が示された。
⑴ パターン1
発電事業者と需要家の間でバーチャルPPAが締結されるとともに、発電事業者とアグリゲーターの間で電力の売買契約が締結される場合
→特段の対応は行わない。
⑵ パターン2
発電事業者とアグリゲーターの間で電力の売買契約が締結され、アグリゲーターと需要家の間でバーチャルPPAが締結される場合
→需要家に生じる権利および義務が本公開草案の適用範囲とした契約から生じるものと同一視できると考えられる一定の要件を定め、当該要件を満たす契約を本実務対応報告の適用範囲に含める。
また、当該契約に本実務対応報告を適用するにあたって、「国による電力量の認定時点」の定義(本公開草案3項⑷)と対価の差金決済を行う場合の取扱い(本公開草案6項)における「発電事業者」を「特定卸供給事業者」と読み替える。
委員からは、特段の異論は聞かれなかった。
第553回親委員会(2025年9月10日号(№1753)情報ダイジェスト参照)に引き続き、企業会計基準公開草案83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応案の検討が行われた。
前回聞かれた意見をもとに、固定資産の減損と切放し法との関係を追記するなどの修正を行ったコメント対応案が示され、特段の異論は聞かれなかった。
次回文案を検討する予定。
〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉
本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
『経理情報』は、会社実務に役立つ、経理・税務・金融・証券・法務のニュースと解説を10日ごとにお届けする専門情報誌です。タイムリーに新制度・実務問題をズバリわかりやすく解説しています。定期購読はこちらから。
電子版(PDF)の閲覧・検索サービスもご用意!詳細はこちらから。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
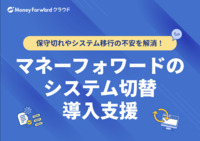
マネーフォワードのシステム切り替え導入支援
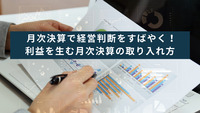
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
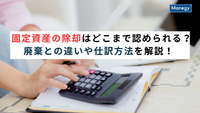
固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

オフィスステーション導入事例集

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
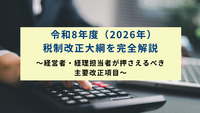
令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説
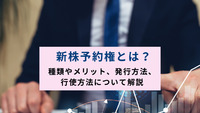
新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説
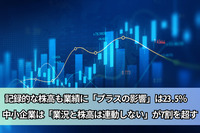
記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは
公開日 /-create_datetime-/