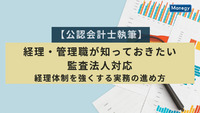公開日 /-create_datetime-/
【社労士執筆】管理部門が知っておくべき、2025年育児・介護休業法改正の本質

2025年に育児・介護休業法が改正されることをご存じでしょうか。今回の法改正は、単なる法令遵守にとどまらず、企業が働きやすい職場環境を築き、優秀な人材を確保するための重要な戦略ともいえます。
法改正の背景には、育児や介護と仕事の両立が難しく、やむを得ず離職してしまう人が後を絶たないという、日本の社会が抱える根深い課題があります。
企業側には、多様な働き方を推進し、社員のエンゲージメントを高めることで、人材の定着を図ることが求められているのです。
本コラムでは、人事労務や管理部門の実務担当者、責任者の皆様に向けて、2025年育児・介護休業法改正の要点と、それを「リスク」ではなく「機会」と捉え、企業成長へとつなげるための具体的なアクションについてお伝えします。
目次本記事の内容
1. 2025年育児・介護休業法改正の概要と背景
2025年4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるよう、柔軟な働き方を実現するための措置を拡充するものです。
2025年育児・介護休業法改正のポイントまとめ(4月施行・10月施行)
2025年4月1日から施行される主な改正内容
o 子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されます。取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」が追加され、名称も「子の看護等休暇」に変更されます。さらに労使協定による「継続雇用期間6か月未満の労働者」を除外する規定も廃止されます。
o 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による「継続雇用期間6か月未満の労働者」を除外する規定も廃止されます。
o 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまでは「3歳未満の子を養育する労働者」が対象でしたが、「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大されます。
o 育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者または要介護状態にある対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主は措置を講じることが努力義務となります。
o 育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
これまで従業員1,000人超の企業が対象だった公表義務が、従業員300人超の企業に拡大されます 。公表内容は男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」で、年1回、一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
o 介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
介護休業などの両立支援制度の申出が円滑に行われるよう、事業主は「研修の実施」「相談体制の整備」「事例の収集・提供」「利用促進に関する方針の周知」のいずれかの措置を講じなければなりません 。
o 介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供: 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。また、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければなりません。
2025年10月1日から施行される主な改正内容
o 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置:事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの選択肢から2つ以上の措置を講ずる義務があります 。
1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)
2. テレワーク等(月に10日以上利用可能)
3. 保育施設の設置運営等
4. 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上取得可能)
5. 短時間勤務制度(原則1日6時間)
o 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度に関する周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
o 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
労働者本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間などについて意向を聴取し、配慮する必要があります。
育児・介護休業法改正の背景にある「働き方の変化」
この法改正の背景にあるのは、働き方の多様化と少子高齢化の進展です。共働き世帯の増加や男性の育児参加への意識の高まりに加えて介護を必要とする高齢者が増えたことで、育児や介護と仕事をしながら働く人が増えてきました。
しかし、制度があっても「職場の雰囲気が悪くなる」「評価に響くのではないか」といった理由で、取得をためらう人は少なくありません 。結果として、育児や介護を理由に離職するケースが依然として多く、企業にとって大きな損失となっています。
管理部門がまず押さえるべき育児・介護休業法改正の全体像
今回の法改正は、単に就業規則を改訂すれば済むというものではありません。管理部門には、制度を「使える」環境を整え、従業員に制度を「知ってもらい」「利用してもらう」ための能動的な働きかけが求められています 。
lockこの記事は会員限定記事です(残り5187文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
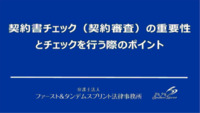
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
ニュース -

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ
ニュース -
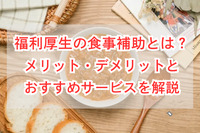
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説
ニュース -

2026年の展望=2025年を振り返って(13)
ニュース -
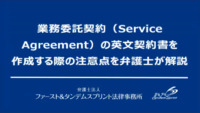
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
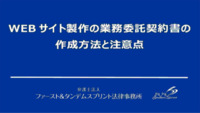
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -
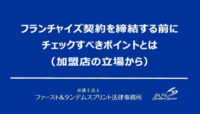
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

監査ログ活用術|セキュリティ強化を実現するログ分析
ニュース -
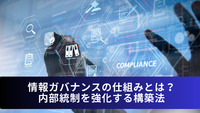
情報ガバナンスの仕組みとは?内部統制を強化する構築法
ニュース -
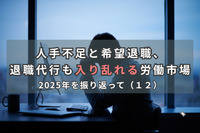
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)
ニュース -

焼津市の建設会社・橋本組、「えるぼし認定」最上位に 女性活躍推進法に基づく全項目をクリア
ニュース -

オフラインアクセスは危険?クラウドストレージの安全な活用
ニュース