公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
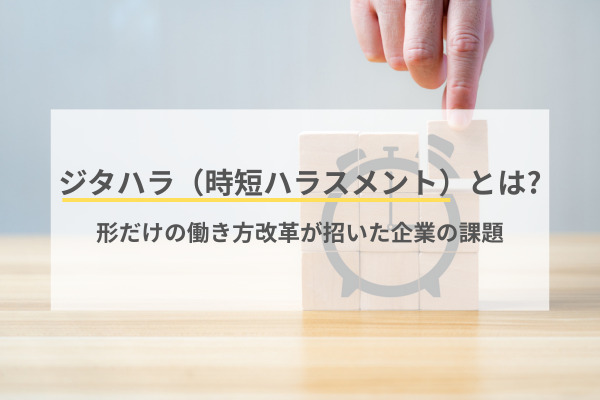
働き方改革が進む一方で、新たに「ジタハラ(時短ハラスメント)」という言葉が生まれました。
残業削減や労働時間の短縮を求めるあまり、かえって従業員に過度な負担を強いてしまうケースが増えています。
本記事では、ジタハラの定義から具体的な事例、発生する背景、そして企業が取るべき対策まで、管理部門担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。
ジタハラ(時短ハラスメント)とは、残業削減や労働時間短縮を過度に強要することで、従業員に精神的・身体的な負担を与える行為を指します。
「時短」と「ハラスメント」を組み合わせた造語で、働き方改革の推進に伴い顕在化した新しいタイプのハラスメントです。
具体的には、業務量や人員体制を見直さないまま「残業するな」「定時で帰れ」と一方的に指示することで、従業員が業務を遂行できない状況に追い込まれることを指します。
厚生労働省が正式にジタハラを「職場におけるハラスメント」として定義しているわけではありませんが、行為の内容によってはパワーハラスメントに該当する可能性があります。
あわせて読みたい
ジタハラの代表的な事例を紹介します。
最も典型的なジタハラの例が、業務量や納期は従来のままで、一方的に残業を禁止するパターンです。
例えば、月末の経理業務で通常10時間の残業が必要な状況にもかかわらず、上司から「今月から残業ゼロにするように」と指示される場合が該当します。
業務プロセスの改善や人員配置の見直しがないため、従業員は定時内に終わらせようと休憩時間を削ったり、持ち帰り仕事をせざるを得なくなります。
このケースでは、表面上は労働時間が短縮されても、実質的な負担は変わらないか、むしろ増加している状態です。
サービス残業や隠れ残業を助長し、労働基準法違反のリスクも高まります。
あわせて読みたい
定時後の残業を禁止する代わりに、始業時刻よりも早い出勤を暗黙的または明示的に求められるケースも見られます。
「残業はダメだけど朝なら来ていいから」と上司が促したり、他の同僚が早朝出勤している雰囲気から断れない状況が生まれます。
このケースも形式的には定時退社を実現していても、実際の労働時間は変わっていません。
「会社では残業するな、でも仕事は終わらせろ」という矛盾した指示により、自宅での仕事を余儀なくされる状況です。
上司が明示的に持ち帰りを指示する場合もあれば、「どうやって終わらせるかは自分で考えろ」と暗に持ち帰りを促す場合もあります。
特に在宅勤務が普及した現在では、勤務時間外のメール対応や資料作成が常態化しやすくなっています。
持ち帰り仕事は労働時間として適切に管理されないケースが多く、労働基準法上の問題だけでなく、情報漏洩リスクも高まります。
労働基準法では労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えることが義務付けられています。
しかし、定時退社を実現するために休憩時間を削って業務を行うよう暗に求められるケースがあります。
「昼休みも働けば定時に帰れるでしょ」といった発言や、休憩中も電話対応や来客対応を求められる環境がこれに当たります。
休憩時間は労働者の権利であり、これを侵害することは法令違反となります。
「残業なしで成果を出せないなら評価は下がる」といった形で、時短と成果の両立を一方的に求め、できない場合は人事評価に影響させると脅すケースです。
業務効率化のための支援や環境整備を行わず、個人の努力だけで解決するよう迫ることは、パワーハラスメントに該当する可能性があります。
特に、育児や介護で時短勤務を利用している従業員に対してこのような圧力をかけることは、不利益取扱いとして法的問題になり得ます。
ジタハラが職場で発生する背景には、制度と現場の乖離、マネジメント能力の不足など、複数の要因が絡み合っています。
2019年4月施行の働き方改革関連法により、企業には時間外労働の上限(月45時間・年360時間)が課され、違反時は罰則も科されます。
このため企業は形式的な対応に走りやすく、業務改革より先に「とりあえず残業を減らせ」という指示が現場に降りがちです。
また、労働時間削減がKPI化されると、管理職は数字達成を優先し、業務改善よりもコンプライアンス対応が目的化してしまうこともあります。
ジタハラの多くは、管理職のマネジメント能力や業務把握不足にも起因します。
管理職には、従業員の業務量やスキル、進捗状況を把握し適切に配分・調整することが求められますが、管理職自身が多忙で現場を十分に把握できていなかったり、マネジメント教育を受けていない場合、形式的な指示に頼らざるを得ません。
ジタハラを防ぐには、業務量の適正化、人員確保、教育研修の3つが柱となります。
時短勤務者には勤務時間に応じた業務量を設定します。
タスク管理で仕事を見える化し、優先度の低い業務や会議を減らし、RPAやAIで定型業務を自動化します。
正社員採用に加えて派遣・契約社員を活用し、業務再配分で負担を分散します。
多能工化やリファラル採用、既存従業員の定着率向上も有効です。
管理職向けの研修でジタハラの定義や法的リスクを周知します。
ケーススタディやロールプレイで実践的に学び、相談窓口や匿名アンケートを整備して早期発見につなげます。
A.
ジタハラは「時短ハラスメント」の略で、残業削減や労働時間短縮を過度に強要する行為を指します。
一方、パワハラは、職場での優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為全般を指します。
ジタハラはパワハラの一形態と考えられ、特に「過大な要求」や「過小な要求」に該当する可能性があります。
A.
まず業務の優先順位を上司と確認し、何を優先すべきか明確にしましょう。
その上で、現在の業務量では定時内に終わらないことを具体的なデータ(タスクリストや所要時間など)とともに報告します。
改善されない場合は、人事部門や社内のハラスメント相談窓口に相談することを検討してください。
記録を残しておくことも重要です。
A.
上司の明示的または黙示的な指示による持ち帰り仕事は、労働時間として扱われるべきであり、適切に管理されない場合は労働基準法違反となります。
また、会社の許可なく業務情報を社外に持ち出すことは、情報セキュリティの観点からも問題があります。
持ち帰り仕事を強要されている場合は、その旨を記録し、人事部門や労働基準監督署に相談することを検討してください。
ジタハラ(時短ハラスメント)は、働き方改革の推進に伴い顕在化した新たな職場の課題です。
残業削減や労働時間短縮という目的自体は正しくても、業務量や体制の見直しを伴わない形式的な対応は、従業員に過度な負担を強いる結果となります。
ジタハラを防止するためには、企業が組織的に取り組む必要があります。
業務量の適正化、人員配置の見直し、ハラスメント研修の実施など、多角的なアプローチが求められます。
特に管理職には、数値目標だけでなく現場の実態を把握し、部下とのコミュニケーションを通じて実質的な改善を図るマネジメント能力が必要です。
他にも知っておきたいハラスメント
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
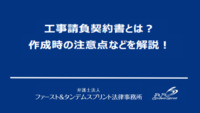
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
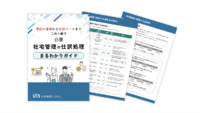
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
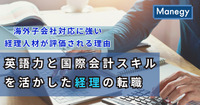
海外子会社対応に強い経理人材が評価される理由|英語力と国際会計スキルを活かした経理の転職(前編)

40年ぶりの労働基準法“大改正”はどうなる?議論中の見直しポイントと会社実務への影響を社労士が解説
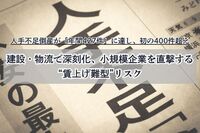
人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク
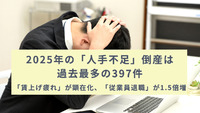
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論
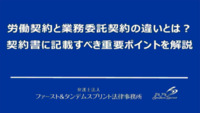
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
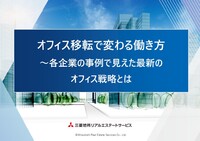
オフィス移転で変わる働き方

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

生成AI時代の新しい職場環境づくり

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
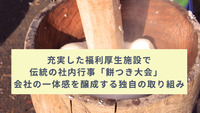
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み

キャッシュフロー計算書を武器にする|資金繰りに強い経理が転職市場で評価される理由(前編)
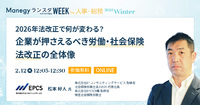
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】

旬刊『経理情報』2026年1月10日・20日合併号(通巻No.1765)情報ダイジェスト①/税務

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
公開日 /-create_datetime-/