公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
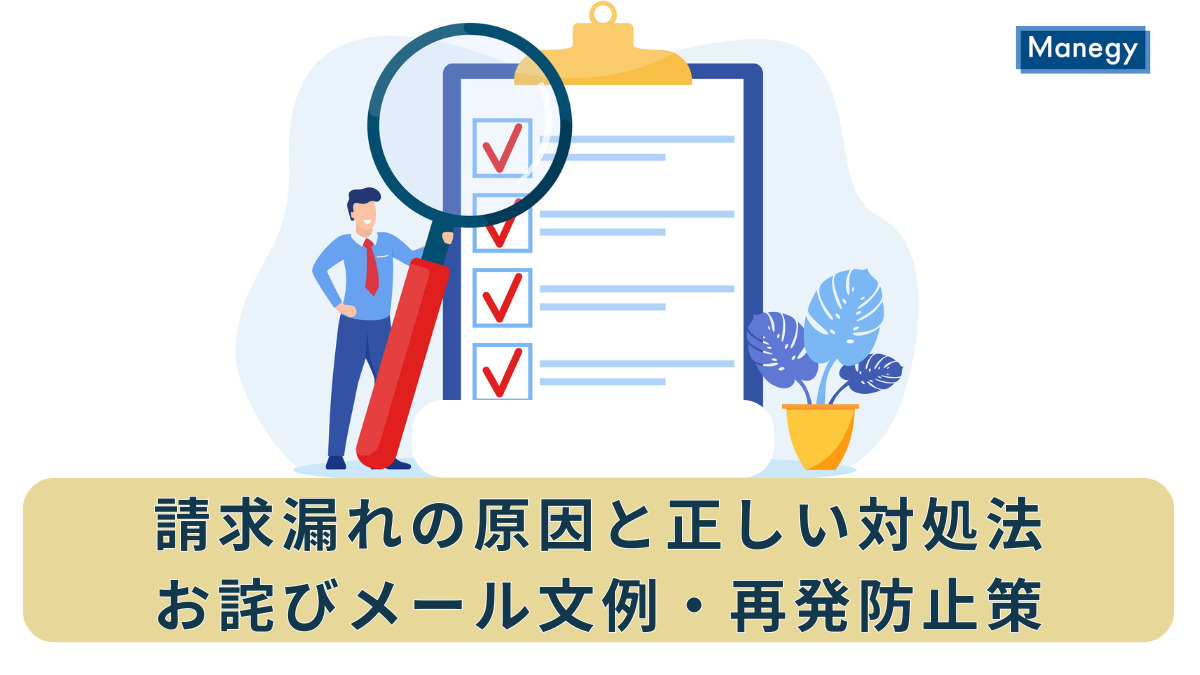
請求漏れは、取引先との信頼や入金管理に影響する重大なミスであり、請求書の送付忘れや入力ミスなど、日々の業務の中でも起こりやすいトラブルの一つです。
本記事では、請求漏れの原因と正しいお詫び対応、再発防止のポイントを実務担当者向けに解説します。
「請求漏れ」とは、本来発行すべき請求書を送付していなかったり、金額や対象期間を誤って請求していなかったりする状態を指します。
請求漏れが発生すると、入金遅延や売上計上のズレが生じ、キャッシュフローや取引先との信頼関係に悪影響を与えかねません。
特に、月末・期末の繁忙期や担当者変更のタイミングは、注意が必要です。
請求漏れの多くは、「請求書を作成したつもり」「送信ボタンを押し忘れた」といったヒューマンエラーに起因します。
また、Excelなどでの手作業入力では、金額・日付・顧客名の転記ミスや入力忘れが起こりやすく、担当者が複数いる場合は二重・未対応の混在も発生しがちです。
特にメール添付や郵送での送付を並行している場合、どこまで対応したかを可視化できていないケースが多く見られます。
管理部門では、請求書の作成・承認・送付といった工程が分業化されているため、確認フローの抜けが発生しやすくなります。
また、社内システムや会計ソフトと販売管理システムが連携していないと、受注情報や納品データの反映漏れが請求漏れの原因になるケースも多いです。
一方、担当者ごとに作業方法やチェック基準が異なると、属人化によってミスが再発しやすくなる点も見逃せません。
「請求漏れ」は、請求すべき金額を請求していない状態を指すのに対し、「誤請求」は金額や内容を誤って請求してしまうケースをいいます。
いずれも取引先との信頼を損ねるリスクがあり、対応を誤るとトラブルに発展するおそれがあります。
請求漏れが発覚した際は、慌てて取引先に連絡する前に、まず社内で状況を正確に把握することが重要です。
一連の流れを整理したうえで、適切な手順で謝罪と再請求を行えば、信頼を維持したまま問題を収束させることができます。
最初に行うべきは「事実確認」と「社内報告」です。
請求書の発行履歴・送付状況・入金データを照合し、漏れの発生原因を特定します。
特に以下の3点を確認しておきましょう。
また、関係部署(営業・経理・経営企画など)への報告を早期に行うことで、社内対応の方針を共有できます。
請求書を再発行する際は、日付・金額が正しいかも再度チェックしましょう。
社内での確認が終わったら、できるだけ早く取引先に連絡します。
信頼関係を維持するためには、「発覚後すぐの誠実な説明」が何より大切です。
まずは電話で直接お詫びし、事情を簡潔に伝えたうえで、改めてメールで正式な請求書を送付するのが望ましい対応です。
連絡の際は、以下の点を意識しましょう。
感情的な言い訳や責任転嫁は禁物です。冷静かつ誠実な姿勢が信頼回復につながります。
請求漏れのお詫び対応では、「スピード」「誠実さ」「再発防止」の3点がポイントです。
早期対応で相手の不安を軽減し、謝罪の言葉だけでなく「今後はこのように改善します」という具体策を添えることで、信頼回復の印象が強まります。
請求漏れが発覚した場合、まず取引先に誠実なお詫びメールを送ることが重要です。
単に「申し訳ありません」と伝えるだけでなく、原因説明・再発防止策・支払い依頼までを明確にすることで、相手の不安や不信感を最小限に抑えられます。
請求漏れのお詫びメールには、以下の5つの要素を含めると伝わりやすくなります。
文面全体は丁寧・簡潔・前向きなトーンを意識すると良いでしょう。
① 請求遅延の場合
「弊社の確認不足により、〇月分のご請求書の送付が遅れておりました。誠に申し訳ございません。
別添の請求書をご確認のうえ、ご対応を賜りますようお願い申し上げます。
今後は社内確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。」
② 未請求(完全な漏れ)の場合
「弊社の手続き上の不備により、〇月分のご請求が漏れておりました。心よりお詫び申し上げます。
別添の請求書をご確認いただき、〇月〇日までにご入金をお願いできましたら幸いです。
今後は請求管理体制の見直しを行い、再発防止に努めます。」
③ 金額ミス・誤請求の場合
「このたびのご請求書に金額の誤りがございました。大変申し訳ございません。
正しい金額を記載した請求書を再送いたしますので、ご確認をお願いいたします。」
お詫びの文面のなかで「支払いをお願いする」ことにためらいを感じる担当者も多いですが、依頼を曖昧にすると入金遅延につながるため注意が必要です。
「お手数をおかけいたしますが」「ご確認のうえご対応をお願いいたします」といった柔らかい表現を使うことで、角の立たない伝え方ができます。
また、入金期日や支払方法を明記しておくと、相手もスムーズに対応しやすくなります。
メール送信後は電話でフォローを入れると、より誠意が伝わるでしょう。
請求漏れが発覚した際、メールだけでなく電話や対面で直接お詫びを伝えることが望ましいケースもあります。
ここでは、電話・対面での謝罪時に押さえておくべきポイントと、避けるべき対応例を整理します。
電話や口頭での謝罪では、結論から伝えることが基本です。
まずは「請求漏れが発生した事実」と「お詫びの気持ち」を明確に伝え、加えて原因と今後の対応策を簡潔に説明します。
次の流れを意識すると、誠意が伝わりやすくなります。
【謝罪】
「このたびは弊社の不手際により、〇月分の請求が漏れておりました。誠に申し訳ございません。」
【事実説明】
「社内で確認したところ、請求データの反映漏れが原因でした。」
【今後の対応】
「すでに再発防止のためのチェック体制を強化しております。」
【支払い案内】
「改めて請求書をお送りいたしますので、ご確認をお願いいたします。」
謝罪の場では、言い訳や原因追及よりも「相手にどう対応するか」を重視しましょう。
また、声のトーンや話す速度にも注意が必要です。焦りや弁解が伝わると、誠実さが損なわれてしまいます。
請求漏れや誤請求は、一度発生すると信頼回復に時間がかかります。
そのため「お詫び」で終わらせず、再発防止の仕組みづくりを行うことが重要です。
ここでは、管理部門で実践できる3つの改善アプローチを紹介します。
まずは、請求書作成から送付までの流れを洗い出し、「どの段階でミスが起きやすいか」を可視化しましょう。
作業が属人化している場合、担当者が確認を怠ることで請求漏れが発生しやすくなります。
これを防ぐには、ダブルチェック体制を導入し、請求データの整合性を複数人で確認することが効果的です。
たとえば、以下のような仕組み化が有効です。
責任の所在を明確にし、記録を残すことでミスの再発を防げます。
担当者によって作業手順が異なると、ミスの温床になります。
請求処理のルール(請求締日・承認フロー・送付方法など)を文書化・マニュアル化して共有することで、誰が担当しても一定品質で対応できるようになります。
マニュアルには、以下のような項目を盛り込むとよいでしょう。
新人教育にも活用でき、部門全体の業務効率化にもつながります。
近年は、請求漏れ防止を支援するクラウドサービスや会計ソフトが多数登場しています。
これらを活用することで、手作業によるミスを大幅に減らすことができます。
代表的な機能例としては、以下のようなものがあります。
請求管理システムを導入すれば、請求処理の進捗をリアルタイムで確認でき、担当者間の引き継ぎもスムーズになります。
中小企業でも導入しやすい低コストのクラウド型ツールも多く、費用対効果は高いといえます。
請求漏れは、どの企業・担当者にも起こりうるミスですが、対応の仕方次第で信頼を守ることができます。
発覚時には、まず社内で事実確認を行い、取引先へは誠実かつ迅速にお詫びを伝えることが大切です。
また、謝罪の際には原因や再発防止策も併せて伝えることで、信頼関係を維持しやすくなります。
再発を防ぐためには、チェック体制やマニュアルの整備、請求管理ツールの活用など、仕組み面での改善が不可欠です。
まずは、自社の請求フローを見直し、「ミスを防ぐ仕組みづくり」から始めてみましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

オフィスステーション導入事例集

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

英文契約書のリーガルチェックについて

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

人的資本開示の動向と対策

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは
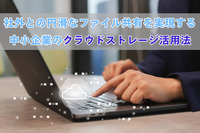
社外との円滑なファイル共有を実現する中小企業のクラウドストレージ活用法
公開日 /-create_datetime-/