公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
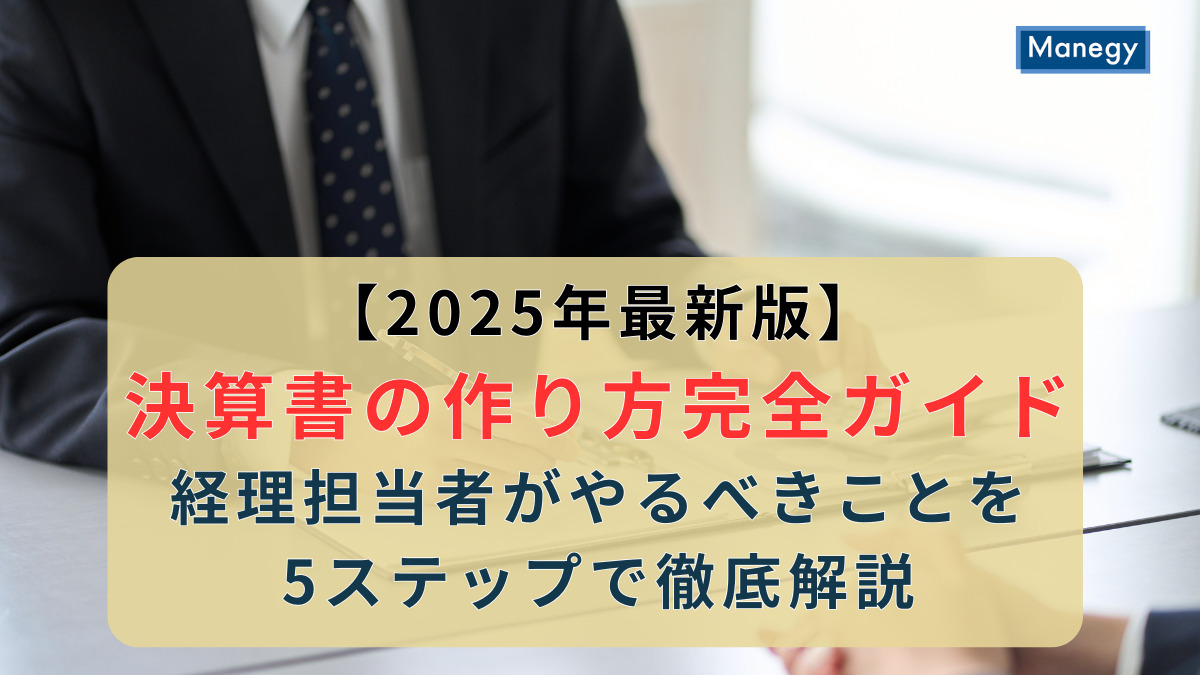
決算書の作成は、経理担当者にとって一年の集大成ともいえる重要な業務です。
しかし「初めての決算で手順が分からない」「毎年やってはいるが自己流で不安が残る」と感じる方も少なくありません。
決算書は単なる社内資料ではなく、金融機関や株主、税務署など外部への信頼性ある情報開示としての役割も担っています。
つまり、正確さと分かりやすさが強く求められるのです。
本記事では、「決算書の作り方」を初心者にも分かりやすく5つのステップに整理し、実務でつまずきやすいポイントや効率化のコツを解説します。
まずは全体の流れを理解し、自社の状況に合った決算スケジュールを立てることから始めてみましょう。
決算書作成の第一歩は、「どんな書類を作るのか」を正しく理解することです。
これを知らずに作業を進めると、ただ数字を並べるだけの作業になりがちです。
決算書は、会社の「通知表」であり「健康診断書」であり「家計簿」のような役割を持っています。
つまり、会社の状態を内外に伝える共通言語なのです。
決算書は、経営者や従業員といった社内関係者だけでなく、株主・銀行・税務署など社外のステークホルダーにも会社の状況を伝える重要な資料です。
会社が「どれだけ儲かったか」「今どのくらいの財産や借金があるか」「資金繰りは健全か」といった点を示し、経営判断や融資の可否、税務申告などに直結します。
損益計算書(Profit and Loss Statement、略してP/L)は、会社の1年間の成績表にあたります。
「売上」という得点をどれだけ積み上げ、そこから「費用」という失点を差し引いた結果、最終的にどれだけ利益を残せたのかを示すものです。
部活動で例えるなら、1年間の試合で勝った試合数と負けた試合数、その合計成績をまとめた一覧表のようなイメージです。
貸借対照表(Balance Sheet、略してB/S)は、決算日の一時点における会社の財産の棚卸しを示します。
会社が保有する資産(現金・建物・売掛金など)と、返済すべき負債(借入金・買掛金など)、そして残りの純資産(自己資本)がどのような構造になっているかを一覧できます。
家計でいえば、「貯金や家・車などの資産」と「住宅ローンや借金」などをまとめた財産目録のようなイメージです。
キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement、略してC/F)は、会社のお金の流れを追跡する書類です。
「営業活動(本業で稼いだかどうか)」「投資活動(設備投資などでお金を使ったか)」「財務活動(借入や返済で資金が動いたか)」という3つの区分で、現金がどのように増減したのかを示します。
家計簿でいうと「給料収入」「投資や大きな買い物」「ローン返済」などをまとめて、1年間でお金が増えたのか減ったのかを把握するイメージです。
決算書の作成は一度きりの大仕事ではなく、明確なステップに沿って進めることで効率的かつ正確に仕上げられます。
ここでは、準備から完成までの5ステップを体系的に整理しました。
それぞれの段階で「やること」「注意点」「効率化のヒント」を押さえていきましょう。
やること
注意点
ここでズレを放置すると、後の工程で原因追跡に膨大な時間がかかります。
期末直前ではなく、月次で確認しておくことが重要です。
効率化のヒント
毎月の月次決算を正確に行っていれば、年次決算は「確認作業」で済み、大幅に負担を軽減できます。
やること
決算期特有の仕訳を計上します。具体的には:
注意点
計上漏れや金額の算定ミスが最も多いポイントです。
過年度の仕訳例を参照したり、監査法人・税理士との連携でダブルチェックを行いましょう。
効率化のヒント
あらかじめ「決算整理仕訳チェックリスト」を作っておけば、毎年の確認漏れを防げます。
やること
決算整理仕訳を反映させ、「決算整理後残高試算表」を作成します。
注意点
試算表は借方と貸方の合計が必ず一致する必要があります。
不一致の場合は、仕訳ミスや入力漏れがあるため、早急に確認しましょう。
効率化のヒント
勘定科目ごとに「チェック担当者」を割り振ると、属人化を避けつつ精度を高められます。
やること
試算表の数値を損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)に転記し、両者で算出される当期純利益が一致しているかを確認します。
必要に応じてキャッシュフロー計算書(C/F)も作成します。
注意点
科目の分類や表示区分を誤ると、財務分析や融資判断に影響するため注意が必要です。
効率化のヒント
会計ソフトを活用すれば、試算表から自動でP/LやB/Sを作成でき、転記ミスを防ぎつつ工数を削減できます。
やること
注意点
中小企業では軽視されがちですが、金融機関や投資家にとって重要な開示情報です。
正確かつ簡潔にまとめる必要があります。
効率化のヒント
過年度のフォーマットをベースにし、更新すべき箇所だけ差し替える形にすれば効率的です。
決算書の作成が終わっても、経理業務はまだ完結しません。
取締役会での承認や株主総会での報告、税務申告、書類の保存など、会社として果たすべき重要な手続きが残っています。
ここでは、決算書完成後に必ず行うべき業務を整理します。
株式会社では、完成した決算書をまず取締役会で承認する必要があります。
その後、株主総会で株主に報告し、承認を得る流れとなります。
特に株主総会は、株主への説明責任を果たす場であり、決算情報の透明性を確保することが会社の信頼維持につながります。
決算書を基に、法人税・消費税・地方税などの税務申告書を作成し、法定期限までに納税を行います。
ここで注意すべきは、会計上の利益と税務上の所得は必ずしも一致しない点です。
減価償却の方法や引当金の扱いなど、会計と税務のルールには違いがあるため、調整が必要となります。
そのため多くの企業では、税理士などの専門家に申告書の作成を依頼し、適正な申告と納税を行っています。
決算書や関連する帳簿書類は、会社法や法人税法に基づき一定期間の保存義務があります。
また、電子帳簿保存法を活用すれば、紙ではなくデータでの保存も可能です。
保存方法を誤ると法令違反となる可能性があるため、規定に沿った適切な管理が求められます。
決算書作成は、経理経験の有無や企業の規模によって疑問点が変わってきます。
ここでは、実務でよく寄せられる質問に答えました。
A. 小規模事業であれば可能ですが、税務や会計基準の知識がないと正確な決算書を作成するのは難しいのが実情です。
初めての場合は、会計ソフトを利用したり、税理士に確認してもらうことで、精度と安心感を高めるのがおすすめです。
A. 特にミスが多いのは、減価償却費、棚卸資産、経過勘定(前払費用・未払費用など)、引当金の計上です。
金額の算定や計上漏れが起こりやすいため、過年度の仕訳やチェックリストを活用して確認することが重要です。
A. 技術的には可能ですが、入力ミスや転記漏れのリスクが高く、効率面でも大きな負担になります。
会計ソフトを使えば自動仕訳や転記機能があり、決算書の作成もワンクリックで行えるため、特に初心者や少人数経理では導入を検討する価値があります。
A. 決算書は会社の経営状況を示す財務報告書(会社法に基づく外部開示資料)です。
一方、税務申告書は法人税や消費税などを計算するための税法上の資料です。
両者は作成目的も算定ルールも異なるため、会計上の利益と税務上の所得が一致しないことがあります。
あわせて読みたい
決算書の作成は、経理担当者にとって年に一度の最重要業務であり、その正確性とスピードは会社全体の信頼に直結します。
単なる数字の取りまとめではなく、会社の経営状況を正しく示す責任ある仕事だからこそ、専門性と丁寧さが求められます。
本記事で紹介したように、決算は「準備」「決算整理仕訳」「試算表作成」「決算書作成」「附属明細作成」というステップを踏めば、迷わず進められます。
各段階でのチェックを怠らず、効率化の工夫を取り入れることが、ミスを防ぎスムーズに決算を終える最大のポイントです。
まずは、自社の決算スケジュールを確認し、どのステップに改善の余地があるかを洗い出してみましょう。
その一歩が、正確で信頼される決算業務につながり、経理担当者としての評価や信頼を確かなものにします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

外国人を雇用する際の雇用保険はどうする?注意点について国際業務に詳しい法律事務所が解説

ダイバーシティ推進の現在地―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~
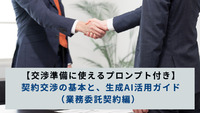
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)

オフィスステーション導入事例集

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

オフィスステーション年末調整

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
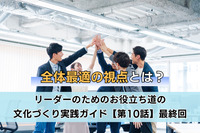
全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?

法務FAQ構築の手順とポイントを解説|AIを活用した効率的な運用・更新手法も紹介

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
公開日 /-create_datetime-/