公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
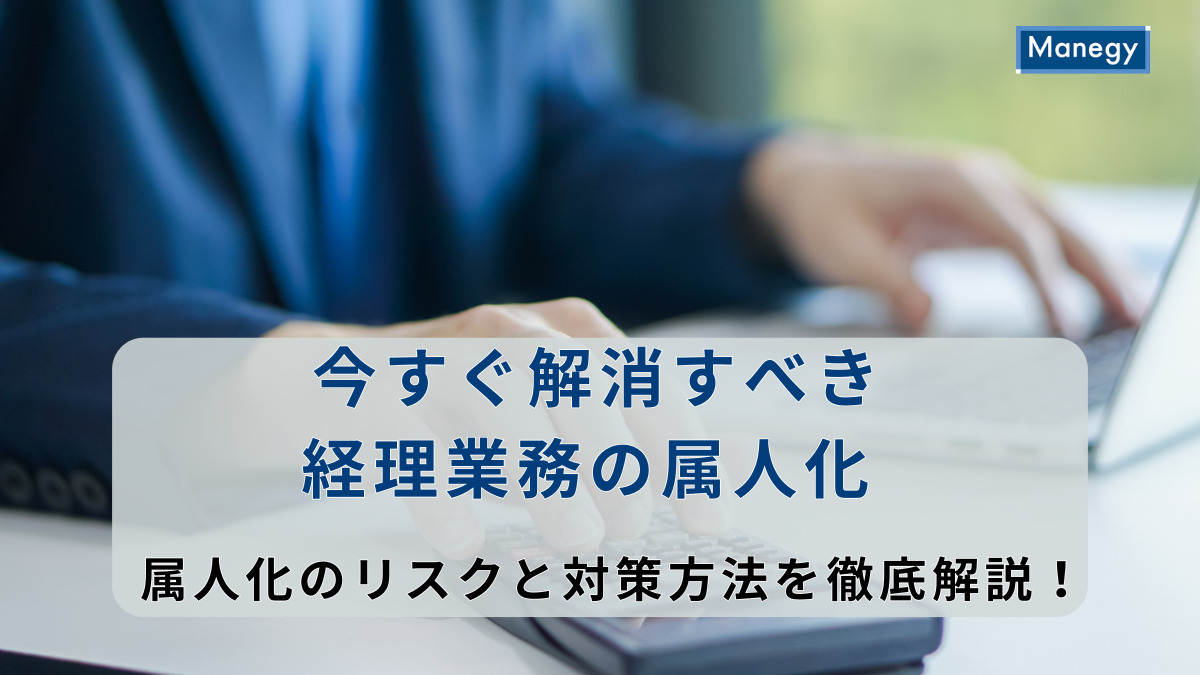
「うちの経理は〇〇さんがいないと回らない」
このような状況に心当たりはありませんか。これが経理業務の「属人化」です。
本記事では、経理の属人化がもたらすリスクとその原因を整理し、解消に向けた具体的なステップをわかりやすく解説します。
属人化とは、特定の担当者だけが業務手順や判断基準、ノウハウを把握しており、その人がいなければ業務が進まない状態を指します。
請求書処理や仕訳ルール、取引先対応など、本来共有すべき情報が個人に集中すると、経理機能全体が脆弱になります。
特に中小企業では、経理担当者が1〜2名しかいないケースも多く、長年の経験に依存した業務運用が常態化しやすい傾向があります。
担当者が多忙で手順を言語化できないまま業務が積み重なり、「この処理は〇〇さんしか分からない」といった状況が生まれやすいのです。
経理部門は正確性と期日厳守が求められるため、一見スムーズに見えても、実際には“優秀な個人頼み”という危ういバランスで成り立っているケースが少なくありません。
経理の属人化は、日々の業務をこなしている間は目立たないものの、知らないうちに組織の基盤を弱らせていくリスクを抱えています。
ここでは、経理の属人化が引き起こす4つのリスクについて紹介します。
特定の担当者に業務が集中していると、その人が急に休職や退職した際、業務が止まる恐れがあります。
月末締めや給与計算、税務申告など、期限の厳しい処理が滞れば、資金繰りや取引先との信頼に影響します。
引き継ぎ期間が短いまま後任が手探りで対応すると、ミスや遅延が発生しやすく、混乱が長期化することもあります。
実際に、ベテラン経理の退職をきっかけに数カ月間経理機能が混乱した例も少なくありません。
属人化が進むと、チェック体制が形骸化し、不正や誤処理を見逃しやすくなります。
経理は金銭を扱う業務であるため、複数人での確認が欠かせません。
しかし「任せているから大丈夫」という油断が広がると、実質的な牽制機能が失われます。
長年一人で経理を担っていた社員の退職後に不正が発覚した例もあり、意図的でなくても誤った処理が監査で問題になるケースもあります。
一人の担当者が独自のやり方で業務を抱えると、改善の視点が生まれにくくなります。
本人は慣れた手順で効率的に進めているつもりでも、実際には手作業や重複作業が残っていることが多いものです。
他のメンバーもプロセスを把握できず、改善提案が出せません。
結果として、非効率な業務が放置され、DX推進やコスト削減の機会を逃すことになります。
あわせて読みたい
属人化により、知識やノウハウが特定の担当者に偏ると、若手の育成が難しくなります。
若手が補助業務しか経験できず、専門性を高める機会を失うことで、部門全体のスキルが伸びません。
担当者の退職とともにノウハウが失われれば、経理機能の水準が低下し、組織全体の対応力にも影響します。
経理の属人化がこれほど大きなリスクを孕んでいるにもかかわらず、多くの企業で問題が解消されないのはなぜでしょうか。
ここでは、経理業務が属人化しやすい主な3つの原因を紹介します。
多くの企業では、経理部門が常に人手不足の状態にあります。
営業などの直接部門(売上に直結する部門)が優先され、経理は最小限の人数で運営されることが一般的です。
この状況では、効率化よりも「目の前の処理を終えること」が最優先となり、スキルの高い担当者に業務が集中します。
また、中小企業では人事や総務を兼任しているケースも多く、マニュアル整備や仕組み化に時間を割くことができません。
経理業務には、勘定科目の判断や取引先ごとの処理方法など、経験に依存するノウハウが多く存在します。
これらが文書化されず、担当者の頭の中に留まっていることが属人化の大きな要因です。
忙しさを理由にマニュアル作成が後回しになったり、「書くほどのことではない」と判断されたりして、知識が個人に閉じてしまいます。
古いシステムやExcel・紙ベースの管理が残る企業では、作業が属人的になりやすい傾向があります。
データが個人のPCやローカルフォルダに保存されていると、他の担当者が確認できず、業務全体の可視化が困難です。
また、手作業が多い分、業務負荷が高まり、改善よりも「自分で処理する方が早い」と属人的な方法を続けてしまいます。
経理の属人化を断ち切るには、組織全体で解消にコミットし、体系的かつ段階的に取り組む必要があります。
ここでは、属人化を解消するための具体的な5つのステップをご紹介します。
まずは現状の業務を「見える化」することから始めます。
誰が、いつ、何を、どのように処理しているのかを整理し、業務フロー図やタスクリストに落とし込みます。
決算や支払処理などの主要業務を図解することで、特定の担当者に依存している工程や非効率な作業が明確になります。
棚卸で洗い出した業務内容をもとに、誰でも再現できるマニュアルを作成します。
目的や手順、注意点、イレギュラー対応を具体的に記載し、画面キャプチャや記入例を活用すると理解しやすくなります。
完璧を目指すよりも「まずは形にする」ことが重要です。
法改正や業務変更に応じて更新し、クラウド上で常に最新版を共有しましょう。
マニュアルだけでなく、知識を共有する仕組みづくりが欠かせません。
月次決算後の振り返り会や勉強会を定期開催し、複雑な処理やイレギュラー対応をチーム全体で共有します。
また、社内Wikiやクラウドストレージを使い、ノウハウや資料を一元管理する「ナレッジベース」を構築すると、検索性が高まり教育にも活用できます。
一つの業務を複数人で担当できる体制を作り、リスクを分散します。
重要な業務には主担当とサブ担当を設け、相互チェックと情報共有を習慣化することで、担当者の不在時でも業務が止まりません。
また、経理のアウトソーシングサービスを利用することも有効です。
専門性の高い業務を外部に委託することで、社内担当者の負担を軽減し、属人化リスクを抑えながらコア業務に集中できる体制を整えられます。
属人化を根本から解消する鍵は、ITツールの活用です。
クラウド会計ソフトやRPA、ワークフローシステムを導入すれば、仕訳や経費処理などの定型業務を自動化し、作業の標準化と透明化を実現できます。
システム上に業務ルールを組み込むことで、担当者の判断に依存せず、誰が行っても同じ品質で処理できる体制を構築できます。
経理の属人化は、表面上は業務が回っていても、担当者の不在による停滞や不正・ミス、業務改善の遅れ、人材育成の停滞など、深刻なリスクを抱えています。
まずは業務の棚卸とマニュアル作成で“見える化”し、ナレッジ共有や担当の二重体制、IT化といった流れで段階的に「経理の属人化」を解消していきましょう。
「経理の属人化解消」は一朝一夕ではありませんが、組織全体で計画的に取り組めば、誰が担当しても安定して業務が回る持続可能な経理体制を実現できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

IPO審査で問われる「労務コンプライアンス」の重要項目と対策~JPXガイドブック2026年1月版を踏まえて~
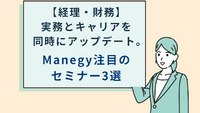
【経理・財務】実務とキャリアを同時にアップデート。Manegy注目のセミナー3選
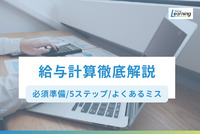
【人事・経理の基本】給与計算のやり方、何から始める? 必須準備から5ステップ、よくあるミスまで徹底解説
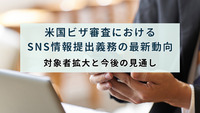
米国ビザ審査におけるSNS情報提出義務の最新動向:対象者拡大と今後の見通し

「ピアコーチング」で横のつながりを強め、組織パフォーマンスに結びつけていく方法とは

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
公開日 /-create_datetime-/