公開日 /-create_datetime-/

企業が法令に違反する行為をした場合、行政から「営業停止処分」を受ける場合があることをご存知でしょうか。営業停止処分の基準は各種法令において定められており、例えば建設業者であれば、建設業法等に定められている規定に違反した場合、その法に基づいて行政が営業停止処分を下すわけです。
今回は、営業停止処分が課せられるのはどのような場合なのかについて、建設業に焦点を当てつつ解説します。
そもそも営業停止処分とは
営業停止処分とは行政庁による営業の禁止・営業許可の効力の停止のことです。企業が事業を行う上で従うべき法令に違反したときに、違反の継続の防止および制裁を与えるために行われます。どのようなケースに対して営業停止処分が行われるのかは各産業法において規定されており、行政は法規に則って営業停止処分を下すのです。
例えば建設業者の場合、不正入札や違法建築、あるいは行政に対する虚偽申請などを行い、それが発覚すると、営業停止処分の対象となります。通常は、状況を改善するよう指示処分を下して、なおそれに従わない場合に営業停止処分が下されますが、刑法や独占禁止法などに明確に違反する重大な行為があったときは、指示処分を飛ばして営業停止処分が下される場合もあります。
リニア談合事件で下された営業停止処分
最近営業停止処分を受けた有名なケースとしては、今年1月に大手ゼネコンの大林組と清水建設に対するものが挙げられるでしょう。昨年、リニア中央新幹線の建設工事をめぐって大手ゼネコン4社が談合を行ったことが分かり、大林組と清水建設が独占禁止法違反の罪に問われました。そして昨年10月の判決公判において、「国家的なプロジェクトで違法受注をした罪は重い」として大林組に対しては2億円、清水建設に対しては1億8,000万円もの罰金刑が言い渡されたのです。
この判決を受けて国土交通省関東地方整備局は、今年1月、大林組と清水建設に対して建設業法に基づいて営業停止処分としました。具体的な期間は2月2日から6月1日までの120日間です。独占禁止法違反により有罪判決を受けたことが、営業停止処分の決め手になったわけです。
具体的な違法内容としては、大林組、清水建設、大成建設、鹿島建設の4社の担当幹部が、「リニア中央新幹線の品川駅と名古屋駅の新設工事をめぐって、お互いに話し合いをして受注予定業者を決めたこと」、そして「JR東海に見積書を提出する前に、お互いに清算資料を見せ合って、より高額で受注できるようにしたこと」などが判決の中で挙げられています。こうした談合行為が、独占禁止法違反として有罪判決を受け、営業停止処分を受ける原因となりました。
営業停止処分が下されるまでのプロセス
通常、行政から営業停止処分を受けるときは、いきなりその通知が来るわけではありません。ひとまず行政側から、なぜ法令に違反するような行為を取ったのか、企業側の弁明を聞く機会が与えられます。行政側を納得させるような合理的な弁明ができなかった場合、営業停止処分の正式な通知が伝えられ、通知を受けた14日後から営業停止となるのが一般的です。
もし営業停止処分の通知がきたら、2週間以内に処分の通知前に取り決めた契約の相手に、営業停止処分を受けたことを連絡する義務があります。もしこの連絡を怠った場合は罰則が科せられるので、確実に相手側に伝えなければなりません。契約相手は、その企業が営業停止処分を受けた日、もしくは営業停止処分が下されたと連絡があった日から30日以内であれば、締結した契約を解除できます。
営業停止処分によってできなくなる行為 ―建設業のケース―
もし営業停止処分を受けると、建設業の場合は新規の建設工事の請負契約締結ができません。また、処分を受ける前に締結された請負契約に新たな工事を追加すること、新規工事の請負契約を結ぶために行う入札や見積もり、交渉等も禁じられています。さらに、営業停止処分の内容が、公共工事または公共工事以外の工事に限定されている場合、地域が限定されている場合、業種が限定されている場合などは、それぞれ該当する内容に従って、新規の契約請負や新たな工事の追加契約などは締結できません。
ただ、営業停止処分前に結んだ請負契約に基づく建設工事は行えます。また、建設業の許可と入札参加資格の申請、各種修繕工事、請負代金等の請求や支払い、銀行からの借り入れ等も行えるので、大企業であれば会社が倒産するほどの危機は避けられるのではないでしょうか。
まとめ
行政から営業停止処分を受けるということは、それだけ重大な法を犯して企業経営を行っていたということです。重大なコンプライアンス違反が露見して実際に営業停止処分を受けてしまうと、営業停止期間中は本来行うべき業務を行えなくなるので、業績の大幅な落ち込みは避けられません。株式会社であればそのことは株価にも大きく影響することとなり、実際、リニア談合によって営業停止処分を受けた大林組の株価は、談合の事実が報道されてからどんどん下降していきました(現在は、大阪万博開催の請負業者としての期待感等から、株価は上昇しつつあるようです)。営業停止処分は、企業にとって様々な形でマイナス効果をもたらす事態であると言えるでしょう。
関連記事:改めて考える「内部通報制度」の重要性
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
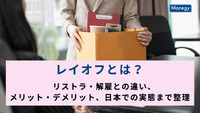
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
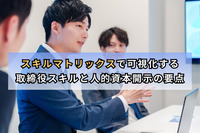
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース



































