公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
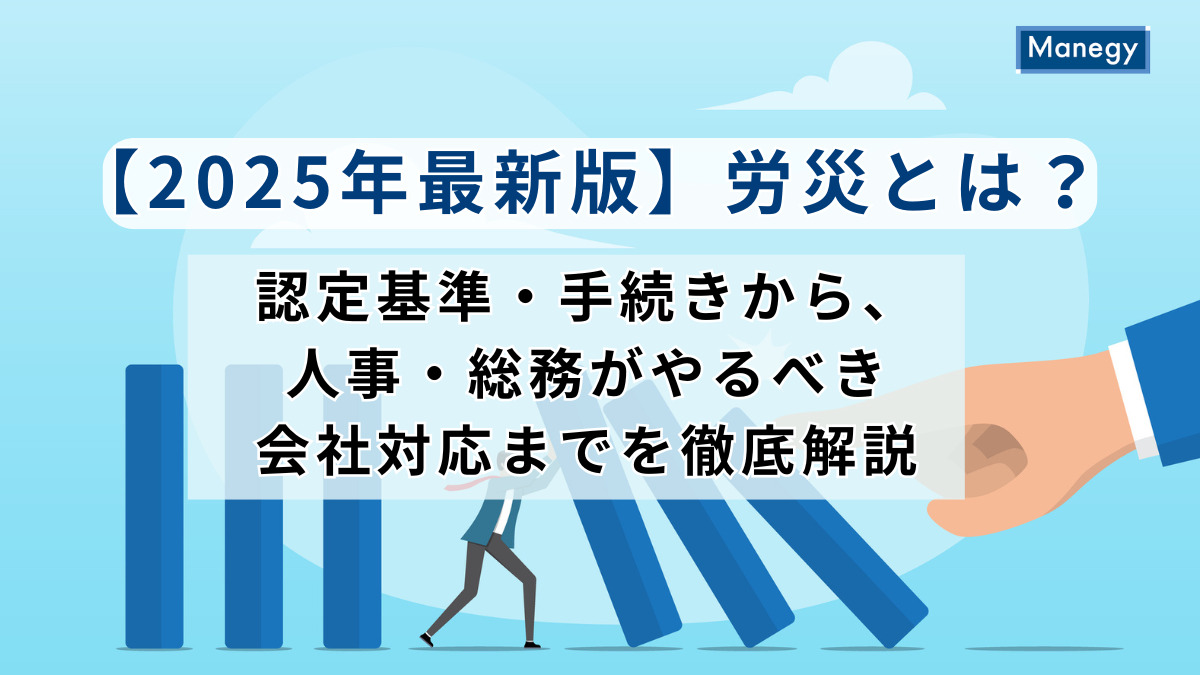
労災(労働災害)は、企業にとって「いつ起きてもおかしくないリスク」のひとつです。現場で従業員がケガをしたり、通勤途中に事故に遭ったりした場合、人事・総務担当者は迅速かつ正確に判断・対応しなければなりません。対応を誤れば、従業員の不利益や会社の法的責任につながるだけでなく、信頼関係を損なう恐れもあります。
本記事では、2025年の最新情報を踏まえ、「労災とは何か」という基本から、認定基準、会社が行うべき具体的手続き、そして再発防止策までをわかりやすく解説します。万一のトラブルに備え、まずは基礎知識の整理から始めてみましょう。
「労災(労働災害)」とは、労働者が仕事に関連して負傷・疾病・障害・死亡に至った場合を指します。例えば、工場での機械操作中に手をケガしたケースや、長時間労働による過労死、パワハラが原因の精神疾患なども労災に含まれます。重要なのは「仕事との関連性」があるかどうかです。私生活でのケガや病気は原則として対象外ですが、勤務や通勤と密接に結びついた出来事であれば、労災として認定される可能性があります。
労災保険制度は、労働者が安心して働ける環境を守るために国が設けた制度で、事業主は原則として必ず加入しなければなりません。目的は、業務や通勤に起因する災害によって被災した労働者やその遺族に、治療費・休業補償・障害補償などを給付し、生活の安定を図ることにあります。
対象となるのは正社員だけではありません。パート、アルバイト、日雇い労働者、さらには短時間勤務の従業員も含まれ、「労働基準法上の労働者」であれば一律にカバーされる点がポイントです。実務上、「非正規だから労災は対象外」と誤解している従業員も少なくないため、管理部門が正しく説明できるよう備えておく必要があります。
労災には大きく分けて2つの類型があります。
この2つの区分を押さえておくことが、労災の判断を行う際の第一歩です。特に人事・総務担当者は、従業員からの相談を受けた際に「これは業務災害か、それとも通勤災害か」を整理して回答できるようにしておきましょう。
労災の認定にあたり、最も基本となるのが 「業務遂行性」 と 「業務起因性」 という2つの要件です。
業務遂行性:会社の指揮命令下にあり、業務を遂行していたかどうか
業務起因性:その業務が原因となって傷病が発生したかどうか
この両方を満たしてはじめて「業務災害」として認定されます。
OK事例
NG事例
一見グレーに見える事例も、2要件に当てはめて整理することで判断がしやすくなります。人事・総務担当者は、相談を受けた際に「会社の管理下か?」「業務が原因か?」という2つの視点で切り分けるとスムーズです。
通勤中の災害も「合理的な経路・方法」で発生した場合には労災として認められます。ここでいう合理的とは、自宅から会社への往復、あるいは業務に必要な経路を意味します。
OK事例
NG事例
寄り道や経路変更が「日常生活に通常伴う程度」であれば認められますが、明らかに業務や通勤とは関係ない行動であれば対象外となります。この線引きは実務でもよく相談を受けるポイントです。
近年増えているのが、精神疾患や過労死に関する労災申請です。厚生労働省は「長時間労働(いわゆる過労死ライン=月80時間超の時間外労働)」や「強い心理的負荷(パワハラ、いじめなど)」が原因の場合、労災として認定されることがあるとしています。
ただし、身体的なケガに比べて 認定のハードルは高く、詳細な証拠(勤怠記録、業務内容の証明、医師の診断書など)が求められる のが実情です。
一方で、認定されれば企業にとって重大な社会的影響を及ぼします。人事・総務担当者は、長時間労働や職場環境の改善を怠ると労災リスクが高まることを理解し、予防的なマネジメントを徹底する必要があります。
労災が発生したとき、人事・総務担当者に求められるのは「迅速かつ正確な対応」です。ここでは、事故発生の瞬間から会社が取るべき行動を、時系列で整理します。
まず最優先すべきは 従業員の命と健康の保護 です。速やかに応急処置を行い、必要に応じて救急車を手配します。その際、二次被害を防ぐため現場の危険箇所を封鎖し、安全を確保することも忘れてはなりません。初動対応が遅れると、従業員の健康被害だけでなく、会社の責任問題に直結します。
救護が終わったら、事故の状況を 5W1H(いつ・どこで・誰が・何をして・どうなったか・なぜ) で整理し、正確に記録します。
可能であれば現場写真を撮影し、目撃者からヒアリングを行うことも重要です。記録は後の労災認定や再発防止策に直結するため、漏れなく残しておきましょう。
労災での治療は、健康保険ではなく労災保険を利用するのが原則 です。従業員が誤って健康保険証を使ってしまうと、後で煩雑な手続きが必要になります。
そのため、被災者には必ず「労災指定病院」での受診を案内しましょう。労災指定病院であれば、従業員は窓口での自己負担なく治療を受けられます。人事・総務が事前に近隣の指定病院を把握しておくことは、迅速な対応のために欠かせません。
事故の初期対応が完了したら、法定の報告・申請手続きに移ります。
■ 労働者死傷病報告の提出
従業員が 休業4日以上 の負傷または疾病に至った場合、労働基準監督署への提出が義務づけられています。
■ 保険給付請求書の作成・提出
治療費や休業補償給付を受けるためには、従業員本人による請求書作成が必要ですが、会社にはその手続きをサポートする「助力義務」があります。必要な様式を案内し、記入方法を指導することが求められます。
これらの手続きが遅れると、従業員の補償が受けられずトラブルに発展しかねません。法定の期限や必要書類をあらかじめ整理し、チェックリスト化しておくと安心です。
労災が発生した後に求められるのは、単なる処理対応ではなく、「なぜ起きたのか」を振り返り、二度と同じことを繰り返さない仕組みを作ること です。ここからは、再発防止に向けた具体的な流れを解説します。
まずは発生した事故や疾病の原因を正確に把握することが重要です。表面的な「作業手順を誤った」だけではなく、
といった多角的な視点で分析します。ヒューマンエラーだけでなく、組織や仕組みの問題に焦点を当てる ことが、根本的な改善につながります。
労災発生後は、事業場に設置されている 安全衛生委員会 で原因と対応策を検討するのが基本です。ここでは、
など、再発防止につながる具体策を議論します。決定した施策は書面にまとめ、実施計画として責任者と期限を明確化しておくことが実務上のポイントです。
策定した対策は、関係部署だけでなく 全従業員に周知 する必要があります。具体的には、
といった方法が考えられます。また、年1回以上の安全衛生教育を行い、労災リスクや対応手順を従業員一人ひとりが理解している状態を維持することが重要です。
はい、対象になります。労災保険は「雇用形態」に関わらず、労働基準法上の労働者すべてに適用されます。正社員はもちろん、パート、アルバイト、日雇い、契約社員も加入対象です。実務では「短時間だから対象外」と誤解しているケースが多いため、会社側が正しく説明し、安心して働けるよう周知しておくことが重要です。
条件を満たせば労災の対象となります。ポイントは 「業務遂行性」と「業務起因性」 があるかどうかです。例えば、勤務時間中に会社の指示に基づいて作業していた際のケガは労災と認められる可能性があります。一方、私的な家事中(掃除や料理中)のケガは対象外です。テレワークの場合、業務と私生活の線引きが曖昧になりやすいため、勤務ルールや業務指示を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
会社は従業員の意思だけで労災の利用を避けることはできません。労災隠しは違法行為 とされ、会社に罰則が科される可能性もあります。従業員が「周囲に迷惑をかけたくない」「昇進に響くのでは」と懸念するケースもありますが、労災は労働者の権利であり、適切に利用することが会社の義務です。人事・総務担当者は正しい制度内容を説明し、安心して申請できる環境を整えましょう。
労災申請が不支給とされた場合でも、従業員には 審査請求・再審査請求 などの不服申し立て手段があります。まずは行政からの不支給理由を確認し、必要に応じて証拠書類(勤怠記録や診断書など)を追加提出することが有効です。会社としては、従業員が適切に権利を行使できるよう情報提供を行い、サポートする姿勢が望まれます。
労災保険料は、原則として事業主が全額負担しますが、個別の労災発生件数によって直ちに保険料が上がるわけではありません。ただし、一部の業種では メリット制 が適用され、一定期間内の労災発生状況に応じて料率が上下する仕組みがあります。いずれにせよ、労災を正しく申請することは法律上の義務であり、隠すことによるリスクの方がはるかに大きいと理解しておきましょう。
労災への対応は、企業に課された法的義務であると同時に、従業員の生活と健康を守るための最も重要な仕組みです。発生時に適切な手順を踏み、確実に補償を行うことは、単なる事務処理ではなく、従業員との信頼関係を築き、安心して働ける職場環境を維持する“土台”となります。
また、対応を誤れば法令違反や訴訟リスクにつながる一方、正しく対処すれば企業のコンプライアンス力や組織の健全性を示すことができます。労災対応は「万が一のときにだけ必要なもの」ではなく、日頃からの準備と教育が欠かせません。
この記事を参考に、まずは自社の安全衛生体制やマニュアルを確認し、不備があれば改善するところから始めてみましょう。平時から知識を蓄え、有事に備えることこそが、管理部門に求められる大切な役割であり、従業員と会社の信頼を守る確かな一歩となります。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

ラフールサーベイ導入事例集

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

社員研修を成功させる計画立案とKPI設定と効果測定

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!
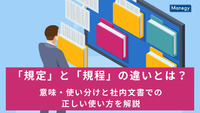
「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説
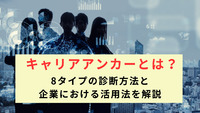
キャリアアンカーとは? 8タイプの診断方法と企業における活用法を解説
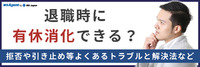
退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
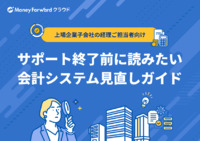
サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
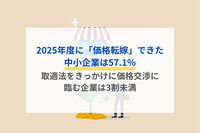
2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
公開日 /-create_datetime-/