公開日 /-create_datetime-/
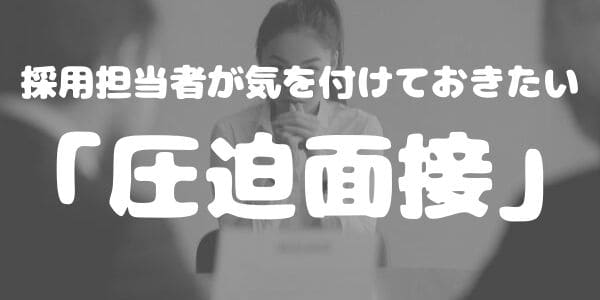
就職・転職希望者に対して面接を行う際、面接官が応募者に対して圧迫感や心理的ストレスを与える「圧迫面接」を行う場合があります。日本のみならず海外の企業でも行われる面接手法の1つであるため、実施しても問題はないと考える経営者・管理者は少なくありません。しかし最近では、圧迫面接にはデメリットが多く、行うべきではないとの見方も広まってきました。
今回は圧迫面接について取り上げ、その概要と行われる理由、行うことのデメリットなどについて詳しく解説します。
圧迫面接とは
採用面接時、面接担当者が応募者に対して意図的に意地の悪い質問、厳しい批判等を行った場合、あるいは横柄な態度をあからさまに示した場合、一般的にそれは圧迫面接と呼ばれます。
具体的には、言葉で応募者を圧迫するケースでは「この仕事に向いていない」、「入社してもすぐに辞めるのでは」等と言い放つ、あるいは応募者が話す意見を「私はそうは思わない」、「その考え方では通用しない」等と全否定することが典型例です。中には、本人の人間性や、それまでの経歴(学歴や職歴)を全否定する面接官もいます。さらに態度で圧迫するケースとしては、机に肘をつく、応募者に対して興味がなさそうにふるまう、上から目線でものを言う、表情を作らず冷たい視線を送り続ける、怒鳴る、といったことが挙げられるでしょう。
圧迫面接が行われる理由とは
圧迫面接はモラル的に好ましいとは決して言えませんが、企業側にはそれを行う理由があります。その1つが、応募者のストレス耐性を見極めるためです。入社後、会社組織で仕事をしていく以上、職務内容や人間関係においてどうしてもストレスに直面します。面接時に圧迫面接をし、敢えて応募者を精神的に追い込むことで、ストレスに弱いのか、それとも強いのかを対応や態度から読み取ろうとするわけです。面接官は、応募者が圧迫面接を前に明らかに落ち込んでいる、心が沈んでいる様子が見受けられたら、ストレス耐性が低いと判断して評価を低くします。一方、そのようなそぶりを見せずに堂々とコミュニケーションがとれている応募者には、高い評価を与えるのです。
さらに圧迫面接は、応募者がどれだけ臨機応変に受け答えできるかを試験するためにも行われます。自分に不利になるような意見、状況に直面したときでも、感情を表情に出さずに冷静に対応できるかどうかを、圧迫面接によって審査するのです。心の中で動揺が起こっていても、そのことを一切表に出さずに落ち着いて的確な受け答えができれば、面接官は良い印象を持ち、高評価を与えます。もし冷静さを欠き適切な受け答えができないままでいるようなら、低い評価を与えるわけです。
圧迫面接にはデメリットが多い
しかし、圧迫面接を行うことによって企業に生じるデメリットは小さくありません。その最たるものが、企業イメージの悪化です。圧迫面接が行われているとの評判が広まれば、人権侵害企業、ブラック企業と評価され、優秀な人材が応募しなくなる恐れがあります。そのような悪評が広まると取引先や顧客からの信用を失うため、長い目で見れば経営状況を悪化させる原因にもなりかねません。
また、面接官が高評価を下して採用を決定しても、応募者の側が圧迫面接における悪い印象をぬぐいきれず、内定を辞退することも考えられます。内定辞退者が増えると予定通りに人材を確保できなくなり、時間と費用もより必要となるでしょう。さらに圧迫面接を受けた応募者が、精神的に傷ついたとして訴訟を起こすリスクもあります。仮に訴訟が起こされれば、裁判における勝敗に関係なく、企業の社会的信用、名声が失墜することは避けられません。
圧迫面接を無意識にしている場合もあるので注意
面接官の側は圧迫面接を行っているつもりがまったくないのに、応募者の側から見て「圧迫面接だった」と判断されるケースもあります。その代表例の1つが、応募者の話す内容に対して、面接官の反応が極端に小さい場合です。面接官が一切笑顔を見せない、表情が変わらない、パソコンやスマホを使いながら話を聞いている、応募者の発言を無視するなどの行動は、応募者に圧迫面接が行われたとの印象を与えます。
ほかにも、応募者に対して侮辱する言葉を言ってしまう、態度が威圧的になってしまう、「なぜ」や「どうして」といった質問をくどいほど行うといった行動を見せると、面接官にその意図がなくても、応募者は圧迫面接を受けたと捉えるでしょう。こうした面接官のマナー不足、認識不足が「意図せざる圧迫面接」を生み、企業の評判を落とす危険性があるので、面接を任される人は注意が必要です。
まとめ
圧迫面接は応募者のストレス耐性や臨機応変な対応力等を評価する1つの方法とはなるものの、行うことによって生じる企業イメージの悪化や内定辞退のリスクなどのデメリットは非常に大きいと言えます。企業側が圧迫面接をするつもりがなくても、面接官のマナーが悪いために応募者が圧迫面接を受けたと感じる場合もあるので、採用担当者は気を付けたいところです。企業としても、採用担当者・面接官に対して、圧迫面接を行わないよう事前に教育、指導を行うことを検討すると良いでしょう。
関連記事:その言動、オワハラになっていませんか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース



































