公開日 /-create_datetime-/
優秀なのに「独り立ち」できない若手の扱い方
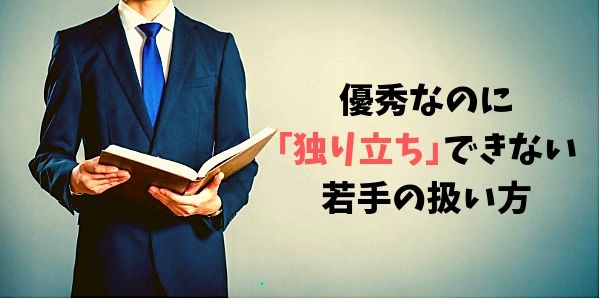
世代間のギャップを象徴するのが「最近の若者は・・・」というフレーズです。若手の部下が、「何を考えているのかわからない」という悩みを抱えている上司や職場のリーダーも多いのではないでしょうか。そんな、部下の掌握がなかなかうまくいかないビジネスパーソンに、参考になる記事をみつけたので紹介します。
言われたことはそつなくこなすが・・・
「優秀なのに“独り立ち”できない若手に欠ける物 “近頃の若者は”と愚痴っても仕方がない」という記事が掲載されているのは、東洋経済オンラインのアルファポリスビジネス編集部提供の記事です。
「最近の若者は・・・」という愚痴は、いつの時代にも共通するフレーズのようですが、最近の傾向として「有能で仕事の覚えは早いが、 “そろそろ仕事を任せてみようか”という段階になると、途端に問題が発生する」というケースが多いようです。
上司としては、指示したことをそつなくこなす若手に、独り立ちさせようと思うのはよくあることでしょう。しかしそうなると、途端にパニックになって仕事が滞ってしまうことが多々あるようで、自分で考え、判断することに対応できないのかもしれません。
その背景には「インターネットの普及による、情報環境の激変がある」と指摘されています。つまり、上司からの指示をこなすための情報はパソコンでもスマホでも、簡単に入手することができるため、そうした情報環境を活用することでスピーディーに業務を片付けることは、経験が浅くてもそれほど難しいことではないでしょう。
しかし、それはあくまでも「上司の指示に従って作業を的確にこなす」のができているだけであり、なぜこの作業が必要なのか、それをいつまでに仕上げなければならないのかなど、仕事の全体像を理解して取り組んでいるわけではないということです。
仕事全体像の把握が必要
同記事では、「仕事の全体像を把握し、自分でマネジメントする能力を身に付けるには、やはりそれなりの時間と経験が必要だ」と、指摘しています。
確かに、与えた業務をスピーディーにこなす仕事ぶりを見ていたら、「そろそろ任せても大丈夫だろう」と、思いたくなります。しかし、入社して半年、1年程度の若手は、やはりまだまだ半人前というのが実態なのではないでしょうか。
それを理解しなければ、任せられた若手も混乱し、パニック状態に陥ってしまうのも当然かもしれません。
“クローズド・クエスチョン”と“オープン・クエスチョン”
では、そのような若手社員を、1人前に育てていくためには、何が必要なのかを見ていきましょう。
まず必要なのは、「仕事の全体像を把握する意識を持たせる」ことで、その方法は「部下に話しをさせる」ことと、記事では紹介されています。
「えっ、そんな単純なこと?」「部下との対話は意識して多くしているよ」という声が聞こえてきそうですが、実は、そこにも落とし穴があるようです。
【上司と部下の典型的な会話例】
上司:「前回は、発売1か月でどれくらい売れたんだっけ」
部下:「ええと、○○個ですね」
上司:「そうか。今回は発売1か月で○○個だから、前回の20%増ぐらいは目指せそうだな!」
部下:「そうですね。頑張って売っていきましょう!」
こうした会話が、上司と部下の間で日常的に交わされているでしょう。ところが、部下は上司の言葉にただ反応しているだけで、「自分で考え、判断することはできていない可能性がある」というのです。
この会話で注目すべきは、イエス・ノーで答えられる“クローズド・クエスチョン”ではなく、たとえば「次の新製品は、どれくらい売れるだろう?」「次はどんな商品をつくるべきだろう?」などの“オープン・クエスチョン”を投げかけることです。そうすることで、部下が本当に仕事の全体像を把握しているのか、上司の言葉に反応しているだけなのかが見えてくるというわけです。
ぜひ実践してみてください。
まとめ
この記事の結論は、若手が“独り立ち”できるようになるためには、作業の手順を覚えるだけでなく、全体像を把握する意識を持つこと、そのためには、若手に意見を述べさせることが大切ということでした。
この記事を参考に、なかなか独り立ちできない若手部下を抱えているビジネスパーソンは、部下との会話の内容を見つめなおしてみてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース



































