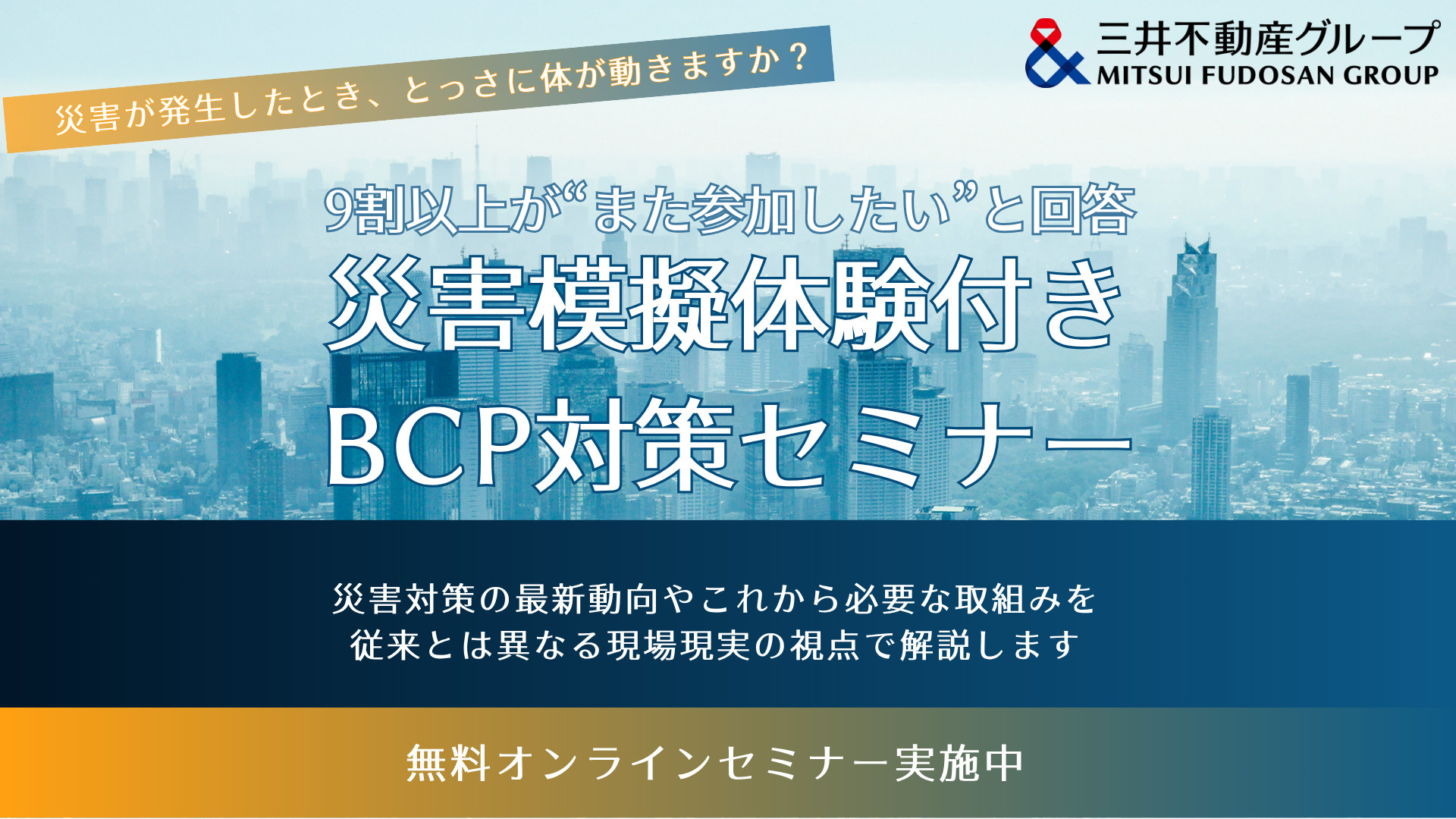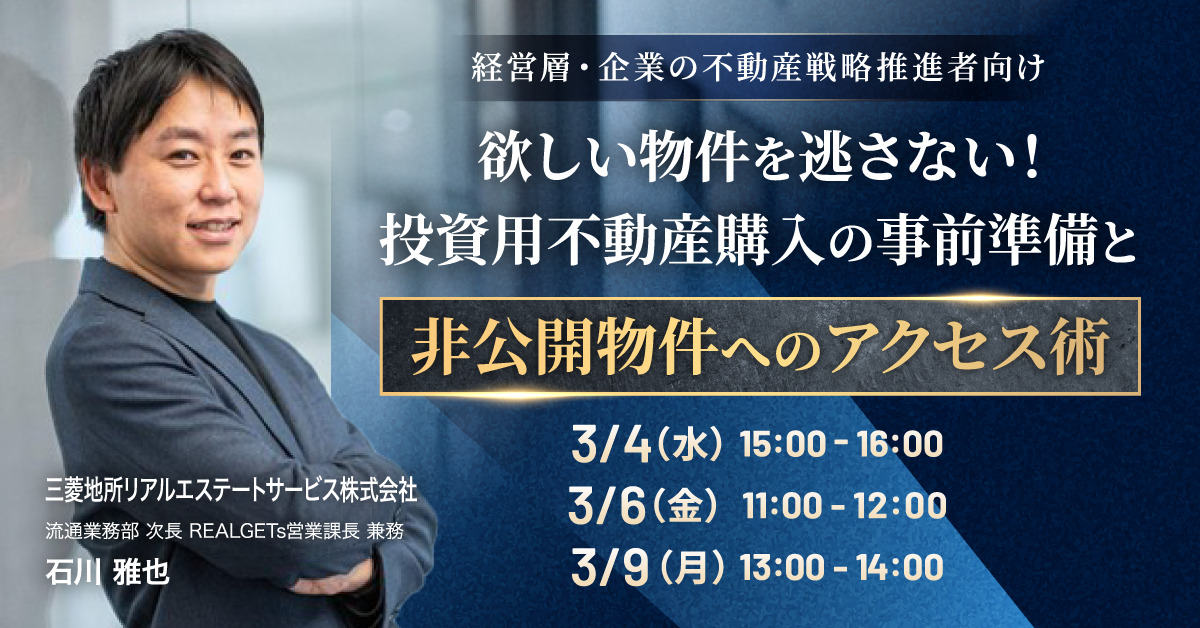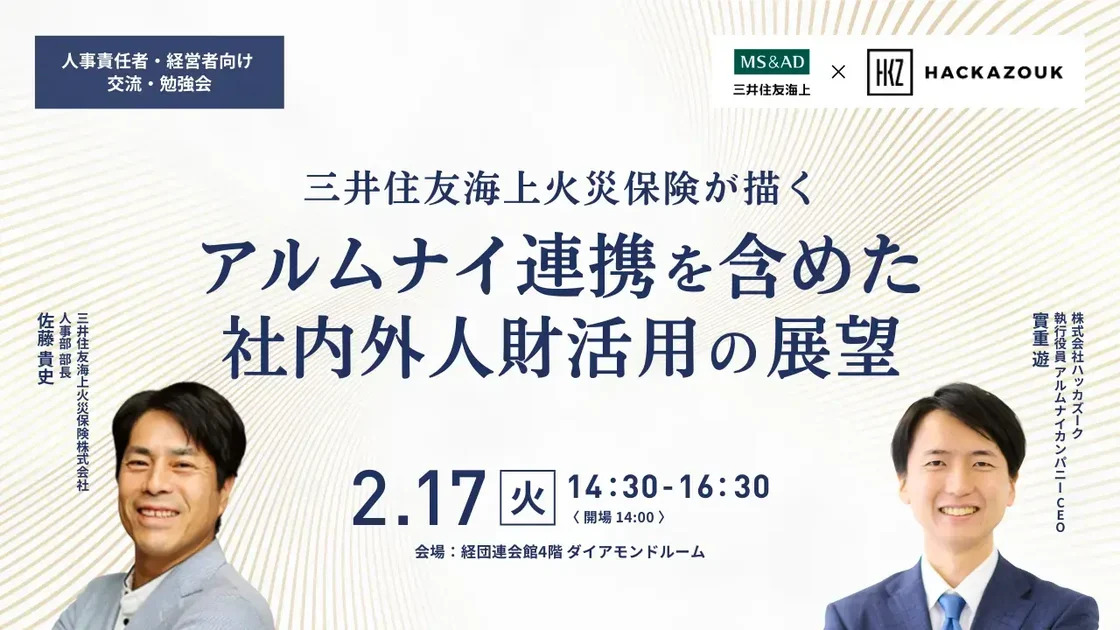公開日 /-create_datetime-/
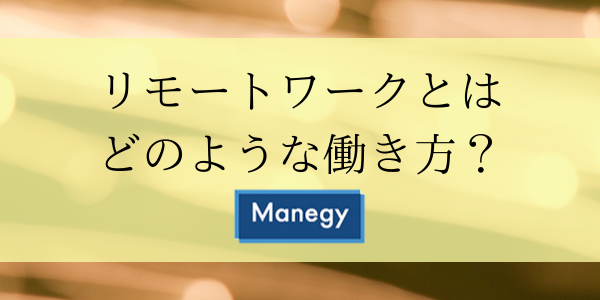
情報インフラが整い、チャットやクラウドサービスによるコミュニケーションが容易になりつつある現在、オフィスに通わずに仕事を行う「リモートワーク」に従事する人が増えてきました。情報化社会が進展する中、新時代に適した働き方として、リモートワークはビジネスの場で注目を集めつつあります。
今回はこのリモートワークとはどのような働き方なのか、リモートワークとにはどのようなメリット、デメリットがあるのか、について解説していきましょう。
リモートワークとは
リモートワークとは、企業に雇用されている人が会社から離れた場所で働くこと、もしくは企業と外部委託の契約を結んでいる人が、自由な場所で働くことです。通常、会社と雇用契約を結んでいる従業員は、会社に出社して働きます。一方、リモートワークは自宅や喫茶店など、会社ではない場所で就労するという働き方です。育児や介護に追われて通勤が難しい場合、あるいは体調を崩して通勤が困難な場合などでも、リモートワークが認められている会社であれば、社員として働き続けることができます。
リモートワークには大きく分けて、自宅を就業場所とする「在宅勤務型」、自宅に限らずどこでも仕事に従事する「モバイルワーク型」、テレワークセンターなど特定の施設等で働く「施設利用型」の3タイプがあります。
実施頻度も決まっているわけではなく、就労者によっては週に1~2日だけ、月に数回だけ、午後だけなど、時間を限ってリモートワークに従事しているケースも多いです。
なお、フリーランスでテレワーク(離れた場所で仕事をすること)を行う個人事業主は、リモートワークには含まれません。リモートワークは企業と雇用契約を結んでいる就労者のことを指します。
リモートワークに注目が集まる背景
通勤しないで自宅等で働くリモートワークに注目が集まりつつある背景には、日本の社会構造上の影響があります。
1つは日本における少子高齢化と人口減少の問題です。『平成30年版高齢社会白書』によると、2017年時点における日本の高齢化率は28.0%に達している一方、労働力人口は年々減少しています。
高齢者人口が増える一方で少子化により現役世代が減少しつつある日本では、労働力を確保することは喫緊の課題となっています。そこで注目を集めているのが、育児や介護に直面しても離職せずに続けられるリモートワークという働き方です。
リモートワークは、企業にとっては働き手をつなぎとめるための重要な手段となり、労働者にとっては、ワーク・ライフ・バランスを実現するための有効な就労手法となるわけです。
2つ目は情報化の進展です。今やどこにいてもパソコンさえあればネットを通じて仕事を行うことができる社会となっています。ICT(情報通信技術)は日々進化しており、リモートワークのやりやすさは、今後さらに増していくのは確実です。国としても、働き方改革を推進する上でテレワークの重要性を認識しており、情報通信をつかさどる総務省が中心となって、その普及に向けた取り組みに注力しています。
地方の中小企業がリモートワークを導入するメリットは大きい
こうしたリモートワークという雇用形態は、特に地方の中小企業において重要になるといわれています。現在、地方の中小企業には優良企業が数多くありますが、人材不足が深刻化しているのが現状です。少子高齢化、過疎化は地方において特に進んでいるため、若手不足・後継者不足により事業継続が危うくなるケースが少なくありません。
リモートワークを導入することで、人材確保方法の幅が広がり、人手不足を解消しやすくなることが期待されます。
さらに地方には、大都市圏に比べると優秀な人材を確保しにくいのも事実です。例えば地方の中小企業の場合、海外進出を見据えて、海外の大学でMBAを取得した語学力の高い人材を得ようとしても、地方の労働市場にそのような人材がそもそも乏しいことが多いです。
しかしリモートワークであれば、大都市圏からでも人材を募集できるので、全国各地から企業が望む人材を確保できます。
リモートワークの問題点
ただし、リモートワークには問題点もあります。
まず、企業側にとっては、労働者の評価が困難になるという点が挙げられるでしょう。成果が数値で把握できる業務ならば離れていても評価しやすいです。しかし事務系の仕事など個人の寄与率が明確化しにくい業務の場合、直接仕事をしている姿を見られないリモートワークでは、適正な評価は行いにくいといえます。
さらに労働者側からすると、仕事量の調整が難しいという問題点が挙げられるでしょう。雇用主・上司は普段からリモートワーカーと直接顔を合わせていないため、どのくらいの仕事量を任せられるのかイメージしにくい面があります。そのため、時として過大な仕事を任せてしまい、リモートワーカーの労働時間を増大化させるという事態が起こりやすいのです。「どこでも仕事ができること」が利点だったはずのリモートワークが、「どこにいても仕事をする必要がある」という仕事に縛られる状況をもたらす恐れさえあります。
まとめ
リモートワークという働き方は、自宅などでリラックスして仕事に打ち込めるため、ナレッジワーク(知的創造を必要とする仕事)にも適しているといわれています。職場で同僚の目を気にしながら仕事をするよりも、解放感のある環境で仕事をした方が、イノベーションをもたらすアイデアが出やすい、というわけです。しかしその一方、リモートワークにはデメリットがあるのも事実です。リモートワークを導入する場合は、それによって生じる弊害や問題点を事前に確認し、対応策を考えておく必要があるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -
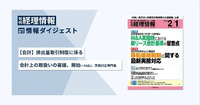
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -
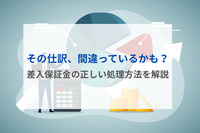
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース -

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説
ニュース