公開日 /-create_datetime-/
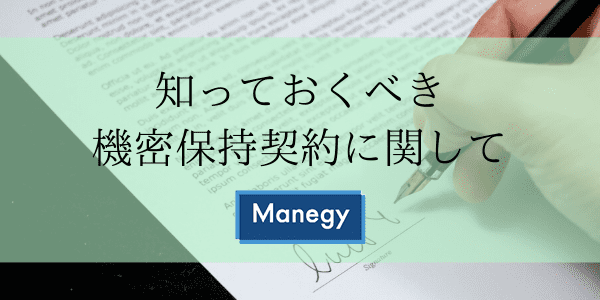
近年、経営や業務の効率化を図るため共同研究開発、事業提携、共同事業、業務委託などを実施する企業が増えており、どの企業においても他社と「機密保持契約(NDA)」を締結する機会が増加しています。自社が不利益を被らない機密保持契約を締結するために、総務担当者が知っておくべきポイントは何でしょうか。
機密保持とは?
機密保持(一般には秘密保持)とは、国家や民間企業が外部に機密情報を開示しないこと。
機密保持契約とは通常、民間企業が自社の機密情報を取引先等外部に開示する際、その情報の取扱い方を定めた契約を指します。国家が機密情報を外部に開示する際の取扱いは、契約ではなく法令に基づきます。
機密保持契約には次の3パターンがあります。
1.自社のみ機密情報を開示するパターン(契約の相手側に機密情報保持義務が発生)
2.契約の相手側のみ機密情報を開示するパターン(自社に機密情報保持義務が発生)
3.双方が機密情報を開示するパターン(双方に相手側の機密情報保持義務が発生)
機密保持契約を結ぶ目的
社会通念上、機密保持契約の対象となる情報は①顧客名簿、②独自の事業オペレーション・業務プロセス、③独自製品の図面・仕様書、④独自製品のサンプル・試作品、⑤独自の技術情報などとされています。
そして、機密保持契約を結ぶ目的は共同研究開発、事業提携、共同事業、業務委託などを実施する際、そのパートナー企業による自社企業機密の情報流出や不正利用の防止にあります。
具体的には次の2つに集約されます。
・特許出願の担保
特許の出願においては
①産業上の利用可能性(その技術が産業上利用できるものであること)
②新規性(新しいものであること)
③進歩性(容易に考え出すことができないものであること)
④先願(先に特許出願されていないこと)
⑤公序良俗に反しないこと
などが特許出願要件になっています。
このため、共同研究開発、事業提携、共同事業、業務委託などのパートナー企業から自社の独自技術が流出してしまうと、その技術は「公知の技術」となり新規性や進歩性の特許出願要件を失い、特許権取得が不可能になります。
・不正使用の防止
例えば自社製品の製造技術が共同研究開発、事業提携、共同事業、業務委託などのパートナー企業に流出すると、パートナー企業はその技術情報を基に同等の製品製造が可能になります。この時、その技術情報が不正競争防止法の「営業秘密」(※)に該当する場合は、販売の差し止め請求や損害賠償請求ができます。パートナー企業の不正使用を防止するためには、機密保持契約による歯止めが不可欠になります。
※不正競争防止法第2条ːこの法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
機密保持契約書のチェックポイント
パートナー企業と機密保持契約書を交わす際、総務担当者がチェックすべきポイントは次の事項です。
1.契約の目的と機密情報の定義
機密保持契約の目的と機密情報の定義・範囲は明確か。また、契約の目的外の機密情報まで情報開示の対象になっていないか。
2.機密保持義務
機密情報利用側の情報取扱い義務が具体的に定められているか。
3.機密情報の目的外利用禁止
機密情報の利用目的が具体的に定められ、その目的外利用禁止条項が盛り込まれているか。
4.機密情報複製の禁止
機密情報複製の禁止条項が盛り込まれているか。
5.機密情報の成果の帰属
機密情報の開示による成果物は、開示側・利用側のどちらに帰属するのか。
6.機密情報の返還・廃棄
機密保持契約期間終了後、機密情報の返還・廃棄義務を利用側に課す条項が盛り込まれているか。
7.機密保持契約の期間
機密保持契約の有効期間は具体的に明記されているか。
8.機密情報の検査権と差し止め請求権
開示した機密情報を利用側がどのように利用しているのかの検査権、ならびに利用側が目的外利用をした場合の利用差し止め請求権が盛り込まれているか。
9.損害賠償請求
開示した機密情報を利用側が第三者に流出・漏洩した場合、利用側に対する損害賠償請求事項が盛り込まれているか。
10.裁判管轄
機密保持契約の内容に関する双方の解釈の食い違いが大きく、法的決着が必要になった時、どこの裁判所で訴訟を起こすのか。
11.日付と署名押印
秘密保持契約締結の年月日記載と契約当事者双方の署名捺印があるか。
これらの事項は法的拘束力の有無と関係しており、また係争事案となり損害賠償請求をする際の立証事項でもあるので、総務担当者は入念なチェックが必要です。
機密保持契約に違反した場合どうなる?
機密保持契約においては社会通念上の、次の行為が契約違反とされています。
・機密情報の複製
機密情報の複製は違反とされています。また機密情報の解析、改変、改竄、転用、流用なども違反と断定される可能性が高いとされています。
・第三者への情報開示
機密情報の利用側が、自社のグループ会社、親密取引先など第三者へその情報を開示することは違反とされています。
・目的外利用
例えば機密保持契約で機密情報開示の目的を「○○の共同研究開発のため」と定めている場合、開示情報を「ついでに」と自社製品の研究開発のために流用することは違反とされています。
これらの違反行為は機密保持契約の「債務不履行」や民法の「不法行為」に該当し、損害賠償請求を免れません。
機密保持契約書のテンプレート
機密保持契約書の作成には手間と時間がかかります。ネットの無料サイトからダウンロードしたテンプレートや、以前の取引先と交わした機密保持契約書を雛型に現案件の機密保持契約書を作成する総務担当者が中には見られます。しかし、このような手抜きは、法的拘束力のない機密保持契約書を作成する結果になってしまいます。
なぜなら、機密保持契約の目的と機密情報の定義・取扱いは案件ごとに異なり、契約書の記載事項もそれに伴い異なるからです。
機密情報開示のリスクが低い機密保持契約書の作成に当たっては、下記に紹介した正しいテンプレートを雛型にするのが賢明でしょう。
秘密保持契約書テンプレート
ダウンロードはこちらから!
機密保持に関する誓約書(入社時) ダウンロードはこちらから!
機密保持に関する誓約書(退職時) ダウンロードはこちらから!
関連記事:機密文書の処理は万全ですか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題
ニュース -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
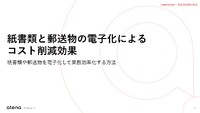
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -
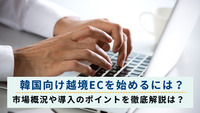
韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース




































