公開日 /-create_datetime-/
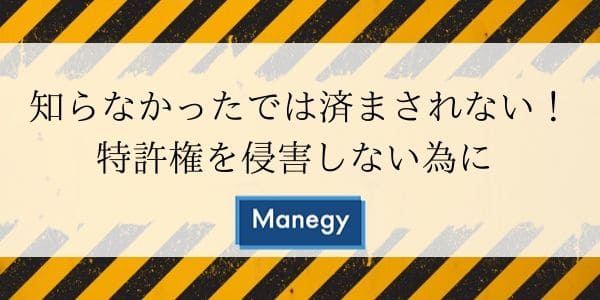
特許権侵害は自社が開発した製品・製法の技術基盤を破壊する行為であり、被害は甚大です。しかし、主観的な疑惑に基づく安易な告発は、侵害行為者に対する単なるクレームや嫌がらせになりかねず、却って危険です。このため、法務・総務担当者はどのような場合に特許権侵害になり、どのような措置を取れるのかを正しく知っている必要があります。
特許権が侵害と判断されるケースは?
「特許権が侵害された」と判断するためには、特許権で保護されている「特許発明の範囲」を明確化する必要があります。もしそれが不明確だったら、第三者はどのような行為が特許権侵害にあたるのか予測できず、法的安定性が損なわれるからです。
特許発明の範囲は、特許法が定める「特許請求の範囲の記載」と「特許発明を特定するための詳細な説明」の2要件により決定されます。
・特許請求の範囲の記載
特許発明の範囲は、特許法で「願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」(特許法第70条1項)と規定されています。ところが、「願書に添付した特許請求の範囲の記載」は要約的な記載なので、曖昧なのが通例です。
例えば「親指袋を備えた安全作業皮手袋で、親指袋の背面皮に親指を背面皮上に出すための切込み部を設け、細かい作業も卒なくこなせるのが特徴」といった具合です。
これでは、切込み部がどんな形状なのか不明で、どこに特徴があるのか漠然としています。この曖昧さを補足するのが「特許発明を特定するための詳細な説明」になります。
・特許発明を特定するための詳細な説明
この説明は「明細書」と「図面」により行うこととされています。
明細書においては、
① その特許発明がどの技術分野なのか
② その技術分野では従来どのような技術的課題があったのか
③ この特許発明はその技術的課題をどのように解決するのか
④ それによりどのような効果を発揮するのか
⑤ どの作業分野に適用するのか
などを記載しなければなりません。
また図面においては、上記詳細な説明の理解を容易にする模式図を記載することになります。
この2要件を特許法は「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」(特許法第70条2項)と規定しています。
したがって、「自社の特許権が侵害された」と判断する場合は、侵害対象製品・製法が2要件構成要素のすべてを満たしていることを確認する必要があります。もし侵害の態様が、2要件構成要素の一部でも欠く場合は判例上「特許権侵害は成立しない」とされています。
特許権を侵害した場合に与えられる罰則
特許権を侵害した場合の罰則として、特許法は7項目の刑事罰と両罰規定を定めています。
◆刑事罰
| (1) 侵害の罪 | 特許法第196条は侵害の罪として「特許権又は専用実施権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定しています。 その理由は「現在においては研究開発に多額の投資を要することから、その成果を保護する特許権の重要性はきわめて高く、例え私益であっても侵害により権利者が被る被害は甚大となる」からとされています。 |
|---|---|
| (2) みなし侵害の罪 | 特許法第196条の2はみなし侵害の罪として「第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定しています。 なお特許法第101条は「業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」など6項目を掲げています。 |
| (3) 詐欺行為の罪 | 特許法第197条は詐欺行為の罪として「詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定しています。 なお、特許法上の詐欺行為とは「審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合」で、具体的には「明細書記載の効果を奏しないにもかかわらず、虚偽の事実を記載した場合や虚偽の実験成績証明書等を提出して特許を受けた場合」とされています。 |
| (4) 虚偽表示の罪 | 特許法第198条は虚偽表示の罪として、「第188条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 なお特許法188条は、虚偽表示として次の行為を掲げています。 ・特許以外の物やその物の包装に、特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 ・特許以外の物であって、その物やその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付し、譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為 ・特許以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許である旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 ・特許発明以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許である旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 |
| (5) 偽証等の罪 | 特許法第199条は偽証等の罪として「この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定しています。 |
| (6) 秘密を漏らした罪 | 特許法第200条は秘密を漏らした罪として「特許庁の職員又はその職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。 |
| (7) 秘密保持命令違反の罪 | 特許法第200条の2は秘密保持命令違反の罪として「秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定しています。 |
◆両罰規定
特許法第201条は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」と規定し第196条・196条の及び第200条の2第1項の場合は3億円以下の罰金刑(第1号)、第197条・198条の場合は1億円以下の罰金刑(第2号)などの両罰規定を設けています。
特許権が侵害されていた場合、どのような対応を行うのか
「自社の特許権が侵害されている」との疑いを持ち、侵害対象製品・製法が「特許権侵害2要件構成要素のすべてを満たしている」ことを確認し、侵害対応措置を取る場合は、次の手順で進めるのが通例とされています。
(1)侵害対象製品・製法を分析し、自社の特許権侵害を立証する
侵害を防ぐためには、まず侵害対象製品・製法を分析し、「特許権侵害2要件構成要素のすべてを侵害(模倣、無断使用)している」事実を立証する必要があります。
(2)侵害者への対応策を決める
立証が済んだら、次に侵害者への対応策を検討し、決定します。対応策には次のものがあります。この中から、自社に最も有利な対応策を選ぶと良いでしょう。
・侵害者とライセンス契約を締結し、ライセンス料を取り立てる
・侵害者に特許権を有償譲渡する
・侵害者に特許発明の利用を一切認めず、侵害行為停止措置を取る
なお、「侵害者に特許発明の利用を一切認めず、侵害行為停止措置を取る」場合は、次のいずれかの措置を取るのが通例です。
| 差止請求 | 侵害行為を停止させる |
| 損害賠償請求 | 侵害により被った損害額を査定し、損害賠償を請求する |
| 不当利得返還請求 | 侵害により侵害者が得た利益の返還を請求する |
| 信用回復措置請求 | 侵害により自社が被った信用・イメージ失墜の回復措置(謝罪広告等)を請求する |
(3)警告書を送付する
侵害者への対応措置を決定したら、侵害者に「警告書」を送付します。警告書には次の3点を箇条書きで記載します。
1.自社の特許権を侵害している新会社の製品・製法
2.自社の特許権を侵害された判断した理由
3.特許権侵害に対する自社の対応措置
(4)法的措置を取る
警告書を送付しても回答しない、特許権侵害の事実を認めないなどの態度を侵害者が取ると、「当事者間で解決を図る」措置が不可能になります。この場合は、
①管轄裁判所に提訴すると同時に仮処分申立を行う
②特許権侵害を警察や検察庁に告訴し、刑事責任追及を求める
などの法的措置を取ります。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため専門家や関連省庁にご確認ください
まとめ
特許権侵害の判断は非常に複雑なので、実際の対応においては企業の総務担当者は手に負えないのが現実です。したがって、この場合は弁理士など外部専門家のアドバイスを受ける必要があります。とは言え、総務担当者が特許権侵害に関する基礎知識を身に着けていないと、外部専門家から適切なアドバイスを受けられない可能性があります。自社の特許権を守るため、総務担当者は特許権侵害の判断基準や対応措置を正しく理解しておくことが重要でしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -
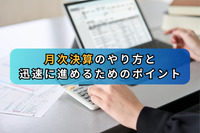
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
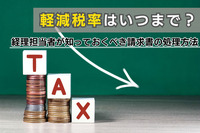
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース




































