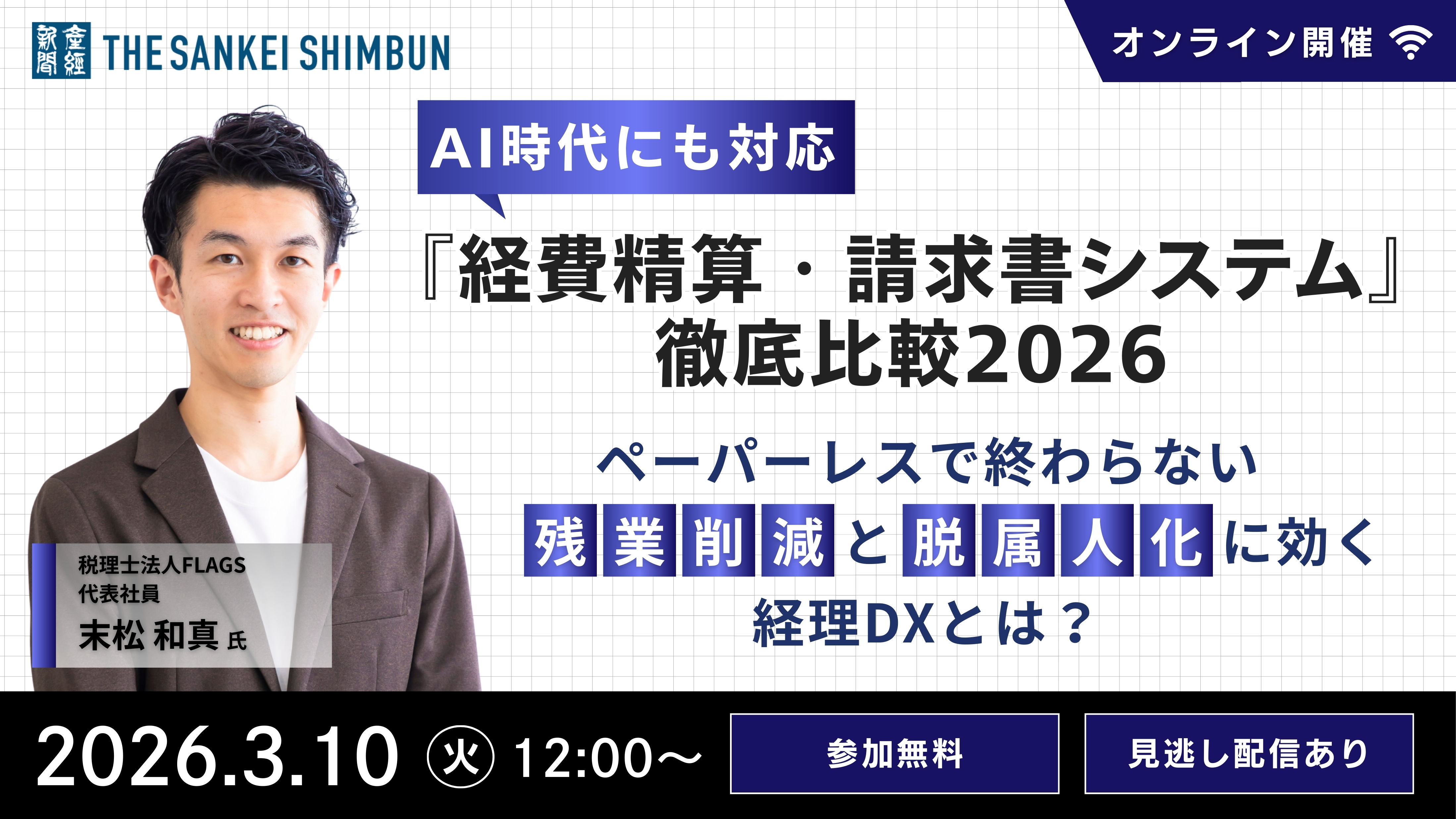公開日 /-create_datetime-/
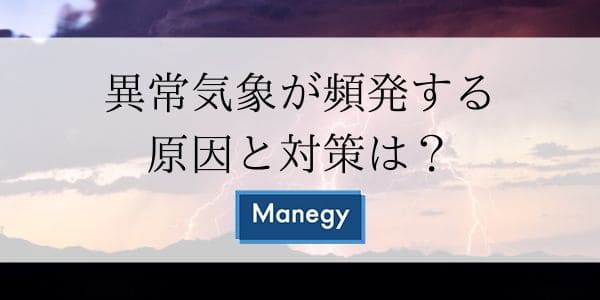
世界各地で、これまでに経験したことのないような気温の上昇や集中豪雨、記録的な大雪などの異常気象が頻繁に発生しています。従業員の通勤や、流通などにも影響があるため管理部門としても無視できません。
なぜ、異常気象が発生するのか、そして、その対策はあるのでしょうか。
異常気象とは30年に1回以下で発生する気候現象
激しい大雨や暴風、極端な気温や降水量の状態を伝える天気予報で、「30年に1度」や「50年に1度」といった表現が、頻繁に聞かれるようになっています。
気象庁では、「ある場所(地域)・ある時期(週、月、季節)において30年に1回以下で発生する気象現象」を、異常気象としていますが、いまや異常気象は決して珍しい現象ではありません。
日本各地で、これまで経験したことのないような集中豪雨が発生し、最高気温の国内最高記録も、どんどん更新されています。このような極端な気象現象は、日本だけで発生しているわけではありません。世界各地で発生し、大きな被害をもたらしています。
地球温暖化と自然のゆらぎ
では、なぜ、このような極端な気象現象が頻発するようになったのでしょうか。その理由の一つに、地球温暖化の影響が指摘されていますが、それが原因とは断定できないようです。また、海水温が上昇するエル・ニーニョや低下するラニーニャ現象、火山の噴火による影響などさまざまな指摘があります。
たとえば、気温の上昇については、上空の偏西風が通常と異なる位置を流れる状態が続いたことや、熱帯地域の対流活動の影響が遠い場所に伝わり、地球の大気と海洋の自律的な変動による“自然のゆらぎ”が一方的に大きく振れたときに、著しい高温となるようです。
この自然のゆらぎは、地球の気候システムに元々備わった性質ですから、地球温暖化によって異常に暑い夏となったと断定することはできないそうです。
しかし、過去数十年の気象観測データの分析からは、世界各地で極端な高温の発生頻度が増えていることは明らかになっています。このような長期的な増加傾向には、地球温暖化の影響の表れでもあり、今後も暖冬傾向や酷暑の日が増えていく傾向がさらに強まると予想されています。
地球規模で取り組むべき課題
頻発する異常気象と地球温暖化の因果関係は明確になっていませんが、大気中の温室効果ガス濃度の増加に伴って、世界中の地域で長期的に気温が上昇していることは、気象データからも明らかです。
地球規模で発生している熱波や豪雨などの自然災害や異常気象が深刻化する中、2015年の国連気候変動枠組条約締約国会議で、産業革命時代からの温度上昇を2度未満に抑えるというパリ協定が決議されています。
地球温暖化と異常気象の因果関係については、世界中で研究が続けられていますが、温室効果ガスの排出が地球温暖化を進め、それが気候変動にも何らかの影響を及ぼしているのであれば、やはり、国家レベル、産業界全体でも、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からもそれなりの対策を取る必要があるのではないでしょうか。
長期的視野の排出ガス削減と直面する災害リスクへのルールづくり
日本では、「地球温暖化対策計画」により、国内の温室効果ガス排出削減・吸収量の確保により、2030年度に2013年度比の26.0%減(2005年度比25.4%減)の水準にする目標を掲げています。
温室効果ガス削減の効果は、すぐに目に見えるものではありませんが、個人や団体、事業所での取り組みが積み重なって、初めて成果が生まれるものです。
身近でできる地球温暖化対策としては、できるだけ車での移動を減らし、徒歩や自転車での移動、オフィスや自宅では、使っていない部屋の照明を消す、商品の過剰生産や過剰廃棄を減らす、適温での冷暖房などによって、CO2の排出削減につながります。
また、こうした地道な努力の積み重ねに加え、台風や集中豪雨などへの対策は、事業の継続にもかかわることですから、事業所などでは平常時から災害時に備えた対策が必要です。飲料水や非常食、懐中電灯や自家発電装置、さらには災害時の社員への対応なども、マニュアル化しておく必要があるでしょう。
交通網が遮断されてしまうこともありますから、その際の出勤はどうするのか、休みとするのか、あるいは早退させるのかなどのルールを定め、それを会社全体で共有しておくといいでしょう。
まとめ
今世紀末には、地球の平均気温が最大で4.8℃上昇するという予測もあり、地球温暖化対策は、地球規模で取り組む課題です。また、事業活動の継続を困難にさせるほど猛威を振るう自然災害の発生数も、年々、増加傾向にあります。管理部門は “備えあれば憂いなし”で、自然災害リスクへの対応策を考えておく必要がありそうです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
ニュース -
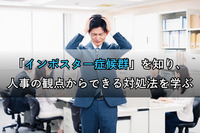
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
ニュース -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
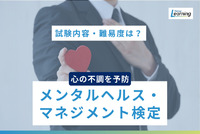
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?
ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
ニュース -
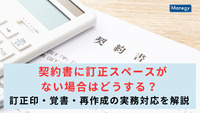
契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説
ニュース -

介護短時間勤務制度とは?―制度の概要と制度設計に必要な視点を考える―
ニュース -
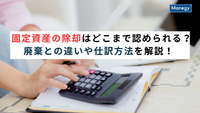
固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!
ニュース