公開日 /-create_datetime-/
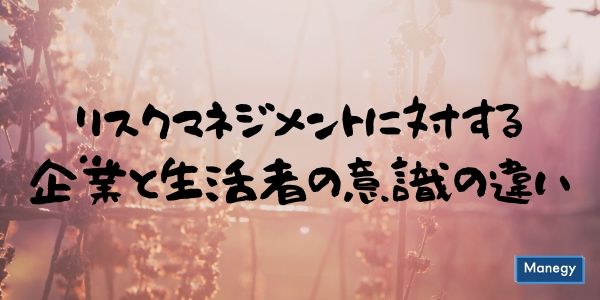
今年も、企業による不祥事が数多く発生したが、その後の対応策によっては、企業の存続が危ぶまれることもあるようだ。企業は不祥事などのアクシデントに対して、どのような意識で対応しているのだろうか。
その参考になりそうなのが、電通PRの企業広報戦略研究所が実施した「企業のリスクマネジメントに関する調査」である。
調査結果によると、「クライシスに直面した経験のない企業は、経験のある企業に比べると、全般的にスコアが低く、クライシス直面経験の有無で最も差が開くのが緊急時対応力」である。
今後強化したい項目でも「緊急時対応力」関連がトップに挙げられ、クライシスを想定したトレーニング実施やマニュアルの整備を重視していることがわかった。
また、総合スコアが高い企業は「信頼回復力」関連も重視しているが、企業と生活者の不祥事に対する意識にギャップがあることが浮き彫りになっている。
企業は、組織全体の体制・体質を問われるような不祥事が最も信頼を損なうと認識しているが、生活者は、身近な製品・サービス関連の不祥事に強く不信感を抱いているのだ。
企業の不祥事が発覚した後は、生活者の35.4%が、その企業の商品・サービスを「購入しない」という行動に出ていることからも明らかで、そのためには「情報収集」と「事実確認」も積極的に行っている。
生活者が企業に求めるのは、被害の拡大防止と再発防止策の策定など、実質的な対策や外部視点の導入である。そして信頼回復には、「第三者組織による原因究明と提言」を強く求めていることが、この調査結果から伺うことができる。
この調査は、国内企業494社のリスク担当者と生活者3,000人を対象としたものだけに、企業のリスク担当者は、生活者との意識のギャップを埋める努力が必要となるだろう。
その反面教師となるのが、今年表面化したかんぽ生命・ゆうちょ銀行の不正販売、関西電力幹部らの高浜町元助役からの金品受領問題などの対応である。いかに、生活者との意識にギャップがあるのかを、如実に物語る不祥事であったといえるのではないだろうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道
ニュース -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -

ESG・業種特化で差をつける!30代公認会計士が選ばれる理由(前編)
ニュース -

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題
ニュース -

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方
ニュース



































