公開日 /-create_datetime-/
所得税控除の見直しによる増税と減税の分岐点は年収850万円

2018年度の税制改正で所得税控除が見直された。
その結果、「年収850万超の高所得者は増税になる」と指摘しているのは、金融ジャーナリストの大西洋平氏(PRESIDENT・2018年1月15日号)だ。
現行の給与所得控除は、最低65万円と定められている。給与の増加に伴い控除額も増え、年収1000万円を超えると220万円が上限となっている。
これが改正案では、一律10万円ずつ控除額が減り、年収850万円超の控除額は195万円が上限となる。
全納税者が対象となる基礎控除は、現状の38万円から48万円に増加。また課税所得2400万円超から段階的に縮小し、2500万円超で控除がゼロとなる。
今回の改正案によると、年収850万円以下の会社員の税負担は変わらないが、年収が1000万円となると年間4万5000円の増税になるという。
基礎控除額が増加することで課税対象額が減り、税額が安くなる仕組みだが、年収850万円以上の、いわゆる高所得者にとっては増税となり、「消費意欲と働くモチベーションの減退につながる」と、警鐘を鳴らすエコノミストもいる。
税制改正によって減税の恩恵を受けるのは、自営業者や請負契約で働く人で、22歳以下の子や特別障害者、要介護3以上の家族を扶養する者は増税の対象外となっている。
新税制は2020年1月から適用される予定である。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -
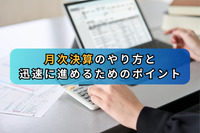
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
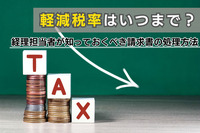
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース




































