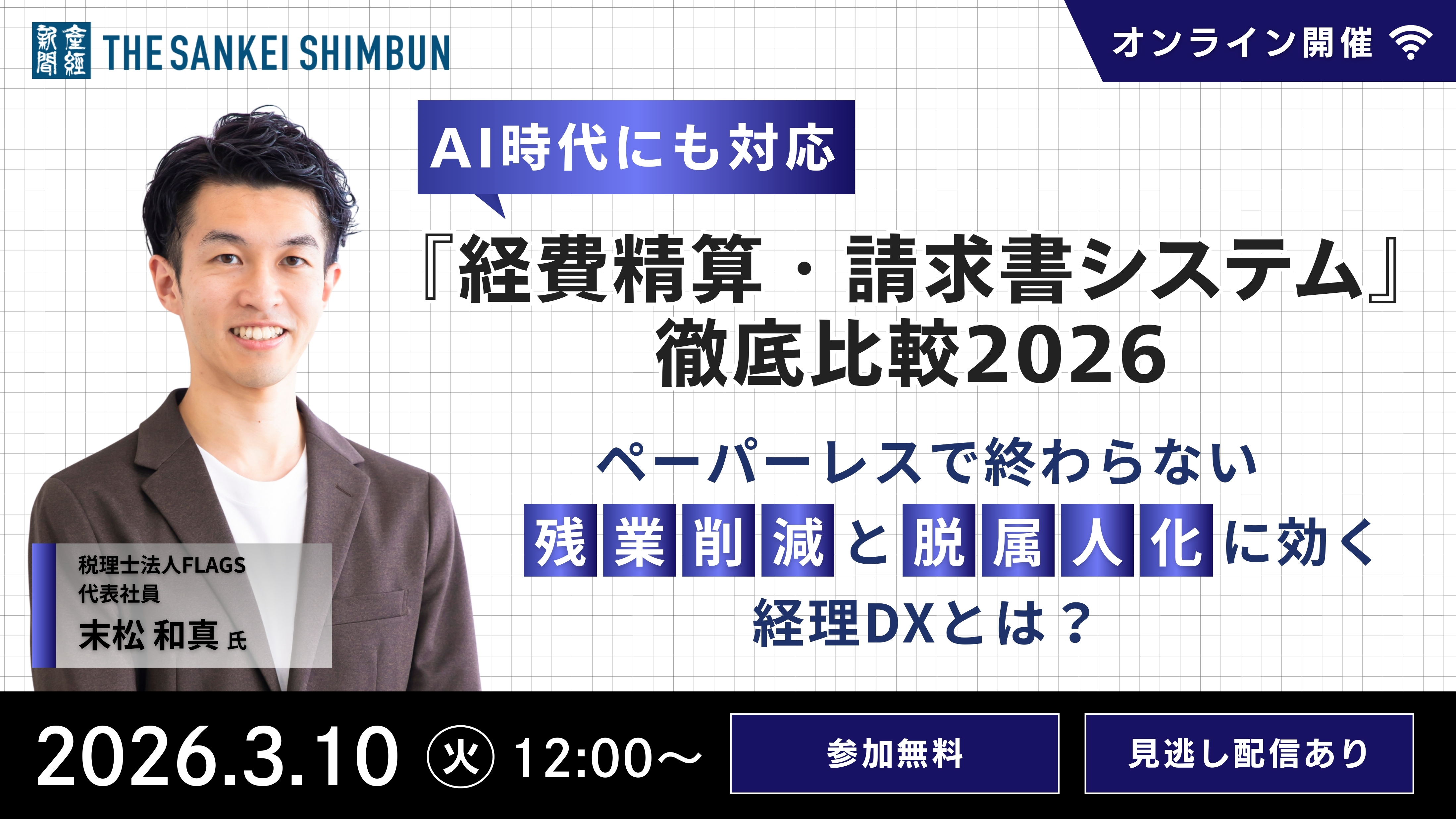公開日 /-create_datetime-/

税理士の有資格者でありながら、税理士登録をしない人が増えています。
税理士事務所の求人募集などでも、「税理士(未登録可)」との表現を見かけることが多くなってきました。
この記事では、有資格者でありながら税理士登録をしないのはなぜなのか、また税理士登録をしないと就職に不利に働くのかについて解説していきます。
税理士登録しない人が増えている理由とは?
未登録税理士が増えている理由はいくつか考えられますが、大きな理由としては2つあります。
1つは、税理士登録をし、即独立するという考え方が少なくなってきていることです。
20年ほど前までは税理士資格を取る最大の理由が独立開業することでした。自ら事務所を構えることこそ、税理士になる最大の理由でもありました。
しかし、近年は税理士業界の先行きが見通せなくなってきていることもあり、独立志向は薄らいでいます。
2つは、税理士法人化です。税理士法人は、2人以上の税理士によって法人化が可能になるわけですが、近年は税理士を多数抱える比較的大規模な税理士法人が増えてきています。
そして、こうした事務所では税理士という資格自体をそれほど重視しなくなっていることが挙げられます。
税理士登録にかかる費用は30万円
税理士登録するには、以下のような費用がかかります。
1. 税理士登録料 5万円
2. 登録免許税 6万円
3. 登録時研修費用 5万円
4. 税理士会入会金 4万円(入会する税理士会による)
5. 税理士会年会費 10万円(入会する税理士会による)
合計すると30万円にのぼります。
年会費以外は登録時だけですが、小さな額とはいえません。
もちろん、独立するとか、税理士法人の社員税理士になるという前提であれば、初期投資ということになると思いますが、そうでなければ多少考えてしまう額かもしれません。
また、税理士会に入会するとそれなりに税理士会による要請(たとえば税務相談など)も生じてきます。
一方で、入会することによるメリットもあります。
地域の先輩税理士と親しくなることで、さまざまな情報が得られ、勉強できることで税理士としての経験値を積むことも可能になります。
ただ、最初から大手税理士法人で働きながら資格取得を目指していた場合、事務所内規定などで「試験合格=税理士とみなす」というようなものがあれば、30万円払うことをもったいなく感じてしまうでしょう。また、そのような多数の税理士が在籍する税理士法人などであれば、地域税理士とのかかわりもそれほど重要ではなくなるともいえます。
記事提供元
管理部門の転職ならMS-Japan
転職するなら管理部門・士業特化型エージェントNo.1のMS-Japan。経理・財務、人事・総務、法務、会計事務所・監査法人、税理士、公認会計士、弁護士の大手・IPO準備企業の優良な転職・求人情報を多数掲載。転職のノウハウやMS-Japan限定の非公開求人も。東京・横浜・名古屋・大阪で転職相談会を実施中。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査
ニュース -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
ニュース -
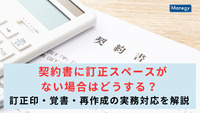
契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説
ニュース -
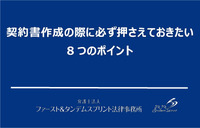
契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
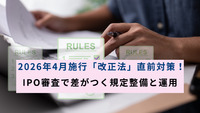
2026年4月施行「改正法」直前対策!IPO審査で差がつく規定整備と運用
ニュース -
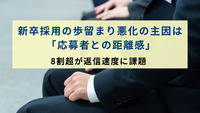
新卒採用の歩留まり悪化の主因は「応募者との距離感」 8割超が返信速度に課題
ニュース -

契約書の条ずれを発見したらどうする? 正しい修正方法と注意点を解説
ニュース -
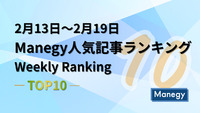
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営
ニュース