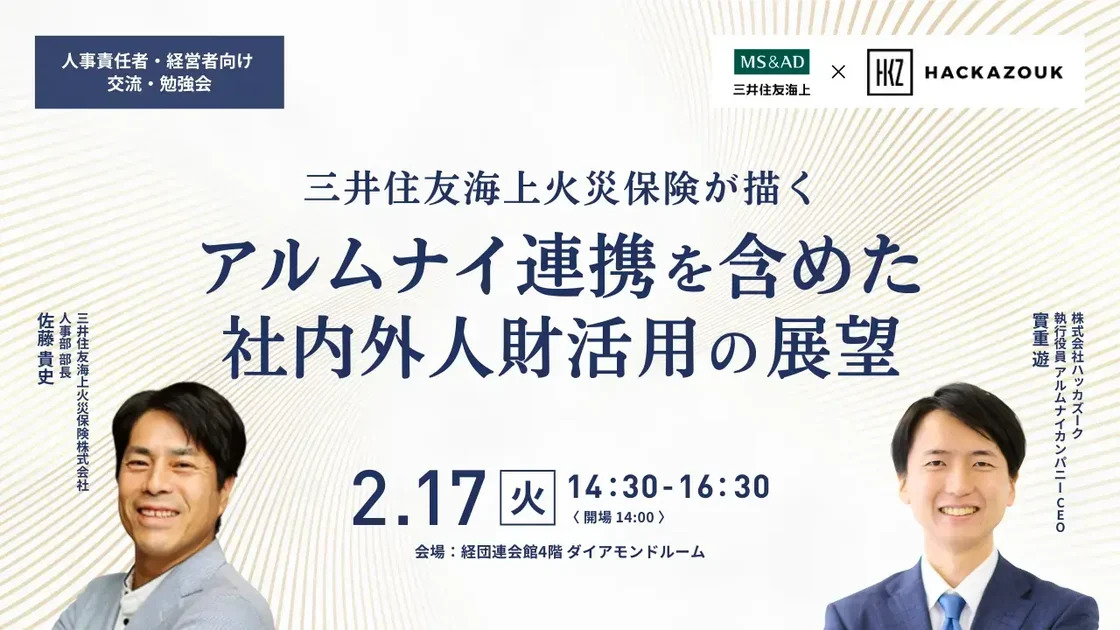公開日 /-create_datetime-/
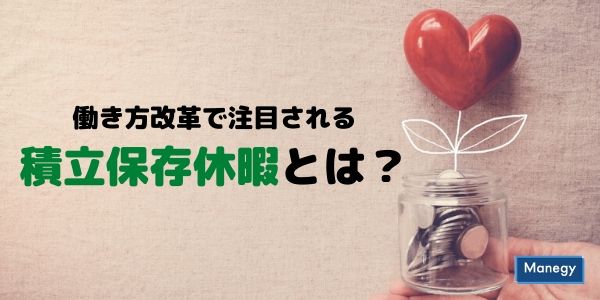
働き方改革の推進により、2019年4月から年次有給休暇の年5日の取得が義務化されました。通常、年次有給休暇は発生した日から2年間で失効してしまうのですが、この失効した年次有給休暇を積み立てて保存しておくのが積立保存休暇制度です。次々と進む働き方改革で、最近注目されている積立保存休暇制度。その概要はどのようなものなのか確認しておきましょう。
積立保存休暇制度の概要
まず年次有給休暇とは、労働基準法第39条の定めにより業種、業態にかかわらず、また正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して与えられるものです。
年次有給休暇の付与日数については、継続勤務年数、週や年間の所定労働日数(パートタイム労働者の場合)によって細かく分かれていますので、その詳細については割愛します。ですがこの年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅することが同じ労働基準法の第115条に記載されています。
以前は、この失効となる年次有給休暇を買い取る制度を作った企業もありましたが、本来の主旨である「休息すること」を妨げる行為であることから、現在では原則として違法とされています。
この失効してしまう年次有給休暇を買い取りではなく、積み立てて(保存して)おくことにより、想定外の事態(急な入院や介護、育児など)に使えるようにしようというのが積立保存休暇制度です。
積立保存休暇制度を導入することは、法律で義務付けられてはいません。ただし行政は、労働者個々の事情を考慮し積立保存休暇制度を利用できるようにすることが望ましいとしています。
積立保存休暇制度の導入状況
人事院が発行している「民間企業の勤務条件制度等調査(平成28年度)」によれば、積立保存休暇制度のある企業は全体の29.6%、従業員500人以上の企業では54.6%、100人以上500人未満の企業では31.0%、50人以上100人未満の企業では19.2%となっています。
積立保存休暇制度のメリット・デメリット
積立保存休暇制度を導入するメリットは、企業側と従業員側、両方にあります。
まず従業員としては、業務の都合などで消化しきれなかった年次有給休暇を無駄にすることなく、想定外の事態へのセーフティネットとして活用できるようになります。
企業側は従業員が安心して働ける環境を用意することにより、モチベーションのアップやワークライフバランスの向上に寄与させることができるでしょう。
この制度を介護や育児に積極的に活用してもらえれば、家庭の事情による退職抑制にも繋がり、離職率の低減や人材確保にも役立ちます。
では導入した場合のデメリット、導入しなかった場合のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
積立保存休暇制度を導入した企業とすれば、本来であれば有給にする必要のない休暇を従業員に与えることになるので、実質的にコストアップとなります。これが導入した場合の一番のデメリットでしょう。
次に導入しなかった場合のデメリットですが、先述したようにこの制度は行政に義務付けられたものではないことから、導入する企業とそうでない企業が存在します。これにより労働者の間では不公平感が増すことになり、場合によっては転職の理由にもなりえます。特に高齢化社会を迎え、介護などの必要に迫られた世代の離職や転職が増えてしまうかもしれません。
政府が積立保存休暇制度の導入を推進する理由
政府が働き方改革を積極的に進める一番の目的は、労働力人口の減少を防ぐことです。現在の人口減少率のままでは、総人口の減少に伴い労働力人口もピークであった8,000万人(1995年)から、2050年には半減してしまうと言われています。
さまざまな生産効率向上の施策を打ったとしても、労働力人口の減少はそのままGDP(国内総生産)の減少に繋がり、これは日本の国力減少と同意義なのです。それを防ぐためには、さまざまな事情で労働から離れてしまう人口を減らし、より多くの人に長く働いてもらう施策が必要なのです。
まとめ
働き方改革関連法案は「長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現」、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」、「働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)」などを柱として、今後も改正されながら順次、実施されていくことでしょう。
積立保存休暇制度についても、その義務化やそもそもの失効期限を5年に延長することも含め、各所で検討が進められています。私たちの生活に直結する労働条件や環境の変化。決して他人事とは思わず、常に注視していきましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -
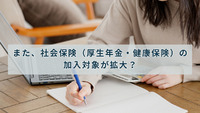
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース -
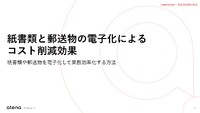
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道
ニュース