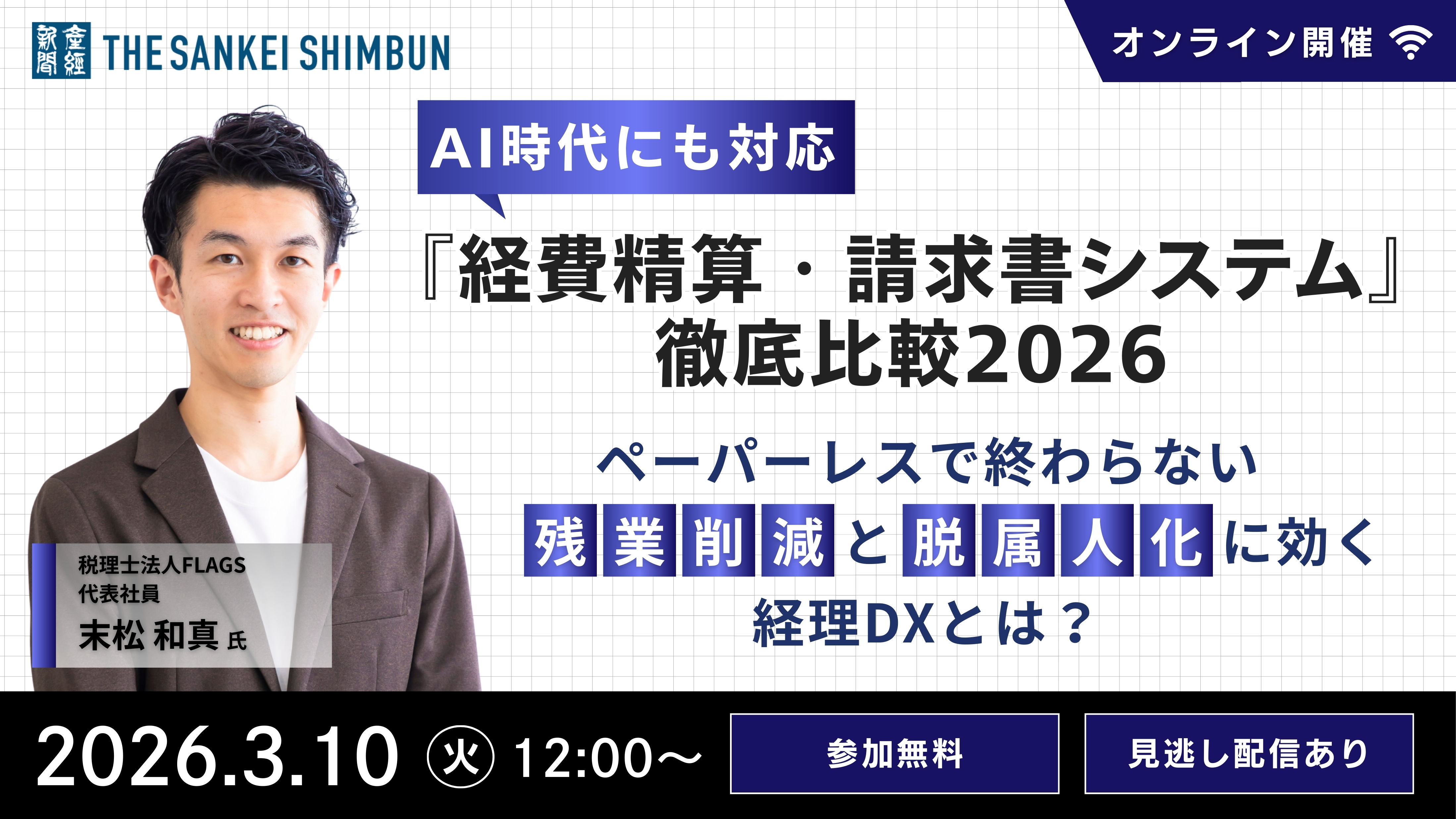公開日 /-create_datetime-/
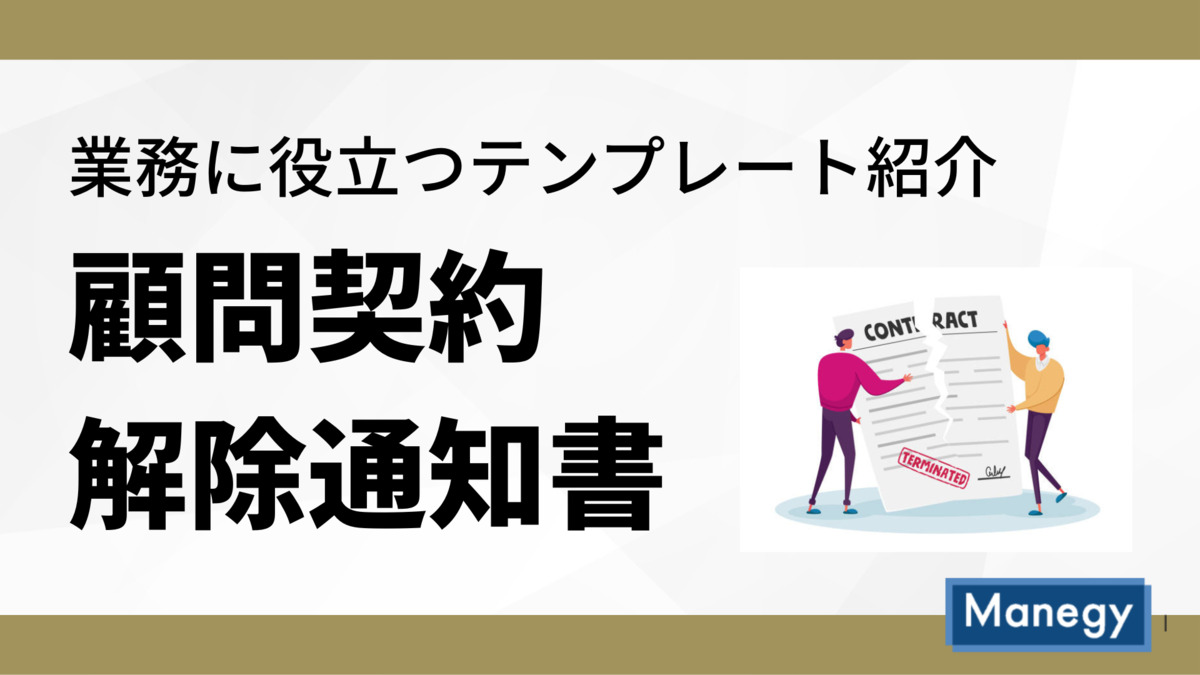
事業活動を円滑に進めていくためには、弁護士や税理士などの専門家のサポートが必要です。
そのため、専門家と顧問契約を結び、いざというときのために備えることが一般的です。
しかし、何らかの理由で顧問契約を解除するケースも出てきます。
そんなときに重宝するのが「顧問契約解除通知書」です。
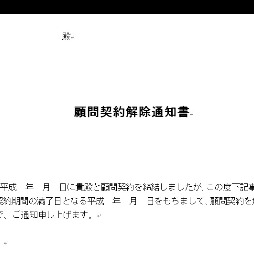
顧問契約解除通知
顧問契約解除通知書は、何かしらの理由で契約期間途中で顧問契約を解除する時に使います。■顧問契約とは特定の分野において幅広い知識や経験をした人物に、企業に対して助言などをしてもらうための契約のことです。主に、経営に関わる分野である弁護士や税理士などと顧問契約を結ぶ企業が多い。■業務委託契約との違い業務委託は、一定の業務に対して外部の企業や個人の方にお願いする契約で、必ず専門的な知識などがないといけないということないところが顧問契約との違いです。こちらでは、専門家が作成した顧問契約解除通知書の書式、テンプレートを無料でダウンロードできますので、ぜひご使用してみてください。
無料でダウンロードする顧問とは企業のアドバイザー
事業活動には、会社法、労働法、税法など、さまざまな法律による制限があります。
経営陣が企業活動に関わるすべての法律を把握していれば問題ありませんが、実際には専門的な知識や経験が求められるため、専門家のアドバイスを受ける必要があります。
そのため、弁護士や税理士などの専門家と顧問契約を結び、企業のアドバイザーとして役割を果たしてもらうのが「顧問」という存在です。
顧問は経営のパートナーともいえる存在であり、本来は深い信頼関係のもとで成り立つものです。
しかし、「親身に相談に乗ってもらえない」「対応が遅くて事業に支障が出る」といった理由から、顧問を変更するケースもあります。
話し合いによって穏便に契約を解除できれば問題ありませんが、一方的に顧問契約を解除した場合、トラブルに発展することもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、「顧問契約解除通知書」を用意しておくことが重要です。
便利な「顧問契約解除通知書」テンプレート
そもそも、顧問契約は深い信頼関係に基づいて締結されることが多く、長年にわたり企業のアドバイザーを務めているケースが一般的です。
そのため、顧問を頻繁に変更することはあまりありません。
したがって、いざ顧問契約を解除しようとしても、具体的な手続きについて詳しく把握している担当者は少ないのが実情です。
そこで活用をおすすめしたいのが、「顧問契約解除通知書」のテンプレートです。
株式会社MS-Japan事務局では、社会保険労務士、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士、中小企業診断士といった各専門家の協力のもと、「顧問契約解除通知書」のテンプレートを作成しています。
Word形式のテンプレートとなっており、自社の状況にあわせてカスタマイズすることが可能です。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
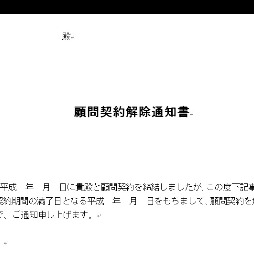
顧問契約解除通知
顧問契約解除通知書は、何かしらの理由で契約期間途中で顧問契約を解除する時に使います。■顧問契約とは特定の分野において幅広い知識や経験をした人物に、企業に対して助言などをしてもらうための契約のことです。主に、経営に関わる分野である弁護士や税理士などと顧問契約を結ぶ企業が多い。■業務委託契約との違い業務委託は、一定の業務に対して外部の企業や個人の方にお願いする契約で、必ず専門的な知識などがないといけないということないところが顧問契約との違いです。こちらでは、専門家が作成した顧問契約解除通知書の書式、テンプレートを無料でダウンロードできますので、ぜひご使用してみてください。
無料でダウンロードする顧問契約を解除するときは顧問契約書の条項も要確認
顧問契約を解除する際に問題となるのは、顧問契約書に契約期間の終了時期や手続きについての条項が明確に記載されていないケースが多いことです。
たとえば、「契約期間満了日の3か月前までに双方から解約の意思表示がない場合、自動更新される」といった内容が記載されている場合、突然「来月から顧問契約を解除します」と申し出ても認められない可能性があります。
このような契約内容であれば、契約書の条項に従い、3か月前に解約の申し出を行う必要があります。
無用なトラブルを避けるためにも、顧問契約を締結する際には、契約終了時の手続きや通知期限について明記し、双方が納得したうえで契約することが大切です。
また、やむを得ず顧問契約を解除する場合は、書類やデータの引き継ぎもきちんと行いましょう。
とくに税務関連では、請求書や領収書、総勘定元帳などは会社にとって重要な書類です。
さらに、意外と見落とされがちなのが「e-Taxのパスワード」です。
顧問税理士に運用を任せていた場合、その税理士しかパスワードを知らないケースもあります。
パスワードが引き継がれていないと、新たに設定し直す必要が生じ、過去のデータが見られなくなるおそれがあります。
解除時にはこの点にも十分注意しましょう。
まとめ
顧問という存在がどのような役割を担い、企業にとってどのような立場にあるのかを、明確に理解していないビジネスパーソンも少なくないのではないでしょうか。
顧問には、外部のコンサルタントや弁護士、税理士、社労士といった専門家が就く場合もあれば、元社長や元会長など社内の経験者が選ばれるケースもあります。
いずれの場合も、専門的な知識や経験をもとに、企業からの相談に対して助言を行う役職であるため、顧問契約の締結時だけでなく、解除時においても慎重な対応が求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -
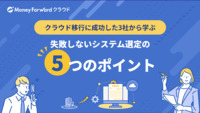
クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
ニュース -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説
ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
ニュース -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
ニュース -
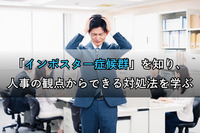
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
ニュース -
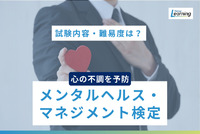
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?
ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
ニュース