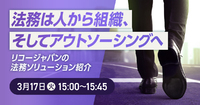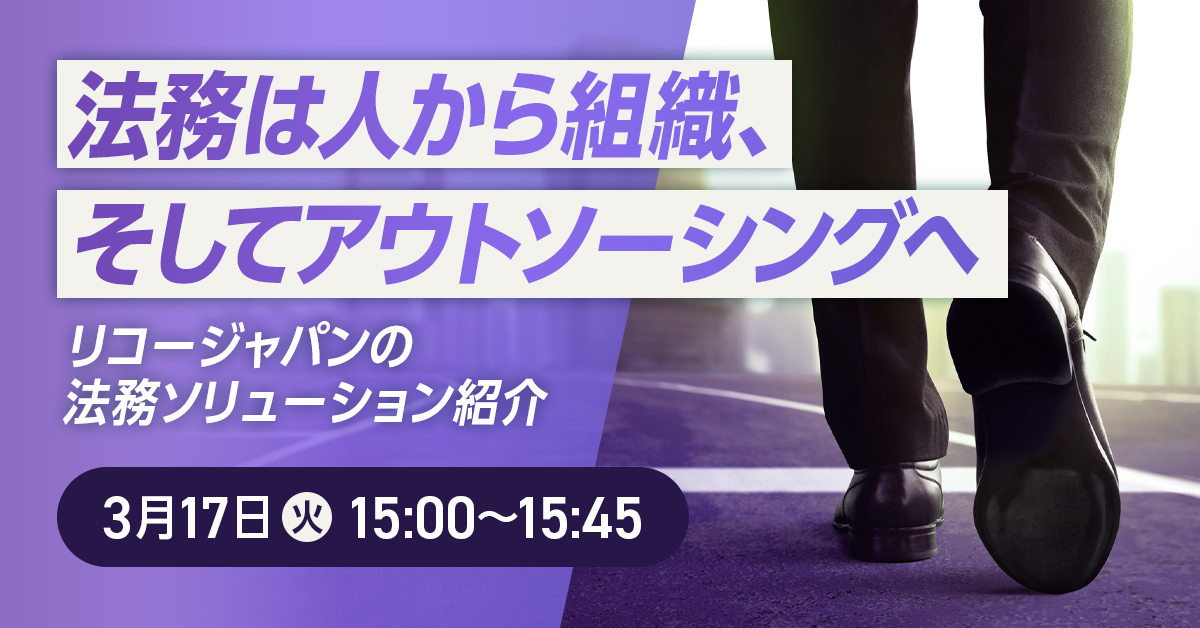公開日 /-create_datetime-/
テレワーク・リモートワーク下での「チームビルディング」で必要なこと

記事転載元:テレワーク・リモートワーク下での「チームビルディング」で必要なこと
新型コロナウィルスによる緊急事態宣言をきっかけに、テレワーク・リモートワークを導入する企業が増えました。また、SlackなどのチャットやZoomなどのWeb会議ツールの利用者も増え、非対面でのコミュニケーションが徐々に一般的になりつつあります。
しかし、対面でのコミュニケーションが取れないことによって、「チーム内のコミュニケーションが減った」「メンバーが孤独感を感じている」「働き方は改善されたはずなのに、思うように生産性が高まっていかない」といった新たな課題が浮かび上がってきています。そこで今回は、複数の企業で人事領域を管掌し、メガベンチャーからスタートアップまで多くの組織づくりに従事してきた小島隆秀さんに、「チームビルディング」の観点からこの変化を乗り切るポイントをお聞きしました。
<プロフィール>
小島 隆秀
WAmazing株式会社の人事責任者として、人事総務全般を担当。新卒でリクルートエージェント(現:リクルートキャリア)に入社後、法人営業に従事。その後、グリー株式会社にて、人事および新規事業開発に従事。その後、SORABITO株式会社の人事責任者として人事全体を管轄したのち、現職。
「チームビルディング」とは何か
───チームビルディングの「定義」や「目的」といった観点から、小島さんの考えについて教えてください。
チームビルディングを考える前に、まず「チームとは何か」から整理しましょう。
私が考えるチームの定義は、「ある共通目標に向かって、メンバーが連携し能力を高め合いながら、人数以上の成果を生み出す集合体」です。個々の能力に依存するのではなく、多様性を尊重しながら協働し、いかに掛け算的な成果を生み出すか。そこにチームの意義があります。
するとチームビルディングは、「チームの成果を最大化するための手段」であると定義できます。個性や多様性を認めつつ、いかに同じ目標に向かってパフォーマンスを発揮できるか。チームの連帯感をどう高めるか。それがチームビルディングの本質であり重要なことだと思います。
───チームビルディングは、なぜ重要なのでしょうか。
ひとつ、分かりやすい例があります。
一般的に優秀なタレントが揃えば、チームとしても高い成果が出せると思われがちです。実際にスタートアップ組織などにおいては、国籍やバックグラウンドがさまざまで、個性や多様性が強く、能力の高いメンバーがチームを組むことが多くあります。
しかし、そんなチームであっても必ずしも高い成果が出るとは限らず、むしろ思うように成果を上げられないといったこともあるのです。仮に組織ビジョンに共感するメンバーを集められたとしても同様です。
原因はいくつか考えられますが、以下のような事象が起こりがちです。
ビジョンを実現する上での目標や規範が、正しく経営から各組織(部門やチームなど)にブレイクダウンされていない
正しく各組織にブレイクダウンされていたとしても、それらが組織内の共通言語としてメンバーに伝わっていない、浸透していない
このような状況下では、メンバーが正しいやり方・方向性でパフォーマンスを発揮することができません。結果的に個人の業績がチームの業績に連動せず、チームが機能不全に陥ってしまいます。つまり、チームビルディングなしでは、どれだけタレントが揃っていたとしても成果を最大化できないということです。
そうならないためには、チームメンバー1人ひとりの頑張りがチームの成果に結びつくようにする必要があります。そのための具体的な方法は、以下の2つです。
①チーム目標の明確化(行動規範や判断基準などの決めごと・ルールも含む)
②協働意識の醸成(行動規範や判断基準などの共通言語を浸透させ、チームメンバーが互いに信頼しながら仕事に取り組める状態を作る)
これらを実現する手段はさまざま。飲み会やレクリエーション、ワークショップ、研修など、チームの状態や課題によって効果的な方法をリーダーが都度選択する必要があります。
「対面ができないこと」で生まれた課題とは
───テレワーク・リモートワークが増えたことで、チームビルディングにも変化がありましたか?
はい。リモートワークが導入されたことにより、出社準備・通勤時間の削減、1人で作業に集中できる環境などから個人パフォーマンスは上がったと考えていいでしょう。実際に私が所属する会社の従業員アンケートでも、約半数以上のメンバーが以前と比べ生産性が上がったと回答がありました。
一方で、「個人パフォーマンスは上がったのに、チームパフォーマンスは下がった」という組織もあるようです。その要因は、先ほどお伝えした2つのポイントが低下したことにあると考えています。
①チーム目標への意識低下
リモートワーク環境下においては、どうしても自らの生産性向上や仕事完遂に意識が働きがちです。そのため自身の仕事がどうチーム目標に接続しているのかを考えることが難しく、ただ目の前の仕事をこなすだけになってしまいます。この状態では、仮にチーム目標が達成されたとしても、メンバーが仕事に対するやりがいや成長感を感じられなくなり、最終的にはエンゲージメントが低下することにも繋がります。
②協働意識の低下
出社前提でお互いの顔が見える環境であれば、自然と他メンバーのことも考える意識が生まれます。しかしリモートワーク環境下では物理的に顔が見えないこともあり、どうしてもこの意識が生まれにくい状態になります。また仕事におけるプロセスが見えづらいことから結果だけがフォーカスされ、チーム内における相互理解や信頼が失われて行き、最終的にはチームの連帯感が低下します。
これらは、リモートワーク環境下ならではの状態と言えるでしょう。これらを改善するためには、上記2つの要因を認識した上で、意図的に環境を整備する必要があります。例えば以下のような施策が有効になるはずです。
■各メンバーの取り組んでいるタスクや進捗状況をチーム内で可視化し、いつでも把握できる仕組みを作る
■コミュニケーション量そのものを増やす。それが難しい場合は、量ではなく機会や頻度を増やす。
(例)週1回1時間のチーム定例ミーティングをする代わりに、毎朝または毎夕10分~15分のショート定例を実施し、互いの進捗やトピックをシェアする機会を設ける■チーム定例ミーティングや1on1などで、チーム目標をリーダーから繰り返し伝える(メンバーが自らの仕事とチーム目標の接続をイメージし、正しくパフォーマンスを発揮できるように)
フルリモートワークになった時に、気をつけるべきポイント
───メンバー全員がフルリモートワークになった企業も多いと聞きます。その場合、どんな点に注意すると良いでしょうか。
フルリモートワークになり困ることはたくさんあります。特に課題となるのが「コミュニケーション」です。中でも業務の大半を占める“テキストコミュニケーション”への配慮が、課題解決においてとても重要になってきます。
対面の場合であれば、相手の発言だけでなく表情や声のトーン、動作などからも情報や感情を読み取ることができます。しかしチャットなどのオンラインコミュニケ―ションでは、テキストからそれらを読み取るしかなく、圧倒的に情報量が減少します。つまり、少ない情報から相手の意図や感情を読み取る「受け手の解釈力」がこれまで以上に求められる形になります。
しかし、受け手の解釈力だけに委ねていては、一向にコミュニケーションは改善しません。だからこそ、送り手側の意識改善や配慮、工夫がより一層重要になるのです。
───具体的にどんな工夫がありますか?
「文字に感情を吹き込むこと」です。
私も普段から意識するようにしています。というのも、これまで長くチャットコミュニケーションが主流であるIT企業で仕事をしてきた中で、送り手の配慮や想像力に欠けた発信による「無用な摩擦」を経験してきたからです。
例えば、「申し訳ありません」と「申し訳ありません!」では、感嘆符があるかないかといった些細な違いしかありませんが、受け手への伝わり方は大きく変わることが理解いただけるかと思います。「申し訳ありません>_<」と顔文字を使うと、さらに印象は変わりますね。
コミュニケーションの効率化を考えるあまり、相手に正しく気持ちが伝わらなかったり、誤解を生んだりしてしまうことは対面でもあり得る話ですが、フルリモートの環境下ではそれが顕著に現れます。感嘆符や絵文字などのちょっとした工夫でそこを補うこと。そうした小さな配慮が、円滑なコミュニケーションのポイントと言えるでしょう。
チームビルディングにオススメの研修・書籍
───新しい働き方や組織のあり方を考えるべく、チームビルディングを学びたいと思っているビジネスパーソンにオススメの研修や書籍があれば教えてください。
<研修>
リクルートマネジメントソリューションズ 「マネスタ」
リクルートが開発した「ピープルマネジメントノウハウ」を3ヵ月49,800円(税抜・1名あたり)で学べる研修プログラムです。 弊社では導入検討をしている段階なのですが、 オンラインのため自分のペースで取り組むことができ、リーダー向け研修の取っ掛かりとして最適だと考えています。
<書籍>
心理学的経営/大沢 武志(著)

リクルートで30年にわたり組織における人間の「感情」や「個性」を深く追求した著者が、「個をあるがままに生かす」ことを前提とした経営論をリクルートでの事例を元にまとめた一冊。1993年に刊行され、今なお人材経営の原点として評価されています。
チームのことだけ、考えた。/青野 慶久(著)

「100人いれば100通りの人事制度を」 多様性を尊重することを前提に、いかに組織をまとめて動かすかについて、サイボウズのこれまでの歴史や組織論が非常に詳しく書かれた一冊。身近な事例に溢れていて、大変参考になると思います。
Team Geek -Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか/Brian W. Fitzpatrick(著)、 Ben Collins-Sussman(著)

ソフトウェア開発チームをうまく運営するコツについて書かれている本ではありますが、組織を率いるリーダーにとっても示唆に富んだ内容に溢れた一冊。「チームを作る三本柱」「チーム文化のつくり方」「有害な人への対処法」など、具体的で楽しい逸話とともに解説されています。
編集後記
今回の小島さんへのインタビューを通じて、テレワーク・リモートワーク環境下におけるチームビルディングの変化を整理することができました。
それと同時に、「チームビルディングの本質は、環境が変わったとしても変わらない」ということにも気づくことができたと思います。人間の心理に基づいて最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作る力は、人事やHR領域に関わる方はもちろん、組織やチームで働く全ビジネスパーソンにとって必要な力だと言っても過言ではないでしょう。
組織やチームとして働く本質が見直されようとしている今、チームビルディングを学ぶことはとても価値の高いことなのかもしれません。
株式会社コーナーではフルオーダーメイドで各社における人事課題に対して実働型解決支援を行っています。
採用以外にも人事制度設計、組織開発、人材開発、MVV策定、労務などあらゆるジャンルを専門とした1800名以上のプロ人事がいます。
専任人事がいない企業や人事戦略のような中長期的な戦略設計の強化、繁忙期のみの採用実務支援など必要な時間・量を最適に支援させていたくことが可能なため、ご興味ある方は是非ご連絡いただければと思います。
サービスの詳細については下記のリンクからダウンロードできる資料にまとめておりますのでご覧いただけたら幸いです。
また相談のお打ち合わせも無料となりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
記事提供元
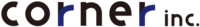
「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」は、採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。
コーナーは1,500名を超える即戦力のプロフェッショナルが登録をし、プロフェッショナルによる課題解決を実働支援型で行います。週1日から必要な業務内容・業務量だけプロフェッショナルの経験を活用できることで、多様化してきている人事・採用課題を効果的に解決します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -
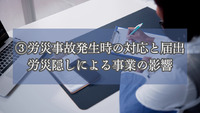
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
ニュース -
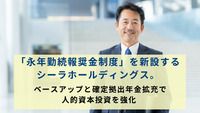
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント
おすすめ資料 -
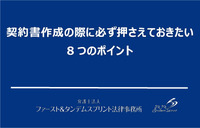
契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -
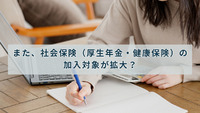
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース -

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査
ニュース