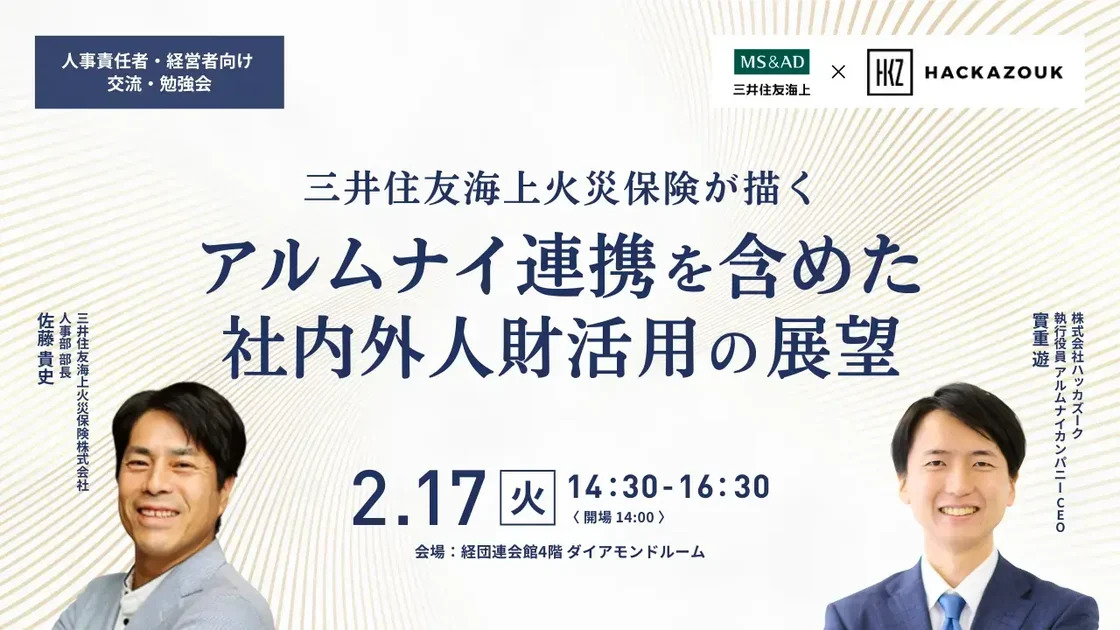公開日 /-create_datetime-/
講談社「with」が発表する「プレゼントで貰ってうれしいもの」1位は!?

コロナ禍で“新しい生活様式”が求められるようになり、人と人とのコミュニケーション方法も変わりつつあります。そんな状況で、多くのビジネスパーソンが痛感しているのは、コミュニケーションの難しさではないでしょうか。今回の記事では、ぎくしゃくとしたコミュニケーションを改善するための手法を紹介します。
コミュニケーションをスムーズにするための手法とは?
テレワークの普及により、対面での社員間のコミュニケーションの機会が、大幅に少なくなっています。また、出社せずに在宅での勤務が増えたことで、家庭内のコミュニケーションにも、微妙な変化が生じているのではないでしょうか。
社員間でのコミュニケーションがうまくいかなければ、仕事がスムーズに進まないし、家にいる時間が増えたことで、家族関係がぎくしゃくすれば、それがストレスにつながることもあるようです。
ビジネスでも、プライベートでも、コミュニケーションの大切さを、改めて意識したビジネスパーソンも多いと思いますが、コミュニケーションをスムーズにするための効果的な方法、それは古典的な手法でもあるプレゼントです。
もちろん、相手に喜ばれるものでなければ、せっかくのプレゼントも逆効果になってしまいます。そこで参考になるのが、講談社の女性誌withの公式ウェブサイト「with online」のOLトレンドランキング「プレゼントで貰ってうれしいもの」です。
貰ってうれしいプレゼント
「えっ、プレゼントなの?」と、思われる人もいるでしょうが、これが、なかなか効果があるので、女性社員や妻とのコミュニケーションに不安を感じている男性ビジネスパーソンは、試してみてはいかがでしょうか。
プレゼントといっても、それほど大げさなものではありません。3,000円以下のちょっとしたプレゼントです。では、OLが選んだ“貰ってうれしいプレゼント”のランキングを見ていきましょう。
第1位 高級めのスイーツ
第2位 コーヒー・紅茶
第3位 ハンドクリーム
第4位 シャンプー・ボディソープ系
第5位 ハンカチ
第1位には、自分で買うにはためらう、ちょっと高めのスイーツが選ばれました。第2位は、家でも仕事場で飲むコーヒー・紅茶です。これなら、贈る方も受け取る方も、気兼ねなくやりとりができそうですね。
第3位のハンドクリーム、第4位のシャンプー・ボディソープ系、第5位のハンカチは、手洗いが欠かせない“新しい生活様式”では、いくらあっても喜ばれそうです。
貰ってうれしくないプレゼント
ちなみに、「プレゼントで貰ってうれしくないもの」(3000円以下で)のアンケートも実施していますので、プレゼント失敗しないためにも、こちらも覚えておきましょう。
第1位は「お酒」です。日ごろからお酒大好きと公言している人以外には、避けた方が無難といえそうです。第2位には、「アクセサリー」が選ばれています。
アクセサリー類が喜ばれるのは、恋愛関係があってこそ。社内でのプレゼントには不向きといえるでしょう。したがって、夫婦間のコミュニケーション回復には、役立つかもしれません。くれぐれも、渡す相手を間違えないようにしましょう。
まとめ
ちょっとしたタイミングで日頃の感謝や労いの気持ちを込めて、負担にならない程度の小さなプレゼントをしてみたら、コミュニケーションの良いきっかけになるかもしれませんね。プレゼント選びに困ったらランキングも参考にしてみてくださいね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -
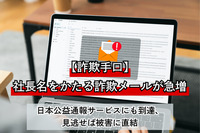
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。
ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース