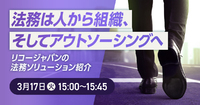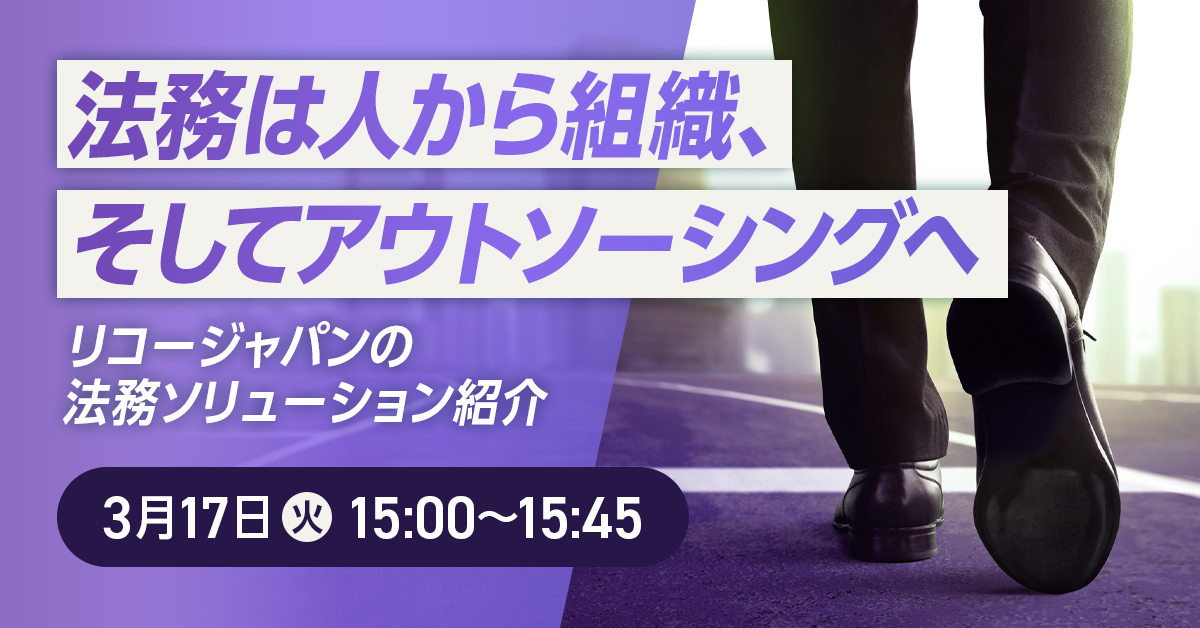公開日 /-create_datetime-/
損益分岐点について詳しく解説 固定費と変動費の割合から利益確保の方向性を探る
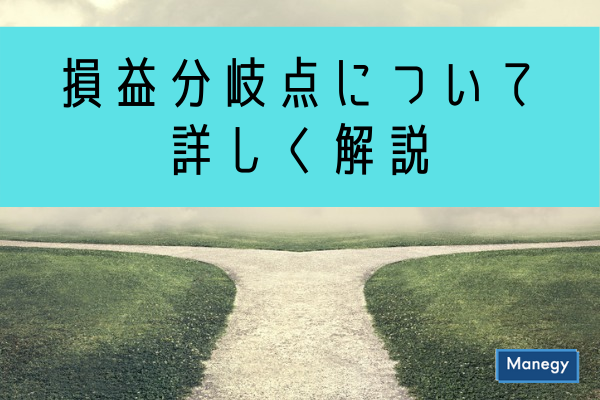
企業が経営計画を立てる場合、どのくらいの利益を上げることができるかを客観的に予測する必要があります。
その際、黒字を確保できるかどうかを検討する上で、「損益分岐点」を計算することが重要です。売上高が損益分岐点を超えているかどうかで、健全な経営を行えるかどうかが分かります。
そこで今回は、損益分岐点とは何か、損益分岐点の分析を通してどのように利益増を目指すことができるのか、について詳しく解説しましょう。
損益分岐点とは?
損益分岐点とは、会社の損益がゼロとなる売上高のことです。損益分岐点となる売上高のことは「損益分岐点売上高」とも呼ばれています。
例えば、1個当たりの原価60円の商品を100円で販売し、市場で1万個を売り上げた場合を考えてみましょう。
この場合、企業としての売上高は100万円、原価60万円、利益額40万円です。この場合の損益分岐点売上高はいくらでしょうか。このことを考える上で重要になるのが、原価60万円の構成内容です。
損益分岐点は固定費と変動費がポイント
原価は固定費と変動費で構成されています。固定費とは人件費や広告費など、売上高に関係なく発生する費用のことです。一方、変動費とは売上額に応じて増減する費用で、商品の原材料費や仕入れ原価、販売時の手数料などが含まれます。
では先ほどのケースで、原価60万円のうち固定費が10万円、変動費が50万円という状況を考えてみましょう。
商品は1万個販売したわけですから、商品1個当たりの変動費(原材料費など)は「50万円÷1万個=50円」です。また、1個当たり100円で販売していますから、商品を1個売ったときに得られる限界利益(売上から変動費のみを差し引いた利益のこと)は50円と計算できます。
ここで、固定費は商品を1個も販売しなかったとしても発生する人件費などの費用であることを思い出しましょう。そのため、損益分岐点を確保するには、固定費の10万円分を限界利益で補う必要があります。
つまり、「固定費10万円÷限界利益50円=2,000」となり、固定費を補うためには2,000個を販売することが必須であるわけです。1個100円で販売すれば、「商品2,000個×100円=20万円」となり、損益分岐点売上高は20万円であることが分かります。
損益分岐点は、固定費と変動費の額によって変動する
損益分岐点は、原価における固定費と変動費の割合がどのくらいかによって変わります。上記の例では原価60万円の構成が「固定費10万円、変動費50万円」という例でしたが、これが「固定費40万円、変動費20万円」というケースを考えてみましょう。
この場合、販売額100円の商品1個当たりの変動費は20円となり、限界利益は80円です。損益分岐点を確保するには限界利益で固定費を補う必要があるので、「固定費40万円÷限界利益80円=5,000」となり、5,000個販売する必要があります。損益分岐点売上高は「販売額100円×5,000個=50万円」となるわけです。
このとき、固定費と変動費が変わったことで、損益分岐点売上高が変わっていることが分かるでしょう。
同じ原価60万円でも、「固定費10万円、変動費50万円」だと損益分岐点売上高は20万円でした。つまり、100円である商品を2,000個以上売り上げれば、黒字を確保できるのです。一方、「固定費40万円、変動費20万円」の場合、損益分岐点売上高は50万円となり、100円の商品を5,000個以上売り上げないと黒字は確保できません。
「固定費10万円、変動費50万円」という原価構成の方が損益分岐点は低く、赤字になりにくいことが計算結果から読み取れます。
固定費と変動費、どちらの割合を高めるべきか
この結果だけを見ると、固定費が低く変動費が高い原価構成の方が損益分岐点は低いので、「損益分岐点を低くするには、固定費をできるだけ抑えるべきだ」と考えたくなるでしょう。
しかし、これまでの計算はあくまで売上高が100万円だった場合のケースです。広告活動が功を奏して、1個100円の商品が3倍の3万個売れて、売上高が300万円となった状況を想定してみると状況は変わります。
「売上高100万円、固定費10万円、変動費50万円」において売上が3倍になると変動費も3倍となり、その費用額は150万円です。「売上高300万円‐(固定費10万円+変動費150万円)=利益140万円」と計算できます。
一方、「売上高100万円、固定費40万円、変動費20万円」において売上が3倍になると、変動費も3倍となり、その費用額は60万円です。同様に計算すると、「売上高300万円‐(固定費40万円+変動費60万円)=200万円」となり、利益は200万円確保できます。
すなわち売上高が300万円になった場合、「固定費40万円」が「固定費10万円」よりも、60万円も多い利益を得ているわけです。売上が伸びると固定費の割合が高い方が利益額は大きくなることが、この結果から分かるでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。一見計算が大変そうにも見えますが、順を追ってゆっくりと考えていくと、損益分岐点の構造が見えてくるでしょう。
損益分岐点のこれまでの計算結果をまとめると、売上高が伸びていない間は変動費の割合が高い方が損益分岐点は低くなり、赤字になりにくいといえます。しかし売上高が伸びてきたときは、変動費の割合が高いと全体としての原価が高くなってしまい、利益額が伸びなくなってしまうのです。
一方、固定費については、売上高が伸びていないときに割合が高いと赤字になりやすいといえます。しかし売上が伸びてくると、変動費よりも固定費の割合が高い方が、赤字になりにくいのです。
つまり、「ビジネス規模が小さい間はできるだけ固定費の割合を低くし、ビジネス規模が拡大していく中で変動費の割合を低くして固定費の割合を高めていく」という経営を行うと、利益を得やすいといえるでしょう。
ビジネスの場で活躍したい方は、この損益分岐点の基本構造を最低限理解しておくことをお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -
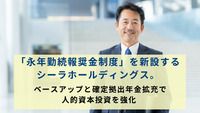
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)
ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
ニュース -
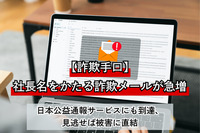
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース