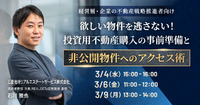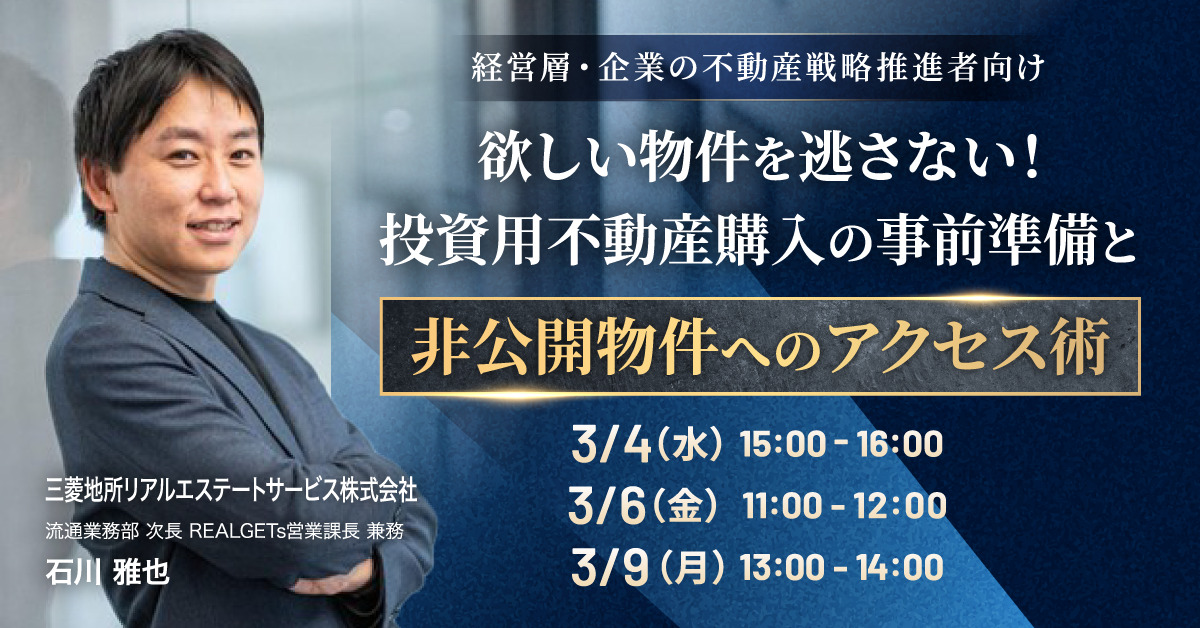公開日 /-create_datetime-/
「株」の語源

経済ニュースや投資家の間で日常的に使われる「株」という言葉。
正式には「株式」のことをさしますが、そもそも、なぜ「株」と呼ぶのかその語源を知って使っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は、「株」の語源とその由来について説明します。
語源の諸説
「株」の語源は、木を切った後に残る「切り株」が由来だとされています。「切り株」は木を切った後もずっと残っているものです。
それが転じて、「世襲などで継続的に保持される地位や身分」も「株」と呼ぶようになったとされています。そこから派生して、江戸時代には、幕府や藩の許可を得た独占的な商工業者の同業組合のことを「株仲間」、出資率に応じた権利が保持されることを「株式」と呼ぶようになりました。
また、「株」は英語で「stock」=「切り株」の意味を持っています。切り株から生えている枝はやがて成長します。それが、「お金が増えていく」ことをイメージするのと同時に、枝分かれしていくことから「分配する」といったものへとつながり、「株」=「stock」となったとも言われています。
「stock」には、本来「蓄える」という意味もあり、時代の変遷とともに、貯金箱、在庫、多額のお金という意味が追加され、使われるようになりました。このように「お金を蓄える」といった意味合いが、「株」につながったのではないかとする説もあります。
「株」の英語のもう一つの表現は、「share」です。分け前、取り分などを意味します。事業に必要な資金を出し合い、その利益を出資した割合に応じて分配するという「株」本来の性質に合ったものだとも言えます。
「stock」と「share」の意味を合わせると、「事業の資金を分担し、成長させながら蓄えを作り、その利益を分配し合う」ものと解釈できるわけです。これがまさに、「株」の言葉の意味となるのです。
「株」の起源
株式会社が誕生したのは、1602年に設立されたオランダ東インド会社が始まりであると言われています。オランダ東インド会社は、航海資金を調達するために、投資家に出資を募りました。出資してくれた投資家に対し、証券を発行したのが「株」の起源とされています。この証券は今でいう株券にあたります。
当時の航海は、海賊の襲撃や疫病などの影響によって、ハイリスクで成功確率は約20%ほどでした。そこで、複数の投資家から出資してもらい、貿易で出た利益を還元していたのです。約40隻の戦艦、約150隻の商船、約1万人の軍隊を擁していたオランダ東インド会社は出資者に多大な利益をもたらしました。出資額に応じてその配当も変動し、平均で20%、多い年には50%もの配当があったと言われています。
また、オランダ東インド会社は、東インド地域において、国家のような存在でした。大口の出資者には、経営に参加できる権利が与えられており、条約の締結や戦争の遂行、通貨の発行などの権限が付与されていたのです。
システムとしては、現在の株式会社と非常に近いものがありました。1799年に解散したオランダ東インド会社ですが、190年以上もの間その権勢を誇りました。
現代にまで通ずる株式会社の仕組み
日本で初めて設立された株式会社は、1873年(明治6年)の「第一国立銀行」(現在のみずほ銀行)です。また、1893年(明治26年)に三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎によって設立された「日本郵船」が、一般会社法規である商法に基づいて設立された最初の会社ですので、こちらを日本初の株式会社とする見方もあります。なお、幕末の1865年に坂本龍馬によって設立された「亀山社中」は、現在のような本格的な株式会社ではありませんが、その前身と捉えることはできるでしょう。
株式会社の基本的な仕組みは現在も変わりません。事業を起こしたい起業家が、複数の人からお金を集めるために株式会社を作ります。株主から集めたお金を使い、設備投資をし、社員を雇用し、事業を始めるのです。社員には給料が支払われ、事業に利益が出ると、起業家はその中から役員報酬を受け取ります。そして、株主は出資率に応じて配当を受け取るほか、株価の売却益(キャピタルゲイン)を得られるわけです。
株価の売却益を得る以外に、株主には「自益権」と「共益権」があります。「自益権」には、配当を受け取る利益配当請求権、会社が解散した時に残った財産の分配を受け取る残余財産分配請求権などがあります。「共益権」は、経営に参加できる権利で、株主総会に参加し、意思表明できる権利などが代表的なものです。出資比率が大きいほど、議決権は拡大します。
これは、上述のようにオランダ東インド会社の出資者が持っていた権利に似たものがあります。当時の株式会社の仕組みは現代にまで通じているのです。
会社を支える株主の存在
現在の株式会社において、株主はオランダ東インド会社の出資者ほど経営に参加する権利はありません。
しかし、「株」を保有する真の意味は、この経営参画にあるのではないでしょうか。
株主は、自分が「株」を保有している株式会社の経営方針を考え、いかに利益を拡大するかという意見を述べられる立場にあるのです。
会社という法人組織が誰のものであるのかという議論を度々耳にしますが、その語源を知り、歴史をひもとくことが個々の会社にふさわしいあり方を導くきっかけを与えてくれるかもしれません。
自らの会社の成長を考える際に、会社の背景にあるもの、株主の経営に対する意見を尊重することで、大きな飛躍を遂げる可能性も秘められているのです。社員を守ることはもちろんですが、会社を支えている株主の存在を顧みることが、新たなステージに進む第一歩となるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -
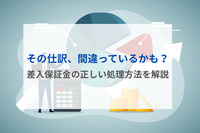
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース