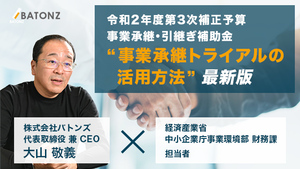公開日 /-create_datetime-/

従業員の健康と福利厚生を管理することは、企業(事業者)にとって非常に重要な義務です。そのため日本では、企業が従業員の健康診断を実施することが、法律によって決められています。
この健康診断にはいくつかの種類があり、受診にあたっては注意すべきポイントもあります。ここでは、企業が行う健康診断の基礎知識について解説し、健康管理業務をサポートする新システムについても紹介します。
企業にとっては義務となる健康診断
法人企業と個人事業主を問わず、事業者は定期的に従業員に対して、健康診断を受診させる義務があります。これは「労働安全衛生法」によって規定されていることです。事業者がこの義務を怠った場合には、労働基準監督署から指導が入ったり、違法行為として罰則を受けたりする可能性もでてきます。
義務の対称になるのは、まず正社員はもちろんですが、契約社員やパート社員であっても、契約期間が1年以上で、正社員の週所定労働時間の4分の3以上勤務していれば該当します。こうした従業員が社内にいる場合は、健康診断の実施義務があるということです。
企業が実施するべき健康診断の種類
すべての企業(事業者)に義務づけられているのが「一般健康診断」です。これは大きく5つに分けられているので、それぞれの要点をまとめておきましょう。
- 雇入時の健康診断:従業員を雇い入れた時点で実施する。
- 定期健康診断:1年以内に1回のペースで定期的に実施する。
- 特定業務従事者の健康診断:「労働安全衛生規則第13条」に該当する従業員に実施。
- 海外派遣労働者の健康診断:海外に6ヵ月以上派遣される従業員に実施。
- 給食従業員の検便:事業所で給食業務を担当する従業員に実施。
上記はあくまでも概要であり、他にも特定業務の従事者に義務づけられた「特殊健康診断」などもあるため、詳細については厚生労働省のホームページなどで確認してください。
健康診断を実施する上でのポイント
健康診断を実施する方法としては、企業の規模に合わせていくつかの選択肢があります。1つめは日時を決め、企業内に検診車が出張して一斉に受診する方法です。2つめは企業側が医療機関を指定して予約をとり、そこで従業員が順次受診する方法です。
もう1つは、受診する医療機関や日時は従業員に一任し、企業側ではその結果を管理するという方法です。どの方法でも決められた内容を確実に実施してもらうため、企業側にはある程度の工夫と手間が求められるでしょう。
さらに、健康診断は実施するだけではなく、従業員の健康を管理することが目的です。そのため健康診断の実施方法や結果の取扱いなどについては、守らなければならないポイントがあります。
まず健康診断の費用に関しては、全額企業が負担することに決まっています。その上で実施した診断結果も、企業が責任を持って一定期間保存しなければなりません。また、50人以上の常勤従業員がいる企業では、診断の結果を所管の労働基準監督署に報告する義務もあります。
診断結果は従業員本人に伝える以外に、もしも健康面で問題が見つかった場合には、企業の担当者は医師の意見を聞いた上で、従業員の業務内容の変更や労働時間短縮などの措置をとる必要があります。近年は精神面でのフォローも重視されているので、企業としてはその点も考慮しておくべきでしょう。
健康管理システムを活用してコストダウンを
ここまでで、実際に健康診断を行う場合には、いくつかの方法があり、さらには結果を管理~報告する義務があることを説明しました。しかし全過程をスムーズにこなすためには、かなりの手間とコストがかかることも事実です。
この問題を解消してくれるのが、従業員の健康情報をパソコン上で一括管理できるサービスです。そのうちの一つに健康管理システム「Carely(ケアリィ)」が挙げられます。Carelyを導入すると、健康診断の予約から診断結果の管理、労働基準監督署への報告書作成まで一貫して対応することができます。
Carelyの特徴はクラウド上で、各従業員の健康情報をすべて管理できることにあります。データをもとに健康診断に関わる業務を一元的に管理することも可能です。さらに、全過程を通じて大幅なペーパーレス化にも貢献するため、企業にとっては経営コストの削減にもつながるでしょう。
また、現代企業の福利厚生では欠かせない精神面でのサポートとして、Web上でストレスチェックを行うこともできます。その他にも多彩な機能を備えていて、クラウドサービスにより常に最新バージョンでシステムを運用することが可能です。
まとめ
企業にとっての健康診断とは、従業員の健康管理をするために欠かせないものであり、法律によって明確に規定された義務でもあります。メンタル面でのケアまで含めると、企業が負担する従業員の健康サポート業務は、今後さらに増える可能性があります。
もしもその負担が業務効率を低下させるようなら、パソコンがあれば使える健康管理システムを導入することも1つの選択肢です。社員の健康管理が効率化できるだけでなく、ペーパーレス化や業務効率の改善効果も期待できるので、1度導入を検討してみることをおすすめします。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -
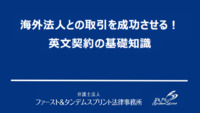
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -
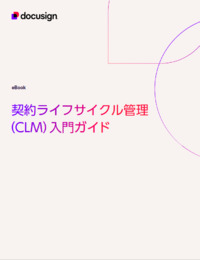
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

【会計】金融資産の減損における期中期間の簡便処理、検討─ASBJ、金融商品専門委 旬刊『経理情報』2025年7月20日号(通巻No.1749)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

【2025年版】ビジネス実務法務検定2級 合格率・難易度・出題傾向・勉強法は?最新データで合格の道筋を解説!
ニュース -

上半期の「後継者難」倒産 2番目の230件 高齢化の加速で、事業承継の支援が急務に
ニュース -

【満足度95%】『ManegyランスタWEEK -2025 Summer-』開催決定!
ニュース -

【最新版】2025年度の簿記2級 試験日程と試験概要まとめ
ニュース -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
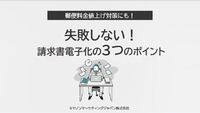
【郵便料金値上げ対策にも!】失敗しない!請求書電子化の3つのポイント
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -
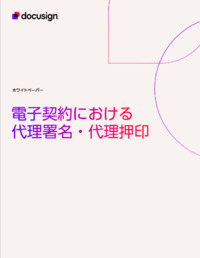
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -
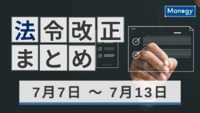
毎月勤労統計調査 令和7年5月分結果速報 など|7月7日~7月13日官公庁お知らせまとめ
ニュース -
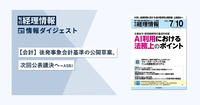
【会計】後発事象会計基準の公開草案、次回公表議決へ─ASBJ 旬刊『経理情報』2025年7月10日号(通巻No.1748)情報ダイジェスト/会計
ニュース -

【税務】リース税制見直し等に関する改正法基通等、公表─国税庁 旬刊『経理情報』2025年7月20日号(通巻No.1749)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -
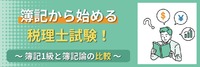
簿記から始める税理士試験!~簿記1級と簿記論の比較~
ニュース -
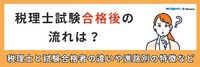
税理士試験合格後の流れは?税理士と試験合格者の違いや進路別の特徴など
ニュース










 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました