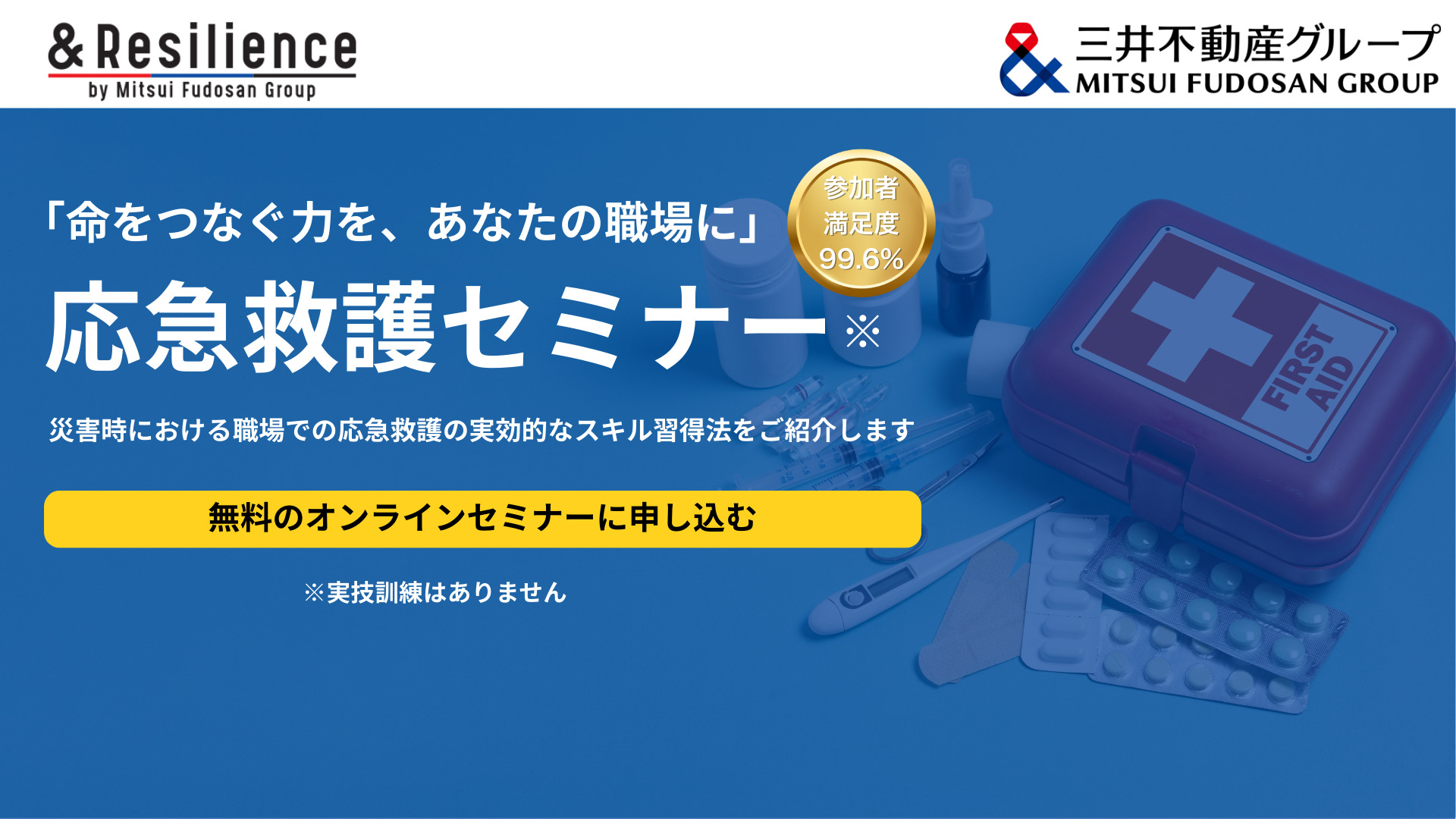公開日 /-create_datetime-/
「ノーレイティング」導入は社員の成長のため。新たな評価制度から3年経ったフィードフォースのこれまで

記事転載元:パラれる / 株式会社コーナー
「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチング支援サービス。採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。社員をランク付けしない人事評価「ノーレイティング」。従来の年度単位の評価やランク付けでは昨今の目まぐるしい変化に対応できないと、GEやGAP、マイクロソフトといった大手グローバル企業の多くが「ノーレイティング」に移行したこともあり、日本企業の注目度も日に日に高まっています。
しかし、実際に導入しうまく運用できている組織はまだまだ多くありません。そんな中、2018年にいち早く「ノーレイティング」を導入し、3年に渡って運用し成果を上げている企業があります。BtoB領域で企業の生産性を高めるサービスを提供している株式会社フィードフォースです。
今回は人事のなべはるさんに、「ノーレイティング」の概念、導入背景や過程などについてお聞きしました。
人事のなべはる/株式会社フィードフォース 人事部
2014年にフィードフォース1人目の人事として中途入社。入社以来、採用・育成・人事制度・労務など幅広い業務に携わり、現在は人事責任者を務める。
ノーレイティングとは
──「ノーレイティング」について、昨今注目されるようになった背景も合わせて教えてください。
ノーレイティングとは、「ランク付けをしない人事評価方法」のことです。rate(評価)が語源であり、年度単位の評価やランク付けを行わない代わりにリアルタイムで目標設定とフィードバックを実施し、その都度評価を行います。
たまに「ノーレイティングとは人事評価をしないことだ」と誤解する方もいますが、あくまで「社員のランク付け」であるレイティングをやめる、もしくは年次で評価することをやめる、が正しい解釈です。
これまで日本ではレイティングが一般的な評価方法として多くの企業で導入されてきました。毎年の年度末に1年間の働きを評価し、A・B・Cなどのランク付けに沿って給与や賞与などを決めてきた形です。
そんな中でノーレイティングが注目された理由は、このレイティング形式の人事評価制度の「限界」を感じている企業が増えてきたことにあります。
例えば以下のような問題が挙げられます。
・評価期間中に目標が変わり、評価の納得感が薄れる
・評価期間内に成果が出ない仕事をしている社員を公平に評価するのが難しい
・昇給原資が限られている以上、相対評価にならざるをえない
・異なるチーム、異なる職種の社員を公平にランク付けするのは至難の業
このような理由から、大手グローバル企業が年次評価を廃止したことをきっかけに、日本企業も関心を示すようになりました。
なぜフィードフォースはノーレイティングを導入したのか
──フィードフォースが「ノーレイティングを導入しよう」と決めた背景には何があったのでしょうか。
フィードフォースは2006年に創業し、今では単体で80名(2021年3月時点)を超える組織となりました。ノーレイティングを導入したのは2018年で、社員数がちょうど50名を超えた頃のことです。
「50名の壁」という言葉があるように、当社においても人事評価制度を含む人材マネジメントの仕組みを整えなければ、今後のスムーズな拡大に支障をきたしてしまう課題感がありました。
それまでは9ブロック(※)方式を導入し、半年に1度の評価(レイティング)を行っていたのですが、「複数のチーム、複数の職種の社員を一定期間の評価で9ブロックに公平に割り振る」ことに限界を感じていたのです。
(※)9ブロックとは、GE(General Electric)社が行っていた人事評価方式のこと。業績を縦軸、行動を横軸にした二軸で評価を決定する。
また、社員からもこんな声が挙がっていました。
「評価されたのはいいけれど、それをどう仕事に活かせばいいか分からない」
「半年前の仕事を評価されたところで、今は全然違う仕事をしていて意味がない」
社員にとって納得感があり、環境の変化に柔軟に対応できて、社員の成長に寄与する制度ってなんだろう──そう考えた結果、定期評価をしない「ノーレイティング」に行きついたのです。特に最後の“成長”が大事だと思っていて。人事評価制度は「社員の成長のためのもの」という認識を強く持っています。
──フィードフォースの評価制度は、実際にどのように変わりましたか?
フィードフォースが実施しているノーレイティングとは、定期的な評価(レイティング)を行わないことを指しています。
概要をご紹介すると、以下のような形です。
■等級制度
・「ジュニア」「メンバー」「シニア」「エキスパート」に等級が分かれ、それぞれの等級で年収レンジが定められている
・職種ごとに各等級の要件が決まっており、年収レンジと共に社内に公開されている
・等級が上がる(昇級する)と給与が上がる
・昇級するためには昇級審査で自身の成長と貢献を被評価者が説明する
・昇級審査は自分のタイミングでいつでも受けられる(昇級すると翌月から昇級した等級の給与になる)
■定期昇給
・半年に1度定期昇給がある
・定期昇給額は全社員一律同額であり、個別の評価は行わない
・自身の属する等級で規定されている年収レンジ上限に達している場合は、それ以上定期昇給はしない
ノーレイティング導入プロセスと運用方法
──ノーレイティングを導入するまでのプロセスや苦労した点、また運用で工夫している点などを具体的に教えてください。
制度導入から3年が経過したこともあって、ある程度軌道に乗ってきています。ただ日々運用する中で課題も見つかっており、まだまだ今後も改善を続ける必要があると思っています。
ここでは今日に至るまでのプロセスやポイントを、以下3つに絞ってご紹介します。
1.これまでの人事制度からの改編方法・プロセス
前述した通り、人事評価制度は「社員の成長のためのもの」という考え方がベースにありました。そのため、「もっと成長を促せる制度にしたい」「成長したら給与が上がるようなシンプルなものがよさそうだね」「定期的な評価は会社都合であって、社員からしたら自分のタイミングで評価されたいよね」「なら定期評価は必要ないのでは?」といった思考プロセスで定期評価をなくす決断に至りました。
その後の進め方は下記の通りです。
↓
合意をとりつつ、経営企画メンバーが職種ごとの等級定義を定めるなどのタスクを行う(職種ごとの等級定義については、数カ月間ほどかけて各マネージャーが作った原案を元に対象職種の意見を聞きながら固める)
↓
新等級に既存社員を当てはめてみて、等級定義と給与設定に違和感がないかを調整
↓
全社員向けの説明会を実施
↓
本施行
2.ノーレイティング導入にあたり苦労した点と、その解決方法
一番苦労したのは「納得感が生まれる等級定義を決めること」でした。先ほど現場も巻き込んで数カ月間ほどかけたとお伝えしましたが、手間がかかることはもちろん、社員に納得感が生まれるように適切な設計をすることがとても難しいのです。
具体的すぎると変化に耐えられないし、かといって抽象的すぎると納得感が生まれません。適切に設計できたとしても、時間経過と共にその定義がしっくりこなくなることも多々あります。そのため「見直し」を継続的に行うことがノーレイティングにおいては大前提。まさに運用が肝になる制度なのです。
3.運用を上手く進めていくための6つの取り組みポイント
a)人事主導ではなく経営陣&現場主導で行う
ノーレイティングは組織の在り方から変える制度であり、経営陣の意思や理解は必要不可欠です。また実際に運用するのは現場なので、経営陣・現場双方の理解・協力が成功のカギを握ります。当社が等級定義を決める際に現場を巻き込んだように、構想段階から関係者を巻き込んで進めていくのが良いでしょう。
b)等級定義の継続的な見直し
こちらは2.で前述した通りです。
c)等級定義において階層を増やしすぎない
目安としては、1つ下の階層との違いを誰もが明確に説明できるくらいの階層数にすること。階層が増えすぎて違いを説明できなくなってしまうと、社員の納得感が薄れてしまいます。
d)等級定義を決める際、職種横断でのガイドラインを作った
例えば「メンバー」は一人前に仕事ができる人、「シニア」はチームに良い影響を与えられる人など、各職種共通の大きな概念を作っておくと、職種ごとの定義も作りやすくなります。
e)昇級審査
「昇級審査はいつでも受けられて、昇級すれば翌月から給与に反映される」のが当社の特徴です。マネージャー推薦だけでなく、所定のフォームから自薦することもできます。
f)マネージャーのサポート
ノーレイティングにおいては、マネージャーが日常的に行っている1on1で業務や成長へのフィードバックを常々行っていくことが大切です。また、定期的な振り返りの機会として2021年からは半年に1度、自身の成長と貢献を振り返る資料を作る「キャリアプレゼン制度」も開始しました。
ノーレイティングがマッチする企業・しない企業
──ノーレイティングがマッチしやすい、もしくはしづらい事業ステージ/ビジネスモデル/カルチャーなどはありますか?なべはるさんのお考えをお聞かせください。
マッチしやすい組織には以下のような特徴があり、逆にマッチしない組織は、以下の反対にあると捉えていただければ良いかと思います。
<ノーレイティングがマッチする組織>
1. 環境の変化が早い
2. 成果が明確な数値で測りづらい職種や仕事が多い
3. 事業が成長し、利益が伸びている
うち1.と2.は、評価の難易度に関わってきます。そもそも変化に乏しく、明確な数値や指標で評価できる組織であれば定期評価でも十分対応できるはずです。逆に変化が激しく、評価期間中に目標ややることがころころ変わる環境であれば、定期的な評価で社員の納得感を醸成するのは難しいかもしれません。
3.に関しては、当社のノーレイティングは「絶対評価」で行なっているので、同様に行う場合は必要なポイントになります。相対評価であれば年間の昇給額はコントロールできますが、絶対評価だと社員が成長し続ける限りは理論上無限に昇給します。社員の成長に対して昇給という投資ができるだけの事業成長が前提になるということです。
オススメ本
──ノーレイティングについて学びたいと思っているHRパーソンに向けて、お薦めの書籍があれば教えてください。
まだまだ実践事例なども少なく、ドンピシャのオススメ本はあまりない印象ですが、考え方の参考になった書籍をご紹介します。
ハーバードビジネスレビュー/2017年4月号
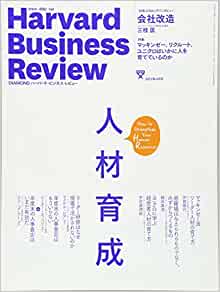
「年度末の人事査定はもういらない」という意見と、「年度末の人事査定はいまだ有効だ」という意見がぶつかり合うプロレス企画記事が掲載されており、考え方の参考になる一冊です。
編集後記
「人事評価で組織は大きく変わる」と言われるほど、評価は影響力が大きいものです。ただ組織の根幹となるため易々と改変できるものではなく、日本企業においては長年大きな変化が見られていません。
しかし適切に人事評価の制度を改変できれば、フィードフォースのように組織が目指す方向性を明確にできるだけでなく、社員全員が正しく会社の目的を認識し、良い関係性の中で事業をアジャイルに進めることができるようになるはずです。
人事評価制度によって社員の成長をより促していきたいとお考えの企業は、なべはるさんのお話を参考に、評価制度の改変を視野に入れてみるのも良いかもしれません。
人事の困りごとはプロフェッショナルへ頼む時代です
コンサルを雇うよりも安く、派遣社員を雇うより専門的で、 正社員を雇うよりもノーリスクで、貴社の悩みや課題を解決できます。こんなこと困っていませんか??
・採用がうまくいかない
・採用に割ける時間がない
・繁忙期だけ即戦力が欲しい
corner inc.は、手を動かす人事コンサルです。cornerには人事・採用関連の豊富な経験とノウハウを持った頼もしいパートナーが多数登録しています。またcornerのメンバーも人事・採用業務をよく知るものばかり。パートナーを紹介して終わりではなく、実際のプロジェクトにも積極的に関与し、 パートナーとともに課題解決に努めます。お悩みや困りごとをまずはお気軽にご相談ください。
人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチングを支援する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」。
記事提供元
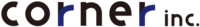
「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」
株式会社コーナーが運営する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」は、採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。
コーナーは1,500名を超える即戦力のプロフェッショナルが登録をし、プロフェッショナルによる課題解決を実働支援型で行います。週1日から必要な業務内容・業務量だけプロフェッショナルの経験を活用できることで、多様化してきている人事・採用課題を効果的に解決します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -
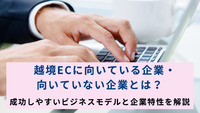
越境ECに向いている企業・向いていない企業とは? 成功しやすいビジネスモデルと企業特性を解説
ニュース -
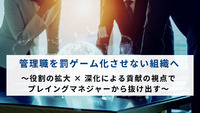
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -
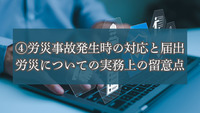
④労災事故発生時の対応と届出│労災についての実務上の留意点
ニュース -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -
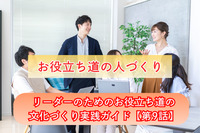
お役立ち道の人づくり/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第9話】
ニュース -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表
ニュース