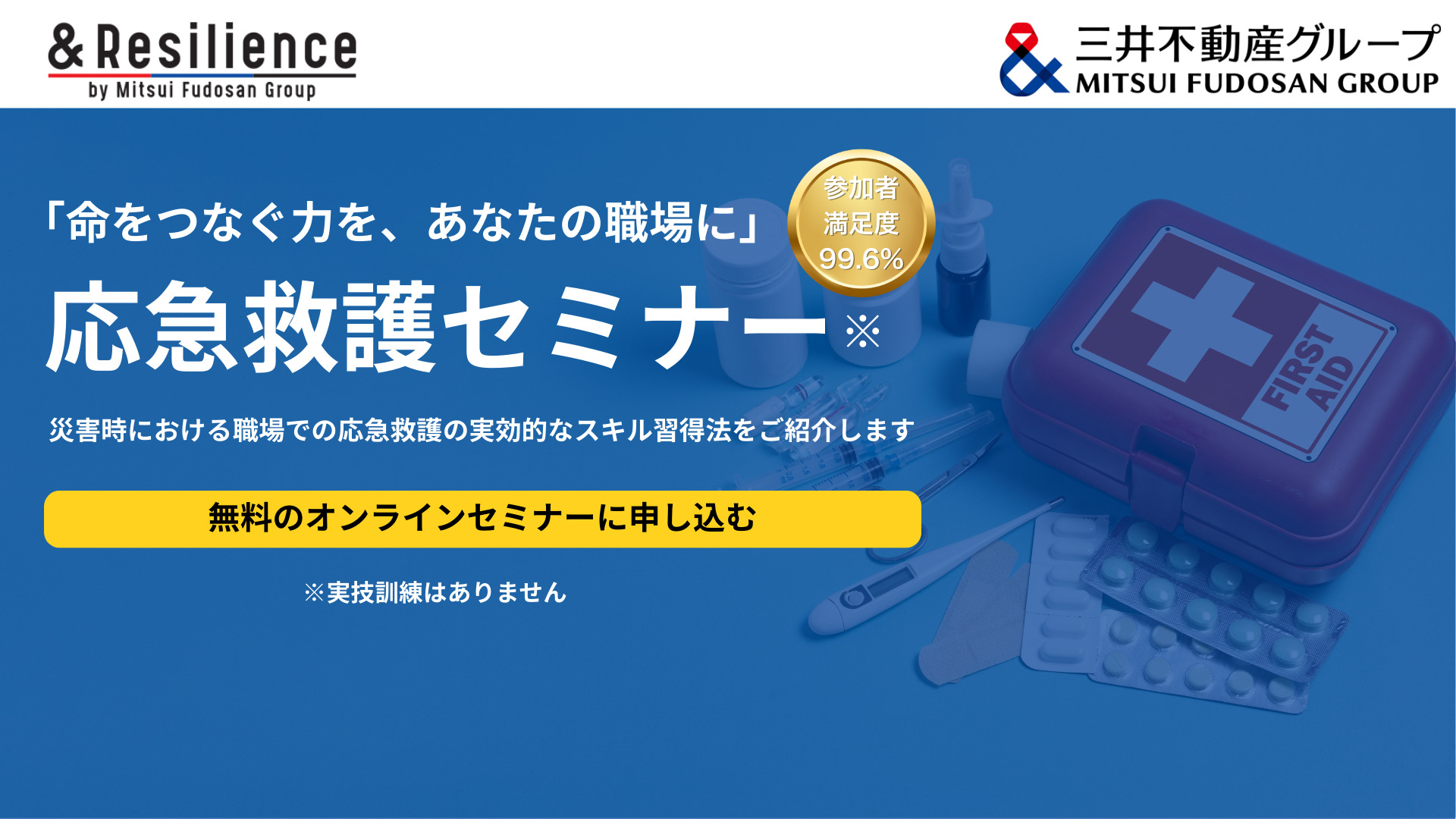公開日 /-create_datetime-/
勤怠管理システムが使いづらい!乗り換えのきっかけや成功事例
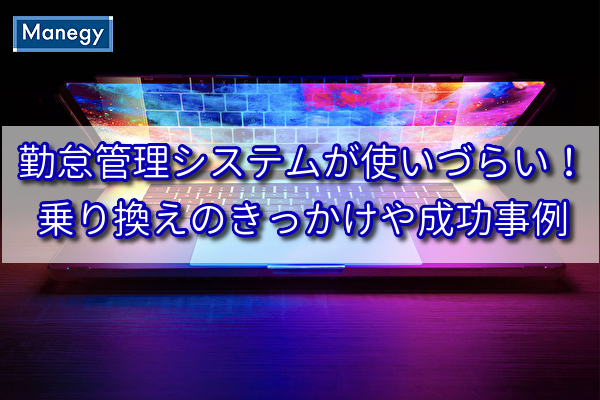
記事作成日(2021年4月12日)
働き方が多様化する昨今、タイムカードやExcel等によるアナログ管理をやめ、勤怠管理システムを導入する企業は増加傾向にあります。しかし、せっかくシステム化を図ったにも関わらず、「思うように使いこなせない」「勤怠管理システムが使いづらい」と感じる人事担当者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、使いやすい勤怠管理システムへの乗り換えを検討している企業の方に向けて、勤怠管理システムの乗り換えを成功させるポイントを紹介していきます。
勤怠管理を楽にしたい人事担当者様へ
労務管理をちゃんとやりたい…。でもリソース不足で手がまわらないし、確かな知識を持った社員もいない…。
そんなお悩みを抱える人事担当者様には、楽に勤怠管理ができる勤怠管理システムの導入がおすすめです。
「MINAGINE就業管理」はコンサルタントが導入・ルール設計から運用まで、"総合的にサポート"します。
【資料内容】
打刻の種類、勤務・休暇の申請機能、残業チェッカー、利用イメージ、導入事例、利用料金
目次【本記事の内容】
勤怠管理システムを使いづらいと感じてしまう理由
勤怠管理システムを導入したものの、残念ながら「思ったような使い方ができていない」と感じる人事担当者の方は多いようです。なかには、「アナログ管理をしていた頃のほうが良かった」とせっかく導入した勤怠管理システムを使用せず、アナログ管理を続けている企業も存在します。 せっかく導入した勤怠管理システムを使いづらいと感じてしまうのは、なぜなのでしょうか。
① 導入後のサポートがない
勤怠管理システムを使うには、導入後に個社ごとのシステム設定が必要です。会社の就業規則や勤務形態などの実態に合わせて細かい設定が必要となるため、人事担当者だけでは設定が難しい場合もあるでしょう。
しかし、導入する勤怠管理システムによってはIDとパスワードを発行するだけで導入サポートがない場合もあります。導入時の設定をスムーズに行うことができなければ、いつまでたっても目的通りに使いこなすことができず、結局タイムカードやExcel等のアナログ管理に戻さざるを得ない事態に陥ってしまうのです。
また、勤怠管理システム導入時のサポートといっても、システム操作方法のサポートのみで、「会社の就業規則や勤務の実態に合わせて使うためにはどうしたら良いか」といった質問に答えてもらえないことや、問い合わせをしてもなかなか返事がない、対応が遅いというケースも珍しくはないようです。
導入後のサポートがない勤怠管理システムは、せっかく導入した勤怠管理システムを有効活用することができないことから、使いづらさを感じる原因となります。
② 多様な働き方に即していない
最近ではコロナ禍によるリモートワークや時差出勤など、多様な働き方が増えてきています。しかし、勤怠管理システムの中には社内サーバー接続が条件になっているものや会社に設置したICカード打刻機を使用した勤怠管理しか行えず、リモートワークに対応していない勤怠管理システムもあります。また、コロナ禍で増えた時差出勤による勤務開始時間の遅延に関して、毎回手作業で修正しなければいけないという場合もあるようです。
今後、働き方はさらに多様化していくことが予想されています。それぞれの企業の勤務スタイルや実際の働き方に合わせた勤怠管理ができなければ、せっかく勤怠管理システムを導入したとしても、使いづらさを感じてしまうでしょう。
③ 打刻漏れや承認漏れが多い
タイムカードやExcel等によるアナログ管理をやめて勤怠管理システムを導入した企業のなかには、従業員の打刻漏れや上長の承認漏れが増えてしまったと悩む人事担当者もいます。
勤怠管理の方法が変わると、どうしても慣れるまでに時間がかかるものです。しかし、打刻漏れや承認漏れがあると、勤怠集計を行うタイミングで人事担当者がこの対応漏れを各部署に依頼しなければならず、余計な手間と時間がかかってしまうのです。
人事担当者が勤怠集計をスムーズに行うには、各従業員や管理者の対応漏れを最小限に抑える必要があります。
このような打刻漏れや承認漏れに対応しなければならない人事担当者の負担を軽減するためにも、そもそもアラート機能のついていない勤怠管理システムの導入は避ける必要があるでしょう。打刻漏れや承認漏れを防ぐためのアラート機能が備わった勤怠管理システムも少なからずありますが、こちらも導入時のシステム設定がスムーズにできなかったことから、活かせていないケースは珍しくありません。
④ 打刻修正の履歴が分からない
勤怠管理システムを利用するうえで注意しなければならないのが、打刻修正です。一般的な勤怠管理システムでは、打刻修正が行われた場合に修正後の時刻にて打刻時間が上書きされてしまうことが多くなっています。そのため、打刻修正が行われた事実は確認できたとしても、修正前の打刻時間が何時だったのかという履歴が残らず、本来の打刻時間が分からなくなってしまうのです。
打刻修正の履歴が残らないことは不正申告やサービス残業の温床になりやすく、あまりにも打刻修正が多い場合、労働基準監督署の調査や監査が入った場合に従業員の勤務実態を正確に証明することは難しくなります。
⑤ 給与計算システムとの連動した作業効率化ができていない
勤怠管理システムを導入する目的として、給与計算システムと連携させることで人事担当者の手間を省きたいと考える企業は多いです。
しかし、勤怠管理システムのなかには、給与計算システムとの連携ができないものもあります。また、給与計算システムとの連携ができる場合も、システム連携のやり方が複雑、あるいはCSVファイルを毎回手動で加工して給与計算システムに取り込まなければならない等、上手く連携ができず、使いこなせていないという企業は意外と多いものです。
⑥ 自社の就業規則やルールを反映できない
勤怠管理システムの導入後に就業規則の変更やコロナ禍における時差出勤、リモートワークなど勤務スタイルに変化があったという企業のなかには、このような働き方の変化を勤怠管理システムに反映することができず、結局、出勤時間と退勤時間からエクセルで勤務時間を計算しているというケースも少なくありません。自社の実態に合った管理が行えないと、勤怠管理システムを導入しても使うことができず、むしろ手間がかかってしまうこともあるでしょう。
就業規則や働き方は変化していくものです。自社のルールを適切に反映することができない場合も、勤怠管理システムが使いづらいと感じてしまう原因となります。
勤怠管理システムの乗り換えは大変?
現在利用している勤怠管理システムに使いづらさを感じていても、いざ乗り換えるとなると手間や労力、初期費用などを考えて、一歩踏み出すことが出来ない人事担当者も多いのではないでしょうか。
しかし、勤怠管理システムの乗り換えは、乗り換えるシステムの選び方によっては、それほど大変なものではありません。
例えば「MINAGINE就業管理」では、勤怠管理システムを導入いただいた企業様が、本来の目的通りに勤怠管理システムを活用していただけるまで、最大3ヶ月間徹底的なサポートを行っており、その後も必要に応じたサポートをさせていただきます。
また、ミナジンの導入サポートは、ただ単にシステムの操作方法や設定方法をサポートするだけではありません。労務管理に関する知識を有したスタッフが、会社の就業規則や働き方に合わせて最適な勤怠管理の方法をご提案させていただくため、会社の勤務スタイルや実態に即した勤怠管理が可能です。現状の問題点をヒアリングしたうえで、勤怠集計にかかる手間を削減するにはどうすれば良いかのアドバイスもさせていただきます。
そのため、「MINAGINE就業管理」であれば、乗り換え時の手間や労力を最小限に抑え、スムーズに勤怠管理システムの乗り換えをすることができるでしょう。
乗り換え後は、「勤怠管理システムを乗り換えて良かった」と実感していただけるまで、徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。
勤怠管理システム乗り換えのきかっけは?成功事例を紹介
導入サポートが充実した「MINAGINE就業管理」は、タイムカードからの乗り換えはもちろん、現在の勤怠管理システムに使いづらさを感じていた企業からの乗り換え先としても選ばれています。
ここでは、実際に勤怠管理システムの乗り換えに成功した企業様の成功事例を紹介します。
株式会社ビーアイメディカル様
国内外の製薬企業からMR業務を受託・代行し、広範囲な医薬品の情報提供を支援されている株式会社ビーアイメディカル様は、他社の勤怠管理システムから「MINAGINE就業管理」への乗り換えに成功した企業様の一つです。
株式会社ビーアイメディカル様は、これまでの勤怠管理システムにおいて、残業集計が不適切であったり、休日出勤と振替休日・代休の紐付けが行えなかったりといった不都合を感じていました。それにより、給与計算や休暇管理において手作業が発生してしまい、それが大変な負担となってしまっていたそうです。
さらに、「一定のことができる」だけの勤怠管理システムではなく、コンプライアンスの徹底を重視した勤怠管理システムという視点で比較検討し、弊社の「MINAGINE就業管理」への乗り換えをご決定いただきました。
株式会社TAT様
ネイリスト、ネイルサロン、スクール、専門学校などに材料を販売しているネイル用品専門商社である株式会社TAT様も、他社の勤怠管理システムから「MINAGINE就業管理」への乗り換えに成功した企業様の一つです。
株式会社TAT様は福利厚生が充実しており、一般的な有給休暇だけでなく、「記念日休暇」「誕生日休暇」といった独自の休暇を設けています。これまで使用していた勤怠管理システムにも、基本的な出勤・欠勤の他に有休休暇の申請機能は備わっていたものの、それ以外の特殊な申請方法には対応できていないというところが課題となっていました。
「MINAGINE就業管理」なら、このような特殊な休暇についても個社ごとに設定することができ、効率の良い管理ができるところが乗り換えの決め手となったということでした。
怠管理システムの乗り換えに失敗しないための注意点
勤怠管理システムを使いづらいと感じる企業は意外と多いものです。しかし、勤怠管理システムの導入には手間も費用もかかるため、使いづらいからといってすぐに乗り換えができるものでもありません。そのため、どの勤怠システムに乗り換えるのかが重要なポイントになります。そこで続いては、勤怠管理システムを乗り換える際の注意点として、勤怠管理システムの選び方を紹介します。
サポートが充実した製品を選ぶ
勤怠管理システム乗り換え後も、就業規則の変更等が行われる可能性は高いでしょう。規則やルールの変更によって再び勤怠管理システムを使いづらいと感じることもあるかもしれません。 そのため、勤怠管理システムの乗り換えを成功させるためには、単にシステム操作の方法だけでなく、将来の運用変更まで見据えてサポートが受けられる勤怠管理システムを選ぶことが大切です。
勤怠管理システムを活用する
最新の勤怠管理システムには、タイムカードやExcel等のアナログ管理にはない便利な機能がたくさん備わっています。しかし、勤怠管理システムの乗り換えで大事なことは、これらの機能をしっかりと使いこなすということです。新しい勤怠管理システムを導入しただけで、改善や効率化が図れるわけではないということは、あらかじめ理解しておく必要があるでしょう。 ミナジンでは「MINAGINE就業管理」を導入いただいた企業様に対して、勤怠管理システムをご活用いただき、便利だと感じて頂けるまでしっかりとサポートを続けていくことを使命としていますので、安心してご相談ください。
自社の就業規則や実態に合った製品を選ぶ
勤怠管理システムの乗り換えをするなら、「出勤」「退勤」「有休」といった基本的な勤怠管理ができるだけでなく、自社の就業規則や働き方の実態に合わせた勤怠管理ができるかどうかを確認しましょう。また、現状の課題が解決できるか、働き方の多様化やコンプライアンスに対応できるか否かも確認することが大切です。 ミナジンでは就業規則や勤怠管理のお悩み、実態をヒアリングさせていただいたうえでシステムへ反映させ、1ヶ月間の試用運用で問題点を明らかにします。完全移行として本稼働を始めてから少しずつ手直しをして軌道に乗せていくことから、自社の就業規則や実態に合わせて勤怠管理システムを整えることができます。
本当に必要な機能が備わった製品を選ぶ
勤怠管理システムを選ぶときは、本当に必要な機能が備わった製品を選ぶことが大切です。 勤怠管理システムは便利な機能が多い反面、自社に不要な機能が搭載された勤怠管理システムも存在します。ただ機能が多いだけの勤怠管理システムでは、導入しても使いこなせず逆に実際に使用する従業員に対して使いづらさを感じさせてしまう原因にもなり兼ねません。 「MINAGINE就業管理」は、従業員と管理者・人事担当者すべての方が見やすく、使い勝手の良いシンプルな画面操作もおすすめのポイントです。
勤怠管理システムは使いやすさが大事!乗り換えにはミナジンを
勤怠管理システムは、人事担当者はもちろん現場で実際に使う従業員にとっても使いやすいものであることが大切です。現状の勤怠管理システムが使いづらい場合は、システムの乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。
「MINAGINE就業管理」は、人事労務管理の知識を持ったコンサルタントによる徹底サポートで、乗り換えにかかる手間や労力を最小限に抑えることが可能です。また、就業規則や勤務実態に即した勤怠管理が実現できるうえに、コンプライアンスにも対応した勤怠管理システムとして社会保険労務士法人にも推奨されています。
勤怠管理システムの乗り換えをご検討の企業様は、ぜひこの機会に「MINAGINE就業管理」の導入をご検討くださ
勤怠管理を忙しくてできない!という人事担当者様へ
労務管理をちゃんとやりたい。きちんと給与計算をして、未払賃金をなくしたい。
過重労働を減らして時間外勤務の上限規制と36協定を遵守したい。
在宅勤務やフレックス、新しい働き方を導入したい。
しかし、しっかりとやろうとすればするほど、業務は複雑になり確かな知識が必要になります。しかし、多忙で人的リソースが少ないといった理由からそこで足踏みをしてしまう担当者もする方は多いのではないでしょうか?
そこで導入を検討したいのが、労務管理をよくしたい人事労務担当の味方「MINAGINE就業管理システム」です。
・最大3カ月間、全社的に勤怠システムが稼働開始できるまでコンサルタントがサポートします
・導入段階で、就業規則や賃金規定など、就業管理に関するルールで不安な点を、当社社労士がアドバイスします。
・給与計算のアウトソーシングまで一貫してサービス提供が可能です。
労務管理のレベルアップは、「重要だけど緊急ではない」と思われがちですが、働き方改革の流れや、新型コロナウィルスの影響による就業環境の社会的な変化など、後回しにすれば会社にとって大きなリスクになります。
”会社の未来をまもる”ためにも、是非「MINAGINE就業管理」サービスをご検討ください。
記事提供元
人事の力で会社をみんながいきる場所にする
「HRソリューションラボ」
「すべての会社に人事部を」を理念とする株式会社ミナジンが運営する人事労務の課題解決に役立つ情報メディアです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目
おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説
ニュース -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -
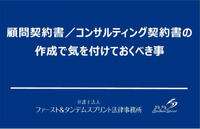
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
ニュース -

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース