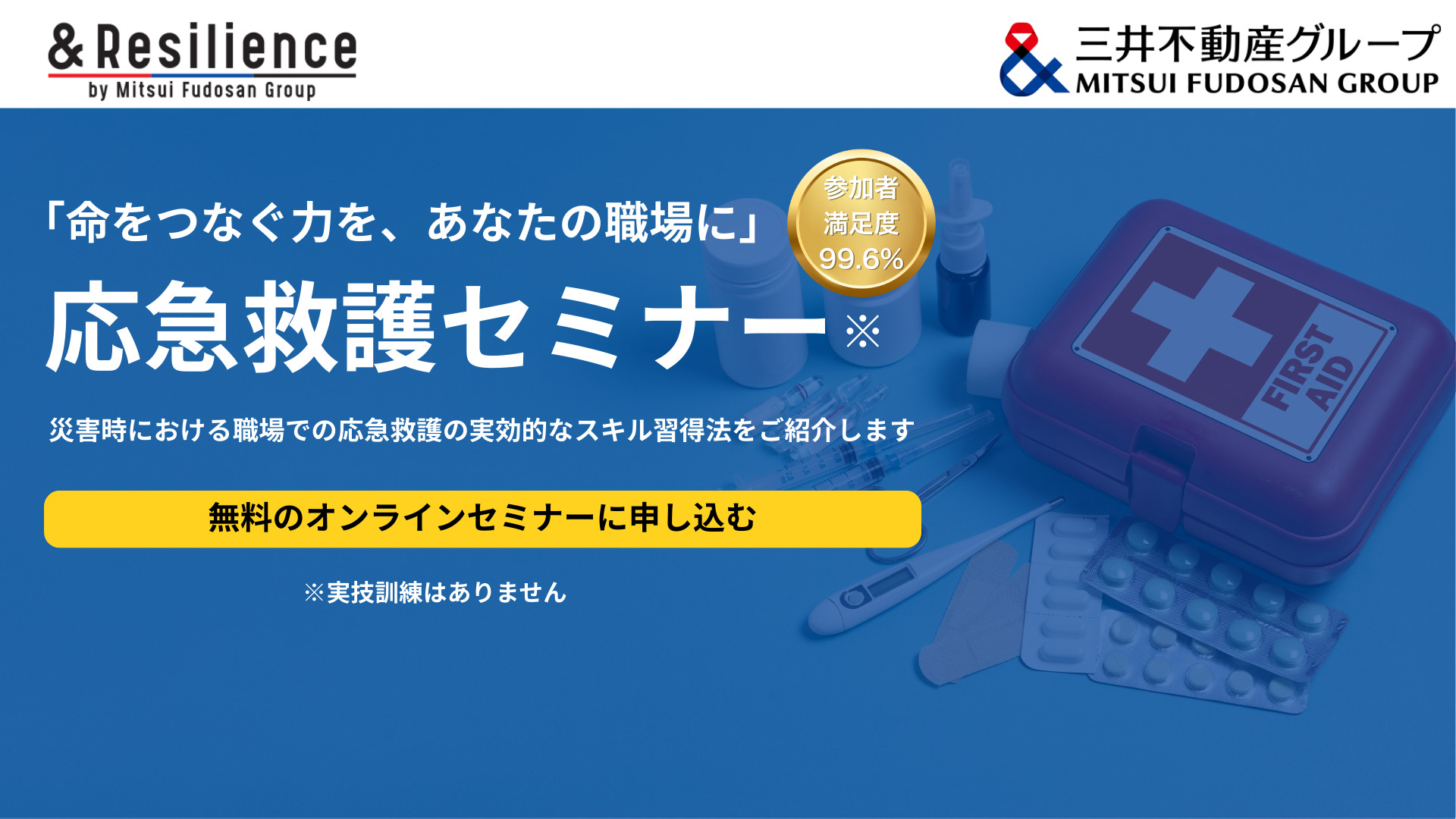公開日 /-create_datetime-/
男性の育児休業取得がより公平に!社会保険料免除はどう変わる

男性女性にかかわらず、育休中は健康保険と厚生年金の支払いが全額免除されます。
しかし、この社会保険料免除の制度を「抜け道的」な使い方をするケースが多くみられ、不公平感が生じたことから、要件が改正されました。
そこで今回は、育休における社会保険料免除の要件が、いつからどのように変わるのかを解説していきます。
\複雑な育休・産休に関する制度の概要を確認!/
男性の育休にも対応したお役立ち資料はこちら
そもそも男性の育児休業制度の目的は?
女性は出産や子育てのタイミングで休業したりキャリア形成がしにくかったりと、労働者として不利な立場にありました。
そこで、男性も育児や家事を手伝い、子育ての負担を男女でシェアできるようにと作られたのが、男性の育児休業制度です。
女性の育児休業取得率は、1996年度の49.1%から上昇し続け、2007年度からは80%台を維持してきました。
一方、男性による育児休業取得率は低いものの、順調に上昇しています。
1996年度は0.12%だったものの、2019年度には7.48%に上昇。さらに、2020年度には12.65%と飛躍的な増加を示し、初めて10%の壁を超えました。
少しずつ上昇傾向をみせる男性の育児休業取得率ですが、決して順調に推移してきたわけではありません。
2002年、政府は少子化対策の一環として、2012年までに10%の達成率を目指していたものの、なかなか普及しませんでした。
目標値を思うように達成できないなか、「2017年までには10%を目指す」「2020年までには13%」と先送りし、ようやく2020年度にほぼ達成できた経緯があります。
政府は今後も男性の育児休業取得率をさらに高めたい考えで、2025年には30%の取得率を目標に掲げています。
いつから・なにが・どう変わる?
2022年10月1日以降、育児休業制度のうち、「社会保険料の免除の要件」が以下のとおり変わります。
【現行制度】
「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」において、社会保険料が免除されています。
また、ボーナス支給月の末日に育休を取得していれば、ボーナスにかかる保険料も免除されます。
つまり、ボーナス月の月末日1日だけ育休を取ったら、ボーナス分を含めたその月の社会保険料が免除される、ということになります。
【改正後】
月末日のみ育休を取得していた場合は対象となりません。
従来どおり育休取得月の末日が育休期間中である場合に加え、同じ月に2週間以上取得した場合も免除対象となりました。
ボーナス月の育休に関しては、休業期間が1カ月を超える場合にのみ、免除の対象となります。
抜け道となってしまった原因
「月末日に育休を取得するだけで、社会保険料が免除される」という要件が、抜け道を作った大きな原因です。
月末日をまたぐか否かで、両者の手取り金額には10万円以上の差が生じる可能性があり、不公平感や抜け道的に利用するケースが生じていると問題視されてきました。
先述の「その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」という定義を逆手に取り、ボーナスにかかる社会保険料の免除を目的にした育休を取る人が増えてしまったのです。
ここで、7月にボーナスが支給される会社の従業員、AさんBさんの育休取得を例に、現行の抜け道内容を見ていきましょう。
- ● Aさんは、7月31日に1日のみ育休を取ったので、7月分の給与+ボーナス分を対象に社会保険料が免除され、実質手取り額が増えて得します。
- ● Bさんは、7月1日から7月15日まで育休を取ったので、7月分の免除はありません。
このような抜け道手法が社内で頻発すれば、社員間に不信感や業務負担感、分断などマイナスの雰囲気が蔓延しかねません。
こうした現状を受け、今回の改正が実施されることになりました。
男性の育休取得のボトルネック
男性が育休を積極的に取得するには、「職場の雰囲気」が重要です。
2020年2月、当時の小泉進次郎環境相が、長男誕生時に育休を取得したのは記憶に新しいところでしょう。
育休を取得したことで「世の中のお母さんはすごいと心から感じている」とも述べていました。
しかし、小泉氏が育休を取得するにあたり、「男性の取得率向上につながる」と期待する声がある一方で、「環境相の立場を踏まえるべきで、各方面の理解を得てから判断してほしい」という声も聞かれました。
民間企業においても、育休の取得に対して相反する声があるのが現実です。
さすがに言葉に出さなかったとしても、「この時期に育休か……」「育休取得者のせいで仕事がまた増える」「空気が読めないのか?」といった社内の雰囲気があれば、取得率向上にはつながりません。
そこで、2022年4月1日からは、事業者には労働者が育休を取りやすいよう、研修や相談窓口の設置など雇用環境の整備措置が義務付けられます。
いくら政府が旗を振っても、事業者側の取り組み姿勢いかんで、男性社員の育休取得率は大きな影響を受けてしまいます。
従業員から「働きながら豊かな家庭生活が両立できる会社」と評価されることは、企業の将来にとって大きなメリットがあるでしょう。
日本経済を支えるためにも、過去の風習に捉われることなく、男性社員が育児休暇を当たり前に取れるような環境整備が必要です。
まとめ
現行は、月末日1日のみ、もしくは月末日まで育休を取った場合は、ボーナスも含めて該当月の社会保険料が免除されます。
改正後は、同じ月に2週間以上取得した場合、ボーナス月は1カ月を超えた場合が免除対象になるので、抜け道的に育休を使うケースはなくなります。
将来の日本経済を支える子どもを増やすためにも、男性が育休を取りやすい環境を整えておきましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
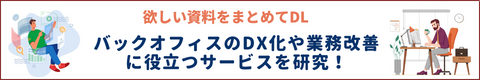
関連お役立ち資料
育休・産休の手続きの基礎とポイント
複雑な育休・産休に関する制度の概要を確認!男性の育休にも対応
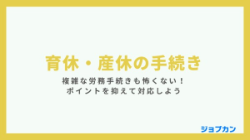
複雑な育休・産休に関する制度の概要をまとめた資料です。
基本的な社会保険手続きや、給付金・手当などもまとめられています。実務上、判断に迷いがちな適用ポイントや、男性の育休制度などもしっかり確認できます。
★ジョブカン労務HRでは、そんな複雑な産休手続きを以下の機能で効率化をサポート。
・スマホから出産報告&産休手続きの開始
・時系列ToDoで産休終了までの複雑なスケジュールを管理
【ポイント】
■対象:人事労務担当者の方など
■資料名:【人事労務お役立ち資料】育休・産休の手続きの基礎とポイント
■提供元:株式会社DONUTS
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -
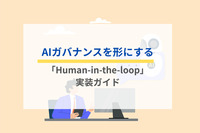
AIガバナンスを形にする「Human-in-the-loop」実装ガイド
ニュース -
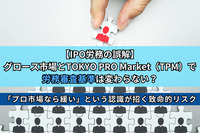
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
ニュース -

子育て座談会やバイアス研修で風土改革 モノタロウ、女性活躍最高位「プラチナえるぼし認定」取得
ニュース -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点
ニュース -
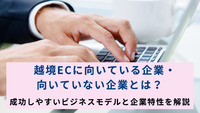
越境ECに向いている企業・向いていない企業とは? 成功しやすいビジネスモデルと企業特性を解説
ニュース -
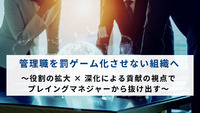
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理
ニュース