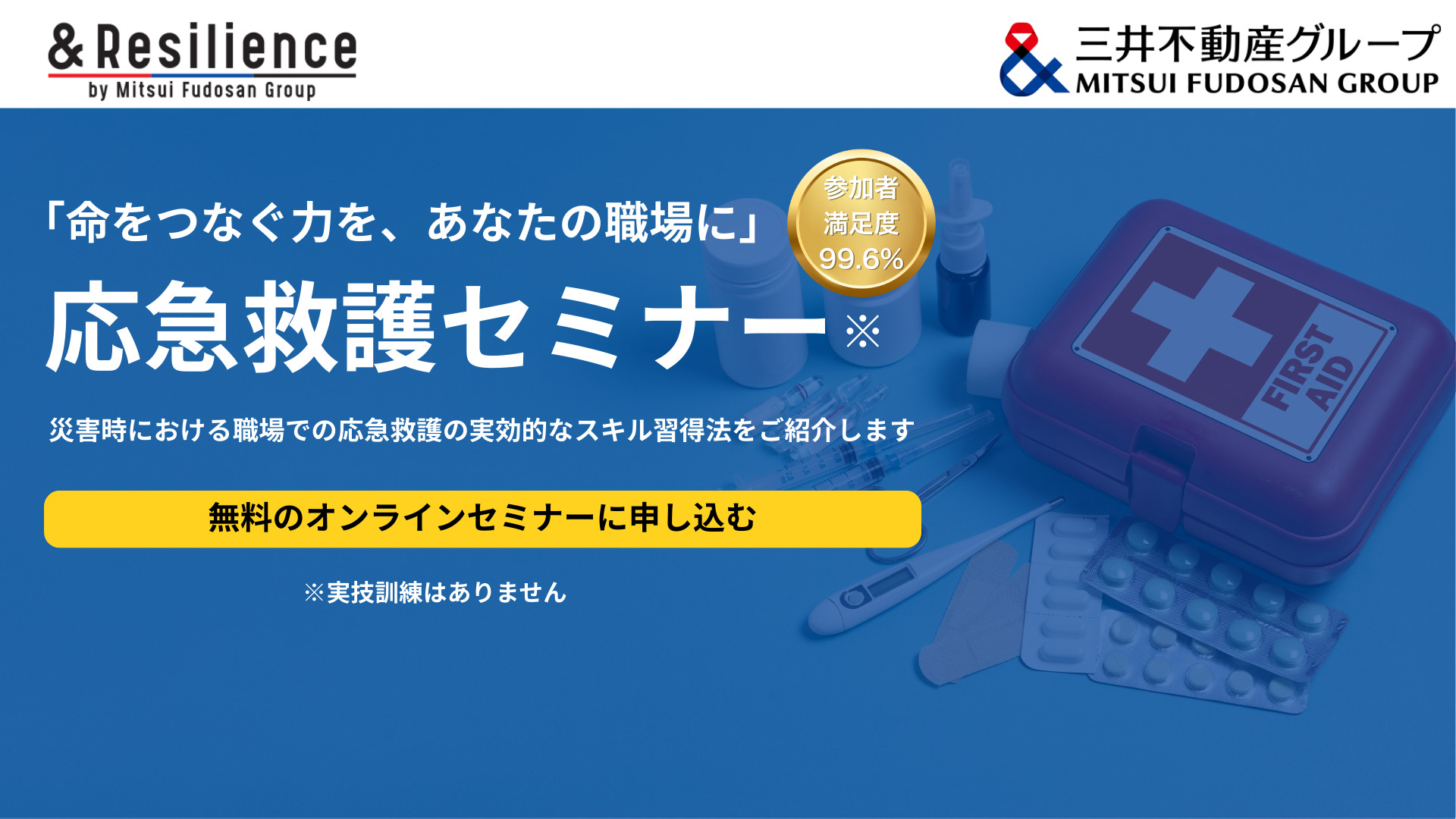公開日 /-create_datetime-/
在宅勤務中の禁煙要請、企業と社員の関わり方はこれでいいのか?

新型コロナウィルスの感染拡大により、リモートワークという働き方が広がる中で、一部の企業が在宅勤務中の禁煙を求めていることが報じられました。オフィスでの禁煙を前提として、在宅中の社員の健康管理も積極的に進める姿勢でしょう。
ところが、このニュースが予想外の議論の引き金になりました。社員を子ども扱いするのか、自宅での生活まで管理されるのか?この記事では、企業と社員との関わり方について改めて考えてみます。
在宅勤務中のタバコはダメ?
在宅勤務中の禁煙に関しては、社会派メディアの「PRESIDENT(プレジデント)」がとり上げており、野村ホールディングス、イオン、味の素、カルビーなど、日本を代表する企業が、社員に対して在宅勤務中の禁煙を求めていることについて検証しています。
オフィスでの喫煙は周囲に対する影響もあり、今では職場内での禁煙が一般的になっています。しかし自宅であれば、社員本人が注意すれば周囲に迷惑はかかりません。喫煙は個人の自由でもあります。このような企業の姿勢は、とらえ方によっては個人の権利への干渉にあたるのではないでしょうか。
リモートワークでの禁煙を促す意図は?
企業が禁煙を求める理由は、第一に社員の健康を考慮してのことと考えられます。さらにもう1つ、企業の健全な取り組みの一環として、対外的にアピールする狙いがあると思われます。従業員を大切にする企業は、優良企業として高く評価されるからです。
ただし喫煙や飲酒は、場合によっては健康を損なうリスクがあるとはいえ、基本的には個人の自由です。勤務中の飲酒は問題ですが、喫煙はコーヒーやお茶を飲む行動と同様に個人の嗜好です。それを遠隔的に企業が禁止するとは、まるで社員を子ども扱いしているようにも見えます。
企業は個人の権利に干渉できるのか
企業と従業員との契約に関しては、労働基準法や労働契約法などで詳細に規定されています。その中には服務規定という条件もあり、社員は職場内と一部職場外でも雇用主の指示に従うことが義務づけられています。
服務規定には「企業秩序維持義務」という項目があり、社員が企業の秩序を乱す行為を禁じるとともに、企業の指示に従うことを義務づけています。また、こうした規定がないとしても、日本社会は組織としてのまとまりを重視するため、雇用主である企業が社員の行動を律することは、ある程度常識的に受け入れられています。
では、在宅勤務中の社員が喫煙することは、企業にとっての秩序を乱す行為になるのでしょうか。さらに社員が喫煙しているかどうかを、企業はどのようにチェックするのでしょうか。もしも監視システムを導入するとなれば、プライベートを侵害することにもなるでしょう。
企業が意識を変えるのは今!
法的に検証すると、在宅勤務中の社員に禁煙を求めることは、服務規定に該当しないと思われます。つまり社員に従う義務はないということです。とはいえ、日本の企業風土では企業側と社員とは完全な主従関係にあるとみなされてきました。この場合も社員側が従うべきだと考えられるかもしれません。
しかし、このように企業が社員の自立を認めない、つまり子ども扱いをすることには、多くのデメリットがあるといわれています。その一つは、社員の自主性が育たず、海外企業と比較して組織としての能力が低下してしまうことです。自立できない社員がまとまったところで、企業の経営力が高まるとは考えられません。
もう一つは、本来チームをまとめて企業の経営力を高めるはずの管理職が、不必要な社員の管理まで責任を負わなければならず、業務管理に大きく影響することです。管理職の仕組みが変化しつつある今、企業の体質も変わるべき時に来ているのです。
変化する企業と社員との関わり方
これまでの伝統的な企業経営では、終身雇用と年功賃金が当たり前とされてきました。しかし現在企業側が、その伝統にとらわれない働き方へのシフトを進めています。それにもかかわらず、社員の側には自律的な働き方を認めないのであれば、日本企業での働き方改革には限界があるでしょう。
この因習を打破するためには、企業と社員との関係を改めて見直す必要があるでしょう。
企業側は社員の自主性を重視し、社員も積極的に自立することが、これからの日本では重要な課題になるはずです。社員の禁煙に関する今回の議論は、その課題を直視するきっかけになったかもしれません。
まとめ
従来の職場環境では、企業が社員の細かい行動まで管理することが一般的でしたが、働き方が多用化する中で、現状のままではさまざまな弊害が生じる可能性が出てきました。今こそ企業と社員との関わり方を、もう一度見直す必要があるのです。
リモートワークの普及によって、今後は一段と柔軟な労働環境の構築が求められます。在宅勤務まで規則で縛るのではなく、社員が自主的に自身の能力を発揮できるようにすることが、現代ビジネスにとって必要なことではないのでしょうか。
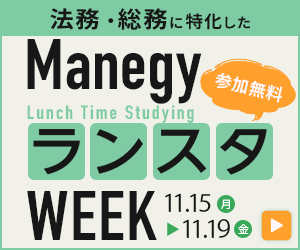
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース