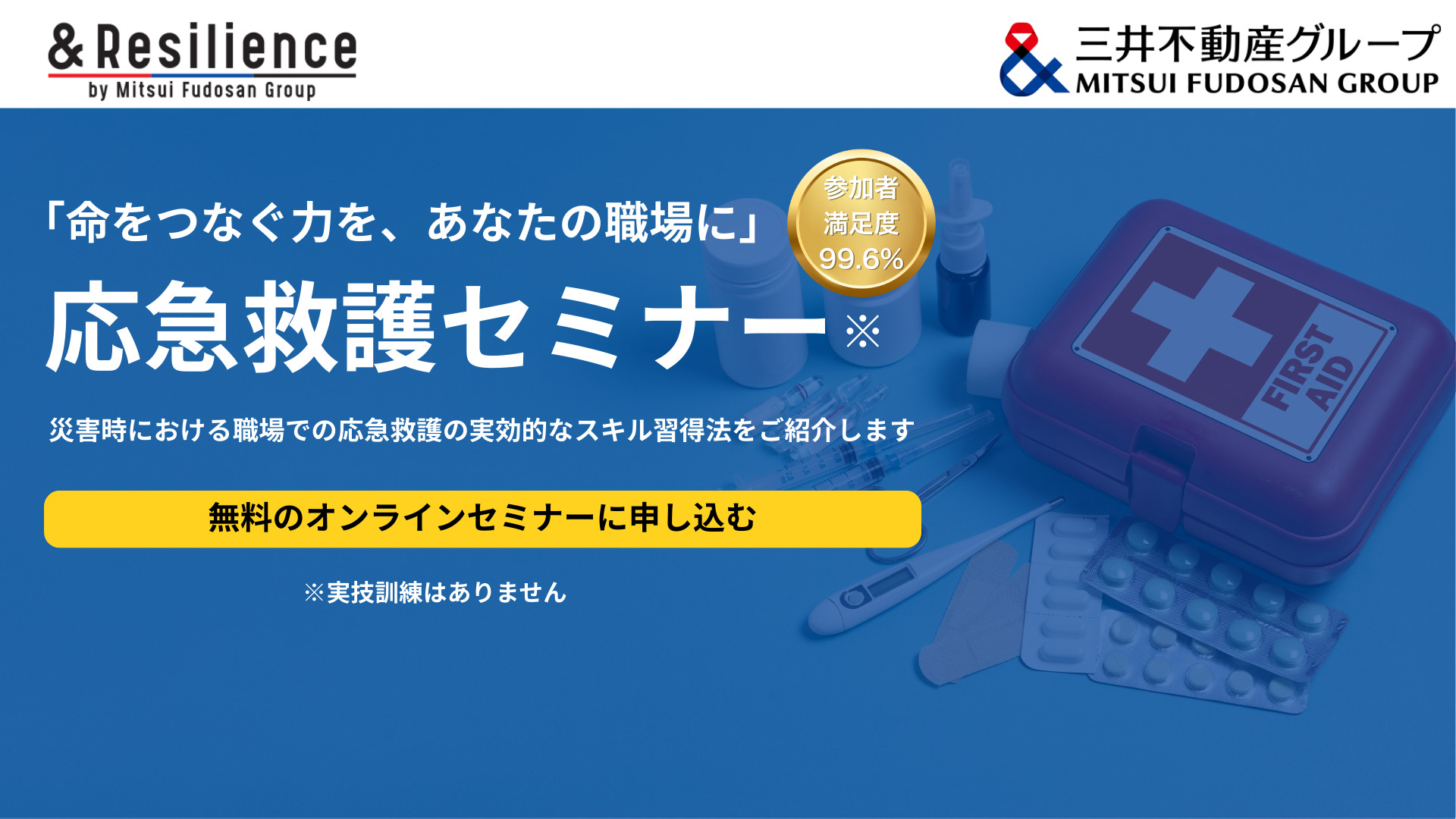公開日 /-create_datetime-/
給与明細を見て思わずため息が出そうになる天引き項目
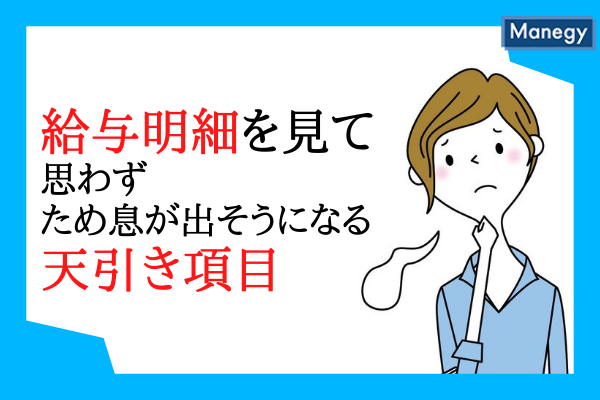
ビジネスパーソンにとっての一番の楽しみは、やはり給料日ではないでしょうか。しかし、給与明細を見るたびにため息をつきたくなるのが、保険料や税金など引かれる項目の多さと、手取り額の低さです。何がいくら引かれているのか給与明細を見直してみましょう。
目次【本記事の内容】
所得税と住民税
給与から引かれるのは、主に税金と社会保険料です。税金には、国に納める所得税と、住んでいる自治体に納める住民税があります。
所得税は、会社が“源泉徴収”という名目で給与から天引きし、本人に代わって会社が納めます。税率は5~45%と収入額によって異なります。1年間の正確な所得額は、12月の給与額決定まで未確定のため、年末調整で税額の過不足を清算し、払いすぎていた場合は還付されます。
住民税の税率は一律10%で、その内訳は都道府県に4%、市区町村に6%となっています。政令指定都市の場合は、都道府県に2%、市区町村に8%の割合となります。前年の所得額に応じ納付額が決まり、6月から翌年5月までの給与から天引きし納めるという仕組みです。
4種類の社会保険料
給与明細には「社会保険料合計額」と記されていますが、社会保険料には健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険料があり、40歳以上になれば介護保険料も支払わなければなりません。この4種類の合計が給与から天引きされる社会保険料合計額です。
健康保険は、会社が独自運営する健康保険組合、全国健康保険協会が運営する協会けんぽ、公務員が加入する共済けんぽなどがあり、加入する団体によって保険料は異なります。
また、企業に勤めている人は個人事業主などが加入する国民年金の代わりに、厚生年金に加入し保険料を支払うことになります。
納税は国民の義務であり、社会保険料は病気や失業した場合の備えとして必要です。一つひとつの支払額は少額でも、合計した負担額は決して少なくないとわかります。
共済費や労働組合費も
給与から天引きされるのは、税金と社会保険料だけではありません。それぞれの会社によって異なりますが、財形貯蓄などの貯蓄制度や団体生命保険、共済費、労働組合費などが天引きされる場合もあります。
平均給与額433万1,000円
多少、天引きされる項目が多くても手にする金額が満足できれば、給与明細を見て落胆することもないでしょう。しかし、残念ながらここ30年間、平均給与はほとんど上がっていないのが現実です。
国税庁が公表している令和2年の「民間給与実態統計調査結果」によると、年間を通して民間企業で働いた会社員やパート従業員数は5,245万人で、平均給与額は433万1,000円です。
この平均給与額、実は1990年代後半からほぼ上昇していないといいます。この30年間で所得が大幅に上昇した国もありますが、日本はほぼ横ばいで推移しています。これでは、ただでさえ厳しいビジネスパーソンの懐事情がますます厳しくなることも予想されます。
まとめ
改めて給与明細を見直してみると、総支給額から税金や社会保険料などが天引きされ、その額が大きいことに気づかされます。
手取り額のみならず、天引きされている税金や保険料などの内訳を把握しておくことも、ビジネスパーソンには大切なことです。

バックオフィスにおすすめのイベント|参加者アンケートでギフト券プレゼント!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース