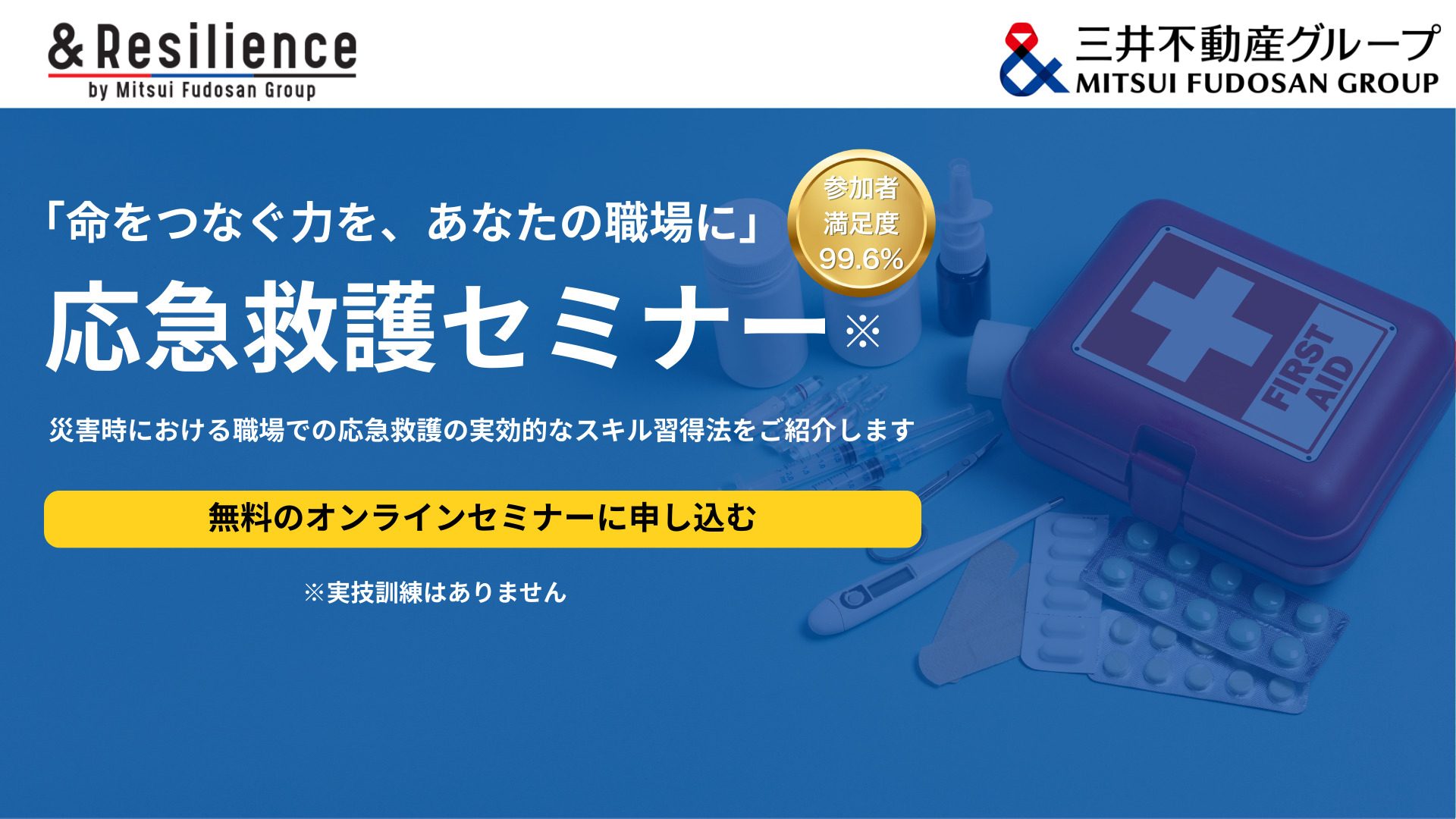公開日 /-create_datetime-/
新年度に向けた引っ越しシーズン、オフィス移転の際の退去時の原状回復義務とは?トラブル防止のポイント

事務所の移転や閉鎖に伴い、退去時に生じる原状回復義務。適正価格に対して原状回復費を3〜6割高く請求されるケースもみられるなど、退去に伴うトラブルが少なくありません。
今回は事務所における原状回復義務の考え方や適用される範囲、トラブル防止のためのポイントについて解説します。
目次【本記事の内容】
原状回復義務とは?
原状回復義務とは、事務所の賃貸借契約が終了した際に契約時の状態に戻すことを指します。実は、賃貸契約における原状回復義務については長らく法律で定められていませんでした。2020年4月施行の改正民法において、原状回復義務が明文化されたのです。
●【改正民法621条】賃借人の原状回復義務
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
●事務所退去時における原状回復義務の範囲
先に挙げた条文では、原状回復義務について住宅・事務所の区別は設けていません。しかし、事務所と居住用住宅では原状回復義務の範囲に大きな違いがある点に注意が必要です。
|
貸主の負担 |
賃借人の負担 |
|
|
居住用住宅 |
経年劣化 ・日焼けによる壁の変色 ・家電背面部の壁の黒ずみ ・画鋲の跡 ・家具設定による床のへこみ など 通常使用による損耗 ・照明など設備の交換 ・自然災害に起因する破損 など |
通常使用を超える損傷 ・カビやシミ、油汚れ ・タバコのヤニや焦げ跡 ・壁の貼り替えが必要な釘の跡 ・床や壁の穴、目立つキズ |
|
事務所 |
経年劣化 通常使用による損耗 ※契約書に特約がある場合を除く |
左記以外の全ての事項 ・カーペットの貼り替え ・壁の塗装、壁紙の交換 ・パーテーションの撤去 ・窓の清掃 ・配線、照明の撤去、回復 など |
端的に言うと、事務所退去時には入居前の状態に完全に戻す必要があります。原状回復に要する費用に関しても、100%賃借人の負担となるのが一般的です。経年劣化や通常使用による損耗も含めて、契約書の特約により賃借人が負担するケースが大半と考えていいでしょう。
事務所と居住用住宅で原状回復義務の範囲に大きな差がみられる主な理由として、次の二点が挙げられます。
・損耗の程度を予測しにくいため
事業用途の賃貸物件では、将来にわたって損耗する程度や範囲が予測しにくい面があります。入居する企業や店舗ごとに使い方や出入りする人数も大きく異なることから、居住用住宅のような「通常使用」を定義するのが困難とされているのです。
・貸主と賃借人は対等に位置づけられるため
居住用住宅においては、貸主と賃借人では賃借人のほうが保護されるべき立場にあるとみなされるのが一般的です。しかし事業用途の賃貸借契約の場合、貸主と賃借人は双方が事業者であり、立場は対等とされます。よって、損耗や汚損に関しては全て賃借人の責任で回復・除去することが義務づけられているのです。
トラブル防止のための確認ポイント
事務所退去時の原状回復義務に関しては、入居時の契約内容に依拠します。退去時のトラブルを防ぐには、次のポイントを押さえておくことが非常に重要です。
●賃貸契約書の確認
入居時に貸主と交わした賃貸契約書を必ず確認し、原状回復の範囲がどのように定められているかを明確にしましょう。とくに特約の項目を注意深く確認しておくことが大切です。契約書に挙げられている項目に関しては、基本的に原状回復義務を負うことになります。
マンションのように事務所としても住居としても利用される物件の場合、通常の事務所とは原状回復義務の範囲が異なるケースもあり得ます。いずれにしても、思い込みで判断することのないよう賃貸契約書を確認した上で原状回復義務の範囲を把握することが重要です。
●原状回復工事の見積書の確認
原状回復工事に向けて施工業者と打ち合わせをし、現地調査を経て見積作成を依頼します。見積書は必ず仔細に確認し、過大な費用を見積もっていないかを慎重に判断しましょう。見積が適正価格かどうかは、一般的な原状回復工事の単価を目安に判断することをおすすめします。
|
面積 |
坪単価 |
|
100坪未満(小~中規模オフィス) |
2~5万円程度 |
|
100坪以上(大規模オフィス) |
5~10万円程度 |
上表はあくまでも目安であり、工事内容によって単価は変動する可能性があります。ただし、一般的な施工単価から大きく逸脱しているようなら見積額が過大である可能性を疑う必要があるでしょう。
●原状回復工事にかかる期間の確認
退去日までに原状回復工事を完了させ、物件を明け渡す必要があります。引っ越し作業が完了するまで原状回復工事を始めることができないため、引っ越し業者を確実に押さえることも退去時のトラブルを防止するための重要なポイントといえます。
とくに事務所の移転が集中する3月や9〜10月前後は、引っ越し業者を押さえるのが難しいことも少なくありません。逆に6〜8月は引っ越し業者の閑散期ですので、時期を動かせるようなら閑散期に合わせて引っ越しを設定するとよいでしょう。
まとめ
事務所退去時の原状回復においては、居住用住宅とは異なり100%賃借人が負担するのが一般的です。契約内容を事前によく確認しておかないと、退去時にトラブルが生じる恐れがあります。本記事を参考に原状回復義務への理解を深め、退去時のトラブル防止に役立ててください。
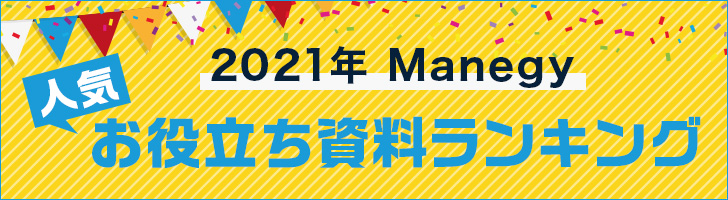
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
ニュース -
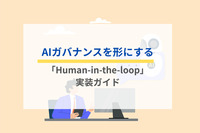
AIガバナンスを形にする「Human-in-the-loop」実装ガイド
ニュース -
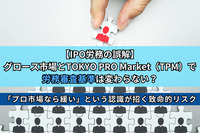
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
ニュース -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

子育て座談会やバイアス研修で風土改革 モノタロウ、女性活躍最高位「プラチナえるぼし認定」取得
ニュース -
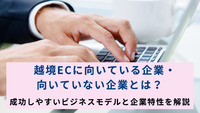
越境ECに向いている企業・向いていない企業とは? 成功しやすいビジネスモデルと企業特性を解説
ニュース -
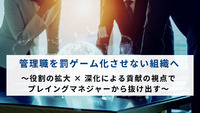
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~
ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース