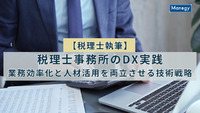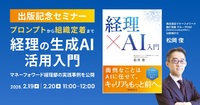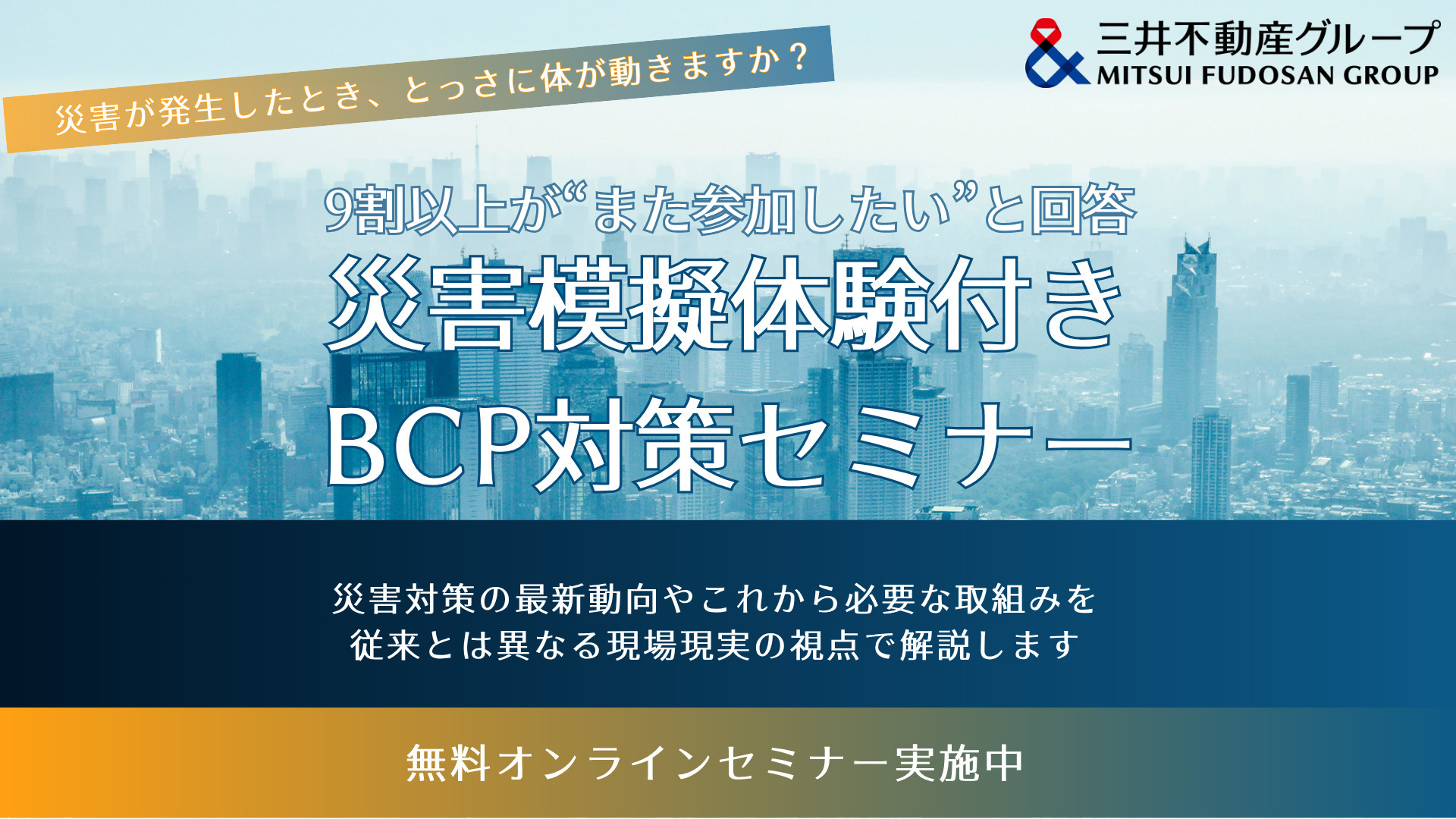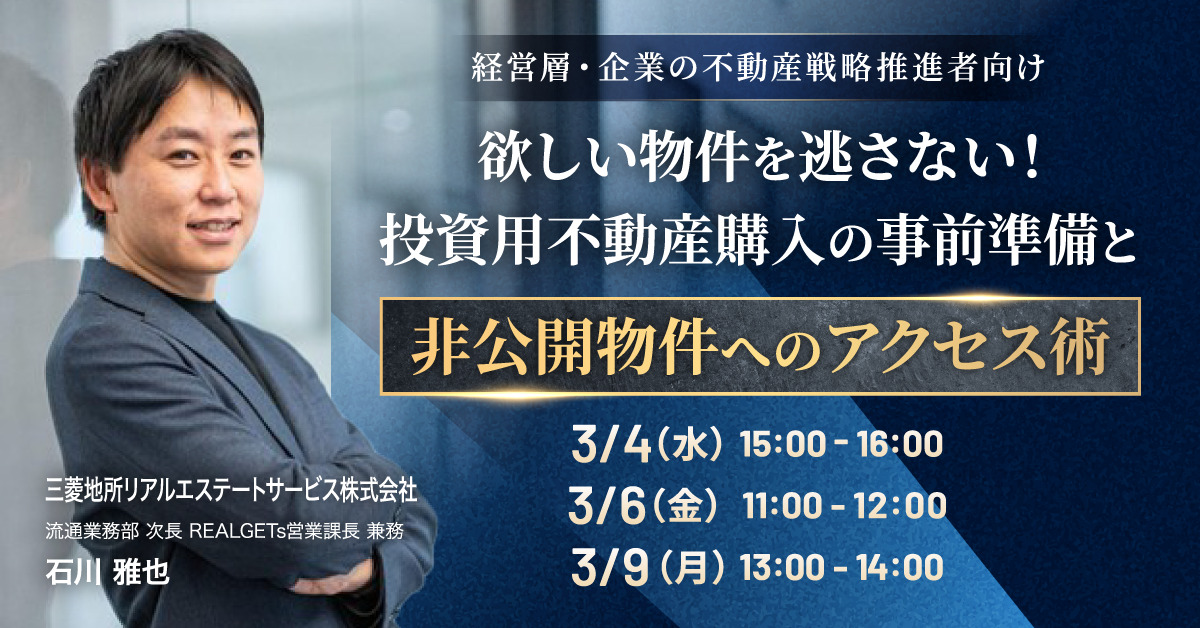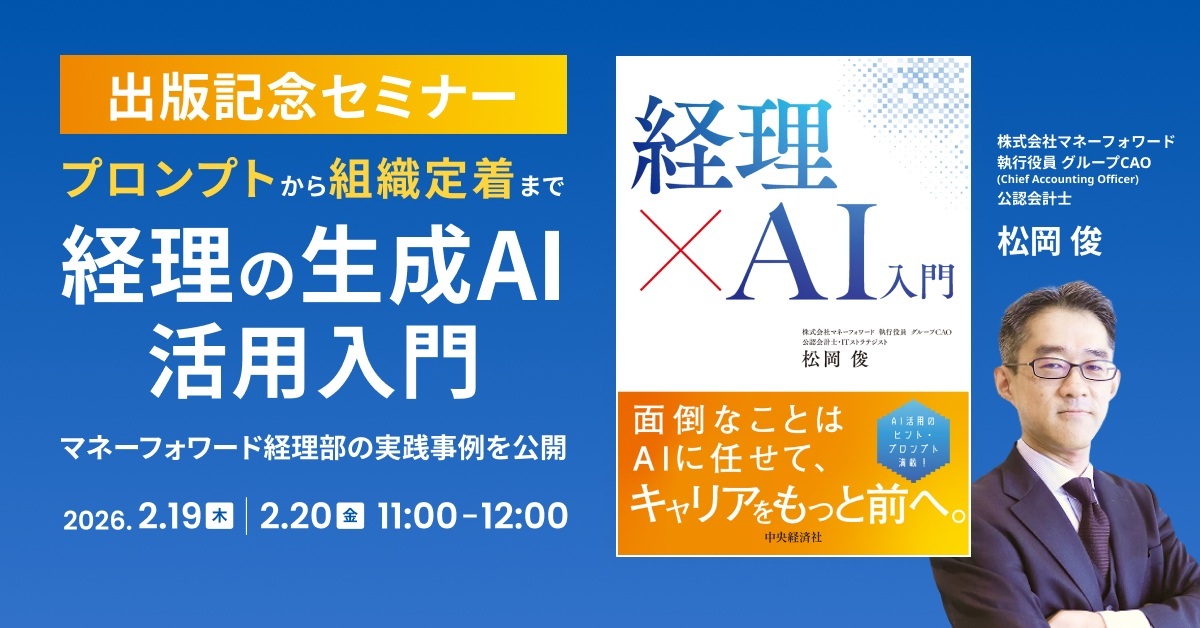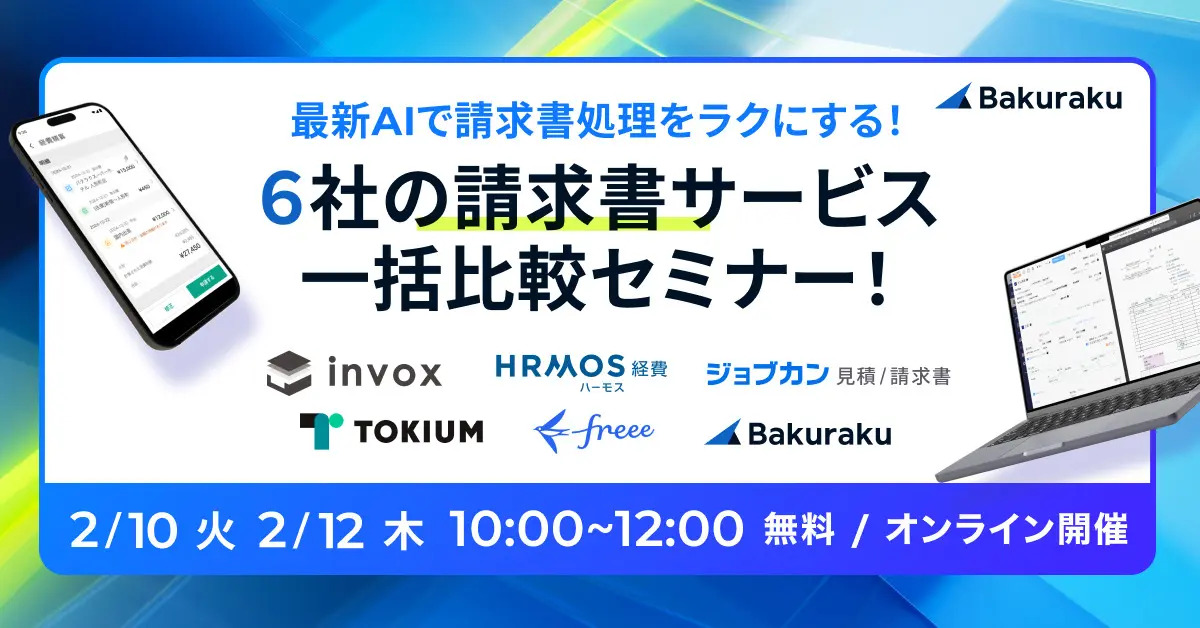公開日 /-create_datetime-/
有給休暇の買取が例外的に認められるケースとは
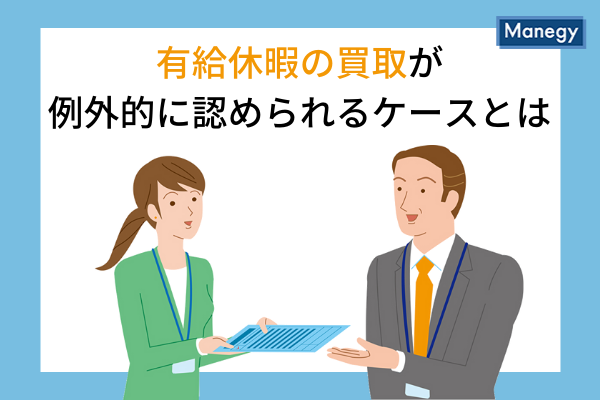
有給休暇は企業が労働者に対して与える休暇制度で、労働基準法第39条によって定められています。要件を満たした労働者へ有給休暇を与えることは義務とされているため、企業側の一方的な都合で労働者の保有している有給休暇を買い取ることは原則禁止とされています。
ただし、法律で定めている以上の有給休暇がある場合など、一部例外的に有給休暇の買取が認められるケースもあります。ここでは、有給休暇の買取が禁止されている理由とあわせて、どのようなケースに該当すれば買取が認められるのかについて解説していきます。
有給休暇の本質と買取可能なケース
有給休暇は、正式には「年次有給休暇」と呼びます。労働者の権利を保障するために労働基準法によって定められており、要件を満たしたすべての労働者が取得の権利を有します。
労働者が有給休暇を消化できなかった場合でも、企業がそれを買い取る行為は原則禁止されていますが、一部例外的なケースとして買取が認められることもあります。
1.労働者の権利に基づいて与えられるのが年次有給休暇
年次有給休暇は、正社員だけでなくパートやアルバイトでも要件を満たしていれば取得できる休暇制度です。
年次有給休暇を取得できる条件は、以下の2点です。この要件を満たせば、労働基準法で定められた付与日数を取得できます。
・半年以上の継続雇用
・労働日全体の80%以上出勤している
|
継続雇用期間 |
6カ月 |
1年半 |
2年半 |
3年半 |
4年半 |
5年半 |
6年半以上 |
|
付与される有給休暇日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
正社員など通常の労働者なら継続雇用6カ月で年間10日の有給休暇を取得でき、継続雇用が6年半以上になると年間20日の有給休暇を取得できます。ただしパートタイマーやアルバイトなど、所定労働時間が週4日以下かつ週30時間未満に該当する労働者は、有給休暇の取得条件が上記とは異なりますので注意が必要です。
また、平成31年の労働基準法改正により、定められた有給休暇が10日以上ある労働者に対しては毎年必ず5日間の有給休暇を取得させなければならない決まりになっています。
2.消化できなかった有給休暇の買取は原則として禁止
有給休暇を与えられていても、実際にすべての日数を消化できない労働者の方が大半です。休暇の取得は海外では非常にポピュラーですが、日本においては上司や同僚に対して後ろめたさを感じてしまう風潮も根強く、なかなか気軽に取得できないのが実情です。
消化しきれなかった有給休暇があった場合、もしくは与えられた有給休暇を労働者側ですべて消化するつもりがない場合などは、いっそのこと企業側で有給休暇を買い取ってそれに見合った賃金を労働者に還元した方が双方にとってメリットも大きいようにも感じてしまいます。
しかし、そもそも有給休暇は労働者の権利として与えなければならないと労働基準法で定められている以上、それを買い取るような行為は違法となってしまうのです。
3.例外的に買取が認められるケース
ただし、以下の内容に該当する場合、有給休暇の買取が例外的に認められています。
・法定日数を上回っている有給休暇
・労働者の退職時点で消化されていない有給休暇
・時効消滅した有給休暇
原則禁止とされている有給休暇の買取ですが、法律上決められている日数よりも多く休暇を与えている場合なら、その分を企業側で買い取ることが可能です。また、労働者が退職する時点で有給休暇が残っている場合も買取できます。
有給休暇は取得後2年が経過してしまうと時効消滅(権利が消滅)してしまうため、この分についても企業で買い取ることができます。
いずれも、労働者の権利として法律で定義されている有給休暇の趣旨に違反するものではないため、適法とされているのです。
有給休暇はどのくらいの価格で買取できる?
では、実際に適法とされる理由で有給休暇の買取を行う場合、どのように価格を決めるのでしょうか。
有給休暇の買取価格は、労働者が有給休暇を利用した場合の賃金と同等であるのが一般的ですが、有給休暇の賃金を就業規則でどのように決めているのかにもよります。
1. 実際に有給休暇を取得する際の賃金で買取
有給休暇の賃金の決め方には、具体的に以下の三つが該当します。
・所定労働時間と同じ賃金
・過去3カ月の平均賃金
・標準報酬月額の30分の1
これらのうち、いずれかが就業規則として定められていればそれを基にして買取価格が決まります。
2. 有給休暇の買取価格は法律上の決まりがない
有給休暇は労働者に与えるものであり、そもそも買い取る前提で付与するものではありません。法律で定められた価格はないため、事前に労働者と個別に合意があれば、就業規則とは関係なく上記以外の金額で買い取ることも可能です。
有給休暇の買取に伴う注意点
1.有給休暇買取は給与所得か退職所得の扱い
有給休暇の買取は、対象の労働者が在職中か退職予定かによって税務上の扱いが異なります。労働者が在職中なら給与所得となりますが、退職に伴う買取なら退職所得の扱いになりますので注意が必要です。
2.有給休暇の買取はあくまでも任意
有給休暇の買取はあくまでも任意ですので、必ず買取しなければならないという決まりはありません。もちろん、労働者から買取の申請があったとしても、それを拒否することもまた可能です。
しかし、労働者側との無用なトラブルを避けるためにも、あらかじめ税理士や社労士などを交え、有給休暇の買取について話し合いの場を設けておくことも大切です。
3.解雇や離職後に買取を請求することはできない
労働者側の注意点として、解雇や離職による有給休暇の買取請求のタイミングがあります。
解雇にしても自己都合退職にしても、労働契約が解消されてしまうとその時点で有給休暇も消滅してしまうため、買取の請求をするなら労働契約のあるうちに行う必要があります。
ただし、即時解雇や即日解雇となってしまった場合は、当然ながら有給休暇も即時または即日で消滅しますので、その場合は有給休暇の買取を請求することはほぼ不可能です。
まとめ
労働者を守るために企業が与える義務を負うのが年次有給休暇という制度です。労働者に休む権利を与えるための制度なので、それを買い取ることは原則として認められていません。
本来、年次有給休暇とは労働者が心身の休養のために取得することが目的のため、それを買い取ってしまっては「労働者を休ませる」という趣旨に反してしまいます。それでは有給休暇を付与する意味すらなくなってしまうため、買取は原則禁止なのです。
ただし「法定より多い日数分」「退職時の未消化分」「時効分」などに限り、買取が可能です。
いずれにしても、企業が有給休暇を買い取るかどうかは強制ではありません。買取については労働者の要請に企業が応じてはじめて成り立つものですので、その点については十分に理解しておく必要があります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
ニュース -
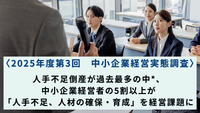
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
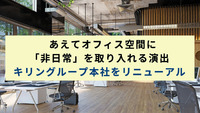
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル
ニュース -
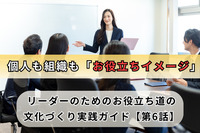
個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】
ニュース -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

「給与レンジ」を適切に設計。採用力や定着率を高める効果も
ニュース -
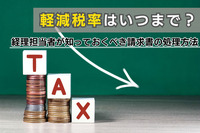
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

従業員の副業における注意点|企業が知っておきたいリスクと対応策
ニュース -

ファイル共有規程ひな形|禁止事項と運用術
ニュース