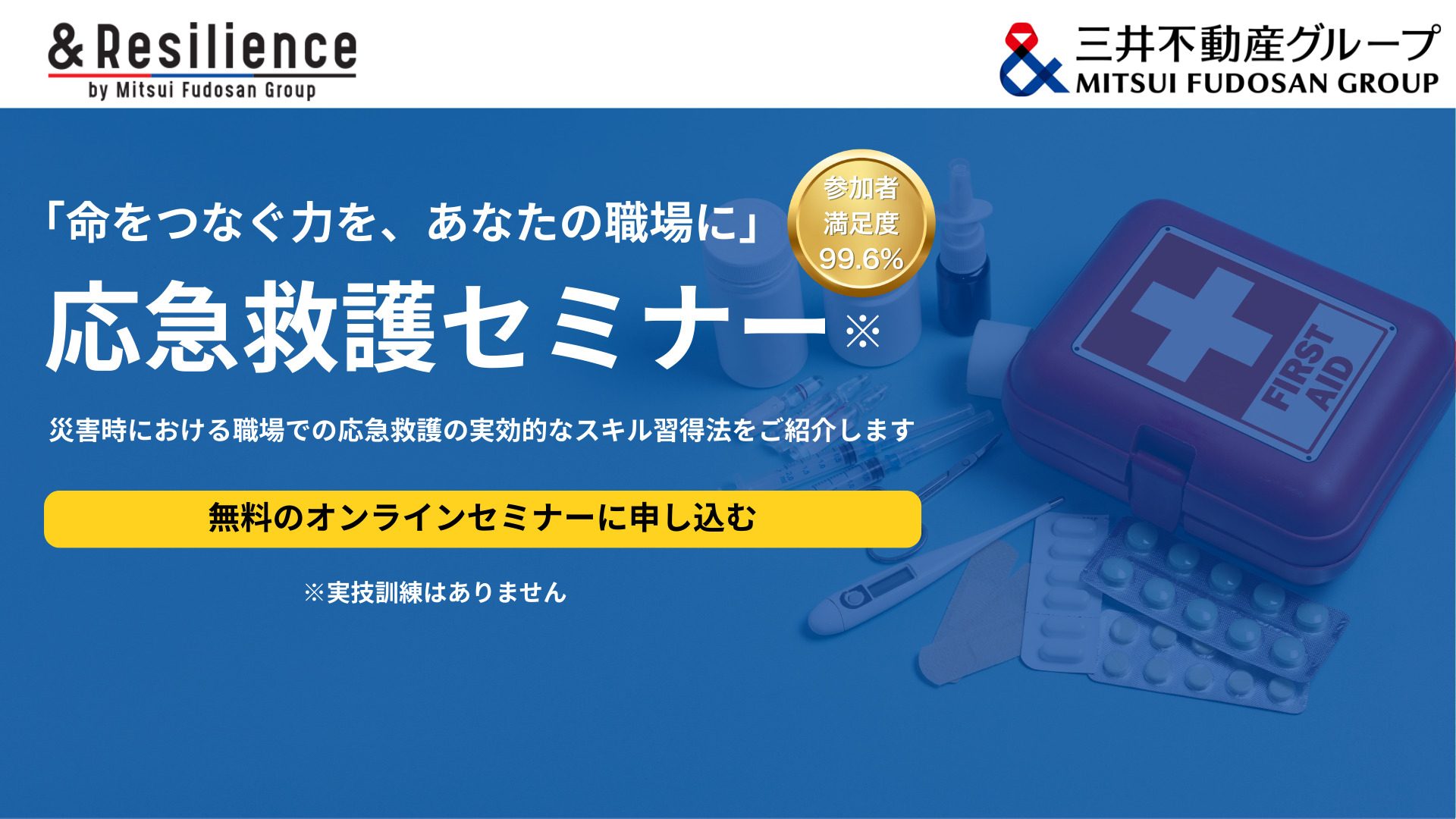公開日 /-create_datetime-/
知っておいて損はない!?会計知識をビジネスに活かすことの意味とは
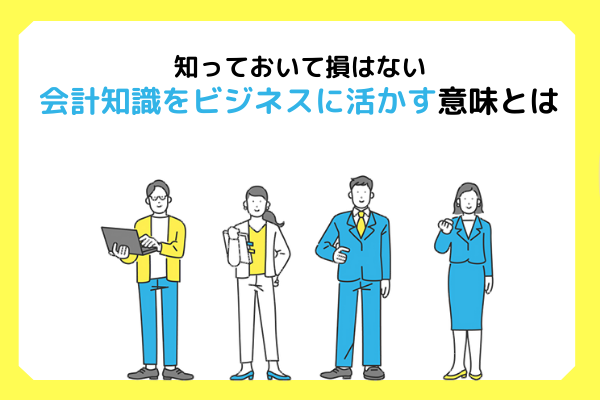
会計知識といえば、一昔前なら会計部門の職業に就く人だけが知っておくべき知識でしたが、現在ではあらゆるビジネスパーソンにとって必要不可欠な存在となりつつあります。
今回は、会計知識をビジネスに活かすことの意味について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
なぜビジネスに会計知識が必要なのか?
「会計」と聞くと、どうしても難解な会計用語ばかりを連想してしまうため、そもそも会計知識を習得することにすら抵抗感を抱いてしまう人も少なくないでしょう。
しかし会計知識を得ることで、これまでと違った視点や思考を身に付けることもできるのです。会計知識のすべてを習得しようとするのは大変ですが、会計用語の意味を知っておくだけでもビジネスに有益な結果をもたらしてくれます。
●事業の継続に会計は必要不可欠
企業の事業規模が大きければ大きいほど、そこで働く社員は末端へいくほど自らの立ち位置を見失いがちです。
「この仕事が会社にどのくらいプラスに働いているのか?」
「そもそも自分のしているこの仕事にどんな意味や役割があるのか?」
――など、実際に自らの仕事に対するやる気(モチベーションアップ)を求めて、その答えを探している人も多いでしょう。
そこで役に立つのが会計知識です。会計知識が必要なのは、何も社長や起業家ばかりではありません。企業の末端で働く従業員であっても、会計知識を持っておくことは大切です。
なぜなら、会計知識を習得して会社に関わるお金の流れがわかると、会社側の視点が身に付き、結果的にビジネスの流れを知ることができるからです。それによって、今現在自分が会社に対してどの程度貢献できているかを把握できるようにもなります。
会社規模の大小を問わず、事業を行っていく上で会計業務は避けて通ることはできません。そして会計は、その会社の行う事業の流れをすべて反映していると言っても過言ではないほどです。
いわば会計とは、非常にざっくりとした言葉で表すとすれば「お金の動きや事業の流れがわかるツール」であり、そこで働く人たちにとっては「自分の立ち位置を知る上での指標」ともなるものなのです。
●会計とは信用を得るための報告書のようなもの
会社として生き残っていくために必要なこととは何でしょうか? それは「信用を得ること」です。会社を取り巻くさまざま人たちからの信用がなければ、事業を円滑に進めていくことは困難なのです。
たとえば「掛け取引」と呼ばれる取引方法があります。「毎月掛け払いで取引を行い、来月末にまとめて支払います」といった取引方法で、ビジネスでは当たり前に行われる取引方法です。これは取引先企業との信用があってこそ成り立つ取引であり、そもそも信用がなければ掛け取引に応じてもらうことすらできません。
もちろん銀行などに対しても同様です。運転資金や設備投資のための融資を受けたいと思っても、信用がなければ融資を受けることはまずできません。
では取引先企業や銀行などは何を基準に信用度を計っているのかというと、それはずばり経営状況です。そして経営状況を知る上で参考にするものが会計資料なのです。つまり会計業務は、社外へ向けた報告書作成のような役割も持っているのです。
●取引に際して健全なものか否かの判断材料にもなる
これは逆の立場でも同じように活用できます。つまり、これから取引を始めようとしている相手の企業基盤は健全か、取引自体にリスクはないのかどうか、それを計る上での参考として会計知識を役立てることができます。
■ビジネスの鉄則!部署を問わず活かせる会計知識
ここまでの説明で、会計知識によって会社のお金の流れを把握できるため、会社としての視点に立って分析できること、そして客観的な視点から信用性や健全度を計ることもできることなどを、漠然とでも理解いただけたでしょう。
会計知識はさまざまな部門で活用することができ、部署を問わず会計知識の習得を推奨している企業も実際に存在します。
●営業から総務まで!さまざまな部門で活かせる会計知識
たとえば営業部門は、取引先と直接やり取りをする部門であり、いわば会社の顔ともなるべき部門です。会社の利益を追求することはもちろん、利益を損なわないための知識も有しておく必要があります。取引先の経営状況などを常に把握しておくことも必要になるため、会計知識は必須です。
また人事部門や総務部門なら、人件費はもちろん社会保険料など福利厚生費にまつわる計算に、経理部門なら各種資金繰りなどに会計知識が活かせます。
その他、仕入管理や原価管理、広告宣伝、販売、運搬等の部門においても、予算作成には会計知識が大いに役立ちます。
●経営者なら会計のプロに一任するのも選択肢
会計知識が必要だとはいえ、経営者自らが会計業務に時間を割かれてしまっては経営に支障をきたしてしまう恐れもあります。そうならないためにも、会計業務をプロへ依頼して一任してしまうのも選択肢の一つです。
しかし経営者として、会計に対してまったくの無知でいいのかというと、そういうわけにもいきません。必要最低限の会計知識を持っておかないと、事業を俯瞰して分析することもできませんし、状況に応じて正しく判断しながら会社を良い方向へ導くことも困難です。企業のトップである以上、部門ごとに必要な会計知識は一通り有しておくのが理想的でしょう。
まとめ
会社とは、極論をいえば商品やサービスを提供して収益を上げるための組織です。そしてそのためにこそ、会計知識が必要になってきます。
会計部門の担当者だけが持っておけばいいのではなく、あらゆる部門のビジネスパーソンも持っておくべき知識――それが会計知識なのです。
総勘定元帳や仕訳帳まで理解する必要はありませんが、せめて財務諸表をはじめとした内部資料から、部門ごとに沿った分析ができるだけの知識は身に付けておきたいところです。
だからといっていきなりすべてを吸収しようとしても一朝一夕にはいきません。まずは、関連する会計用語を少しずつ理解するところからスタートしてみてはいかがでしょうか。
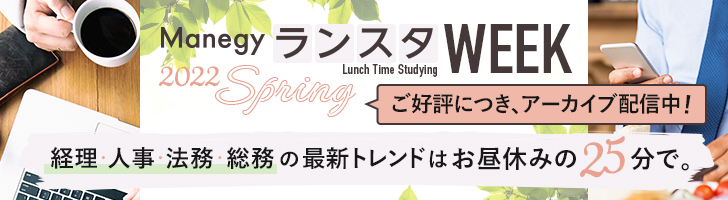
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -
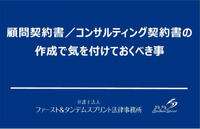
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

子育て座談会やバイアス研修で風土改革 モノタロウ、女性活躍最高位「プラチナえるぼし認定」取得
ニュース -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
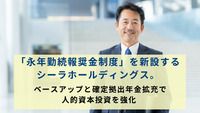
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
ニュース -
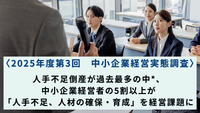
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
ニュース -
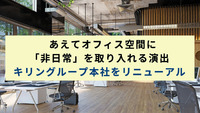
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル
ニュース