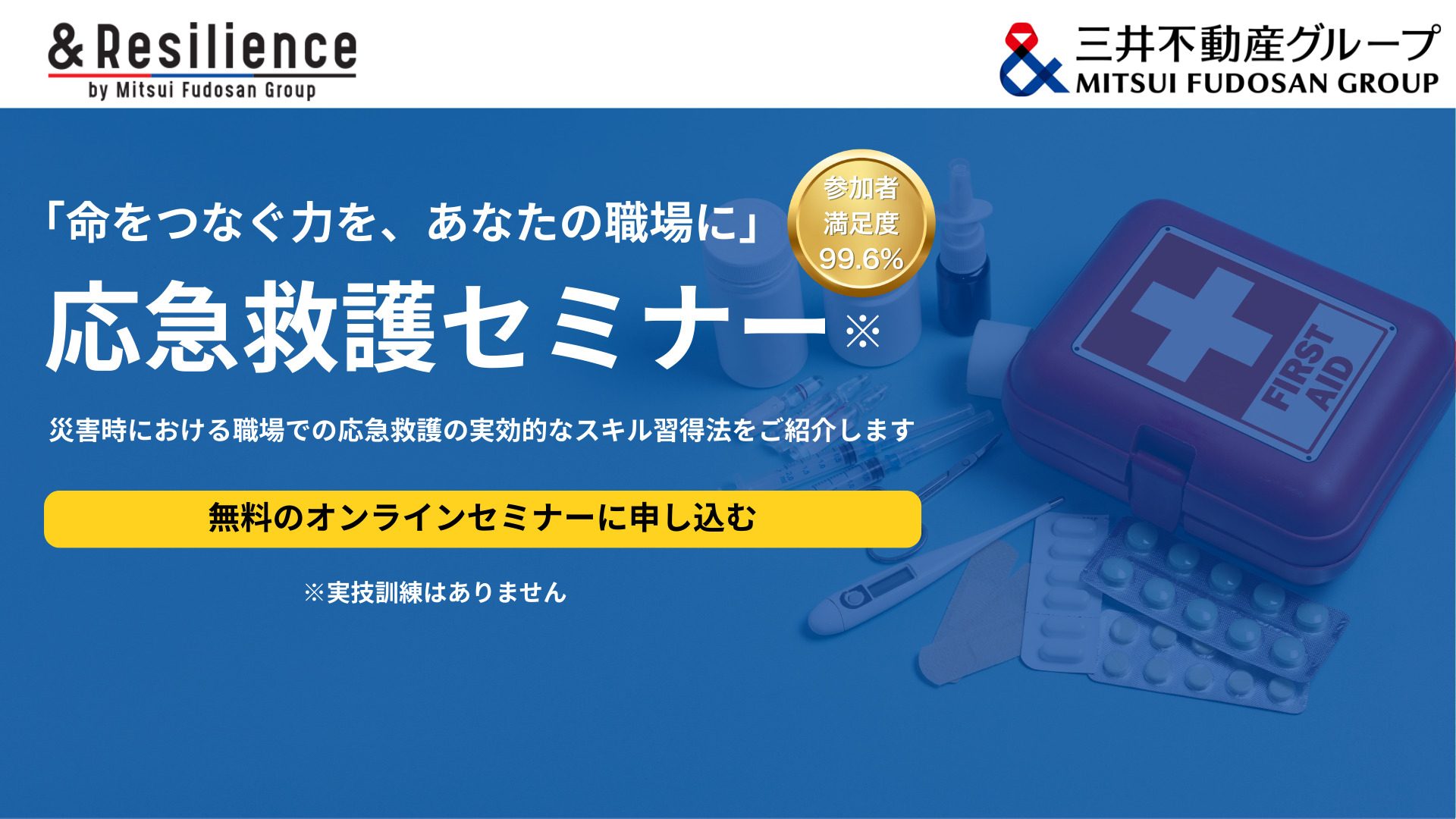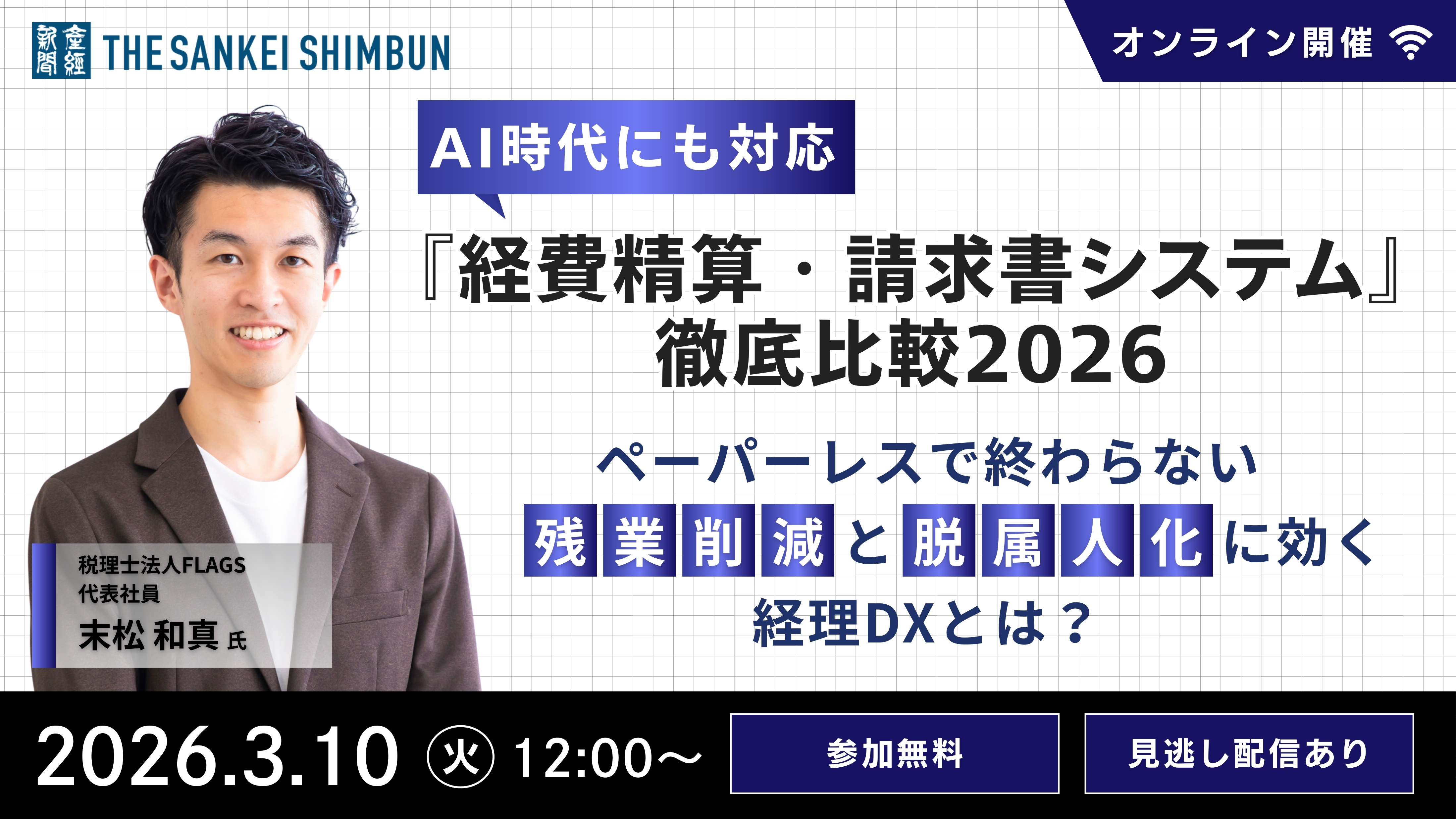公開日 /-create_datetime-/
20代~50代の男女のうち36.4%が「資産形成の余裕がない」

食料品や公共料金の値上げラッシュも、急激な円安も止まる気配がみられず、頼みの賃上げも値上げ幅に追いつかず、庶民の生活を容赦なく圧迫している。
給料が上がらないのであれば、支出をできるだけ抑える工夫が必要だが、それも限界がある。預貯金に余裕があれば、投資で資産を増やすこともできるが、それが可能なゆとりのある人は、果たしてどれだけいるのだろうか。
「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapが、20代から50代の男女1,000名を対象に実施した「資産形成についての意識調査」によると、「資産形成をする貯蓄の余裕がない」と答えた人は36.4%であった。
年収別に資産形成をしている割合をみていくと、1,000万円以上は82.3%だが、300万円未満では50.5%にとどまっている。しかもこの資産形成には、株式や投資信託、不動産だけでなく、預貯金や生命保険、勤務先の積み立て・仮想通貨も含めての割合だ。
純粋な意味での投資に絞れば、投資で資産形成をする割合はさらに低くなる。年収300万円未満の世帯の86.9%が「資産形成に危機感がある」と回答しているが、投資に回したくても回す余裕がないというのが実態だ。
通常国会が閉幕したことを受けて開いた参院選前の記者会見では、岸田首相は「物価・賃金・生活総合対策本部」を立ち上げ、首相本人が先頭に立って迅速な対策に取り組み、「さまざまな社会課題を成長のエンジンに変えて持続可能で力強い成長を実現する」ことを表明した。
では、どのようにして「持続可能で力強い成長を実現する」のかといえば、企業が溜め込んだ320兆円ともいわれる内部留保や、個人が保有する1,100兆円近くの預貯金を分配・投資に回すという「資産所得倍増プラン」である。
当初掲げていた“所得倍増プラン”に、いつの間にか“資産”が組み込まれたようだが、本年度末までに総合的な「資産所得倍増プラン」を策定するようだ。
しかし、急激に進む円安や、長期化の様相を呈しているロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響など、日本経済にマイナス影響を及ぼす要素ばかりが目につき、しかも、これまでの値上げラッシュは序の口で、今秋以降に本格化するという観測もある。
そんなときに「貯蓄から投資へ」と呼びかけられても、果たして投資による資産運用へと動き出すのだろうか。しかも、投資にはリターンもあればリスクもある。投資を検討する前に、家計の支出を見直すなどの地道な節約を心がける方が確実かもしれない。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

ダイバーシティ推進の現在地―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―
ニュース -
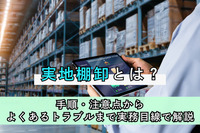
実地棚卸とは?手順・注意点からよくあるトラブルまで実務目線で解説
ニュース -

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~
ニュース -

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~
ニュース -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説
ニュース -
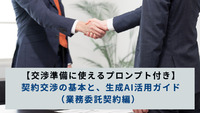
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)
ニュース -
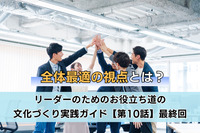
全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回
ニュース -

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ
ニュース -
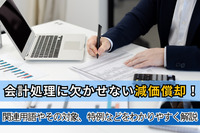
会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説
ニュース