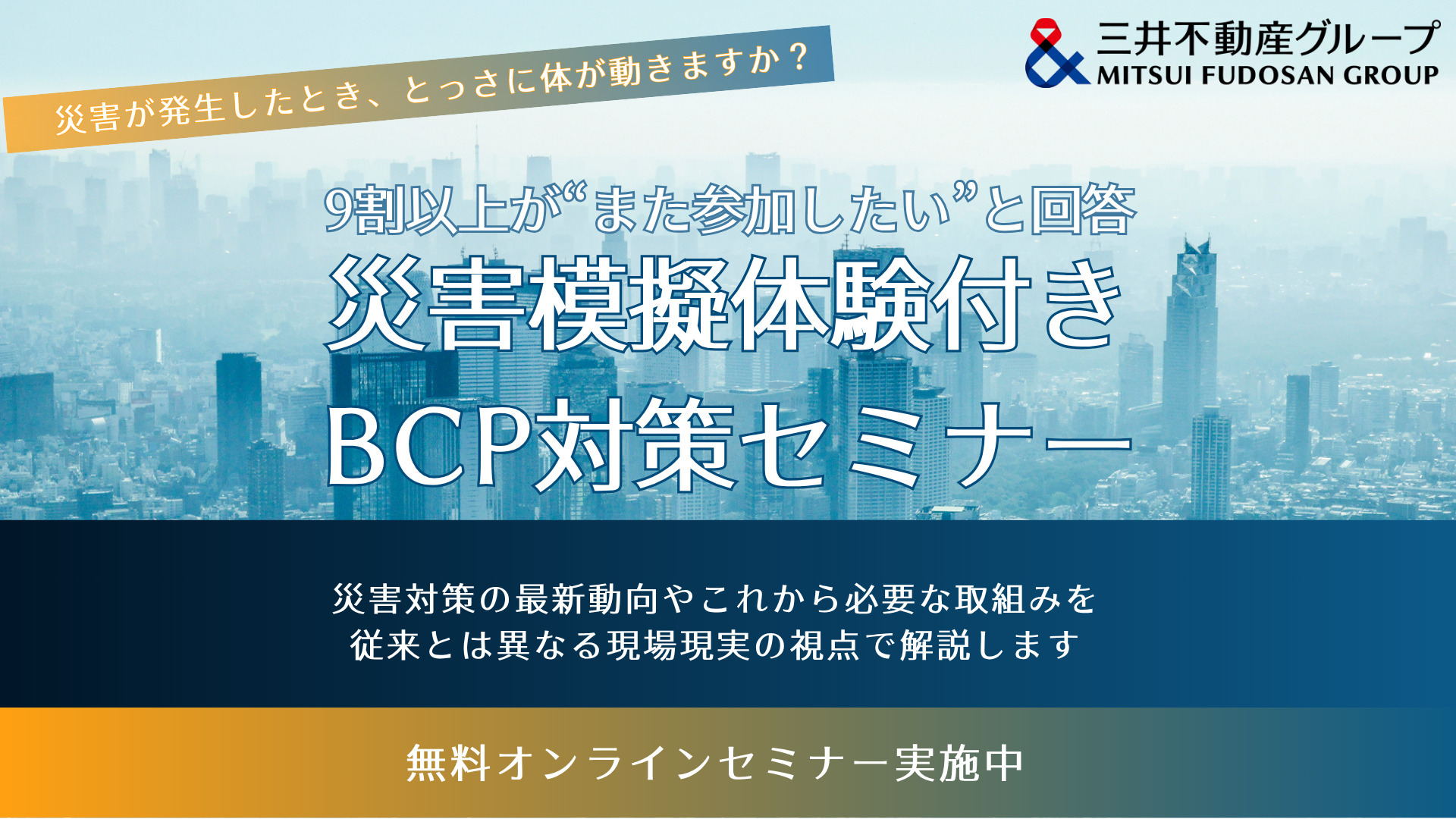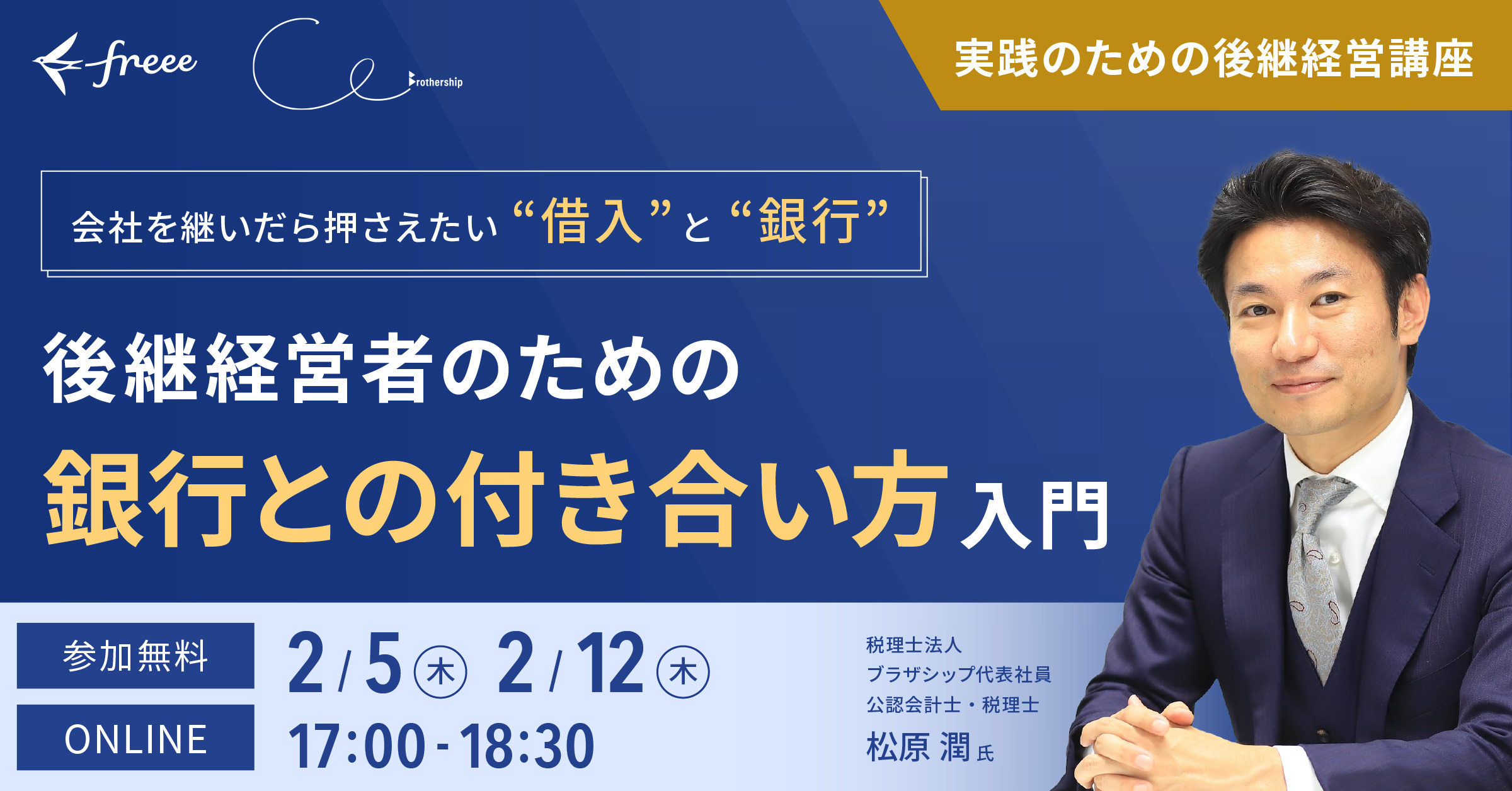公開日 /-create_datetime-/
最低限身に付けておきたい会計・財務の基礎知識を解説
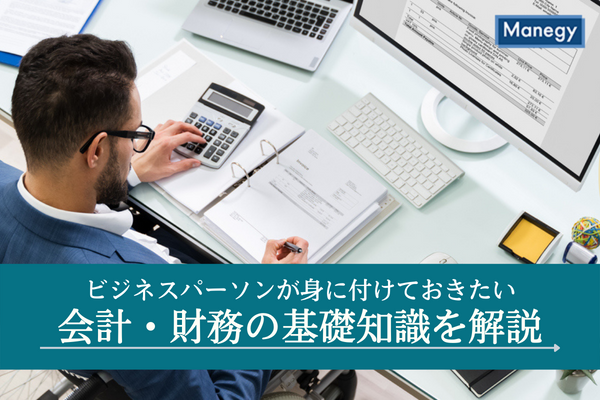
会計や財務と言えば、経理の人材が身に付けるスキルとして知られています。「経理関係の知識は自分に関係ない」と考えているビジネスパーソンも多いでしょう。
しかし会計・財務の知識は、会社目線で物事を考える力や、論理的思考力を養うのに役立ちます。そこで今回の記事では、ビジネスパーソンが身に付けておきたい会計や財務の知識について解説します。
目次【本記事の内容】
会計とは?
まずは会計と財務の基本知識として、それぞれどのような意味を指しているのか確認しましょう。会計とは、「会社の利益や持っている財産について考えること」です。
日常的な例をあげれば、レストランで食事をした時などの「お会計」と言いますが、会社においても同様に「会計とは売った・買ったなどの取引記録だ」とイメージする方も多いかもしれません。
たしかにそうした意味でも間違ってはいませんが、ビジネス目線で「会計」を考える時、別のイメージが見えてきます。より重要なのは、「企業の利益・財産を考えること」「それについて報告・説明すること」です。
企業の利益や財産について報告するというのは、つまり決算書類を作って、株主総会で説明することです。会計は、決算書類を作るための理論的な基礎となります。
財務とは?
ここまで「会計」の意味について解説しましたが、一方の「財務」は何を意味するのでしょうか。財務とは、「適切な企業活動を進めるために、どのような資金を管理し、資金の調達を行うか」を考えることです。ざっくりと言えば「資金繰り」を意味します。
企業が活動を継続するためには、さまざまな費用が必要になってきます。闇雲に活動をしているだけでは、効率的なリソース配分が行われず、企業に悪影響を与えるだけでしょう。企業が健全に活動していくために必要なのが「財務」です。
適切に財務をするためには、財務諸表(貸借対照表や損益計算書などの決算書)を参考にします。つまり、「会計」で考えた内容を基礎にして、「財務」を考えるわけです。会計と財務を同じような意味で捉える人も多いかもしれませんが、上記で確認したように、両者には明確な違いがあります。
会計・財務の基礎知識:決算書の項目について
次に、ビジネスパーソンで最低限身に付けておきたい会計・財務の知識を解説します。
決算書には、売上高や売上原価、売上総利益などさまざまな項目が記載されています。どの数字に注目すればよいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。今回は決算書に書かれている「数値」に注目して、基礎知識を身に付けていきましょう。
決算書のどの項目に注目するかは、「決算書から何を読み解きたいか」によって異なります。たとえば会社の収益について確認したいのであれば、「売上総利益率」「営業利益率」「経常利益率」の3つを確認するとよいでしょう。
売上総利益は、売上高から原価を引いたものです。商品そのものを生み出すのにかかった費用だけを引いた数値であり、「粗利益」「粗利」と呼ばれることも多くあります。
営業利益は、売上総利益から「販売費および一般管理費」を引いたものです。商品を製造して顧客のもとに届けるためには、人件費などのコストもかかります。営業利益に注目すれば、その企業にどれくらい稼ぐ力があるのかがわかるようになります。
経常利益は、営業利益から「営業外収益・営業外費用」を引いた数値です。「営業外収益・営業外費用」は、なんとなくわかりづらいかもしれませんが、「事業とは関係ない利息や投資損益」に関するものです。事業の儲けだけでなく、それ以外の状況も考慮した指標であり、「企業が継続的に利益を出せる力を持っているかどうか」の判断基準になります。
また会社の安全性を確認したい場合は、「自己資本比率」や「流動比率」を確認するとよいでしょう。自己資本比率とは、会社のすべての資本のうち、自己資本が占めている割合を指します。自己資本比率が高ければ高いほど、借りているお金が少ないということになり、経営の安定性につながります。
また流動比率とは、流動資産を流動負債で除したものです。簡単に言えば、流動資産は「1年以内に現金化される資産(受取手形など)」、流動負債は「1年以内に支払うべき金額(買掛金など)」です。
流動比率は「流動資産/流動負債」となっているため、流動資産が多ければ多いほど、そして流動負債が少なければ少ないほど高水準となります。企業の短期的な支払い能力に注目したい方は、この流動比率を見てみましょう。
また企業の生産性を確認したいと考える方も多いかもしれません。その場合は「一人当たり売上高」を見るのがおすすめです。ただしこれは業界や業種によって大きく異なるため、「同じ業界(業種)同士を比べてみる」といった使い方がよいでしょう。
まとめ
今回はビジネスパーソンが身に付けておくべき、会計や財務の基礎知識について解説しました。経理でなければ、専門知識が求められることは多くありませんが、最低限「決算書」を読み解けるようにしておくのがおすすめです。
決算書が読めるようになれば、日々の仕事だけでなく、投資や転職など人生のイベントに大きく役立てられるでしょう。まずは決算書を作るための理論的基礎となる、会計について学んでみてはいかがでしょうか。
▼管理部門の最新トレンドはココでチェック▼

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
ニュース -

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース -

事業用不動産のコスト削減ガイド
おすすめ資料 -

人的資本開示の動向と対策
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント
おすすめ資料 -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
ニュース -

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース -

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは
ニュース -
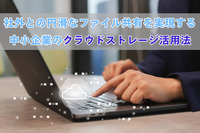
社外との円滑なファイル共有を実現する中小企業のクラウドストレージ活用法
ニュース